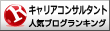先日、来春卒業する高校2年生の就職支援に関する講義をする機会があった。男女共学の県立高校。学年の2~3割の生徒が就職を目指すのだろう。参加者は、男子3割、女子7割。担当の先生の指導が行き届いていたのか、礼儀正しく素直な生徒が多かった。
この講義は厚生労働省の委託事業で、年に5~6回、受託先から依頼された学校に行き基本的にはプログラム通りの講義や演習を講師数名で行う。就職に対する心構えや仕事のこと、コミュニケーションや面接ロールプレイなど、5時間にわたる。
私は普段、中高年を対象としたキャリア支援に携わることが多いので、高校生を相手にするのは新鮮である。ただし、私がメイン講師を努める際は、「多くの生徒にとって講師は、親兄姉や先生等以外で初めて接する社会人である」という自覚と、「楽しそうにがんばってる(講師として働いている)大人の姿を見せる」という意識を持って臨んでいる。服装、言葉遣いや姿勢にも気を遣うし、上から目線で諭す様な物言いは極力しない。生徒の迷いや不安をやわらげて、就職への意欲が高まるような気づきを重視している。たった1日の講義でどれほど意欲向上したり気づきがあったりするのかわからないが、先生や生徒のアンケートは毎回良好だ。よって、一定の役割や責任は概ね果たせていると考えているが、本当は生徒たちのその後が知りたいと思う。
「7・5・3問題」というように、約5割の高卒就職者は3年以内に離職するという現実もある。しかし、若いうちはいろいろと自分の道を探索したり迷ったりしてもいいから、何度でもチャレンジしたり再スタートしたり、素直な姿勢で教えてもらい助けてもらいながら歩いてゆけばいいと思う。そんな時、「自分の親のような年齢でがんばってる大人が学校に来て何か言ってたな・・・」と、一人でも少しでも思い出してくれたら素直に嬉しい。(写真はフリー素材)
この講義は厚生労働省の委託事業で、年に5~6回、受託先から依頼された学校に行き基本的にはプログラム通りの講義や演習を講師数名で行う。就職に対する心構えや仕事のこと、コミュニケーションや面接ロールプレイなど、5時間にわたる。
私は普段、中高年を対象としたキャリア支援に携わることが多いので、高校生を相手にするのは新鮮である。ただし、私がメイン講師を努める際は、「多くの生徒にとって講師は、親兄姉や先生等以外で初めて接する社会人である」という自覚と、「楽しそうにがんばってる(講師として働いている)大人の姿を見せる」という意識を持って臨んでいる。服装、言葉遣いや姿勢にも気を遣うし、上から目線で諭す様な物言いは極力しない。生徒の迷いや不安をやわらげて、就職への意欲が高まるような気づきを重視している。たった1日の講義でどれほど意欲向上したり気づきがあったりするのかわからないが、先生や生徒のアンケートは毎回良好だ。よって、一定の役割や責任は概ね果たせていると考えているが、本当は生徒たちのその後が知りたいと思う。
「7・5・3問題」というように、約5割の高卒就職者は3年以内に離職するという現実もある。しかし、若いうちはいろいろと自分の道を探索したり迷ったりしてもいいから、何度でもチャレンジしたり再スタートしたり、素直な姿勢で教えてもらい助けてもらいながら歩いてゆけばいいと思う。そんな時、「自分の親のような年齢でがんばってる大人が学校に来て何か言ってたな・・・」と、一人でも少しでも思い出してくれたら素直に嬉しい。(写真はフリー素材)