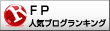創業62年のバーに行った。カウンターのみ10席ほど。細身で寡黙で職人気質に見えるマスターと、小柄で眼鏡をかけた奥様。二人とも白いシャツを着ている。マスターの首には黒い蝶ネクタイ。奥様の顔には人懐っこい笑顔。私が生まれるずっと前から、マスターはこの場所でバーテンダーとして生きてきた。昭和の半ば、戦後20年近くが過ぎ高度成長期の始まるころに、若干二十歳で店を始めたことになる。
この店のメインはハイボール。「濃いめのハイボール」とか、「伝説のハイボール」とも言われている。10年ほど前に数回行ったことがある程度なので、酒の蘊蓄を語るつもりはないが、久しぶりに飲んでみて「あ~なんだかうまい」というような、深く柔らかい味わいを感じた。普段ハイボールは飲まないせいか、そのイメージや味の記憶とは違っていた。作り方は至ってシンプルに見える。グラスにウイスキーを入れ、氷を入れ、ソーダ水を注いでマドラーで軽く混ぜるだけ。それなのに、一杯のつもりがいつのまにか四杯飲んでいた。つまみはポップコーンだけなのに。
マスターは62年間ほぼ毎日店を開け、ハイボールやカクテルを客に出し続けてきた。奥様は、人懐っこい笑顔と方言交じりの会話で客の相手をしてきたのだろう。その変わらない姿勢を想うと、癒される思いがした。お二人の姿勢だけでなく、店のたたずまい、一枚板のカウンター、棚に並んだボトル、灯り、程よい柔らかさの椅子、壁の色紙や客の服を掛けるフック、黒電話など。随所にお二人の歴史が染みついているようでいて決して押しつけがましくなく、居心地が良い。また、客も節度を持って、それぞれ楽しみ方で酒と会話と時の流れを味わっている雰囲気がある。
久しぶりに店をのぞくと、マスターは白いマスクを、奥様は透明のフェイスガードをしていた。席はほぼ満席だったが、丁度3人組の中年客が「私たちもう帰りますから」と席を空けてくれた。少し待って座って「三つください」と注文すると、マスターが黙ってカウンターにグラスを並べて目の前でハイボールを作り始めた。1分もかからなかっただろうか。前にコースターとハイボールが置かれた。乾杯して一口味わったら、すぐに何か温かいものが胸の中に広がる感じがした。初めて来たという連れが、「あ~おいしい。」と言った瞬間、マスターがちらっとこちらを見て満足げな目をした。すると、奥様が「あなた初めてじゃないよね。声でわかるのよ。」と私に声をかけてきた。話してみると本当に覚えていてくれていたことがわかり、今度は少し胸が熱くなった。「男の人のことは良く覚えているのよ。」と奥様が笑った。
三杯目の頃だったろうか。ふと、また来れるだろうかとの思いが頭をよぎった。その時、出張の一元客らしき男性が店の写真を撮って良いかと尋ねると快く応じていた。こちらも、マスターの手のあいたころを見計らって頼んでみると、お二人がマスクとフェイスガードをはずして並んで写真におさまってくれた。創業半世紀以上のいわゆる老舗に行くことはあっても、その創業者自身の仕事ぶりや人柄に直接触れることなど滅多にないだろう。そう考えると、心から敬服する思いだった。
帰り際、マスターが顔を上げて「ありがとう」と声をかけてくれた。「久しぶりに来てよかったです。また来ます。」と、自然に言葉が出てきた。Since1958。。」ぼんやりとした温かい光の中にお二人の人生が映し出されているようだった。