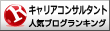キャリアコンサルタントとして、職業訓練の講師を担当している。訓練の中でも、雇用保険を受給しながら受講して早期再就職を目的とするコースを主に担当している。訓練内容は、OAスキル、事務系、特定業界や資格を目指すものがある。私の担当は、専門知識や技能の講義ではなく、就職支援、キャリア支援、コミュニケーション等に関するものである。
受講生は、老若男女、キャリアも様々だが、最近、受講生を見ているとその人が大体どんな働き方をしてきたか想像できるようになった。そのイメージは多くの場合、実際と大きく違わないと思えるようになってきた。
例えば、就職支援等の講義の日に限ってよく休む受講生がいる。確かに、急な所用や体調不良などの理由で一定日数欠席することは認められるが、それを逆手にとって自分が興味がない、不要と思う講義を欠席していると思われることがある。そんなことが何度も続くと、偶然とは考えにくい。職業訓練を受講する立場でありながら、自分に都合の良い勝手な判断をすると思われても仕方ない。再就職をなめているのかプライドがあるのか知らないが、採用担当者目線で見ても使いにくいタイプなのだ。仕事は楽なことだけをさせてもらうわけではない。それなりの年齢でキャリアもある受講生にもそういうタイプがたまにいる。
一方で、訓練を自分の転機ととらえて、素直に、不器用でも懸命に、新しいことでも何でも吸収して将来に生かそうとする受講生も多い。企業が欲しい人材は、圧倒的に後者だ。そのことに気づかないから、前者はこれまでと同じように再就職が難航し転職を繰り返す。家族の支援などの逃げ場があるせいか、定着しない。受講の動機は何であれ、せっかくの機会を自らのキャリアに少しでも生かせば良いのにと思う。講師もプロ意識を持って、受講生の何か役に立とうと懸命にやっている。講師は人を見るのも仕事だ。
受講生は、老若男女、キャリアも様々だが、最近、受講生を見ているとその人が大体どんな働き方をしてきたか想像できるようになった。そのイメージは多くの場合、実際と大きく違わないと思えるようになってきた。
例えば、就職支援等の講義の日に限ってよく休む受講生がいる。確かに、急な所用や体調不良などの理由で一定日数欠席することは認められるが、それを逆手にとって自分が興味がない、不要と思う講義を欠席していると思われることがある。そんなことが何度も続くと、偶然とは考えにくい。職業訓練を受講する立場でありながら、自分に都合の良い勝手な判断をすると思われても仕方ない。再就職をなめているのかプライドがあるのか知らないが、採用担当者目線で見ても使いにくいタイプなのだ。仕事は楽なことだけをさせてもらうわけではない。それなりの年齢でキャリアもある受講生にもそういうタイプがたまにいる。
一方で、訓練を自分の転機ととらえて、素直に、不器用でも懸命に、新しいことでも何でも吸収して将来に生かそうとする受講生も多い。企業が欲しい人材は、圧倒的に後者だ。そのことに気づかないから、前者はこれまでと同じように再就職が難航し転職を繰り返す。家族の支援などの逃げ場があるせいか、定着しない。受講の動機は何であれ、せっかくの機会を自らのキャリアに少しでも生かせば良いのにと思う。講師もプロ意識を持って、受講生の何か役に立とうと懸命にやっている。講師は人を見るのも仕事だ。