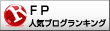「目線」という言葉には、「その立場におけるものの考え方やとらえ方」という意味がある。「お客様目線」とか「子供目線」などの使い方をする。もともとは、映画・演劇界で使われていた「視線」を表す言葉が一般化したものらしい。
最近、時々気になることがある。「やわらかな上から目線」とでも表現したらいいのか、違和感や苛立ちを感じる「目線」である。自分に対してであったり周囲の人に対するものであったりするが、「今の言い方、態度、何かおかしいな」と感じるものだ。その相手との間に上下関係や主従関係があれば仕方ないのだが、本来対等な関係であったり協働する立場であったりするからだろう
例えば、「(さんざん自論を言った後で)さあ、あなたの意見言ってみて。」と人を指しながら話を聞かない年長者。「(関係構築もできていない段階で)あなたの話を聞いてあげるから何でも話してごらんなさい。」と身を乗り出すカウンセラー。「(職場で当然の作業をしただけなのに)ありがとうございますやっていただいて、大丈夫でしたか?」と過剰な礼を言う同僚。それから、個人の自由とはいえ、SNSでの美食自慢や多忙自慢に見える発信も、スルーするのもうんざりすることもある。
いわゆる「明らかな上から目線」の場合、反発、無視、忍従あるいは面従腹背などの対応が考えられる。一方、「やわらかな上から目線」の場合、やり過ごしたとしても、何かもやもやした不快感が残る。それは、自分が馬鹿にされたような慇懃無礼な態度に見えるからだろうか。いちいち指摘するのも腹を立てるのも大人げないとは思うが。
自分自身も、たとえ無意識であっても「上から目線」にならないよう心掛けたい。そのためには、やはり相手を尊重する態度としての「聴く」ことを大切にしたい。そして、視線はなるべく上下より左右に動かそうと思う。相手と自分の自尊心を守るためにも。
最近、時々気になることがある。「やわらかな上から目線」とでも表現したらいいのか、違和感や苛立ちを感じる「目線」である。自分に対してであったり周囲の人に対するものであったりするが、「今の言い方、態度、何かおかしいな」と感じるものだ。その相手との間に上下関係や主従関係があれば仕方ないのだが、本来対等な関係であったり協働する立場であったりするからだろう
例えば、「(さんざん自論を言った後で)さあ、あなたの意見言ってみて。」と人を指しながら話を聞かない年長者。「(関係構築もできていない段階で)あなたの話を聞いてあげるから何でも話してごらんなさい。」と身を乗り出すカウンセラー。「(職場で当然の作業をしただけなのに)ありがとうございますやっていただいて、大丈夫でしたか?」と過剰な礼を言う同僚。それから、個人の自由とはいえ、SNSでの美食自慢や多忙自慢に見える発信も、スルーするのもうんざりすることもある。
いわゆる「明らかな上から目線」の場合、反発、無視、忍従あるいは面従腹背などの対応が考えられる。一方、「やわらかな上から目線」の場合、やり過ごしたとしても、何かもやもやした不快感が残る。それは、自分が馬鹿にされたような慇懃無礼な態度に見えるからだろうか。いちいち指摘するのも腹を立てるのも大人げないとは思うが。
自分自身も、たとえ無意識であっても「上から目線」にならないよう心掛けたい。そのためには、やはり相手を尊重する態度としての「聴く」ことを大切にしたい。そして、視線はなるべく上下より左右に動かそうと思う。相手と自分の自尊心を守るためにも。