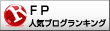その女性は、上司である現場監督や見学者の前で、いつものように作業を続けました。かける、こする、磨く、流す、拭く。使い慣れた道具で、手際よく黙々と作業を進めました。排水口やパイプの中まで手を突っ込み、布は拭く場所によって4種類使い分けます。仕上げは、ゴム手袋の汚れがつかないように素手です。約1時間の作業が終わると、その女性は少し息が上がったまま休憩しました。
職場見学で、あるビル管理会社のトイレ清掃の現場を見学した男性の話です。徹底した仕事ぶりに、感銘を受けたとのこと。それから、現場の案内をしてくれた上司の話も印象に残ったそうです。「彼女は、誰も見ていないところでも手を抜かずに同じように仕事をするんですよ。」「このビルの人たちはきれいにトイレを使ってくれるから、彼女もきれいにしようとがんばっているんですよ。」
見学した男性の感想です。「誰かがやらないといけない仕事をやっているというプロ意識や、トイレを使う人との間に目に見えない信頼関係のようなものがある感じがしたんです。」
年末年始、休暇を取る人が多い一方で働いている人々もいます。身近な所では、警察、消防などの公務。医療、介護、電力、運輸、通信など社会のインフラに関わる仕事。また、ホテルなどのサービス、飲食、販売、娯楽等の業界もそうです。人が集まる場や動く所には、目に見える面だけでなくその裏方にも仕事があります。どんな人々が仕事をしているか想像したり、どんな場所で働いているか観察したりしてみると新たな発見があるかもしれません。
「誰かがやらないといけない仕事を、誰も見ていないところで、誰かのためにやる。そんな働き方が自分に合っているかもしれません。今の自分にもできる事から始めてみようと思います。」職場見学は、転機にいる彼のキャリアにとって啓発的な経験になったようです。キャリアも人生も人それぞれです。
職場見学で、あるビル管理会社のトイレ清掃の現場を見学した男性の話です。徹底した仕事ぶりに、感銘を受けたとのこと。それから、現場の案内をしてくれた上司の話も印象に残ったそうです。「彼女は、誰も見ていないところでも手を抜かずに同じように仕事をするんですよ。」「このビルの人たちはきれいにトイレを使ってくれるから、彼女もきれいにしようとがんばっているんですよ。」
見学した男性の感想です。「誰かがやらないといけない仕事をやっているというプロ意識や、トイレを使う人との間に目に見えない信頼関係のようなものがある感じがしたんです。」
年末年始、休暇を取る人が多い一方で働いている人々もいます。身近な所では、警察、消防などの公務。医療、介護、電力、運輸、通信など社会のインフラに関わる仕事。また、ホテルなどのサービス、飲食、販売、娯楽等の業界もそうです。人が集まる場や動く所には、目に見える面だけでなくその裏方にも仕事があります。どんな人々が仕事をしているか想像したり、どんな場所で働いているか観察したりしてみると新たな発見があるかもしれません。
「誰かがやらないといけない仕事を、誰も見ていないところで、誰かのためにやる。そんな働き方が自分に合っているかもしれません。今の自分にもできる事から始めてみようと思います。」職場見学は、転機にいる彼のキャリアにとって啓発的な経験になったようです。キャリアも人生も人それぞれです。