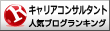「こういうご時勢ですから、やむを得ません。」「こればっかりは、どうにもなりません。」こんな言葉を、よく耳にした。そう言わざるを得ないのだろうが、こんな取りつく島もない言い方にやるせなさを感じた。大人げないが、心の中で突っ込みを入れたくなる。「こういうご時勢って、どういうご時勢なんだ?」「こればっかりは、と言うけれど、”これ”以外に他に何かしたのか?」と。
「慎重に判断せざるを得ません。」と固い表情で話す者は、大体何もしないことを”判断”する。普通、判断には責任が伴うから。人の痛みに鈍感に見える者が、「責任を痛感する」と頭を下げても、結局責任転嫁するだけだろうと見透かされる。「全力で、総力を挙げて」と力まれても、「”やってる感”ばかりじゃなくて、メリハリをつけた方が結果につながるんじゃないか。」と逆に心配になる。「大切な人の命を守る」「安心と安全のため」と、守られた場所の中で守られた立場の者が世間や現場に向かって、だから「~しなければならない」とか「~してはいけない」と、声高に正義・正論を振りかざすのは正直鬱陶しい。「新たなステージ」「新しい生活様式」と仰々しくアピールする割にはそれほど目新しい事はなく、以前から心がけている当たり前の事や、逆に現実離れした事もあったりする。
おうち、with、アフターなど。平仮名やカタカナ、英語表記を使うのは、子供や外国人にもわかりやすくとの配慮かもしれないが、物事の本質や深刻さを曖昧にして、「わかったつもり」に勘違いさせられるような違和感がある。
「言葉のあや」と言ってしまえば、それまでかもしれない。「綾(あや)」とは物の面に表れた様々な線や形の模様のこと。そこから、文章表現の技巧や巧みな言い回しの意味。そう考えると、以上の言葉には、私には雑で軽薄な感が否めず、重みや人の匂いや体温もあまり感じられない。
「考えておきます。」と言ってやんわり断る客の所に、後で「考えてくれましたか」と押し掛ける営業マンの様な強引さに眉をひそめる人は多い。つまり、人は時によって曖昧な言い回しを使う。まさに、「言葉のあや」を好む。それも、人間関係を円滑にする知恵かもしれないが、言葉のあやは言葉の虚しさと紙一重。その言葉を発する人に対する虚しさも映すと感じる。
「言葉が変われば、心が変わる。心が変われば、行動が変わる。(略)」と言われる。私は、まず自分の言葉を変えるために、挨拶をしっかりとしようと思う。最近、仕事場や出先でも、マスクをしたままこもった声で表情を変えずに挨拶することが多かった。人間は相手の言葉と表情が一致しないと、相手に不信感を持ちやすいらしい。相手の目を見て、明るい声で挨拶する。挨拶は、相手との心の距離を縮めるもの。「新しい生活様式」とやらになっても守りたいあたりまえのことを、忘れかけていたように思う。
「慎重に判断せざるを得ません。」と固い表情で話す者は、大体何もしないことを”判断”する。普通、判断には責任が伴うから。人の痛みに鈍感に見える者が、「責任を痛感する」と頭を下げても、結局責任転嫁するだけだろうと見透かされる。「全力で、総力を挙げて」と力まれても、「”やってる感”ばかりじゃなくて、メリハリをつけた方が結果につながるんじゃないか。」と逆に心配になる。「大切な人の命を守る」「安心と安全のため」と、守られた場所の中で守られた立場の者が世間や現場に向かって、だから「~しなければならない」とか「~してはいけない」と、声高に正義・正論を振りかざすのは正直鬱陶しい。「新たなステージ」「新しい生活様式」と仰々しくアピールする割にはそれほど目新しい事はなく、以前から心がけている当たり前の事や、逆に現実離れした事もあったりする。
おうち、with、アフターなど。平仮名やカタカナ、英語表記を使うのは、子供や外国人にもわかりやすくとの配慮かもしれないが、物事の本質や深刻さを曖昧にして、「わかったつもり」に勘違いさせられるような違和感がある。
「言葉のあや」と言ってしまえば、それまでかもしれない。「綾(あや)」とは物の面に表れた様々な線や形の模様のこと。そこから、文章表現の技巧や巧みな言い回しの意味。そう考えると、以上の言葉には、私には雑で軽薄な感が否めず、重みや人の匂いや体温もあまり感じられない。
「考えておきます。」と言ってやんわり断る客の所に、後で「考えてくれましたか」と押し掛ける営業マンの様な強引さに眉をひそめる人は多い。つまり、人は時によって曖昧な言い回しを使う。まさに、「言葉のあや」を好む。それも、人間関係を円滑にする知恵かもしれないが、言葉のあやは言葉の虚しさと紙一重。その言葉を発する人に対する虚しさも映すと感じる。
「言葉が変われば、心が変わる。心が変われば、行動が変わる。(略)」と言われる。私は、まず自分の言葉を変えるために、挨拶をしっかりとしようと思う。最近、仕事場や出先でも、マスクをしたままこもった声で表情を変えずに挨拶することが多かった。人間は相手の言葉と表情が一致しないと、相手に不信感を持ちやすいらしい。相手の目を見て、明るい声で挨拶する。挨拶は、相手との心の距離を縮めるもの。「新しい生活様式」とやらになっても守りたいあたりまえのことを、忘れかけていたように思う。