2025.2.9
◼️三河国分尼寺跡
・愛知県の南東部の都市、豊川市にある奈良時代の遺跡。西暦741年の聖武天皇の命で、全国に作られた国分寺尼寺の一つで、この三河のものは8世紀後半の築造と考えられるとのこと。




説明板



復元された中門




金堂跡





礎石のうち、6つは当時のものであるとのこと。







経堂跡


鐘楼跡。
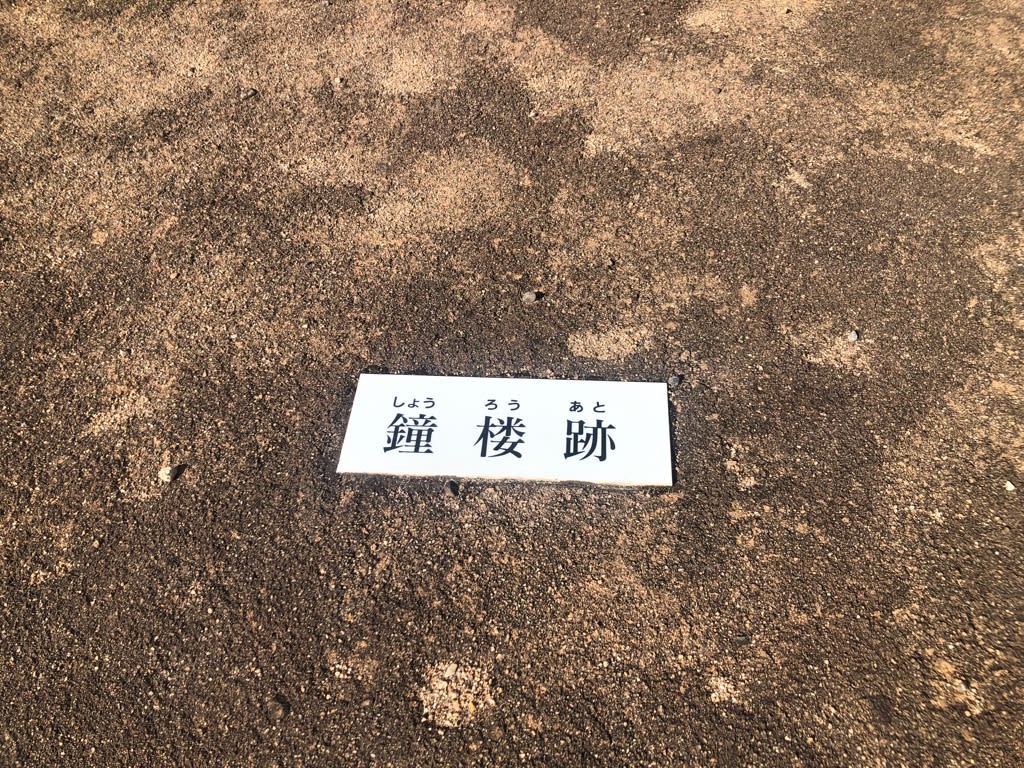

講堂跡


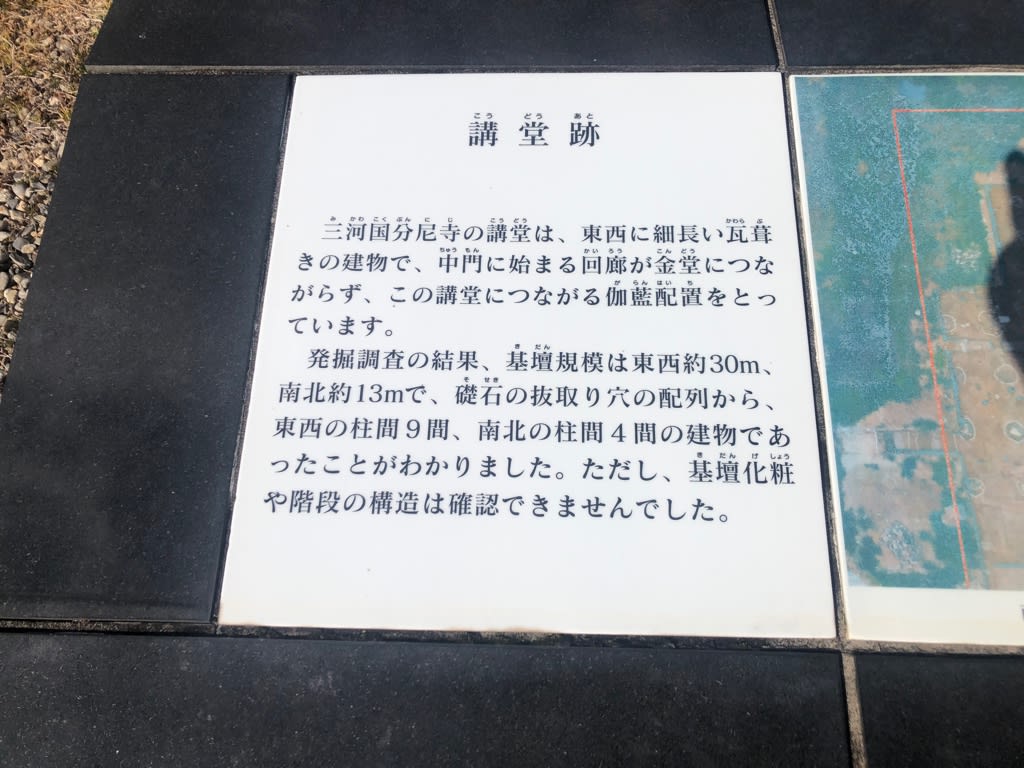



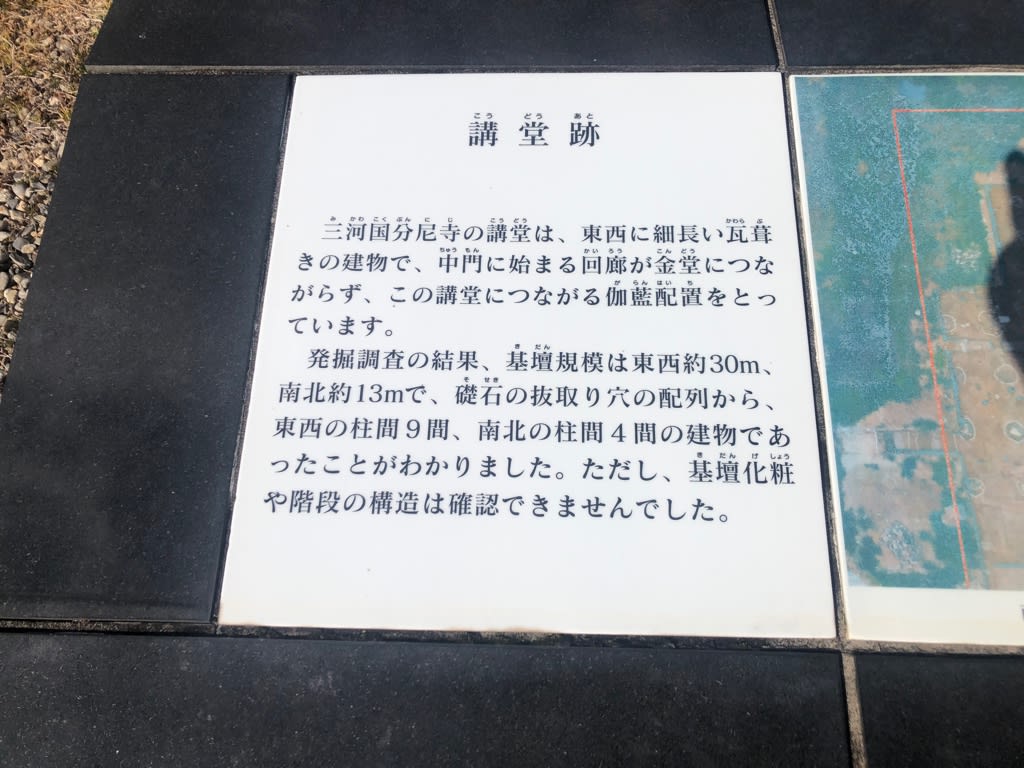


北方建物跡


掘立柱塀跡
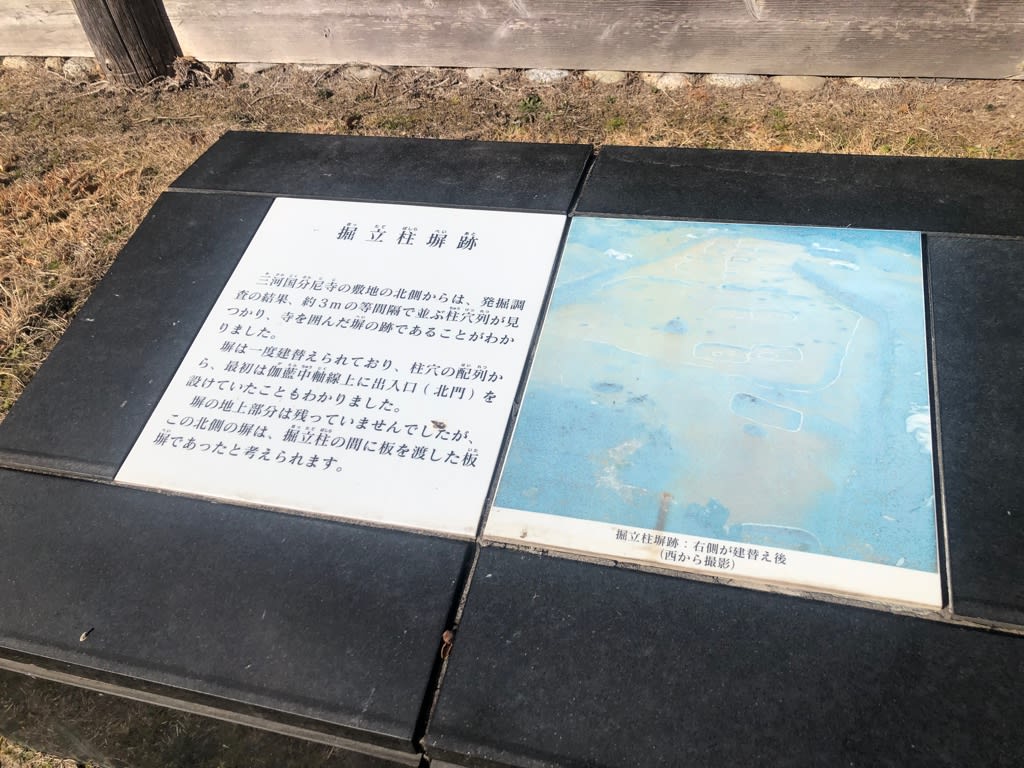


尼房跡


西回廊跡





西回廊跡



東回廊跡
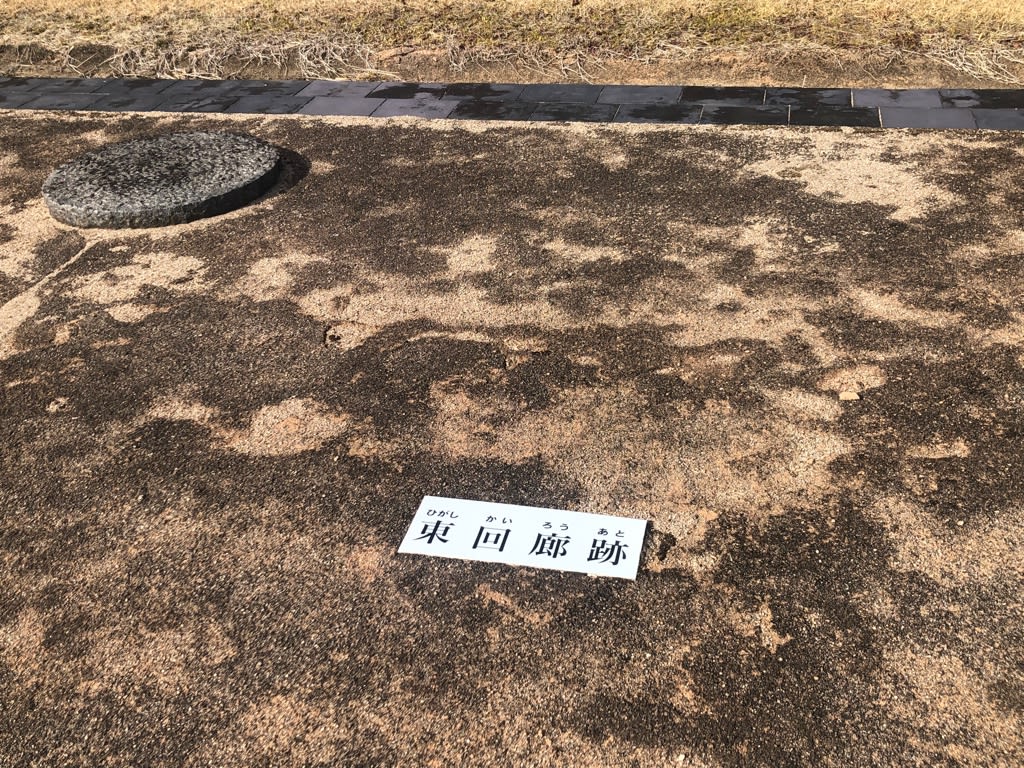


◼️三河天平の里資料館
・国分尼寺跡のすぐ南側に、小ぶりな資料館があり、尼寺跡・僧寺跡からの発掘物などが展示されている。説明板は充実しており、たいへん参考になった。中でも、国分寺の塔跡から発掘の、銅製の水煙の破片はきわめて貴重。

(豊川市八幡町忍地108)
◼️三河国分寺跡
・尼寺跡から西に歩いて10分ほどのところに、国分寺跡の遺跡。尼寺跡に比べ、復元展示的な要素はないが、説明板は充実していた。

説明板
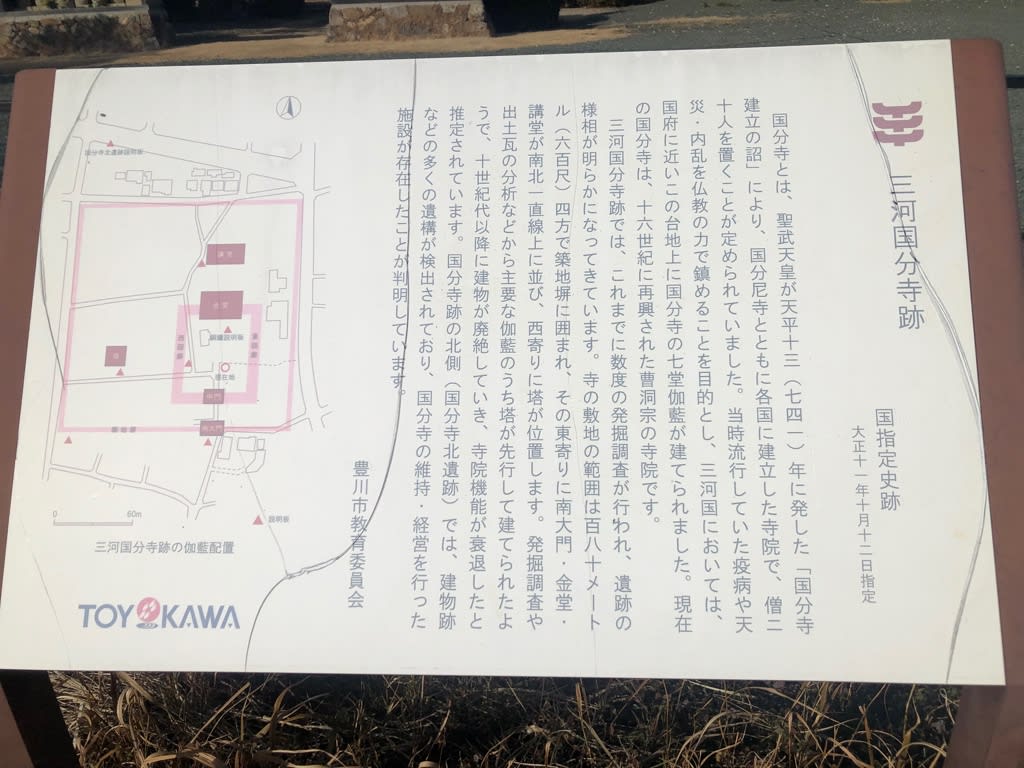


西回廊跡


塔跡



礎石が二つ残っている。




二つ目


塔跡



礎石が二つ残っている。




二つ目

築地塀跡


講堂跡


南大門跡


講堂跡


南大門跡



平安時代の銅鐘



国分寺跡の北の住宅街にあった「国分寺北遺跡」の説明板。



国分寺跡の西側にある八幡宮。国分寺の鎮護のために作られたもので、15世紀の築であるとのこと。


(豊川市八幡町本郷31)
〈関連遺跡:赤塚山古窯〉
・国分寺跡から北東に3kmの、赤塚山公園にある遺跡。国分寺の瓦を焼いた窯跡が保存展示されている。
説明板





登窯の上部と思われる石組みが5つ。







窯を下から見た様子。


敷地内にある円墳「赤塚山古墳」。
案内板によると、6世紀後半から7世紀初頭のもの。


擁壁や地面も瓦が使われていて、瓦窯跡らしい雰囲気を出していた。


赤塚山公園の全景

(豊川市市田町東堤上1番地30)
◼️三河国府跡
・国分寺跡から西に1km弱のところに、「三河国総社」という神社があり、ここに国府があったと考えられるとのこと。礎石などの遺物はなく、説明板のみ。





(豊川市白鳥町上郷中)














































































































































