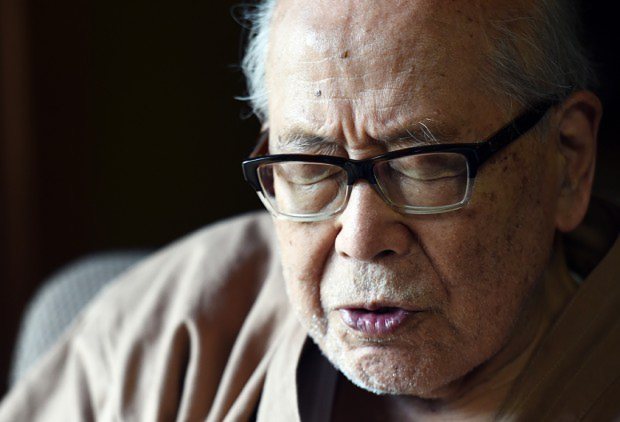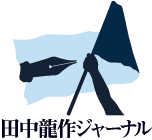「助けて」と言える社会に 元厚労省事務次官・村木厚子さん 瀬戸内寂聴さんらと女性支援プロジェクト
毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20180222/dde/012/040/002000c
2018年2月22日 東京夕刊
「溺れている人がわらをつかまずにすむように、ブイを投げられる社会にしたい」。冤罪(えんざい)事件で164日間、拘置所で生活した。エリート官僚として支える側から支えられる側に一瞬にして転じた。その体験が裏打ちする言葉だ。少女や若い女性に寄り添い支援する一般社団法人「若草プロジェクト」の呼びかけ人になった元厚生労働省事務次官、村木厚子さん(62)。官僚時代にはできなかった新しい「福祉」の道を開拓しようとしている。【玉木達也】
「少女たちが安心して『助けて』と言える社会に」。若草プロジェクトが1月27日、東京都内で開いた連続講座。若い女性らがソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じて知り合った男に殺害されたとみられる、神奈川県座間市の事件がテーマだった。公的な機関で相談業務をしている人や病院で働くソーシャルワーカー、施設の少女らの支援活動をする実業家ら男女約70人が参加。村木さんの知人で、冤罪事件をテーマにした映画でも知られる周防正行監督も「勉強のため」に出席した。
若草プロジェクトは全国で個々に活動する支援者をつなぎ、少女らを取り巻く問題を広く社会に伝え、解決のために何ができるかを学ぶ活動をする。具体的には無料通信アプリ「LINE(ライン)」で相談の受け付けをしたり、東京と京都で連続講座を開いたりしている。6回目の今回は厚労省と総務省の担当者が自殺対策やインターネットの問題について解説。ネット上で自殺対策に取り組むNPO法人の代表が実践的な演習を行った。
座間事件を繰り返させないために何ができるか。出席者は数人ずつのグループに分かれて議論。「若者がよく利用する飲食店のレシートに相談窓口の連絡先を書く」「自殺未遂経験者が相談相手になる」など、当事者の気持ちになったアイデアが次々と発表された。
終了後、村木さんは「どうすれば、孤立している彼女たちに支援の手を届けられるのか。とても難しいことだが、その方法について参加者からさまざまな意見が出たのはよかった」と話した。
私が村木さんを初めて取材したのは2004年4月。厚労省障害保健福祉部企画課長として障害者を巡る制度改革に取り組んでいた。それから5年後、この企画課長時代に不正があったとして大阪地検特捜部に逮捕、起訴された。09年6~11月、大阪拘置所に勾留。この時、今につながる原点ともいうべき出来事に遭遇した。
一貫して容疑を否認する中、ある時、取り調べの合間に、気になっていたことを検事に尋ねた。「あの女の子たちは何をしたのですか」。拘置所で食事や洗濯物の作業をする受刑者たちの多くが若くてかわいらしい。犯罪を犯したように見えなかった。「売春や薬物が多い」との検事の答えに、なぜそんなことをしたのかと疑問が深まった。
無罪が確定し10年9月、厚労省に復職。冤罪被害者という立場から、検察改革など法務省の仕事が増えた。本業では社会・援護局長などを務め、生活困窮者の対策に力を注いだ。両省をまたいで気がついた。「困窮者支援で福祉が相手にしている人と、刑務所に入っている人は多くの部分で重なっている」。薬物に手を染める若い女性のうち、児童虐待や配偶者暴力(DV)の被害者が高い割合を占めていた。「被害から逃げるための薬物だったり、悪い人に引き込まれての薬物だったりする。犯罪者ではなく、被害者の面がすごくある」と知った。
この状況から若い女性を助けたい。しかし行政の施策では、一定の年齢を超えた人は法令で福祉の対象から外れてしまう。そこで作家の瀬戸内寂聴さんとともに若草プロジェクトの呼びかけ人になった。設立は16年4月。村木さんは前年10月、事務次官を退任し官から民に活動の舞台を移していた。支援の対象は年齢ではなく、「少女」や「若い女性」とあえてあいまいな表現にした。厚労省の同僚でもあった夫が理事に入り、代表理事は知人で人権問題に詳しい大谷恭子弁護士(東京弁護士会)が務める。
あきらめたら変わらない
活動を始めてから、ある支援団体の人にこう言われた。「公の福祉はすべての面でJK(女子高生)ビジネスに負けている」。彼らは街に出て若い女性一人一人に「どうしたの?」「ごはん食べた?」「泊まる所あるの?」と声をかけていく。温かい食事を食べさせ、泊まる場所を用意し、働き場を紹介する。これに対し、行政は「困っているなら窓口に来なさい」。このままでは勝てない--。
連続講座への参加をきっかけに、行政の中にも一歩、踏み出そうとする人たちが現れた。複雑な事情を抱えている子供たちを支援する民間グループのネットワーク作りも進む。「単体では十分な支援ができなくても、支援者同士がつながれば対応できる。どこか1カ所につながれば、全部につながるようにしたい」。さらに「あの子たちの自己責任ではなく、非常に重たい問題を背負っている子が多い。何よりも(JKビジネスなどで)もうけているのは大人だということをもっと知ってほしい」と言葉に力を込める。
自分自身の体験が根っこにある。全く覚えのない罪である日突然、逮捕された。公務員として人を支える立場から、すべてが誰かの手を煩わせないとできない状態になった。支えられることのありがたさは身にしみている。
昨年4月から津田塾大総合政策学部で客員教授も務める。初年度は1年生を対象に、障害者や生活困窮者、外交などの問題で第一線で活躍している人たちを招き講義をしてもらった。「世界は一人で変えられるか」がテーマの講義を聴いて、ある学生は「一人の問題からスタートし、一人がそれを解決しようとすることで将来が変わった。一人のことに一人が取り組み始めることが大事と知った」と感想を書いた。
「ちゃんと理解してくれた」と笑顔を見せる村木さん。「『世の中、こんなもの』とあきらめている限り、何も変わらない」。続けてさらっと出た言葉に、あきらめない人間の迫力を感じた。