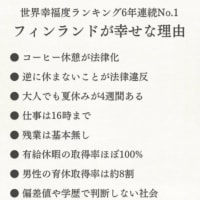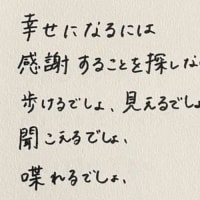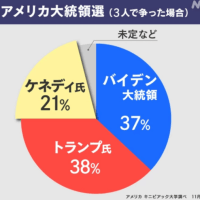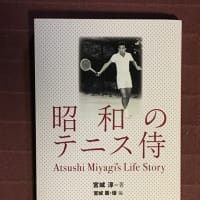友人の小さなギャラリーで、朗読会をすることになりました。
2016年4月23日(土)於:ギャラリー60
テーマ:芥川龍之介『桃太郎』を読む
今日は芥川龍之介の『桃太郎』を読みますが、最初に『桃太郎』の話を確認しておきたいと思います。。
これから写すのは、絵本ムービーです。(★ビデオ)
みなさんの、覚えている『桃太郎』も、この通りでしたか?
多分、同じはずですが、
実は、これは明治20年に国定教科書に掲載されてかららしいのです。
それまでは、いろいろな『桃太郎』が語られていました。四国の香川の方では、桃太郎は女の子で、あまりのかわいらしさに鬼が連れて行ってしまわないように男の子の名前にして育てたことになっていたそうですし、お供になった猿、犬、雉も、地方によっては、カニや臼、卵、水桶なのだったらしいのです。
それから、今の『桃太郎』とは、
3つ、大きな違いがあったようなんです。
(1つは)流れてきた桃は普通の大きさの桃だった。
一つ食べたおばあさんが、おじいさんのために、一つ持って帰った。おじいさんが芝刈りから戻ると、若返ったおばあさん。おじいさんも食べると若返り、子供のなかった二人に赤ん坊が生まれた。
(2つは)3年寝太郎のように、力持ちで大きな体だったが、怠け者で寝てばかり。おじいさんたちも、持て余していた。
(3つは)戦装束など(日の丸の鉢巻、陣羽織、ノボリを立ててえ出陣)していなかったし、動物も道連れになっただけで、上下(主従)関係はなかった。
この昔の『桃太郎』を実際に聞いたという人に、本当か、確かめたかったのですが、明治20年生まれといえば今年139歳ですから、もう確かめようがないのです。
それから、『桃太郎』といえば、落語にも同名の出し物があって、多くの落語家に演じられています。
その最初の『桃太郎』を演じたのが、江戸から明治にかけて活躍した三遊亭円朝だったんです。
この円朝という人は、現代まで続く落語の中興の祖と言われている人です。とにかく話がうまくて、あまりの巧さに嫉妬され、師匠の圓生から妨害を受けた。具体的には、圓朝が演ずるであろう演目を圓生らが先回りして演じ、圓朝の演ずる演目をなくしてしまう。たまりかねた圓朝は自作の演目(これなら他人が演ずることはできない)を口演するようになり、多数の新作落語を創作した、と言われています。
その円朝が、ある日、知り合いの集まりに招かれた時、
『何か一つやってくれないか』と声がかかります。
ところが、あるお偉いさんらしい人が、『桃太郎』が聞きたいと言う。
何で、この俺が桃太郎のような昔話をしなきゃならないんだ、冗談じゃない、俺を馬鹿にしているのか、と思った円朝は、即座に席を立ってしまった。
ところが、その人物が山岡鐵舟と知った円朝は、大人気なかったと全生庵に鐵舟を訪ねて、ぜひ聞いていただきたいとお願いする。すると、遊んでいた子供を集めて、ぜひあの子たちに『桃太郎』を聞かせてやってくれと言われた。
山岡鉄舟という人は、江戸無血開城を決した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立って、勝から全権を委任されて駿府に乗り込んで無血開城への道を開いたという人物です。明治維新後、無刀流の開祖となった人で、また西郷からの求めによって10年間明治天皇の侍従を務めました。そして、その後、谷中に全生庵という臨済宗の寺を建てて、維新で没した士族を弔ったという人です。
当時、すでに世間では名人と言われ、名を成していた円朝は、内心ムッとしながらも、再びケツをまくって帰るわけにも行かなかった。
そこで円朝は、それこそ一世一代の『桃太郎』を聞かせてやろうじゃないかと、腕によりをっけて子供達に聞かせる。
ところが、「もういい」、と鐵舟に遮られてしまった。
そして、こう言われるのです。
「お前の話はうまい。うまいが舌で語るから、話が死んでおる。
私は3つの頃から母に毎晩、桃太郎の話を聞かされた。それでも、飽きなかった。それは、母の話は生きておったからだ」
円朝は絶句して、家に戻り、
『ふざけるな、鐵舟の馬鹿野郎』と大声で叫んだそうです。
円朝は悔しがって、それから、『桃太郎』を手直しして創作落語として演じるようになると、それが人気を呼び、ますます人気者になっていった。
しかし、彼の頭の中では、舌で話しているからダメだといった鐵舟の言葉が引っかかって離れない。
とうとう我慢できなくなって、
全生庵に鐵舟を訪ねて、
「どうか弟子にしてください。どうしたら、舌を使わないで話ができるようになるのでしょうか?」
そして、それから2年の間、円朝は無心になって座禅を組み、修業しました。
そして、明治13年のある日、鐵舟の侍医(お抱え医師)千葉立造の新居披露宴の席で、鐵舟がいる前で、『桃太郎』を演じる機会を得ます。
じっと聞いていた鐵舟は、同席していた滴水和尚(天龍寺)に、2年の修業を終えて、ここまできました、号を与えてやってください、というと、滴水和尚が書いてくれたのが
『無舌居士』
全生庵に今もある円朝の墓石には、だから、三遊亭円朝無舌居士と彫られています。
そして、その横に、彼の辞世の句である
『耳しひて 聞き定めけり 露の音』
(聴力を失って、初めて音を聞く)が彫られています。(★写真)
・・・円朝は69歳で亡くなりましたが、後年は進行性の麻痺にかかっていて、難聴だったそうです。
こうしてみてくると、この円朝の『桃太郎』をぜひ、聞いてみたいと思うのですが、残念ながら、その声は残っていません。
円朝が死んだのが、1900年(明治33年)、NHKが放送用にDENON(電音)に録音機の一号機を作らせたのが1939年(昭和14年)です。
そこで、多分、円朝の『桃太郎』とは違うと思うのですが、去年亡くなった桂米朝の『桃太郎』がありますので、それを聞いてから、芥川龍之介の『桃太郎』を朗読したいと思います。
これも、映像はなくて、音声だけです。『桃太郎』という昔話の意味がとてもよくわかると思います。(★桂米朝音声)
芥川龍之介の『桃太郎』を読む。
★
昔むかしの大昔、ある深い山の奥に、1本の大きな桃の木がありました。
そして、その実が元気な赤ん坊を生み、ある老夫婦に拾われたのは、皆さん、よくご存知のことと思います。
そして、その赤ん坊が立派に成長したある日のこと、
「爺さん、婆さん、世話になったな。
俺は鬼の成敗に行ってくる。
山だの、川だの、畑だの、ちまちま働くのは、性に合わん」
老夫婦は、それを聞いて、大喜びしました。
日頃から、桃太郎のわんぱくに、愛想をつかしていたのです。
一刻も早く追い出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは云うなり次第に持たせることにした。のみならず途中の兵糧には、これも桃太郎の註文通り、黍団子さえこしらえてやったのである。
桃太郎は意気揚々と鬼が島征伐の途に上った。すると大きい野良犬が一匹、饑えた眼を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。
「桃太郎さん。桃太郎さん。お腰に下げたのは何でございます?」
「これは日本一の黍団子だ。」
桃太郎は得意そうに返事をした。勿論実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は黍団子と聞くと、たちまち彼の側へ歩み寄った。
「一つ下さい。お伴しましょう。」
桃太郎は咄嗟に算盤を取った。
「一つはやられぬ。半分やろう。」
犬はしばらく強情に、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃太郎は何といっても「半分やろう」を撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである。犬もとうとう嘆息しながら、黍団子を半分貰う代りに、桃太郎の伴をすることになった。
桃太郎はその後犬のほかにも、やはり黍団子の半分を餌食に、猿や雉を家来にした。しかし彼等は残念ながら、あまり仲の好い間がらではない。丈夫な牙を持った犬は意気地のない猿を莫迦にする。黍団子の勘定に素早
い猿はもっともらしい雉を莫迦にする。地震学などにも通じた雉は頭の鈍
い犬を莫迦にする。――こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼等を家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。
その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうも黍団子の半分くらいでは、鬼が島征伐の伴をするのも考え物だといい出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし雉がとめなかったとすれば、猿は蟹の仇打ちを待たず、この時もう死んでいたかも知れない。しかし雉は犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと云った。それでも猿は路ばたの木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易に雉の言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使いわざと冷かにいい放した。
「よしよし、では伴をするな。その代り鬼が島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。」
欲の深い猿は円い眼をした。
「宝物? へええ、鬼が島には宝物があるのですか?」
「あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打出の小槌という宝物さえある。」
「ではその打出の小槌から、幾つもまた打出の小槌を振り出せば、一度に何でも手にはいる訣ですね。それは耳よりな話です。どうかわたしもつれて行って下さい。」
桃太郎はもう一度彼等を伴に、鬼が島征伐の途を急いだ。
★
鬼が島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだった訣ではない。実は椰子の聳えたり、極楽鳥の囀ったりする、美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を享けた鬼は勿論平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも享楽的に出来上った種族らしい。
・・・・・
鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、頗る安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も機を織ったり、酒を醸したり、蘭の花束を拵えたり、我々人間の妻や娘と少しも変らずに暮らしていた。殊にもう髪の白い、牙の脱けた鬼の母はいつも孫の守りをしながら、我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。――
「お前たちも悪戯をすると、人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒顛童子のように、きっと殺されてしまうのだからね。え、人間というものかい? 人間というものは角の生えない、生白い顔や手足をした、何ともいわれず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすっているのだよ。それだけならばまだ好いのだがね。男でも女でも同じように、はいうし、欲は深いし、焼餅は焼くし、己惚は強いし、仲間同志殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのない毛だものなのだよ……」
★
桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、「人間が来たぞ」と叫びながら、亭々と聳えた椰子の間を右往左往に逃げ惑った。
「進め! 進め! 鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ!」
桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿雉の三匹に号令した。犬猿雉の三匹は仲の好い家来ではなかったかも知れない。が、饑えた動物ほど、忠勇無双の兵卒の資格を具えているものはないはずである。彼等は皆あらしのように、逃げまわる鬼を追いまわした。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。雉も鋭い嘴に鬼の子供を突き殺した。猿も――猿は我々人間と親類同志の間がらだけに、鬼の娘を絞殺す前に、必ず凌辱を恣にした。……
あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は、命をとりとめた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼が島はもう昨日のように、極楽鳥の囀る楽土ではない。椰子の林は至るところに鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に、三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の酋長へ厳かにこういい渡した。
「では格別の憐愍により、貴様たちの命は赦してやる。その代りに鬼が島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。」
「はい、献上致します。」
「なおそのほかに貴様の子供を人質のためにさし出すのだぞ。」
「それも承知致しました。」
鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
「わたくしどもはあなた様に何か無礼でも致したため、御征伐を受けたことと存じて居ります。しかし実はわたくしを始め、鬼が島の鬼はあなた様にどういう無礼を致したのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明し下さる訣には参りますまいか?」
桃太郎は悠然と頷いた。
「日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹の忠義者を召し抱えた故、鬼が島へ征伐に来たのだ。」
「ではそのお三かたをお召し抱えなすったのはどういう訣でございますか?」
「それはもとより鬼が島を征伐したいと志した故、黍団子をやっても召し抱えたのだ。――どうだ? これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺してしまうぞ。」
鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後へ飛び下ると、いよいよまた丁寧にお時儀をした。
★
日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、得々と故郷へ凱旋した。――これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送った訣ではない。鬼の子供は一人前になると番人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼が島へ逐電した。のみならず鬼が島に生き残った鬼は時々海を渡って来ては、桃太郎の屋形へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に嘆息を洩らさずにはいられなかった。
「どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。」
「やっと命を助けて頂いた御主人の大恩さえ忘れるとは怪しからぬ奴等でございます。」
犬も桃太郎の渋面を見ると、口惜しそうにいつも唸ったものである。
その間も寂しい鬼が島の磯には、美しい熱帯の月明りを浴びた鬼の若者が五六人、鬼が島の独立を計画するため、椰子の実に爆弾を仕こんでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を赫かせながら。……
2016年4月23日(土)於:ギャラリー60
テーマ:芥川龍之介『桃太郎』を読む
今日は芥川龍之介の『桃太郎』を読みますが、最初に『桃太郎』の話を確認しておきたいと思います。。
これから写すのは、絵本ムービーです。(★ビデオ)
みなさんの、覚えている『桃太郎』も、この通りでしたか?
多分、同じはずですが、
実は、これは明治20年に国定教科書に掲載されてかららしいのです。
それまでは、いろいろな『桃太郎』が語られていました。四国の香川の方では、桃太郎は女の子で、あまりのかわいらしさに鬼が連れて行ってしまわないように男の子の名前にして育てたことになっていたそうですし、お供になった猿、犬、雉も、地方によっては、カニや臼、卵、水桶なのだったらしいのです。
それから、今の『桃太郎』とは、
3つ、大きな違いがあったようなんです。
(1つは)流れてきた桃は普通の大きさの桃だった。
一つ食べたおばあさんが、おじいさんのために、一つ持って帰った。おじいさんが芝刈りから戻ると、若返ったおばあさん。おじいさんも食べると若返り、子供のなかった二人に赤ん坊が生まれた。
(2つは)3年寝太郎のように、力持ちで大きな体だったが、怠け者で寝てばかり。おじいさんたちも、持て余していた。
(3つは)戦装束など(日の丸の鉢巻、陣羽織、ノボリを立ててえ出陣)していなかったし、動物も道連れになっただけで、上下(主従)関係はなかった。
この昔の『桃太郎』を実際に聞いたという人に、本当か、確かめたかったのですが、明治20年生まれといえば今年139歳ですから、もう確かめようがないのです。
それから、『桃太郎』といえば、落語にも同名の出し物があって、多くの落語家に演じられています。
その最初の『桃太郎』を演じたのが、江戸から明治にかけて活躍した三遊亭円朝だったんです。
この円朝という人は、現代まで続く落語の中興の祖と言われている人です。とにかく話がうまくて、あまりの巧さに嫉妬され、師匠の圓生から妨害を受けた。具体的には、圓朝が演ずるであろう演目を圓生らが先回りして演じ、圓朝の演ずる演目をなくしてしまう。たまりかねた圓朝は自作の演目(これなら他人が演ずることはできない)を口演するようになり、多数の新作落語を創作した、と言われています。
その円朝が、ある日、知り合いの集まりに招かれた時、
『何か一つやってくれないか』と声がかかります。
ところが、あるお偉いさんらしい人が、『桃太郎』が聞きたいと言う。
何で、この俺が桃太郎のような昔話をしなきゃならないんだ、冗談じゃない、俺を馬鹿にしているのか、と思った円朝は、即座に席を立ってしまった。
ところが、その人物が山岡鐵舟と知った円朝は、大人気なかったと全生庵に鐵舟を訪ねて、ぜひ聞いていただきたいとお願いする。すると、遊んでいた子供を集めて、ぜひあの子たちに『桃太郎』を聞かせてやってくれと言われた。
山岡鉄舟という人は、江戸無血開城を決した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立って、勝から全権を委任されて駿府に乗り込んで無血開城への道を開いたという人物です。明治維新後、無刀流の開祖となった人で、また西郷からの求めによって10年間明治天皇の侍従を務めました。そして、その後、谷中に全生庵という臨済宗の寺を建てて、維新で没した士族を弔ったという人です。
当時、すでに世間では名人と言われ、名を成していた円朝は、内心ムッとしながらも、再びケツをまくって帰るわけにも行かなかった。
そこで円朝は、それこそ一世一代の『桃太郎』を聞かせてやろうじゃないかと、腕によりをっけて子供達に聞かせる。
ところが、「もういい」、と鐵舟に遮られてしまった。
そして、こう言われるのです。
「お前の話はうまい。うまいが舌で語るから、話が死んでおる。
私は3つの頃から母に毎晩、桃太郎の話を聞かされた。それでも、飽きなかった。それは、母の話は生きておったからだ」
円朝は絶句して、家に戻り、
『ふざけるな、鐵舟の馬鹿野郎』と大声で叫んだそうです。
円朝は悔しがって、それから、『桃太郎』を手直しして創作落語として演じるようになると、それが人気を呼び、ますます人気者になっていった。
しかし、彼の頭の中では、舌で話しているからダメだといった鐵舟の言葉が引っかかって離れない。
とうとう我慢できなくなって、
全生庵に鐵舟を訪ねて、
「どうか弟子にしてください。どうしたら、舌を使わないで話ができるようになるのでしょうか?」
そして、それから2年の間、円朝は無心になって座禅を組み、修業しました。
そして、明治13年のある日、鐵舟の侍医(お抱え医師)千葉立造の新居披露宴の席で、鐵舟がいる前で、『桃太郎』を演じる機会を得ます。
じっと聞いていた鐵舟は、同席していた滴水和尚(天龍寺)に、2年の修業を終えて、ここまできました、号を与えてやってください、というと、滴水和尚が書いてくれたのが
『無舌居士』
全生庵に今もある円朝の墓石には、だから、三遊亭円朝無舌居士と彫られています。
そして、その横に、彼の辞世の句である
『耳しひて 聞き定めけり 露の音』
(聴力を失って、初めて音を聞く)が彫られています。(★写真)
・・・円朝は69歳で亡くなりましたが、後年は進行性の麻痺にかかっていて、難聴だったそうです。
こうしてみてくると、この円朝の『桃太郎』をぜひ、聞いてみたいと思うのですが、残念ながら、その声は残っていません。
円朝が死んだのが、1900年(明治33年)、NHKが放送用にDENON(電音)に録音機の一号機を作らせたのが1939年(昭和14年)です。
そこで、多分、円朝の『桃太郎』とは違うと思うのですが、去年亡くなった桂米朝の『桃太郎』がありますので、それを聞いてから、芥川龍之介の『桃太郎』を朗読したいと思います。
これも、映像はなくて、音声だけです。『桃太郎』という昔話の意味がとてもよくわかると思います。(★桂米朝音声)
芥川龍之介の『桃太郎』を読む。
★
昔むかしの大昔、ある深い山の奥に、1本の大きな桃の木がありました。
そして、その実が元気な赤ん坊を生み、ある老夫婦に拾われたのは、皆さん、よくご存知のことと思います。
そして、その赤ん坊が立派に成長したある日のこと、
「爺さん、婆さん、世話になったな。
俺は鬼の成敗に行ってくる。
山だの、川だの、畑だの、ちまちま働くのは、性に合わん」
老夫婦は、それを聞いて、大喜びしました。
日頃から、桃太郎のわんぱくに、愛想をつかしていたのです。
一刻も早く追い出したさに旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは云うなり次第に持たせることにした。のみならず途中の兵糧には、これも桃太郎の註文通り、黍団子さえこしらえてやったのである。
桃太郎は意気揚々と鬼が島征伐の途に上った。すると大きい野良犬が一匹、饑えた眼を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。
「桃太郎さん。桃太郎さん。お腰に下げたのは何でございます?」
「これは日本一の黍団子だ。」
桃太郎は得意そうに返事をした。勿論実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬は黍団子と聞くと、たちまち彼の側へ歩み寄った。
「一つ下さい。お伴しましょう。」
桃太郎は咄嗟に算盤を取った。
「一つはやられぬ。半分やろう。」
犬はしばらく強情に、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃太郎は何といっても「半分やろう」を撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである。犬もとうとう嘆息しながら、黍団子を半分貰う代りに、桃太郎の伴をすることになった。
桃太郎はその後犬のほかにも、やはり黍団子の半分を餌食に、猿や雉を家来にした。しかし彼等は残念ながら、あまり仲の好い間がらではない。丈夫な牙を持った犬は意気地のない猿を莫迦にする。黍団子の勘定に素早
い猿はもっともらしい雉を莫迦にする。地震学などにも通じた雉は頭の鈍
い犬を莫迦にする。――こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼等を家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。
その上猿は腹が張ると、たちまち不服を唱え出した。どうも黍団子の半分くらいでは、鬼が島征伐の伴をするのも考え物だといい出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もし雉がとめなかったとすれば、猿は蟹の仇打ちを待たず、この時もう死んでいたかも知れない。しかし雉は犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと云った。それでも猿は路ばたの木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易に雉の言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使いわざと冷かにいい放した。
「よしよし、では伴をするな。その代り鬼が島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。」
欲の深い猿は円い眼をした。
「宝物? へええ、鬼が島には宝物があるのですか?」
「あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打出の小槌という宝物さえある。」
「ではその打出の小槌から、幾つもまた打出の小槌を振り出せば、一度に何でも手にはいる訣ですね。それは耳よりな話です。どうかわたしもつれて行って下さい。」
桃太郎はもう一度彼等を伴に、鬼が島征伐の途を急いだ。
★
鬼が島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだった訣ではない。実は椰子の聳えたり、極楽鳥の囀ったりする、美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を享けた鬼は勿論平和を愛していた。いや、鬼というものは元来我々人間よりも享楽的に出来上った種族らしい。
・・・・・
鬼は熱帯的風景の中に琴を弾いたり踊りを踊ったり、古代の詩人の詩を歌ったり、頗る安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も機を織ったり、酒を醸したり、蘭の花束を拵えたり、我々人間の妻や娘と少しも変らずに暮らしていた。殊にもう髪の白い、牙の脱けた鬼の母はいつも孫の守りをしながら、我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。――
「お前たちも悪戯をすると、人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼はあの昔の酒顛童子のように、きっと殺されてしまうのだからね。え、人間というものかい? 人間というものは角の生えない、生白い顔や手足をした、何ともいわれず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ一面に鉛の粉をなすっているのだよ。それだけならばまだ好いのだがね。男でも女でも同じように、はいうし、欲は深いし、焼餅は焼くし、己惚は強いし、仲間同志殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのない毛だものなのだよ……」
★
桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、「人間が来たぞ」と叫びながら、亭々と聳えた椰子の間を右往左往に逃げ惑った。
「進め! 進め! 鬼という鬼は見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ!」
桃太郎は桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿雉の三匹に号令した。犬猿雉の三匹は仲の好い家来ではなかったかも知れない。が、饑えた動物ほど、忠勇無双の兵卒の資格を具えているものはないはずである。彼等は皆あらしのように、逃げまわる鬼を追いまわした。犬はただ一噛みに鬼の若者を噛み殺した。雉も鋭い嘴に鬼の子供を突き殺した。猿も――猿は我々人間と親類同志の間がらだけに、鬼の娘を絞殺す前に、必ず凌辱を恣にした。……
あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の酋長は、命をとりとめた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼が島はもう昨日のように、極楽鳥の囀る楽土ではない。椰子の林は至るところに鬼の死骸を撒き散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に、三匹の家来を従えたまま、平蜘蛛のようになった鬼の酋長へ厳かにこういい渡した。
「では格別の憐愍により、貴様たちの命は赦してやる。その代りに鬼が島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。」
「はい、献上致します。」
「なおそのほかに貴様の子供を人質のためにさし出すのだぞ。」
「それも承知致しました。」
鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
「わたくしどもはあなた様に何か無礼でも致したため、御征伐を受けたことと存じて居ります。しかし実はわたくしを始め、鬼が島の鬼はあなた様にどういう無礼を致したのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明し下さる訣には参りますまいか?」
桃太郎は悠然と頷いた。
「日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹の忠義者を召し抱えた故、鬼が島へ征伐に来たのだ。」
「ではそのお三かたをお召し抱えなすったのはどういう訣でございますか?」
「それはもとより鬼が島を征伐したいと志した故、黍団子をやっても召し抱えたのだ。――どうだ? これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺してしまうぞ。」
鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後へ飛び下ると、いよいよまた丁寧にお時儀をした。
★
日本一の桃太郎は犬猿雉の三匹と、人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、得々と故郷へ凱旋した。――これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送った訣ではない。鬼の子供は一人前になると番人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼が島へ逐電した。のみならず鬼が島に生き残った鬼は時々海を渡って来ては、桃太郎の屋形へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に嘆息を洩らさずにはいられなかった。
「どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。」
「やっと命を助けて頂いた御主人の大恩さえ忘れるとは怪しからぬ奴等でございます。」
犬も桃太郎の渋面を見ると、口惜しそうにいつも唸ったものである。
その間も寂しい鬼が島の磯には、美しい熱帯の月明りを浴びた鬼の若者が五六人、鬼が島の独立を計画するため、椰子の実に爆弾を仕こんでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を赫かせながら。……