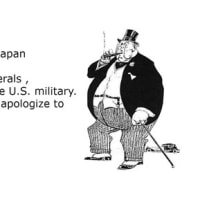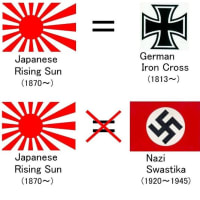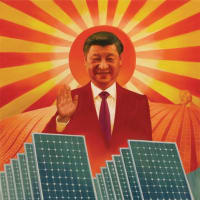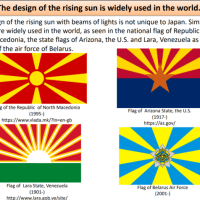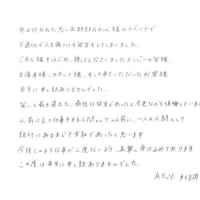The White Knight
1k
378
95
Nicholas Kristof wants to save the world with his New York Times columns. Why are so many of them wrong?
By Amanda Hess
JUNE 18 2014 11:53 PM
via mozu
1k
378
95
Nicholas Kristof wants to save the world with his New York Times columns. Why are so many of them wrong?
By Amanda Hess
JUNE 18 2014 11:53 PM
via mozu
Kristof feels lousy when he has to “cut somebody off and say, ‘It's terrible that you were shot in the leg,’ ” he said. “Meanwhile, I will go off and find someone who was shot in both legs.” But he does it because he knows that if he finds a compelling story abroad, Americans back home will line up to help.
“One death is a tragedy,” he told the students, “and a million deaths are a statistic.”
But typically, “my protagonist will be some American … who’s off in the middle of nowhere. The reason is that it's an awful lot easier to get readers to read about a New Yorker who is off in Haiti than a Haitian who’s doing good work in Haiti.”
when he was criticized for publishing the name and photograph of a child rape victim in 2010, he insisted that “if we leave out names and faces, then there’s no outrage, and the rapes go on and on.”
In short, stories have the power to change the world. “One risk,” he told the Columbia students, “is that I’ll prove wrong―which I do, periodically.” Kristof understands that not every sad story is true. “I’ve learned when to be more suspicious of people,” Kristof said in Reporter, a documentary on his work. “I think there’s a tendency to believe victims, for example. And I think that’s wrong―that in fact victims can lie as much as other people.” That was in 2009.
“It’s a beautiful story, and a lie,”
“Greg’s books may or may not have been fictionalized, but there’s nothing imaginary about the way some of his American donors and Afghan villagers were able to put aside their differences and prejudices and cooperate to build schools―and a better world,” he wrote. “
he cycle repeated itself again last month.
“In worst cases, the truth is distorted or the stories invented to attract more compassion and money.
But it also means that the most effective mechanisms for improving the conditions in these countries are overlooked in favor of those proffered by boot-strapping Western heroes. “The idea that comes across is that nobody is advocating for these people before the bridge character comes along, and that really diminishes the work of people on the ground,” Seay told me. “There’s a limited amount of political capital that can be spent. And if you spend it on the wrong thing, you don’t always get another chance.”
“Radhika’s story is a work of fiction,” the game’s fine print reads. “Reality is much harsher, and issues are never so easy to fix.”
クリストフというのは、日本について、変態日本論を書き始めたはしりみたいな記者かもしれませんが、わりにアメリカでは尊敬されている。それには、どうも、記事の型があるらしい。
アメリカ人読者の同情を買うために、アメリカ人が、未開の国で、ひどく虐待されている弱者と出会い、彼女らを救う、という線にそって記事を書くんだそうですーーー救済者幻想ーーーいや、妄想ですね。
で、そうした型に、無理にはめ込んでしまうせいか、後になって、そうした犠牲者の物語が作り話であったことも多い、と。
また、西洋人”英雄”の介入によって、さらに、現地の人々が改革しようとしている努力を無駄にしてしまう危険もある、と。
今回の都議によるセクハラ発言でも、単純に上から目線の記事と、大衆から抗議活動が盛り上がってきた、というところに着目している記事ではその視点が違うんです。
アメリカでは人種差別がめちゃくちゃひどい、ということだけを強調するのと、それと同時に、差別に対する抗議運動も盛んである、ということも強調する記事が全く違うの同じことです。
前者はこれはこれで一つの差別主義的な視線ですが、後者は、大衆や庶民の力を認め、人々に力を与えている視線なわけです。
タブチとかそこらへんの記者たちは日本の大衆や男女を非人間的にとらえているわけです。
まあ、いずれにせよ、アメリカ人というのは、キリスト教の影響なのか、アメリカ例外主義のせいか、この手のアメリカ人救済者の話にエクスタシーを感じる人がおおいわけですね。
クリストフ だけじゃなくて、救済者妄想を抱いたコラムニスト、英米人というのは意外に多い。
有道のブログに、たむろしていた若い衆なんぞも、遅れていると信じている日本に来て、男女平等や人権概念を教え込んでやろうと努力していると信じている有道を英雄視して、あこがれているのが何人かいたが、この手の英米人の植民地主義的態度というのは、英米で普通に生活していると身についてしまうものなのだろうか?
もっとも、日本人でもアジア、アフリカ地域出身者を馬鹿にして、えらそうなことほざく輩がいるから、アメリカ特有とはいえないかもしれない。 、国際社会の現実の支配関係というか、階級意識みたいなものを反映しているのかもしれない。
ただ、そんな日本人の場合は、レイシストと非難されるけれども、植民地主義的態度をもった英米人は、救済者として、他の英米人のあこがれになってしまう場合が多いのである。
そして、クリストフや有道など、救済者幻想を抱くアメリカ人コラムニストに共通しているのは、アメリカ人、アメリカ兵が加害者である物語であってはならない、ということである。
1人の犠牲者がそんなにインパクトがあるならば、無人機で殺された子供たちの家族の記事を書いて、無人機爆撃をやめさせるのがスジであろうし、米兵にいたぶられた韓国人性奴隷や、レイプ被害者の話がクリストフやファクラーからたぶん期待できないであろう。
それは一つのタブーであるかのようであり、たぶん、愛国心の強い、彼らと彼らの読者のナルチズムを逆なでしてしまうのではなかろうか?
いずれにせよ、日本出身でも英米出身でも、謙虚な気持ちをもって、こうした態度から脱却したいものだ。