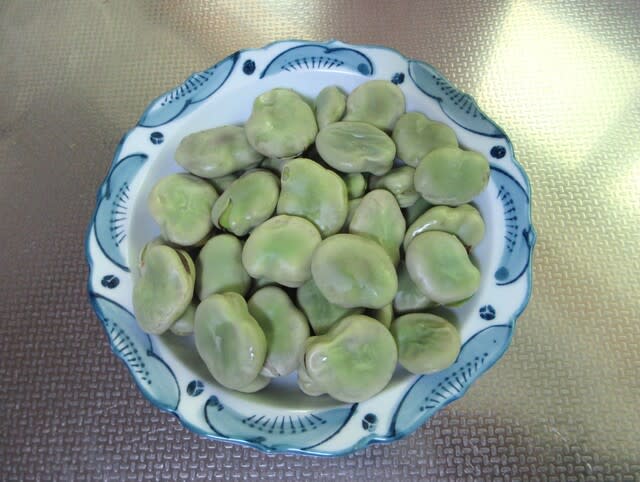昨年は気温が高く生育が進み、お盆の時には大半が終わってしまったので今年は少し遅らせました。
品種は1回目と同じ「ゴールドラッシュ」。
この品種の収穫期までの標準日数どおり逆算しての種まきです。例年は若干早めに播いています。
畝間は広めの1m、株間は30㎝。

種播きは小生我流の直播き法。結果、今回は非常に良好な発芽でした。
タイミング良く降雨があり気温も高かったことが幸いしたようです。
3粒播きにしましたが、殆どが3本とも発芽し、全てが2本以上の発芽で欠株はありません。

生育も順調ですでに本葉7、8枚に達しています。

少し遅くなりましたが、ここで間引きし、土入れを行います。
まず2本に間引きします。引き抜かずに鋏で根元からちょん切ります。

通常は大きなトウモロコシを穫るため1本立てにするのが常道です。
小生は大型のトウモロコシより本数確保優先。中型のトウモロコシを多く穫ることを目標にしています。
そのため、畝間を広くして2本立てにします。
今回は2本立てが100%となりました。7割以上なら合格点なので想定以上です。

この後は土入れです。
移植ベラで根元に周りの土を寄せてやります。

マルチを剥いで土寄せをすれば良いところかもしれませんが、最後まで張りっぱなしにします。

その代わりになるかは不明ながら不定根を増やすことを期待しています。

ここまで気温が高いため想定より進んでいる気がしますが、お盆に上手く合いますか。
こちらは1回目のトウモロコシ。

雄穂が出揃ってきました。

収穫の目標は7月下旬、7月25日くらいを目安にしていますが、早まりそうな気配です。