このほど「文遊社」から「変容する都市のゆくえ 複眼の都市論」三浦倫平・竹岡暢 編著が出版された。帯に「あの街は変わった」ーーーそれは本当だろうか? 「沖縄の基地都市、東京の下町・歌舞伎町、下北沢、渋谷の大規模開発、さいたま、丸の内・東京駅、多摩ニュータウン、、、、目にみえる「変容」と「不変」を疑い、その背後に何が起きているかを問う。
この本に『「村の記録」のなかの都市ーーーテレビドキュメンタリーに描かれた農村の変容』が収録されている。

「序」で三浦・竹岡氏は「執筆者の選定に当たっては「日本のある特定の場所について 都市/街/風景の変容 というテーマで、事実を積み重ねた記述によって論じることが出来る」という基準を採用し多様な専門分野からの参加を得られるように心がけた。、、、必ずしも「都市」そのものを直接取り上げている論考ばかりではない。捉成保志ほか『「村の記録」のなかの都市』は農村から都市を相対化する視点を提供しており、都市を見る私たちの想像力を大いに刺激してくれるだろう。と記している。
総ページ数383の大作の中で『「村の記録」なかの都市』は349ページから378ページまでの29ページにある。
 349ページ
349ページ
そして『「減反詩集」はどのように作られたか』363ページから378ぺージの15ページの詳細な書かれている。
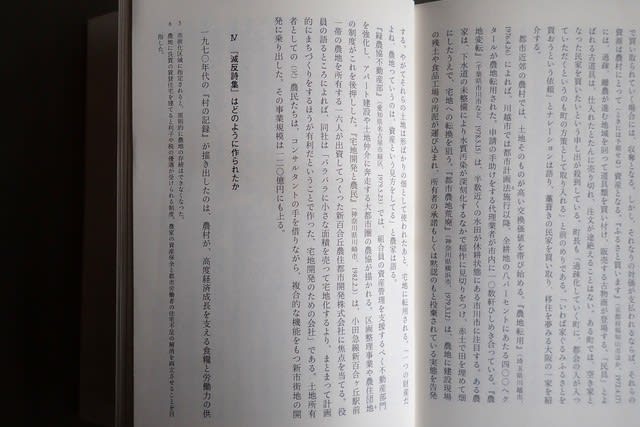 363ページ
363ページ
約47年前のNHkの放送記録。その記録は私の20代頃からの小さな歴史の一端に踏み込んでいた。読ませてもらって猛烈に懐かしさが込み上げてきた。
 375ページ
375ページ
映像の「減反詩集」の背景をつぶさに追跡した姿に格別ともいえる共感を持った。特に「山脈の会」への記述は圧巻だった。20歳前後に「農業秋田」誌に出てくる「鈴木元彦」氏の発言に注目。秋田魁新報の詩壇、詩誌「密造者」に出てくる鈴木元彦の詩等にくぎ付けになっていた。
月刊「農業秋田」は、農業技術の普及雑誌で、国や県の農政の重点施策などを農家に伝えるとともに、農業技術などの情報提供にあたってきた。
昭和二十三年、農業技術の普及と農村生活の改善の指導に当たる農業改良普及員制度が設けられた。約百六十余人にのぼる普及員は、農家のよりよい助言者となるため、相互の連絡を密にして研究錬磨に努めようと、秋田県改良普及員協会を二十五年に結成。同年七月に、会員の機関紙を兼ねて全県の農家を対象とする月刊誌『農業あきた』を創刊したのである。
翌二十六年四月号から現在の名称になり、三十六年八月号からは同協会が組織する「農業秋田友の会」が発行している。雑誌の内容は生産技術、経営技術や農家の生活改善など広い分野に及び、技術普及に力点が置かれていたが農業の取り巻く情勢に立ち向かう姿勢を暗示させる記事もあった。
私は20歳前からこの情報誌を知っていて、農業技術はもとより鈴木元彦氏の蘊蓄に富んだ投稿を常に心待ちして読んでいた。そして当時、伯父のところに「鶴田知也」氏が時々来ており、伯父は我家にも鶴田知也氏を連れてきた。
昭和20年5月、鶴田知也氏は伊藤
そして、農民文学や農民詩のつながりで鈴木元彦氏を知り、白鳥邦夫氏主宰の「山脈の会」、「無名の日本人」を知る。白鳥邦夫著「無名の日本人」(1961)を探しに約10キロの雪道を歩いて湯沢の本屋に出向き店主に頼み込んで求めたのは1963年ころだった。1964年仲間10人で「農業経営をよくする会」を設立。67年に「稲川農業問題研究会」の名称変更。1970年の「第7回稲川農業問題研究会」に初めて鈴木元彦氏に出席要請、県北能代から駆けつけてくれた。これが私と鈴木元彦氏との初めての出会い。その後鈴木元彦氏と晩年まで交流が続いた。この顛末記はいずれ振り返ってみたい。
この度、文遊社出版の「変容する都市のゆくえ 複眼の都市論」の中で、「村の中の都市」の項がどういう位置づけになるのか等は私的には少し複雑な想いもある。第三者の評価があれば今後の糧としたい。
捉成・船戸・武田・加藤の⒋氏が自宅を訪問調査は2015年。長期に分析調査し今回「変容する都市のゆくえ 複眼の都市論」に取り上げていただいたことに感謝したい。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます