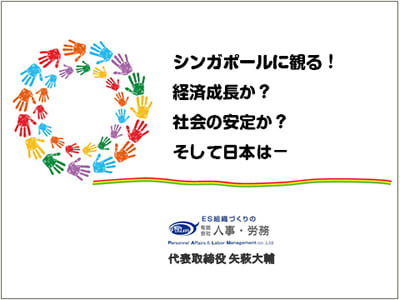パネルディスカッション後のワールドカフェでは、皆さんから、
「下町の未来のはたらくを考える」というテーマでたくさんの創発
が起こりました。

産学官で、台東区の雇用の問題を考えて行こう!
これから、沢山の外国人の方が、日本に観光にそして、居住
することが見込まれているが、日本は、今後どのように
動いていけばいいのか、若い人がどんどん地元から減っていくが、
新参者も地域とのつながりをつくるような取り組みを進めていく
ことは、必要ではないか?

次世代の産業を担う、若者を10年先を見据えて育てていかなくては
ならない。行政任せでなく、自分たちの力で課題を解決していかなくては
などの気づきを皆で共感できたことがよかったなあと思いました。
今回パネリストになっていただいた方々は、
地域を良くしていこうという社会的意識が高く、本業をとおして、
そこに、共感した方が、かかわり、一緒になって
モノづくりを進めているのです。
今回のパネリストの浜野製作所さんの取り組みは参考になります。
浜野製作所は、日本のモノづくりを絶やしてはいけない!
という思いから、「ものづくりインキュベーションを加速する」というコンセプトのもと、
オープンイノベーションな新たな連携を、テックプランターというプラットフォームを
創りだしています。
モノづくりを志す人の、育成から、発掘、登記、試作、投資までを、
さまざまな企業が連携して、これからの日本に必要な価値を創造しているのです。
このような価値は、もちろん、浜野製作所さん、1社ではできないことです。
さて、この取り組みを通して、浜野製作所さんに何が起きたか?
約、200件近い、新たなつながりが出来たのです。

浜野製作所さんは、CSR×オープンイノベーション(ソーシャルイノベーティブ)な取り組みをしたから、
業績が伸びたのでしょうか?
そこにはちょっと違いがあります。私の見てきた事例でも、NPOや企業と連携して、積極的にCSR活動を
行い、地域のために頑張っている企業がありますが、多くの会社は失敗します。
長く続かないのです。浜野製作所さんとその方との違いは、同じソーシャルイノベーションの
取り組みをしているのになぜか、業績が上がらないのです。

そこには、オープンイノベーションを後者の企業は、そのものを、目的にしてしまっているのです。
オープンイノベーションは、手段です。目的は、価値の創造と獲得です。
浜野製作所さんが、優れた成果を達成しているのは、オープンイノベーションを実施
しているからでなく、浜野製作所さんが、「価値の創造と獲得のための社内体制」を
もっているからであり、オープンイノベーションは、そのための一要素なのです。
浜野製作所さんは、テックプランターというプラットフォームの中で、
試作を受け持つという優位性を築いています。
浜野製作所さんの、独自の強みがあり、そこに自信があるからこそ他社との連携が
組めるのです。
今回、浜野製作所さんから、学んだことは、CSR、オープン化を実現するためには、
オープン化によってどんな戦略目標を実現するのかをまず明確にすることなのだなあと
思うのです。
そして、その前に、コアな技術は製造は自ら開発し続けるということなしには、
オープン化はできないのです。
「下町の未来のはたらくを考える」というテーマでたくさんの創発
が起こりました。

産学官で、台東区の雇用の問題を考えて行こう!
これから、沢山の外国人の方が、日本に観光にそして、居住
することが見込まれているが、日本は、今後どのように
動いていけばいいのか、若い人がどんどん地元から減っていくが、
新参者も地域とのつながりをつくるような取り組みを進めていく
ことは、必要ではないか?

次世代の産業を担う、若者を10年先を見据えて育てていかなくては
ならない。行政任せでなく、自分たちの力で課題を解決していかなくては
などの気づきを皆で共感できたことがよかったなあと思いました。
今回パネリストになっていただいた方々は、
地域を良くしていこうという社会的意識が高く、本業をとおして、
そこに、共感した方が、かかわり、一緒になって
モノづくりを進めているのです。
今回のパネリストの浜野製作所さんの取り組みは参考になります。
浜野製作所は、日本のモノづくりを絶やしてはいけない!
という思いから、「ものづくりインキュベーションを加速する」というコンセプトのもと、
オープンイノベーションな新たな連携を、テックプランターというプラットフォームを
創りだしています。
モノづくりを志す人の、育成から、発掘、登記、試作、投資までを、
さまざまな企業が連携して、これからの日本に必要な価値を創造しているのです。
このような価値は、もちろん、浜野製作所さん、1社ではできないことです。
さて、この取り組みを通して、浜野製作所さんに何が起きたか?
約、200件近い、新たなつながりが出来たのです。

浜野製作所さんは、CSR×オープンイノベーション(ソーシャルイノベーティブ)な取り組みをしたから、
業績が伸びたのでしょうか?
そこにはちょっと違いがあります。私の見てきた事例でも、NPOや企業と連携して、積極的にCSR活動を
行い、地域のために頑張っている企業がありますが、多くの会社は失敗します。
長く続かないのです。浜野製作所さんとその方との違いは、同じソーシャルイノベーションの
取り組みをしているのになぜか、業績が上がらないのです。

そこには、オープンイノベーションを後者の企業は、そのものを、目的にしてしまっているのです。
オープンイノベーションは、手段です。目的は、価値の創造と獲得です。
浜野製作所さんが、優れた成果を達成しているのは、オープンイノベーションを実施
しているからでなく、浜野製作所さんが、「価値の創造と獲得のための社内体制」を
もっているからであり、オープンイノベーションは、そのための一要素なのです。
浜野製作所さんは、テックプランターというプラットフォームの中で、
試作を受け持つという優位性を築いています。
浜野製作所さんの、独自の強みがあり、そこに自信があるからこそ他社との連携が
組めるのです。
今回、浜野製作所さんから、学んだことは、CSR、オープン化を実現するためには、
オープン化によってどんな戦略目標を実現するのかをまず明確にすることなのだなあと
思うのです。
そして、その前に、コアな技術は製造は自ら開発し続けるということなしには、
オープン化はできないのです。