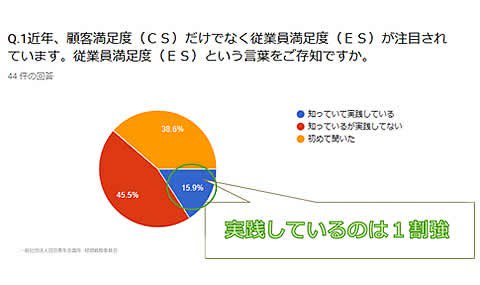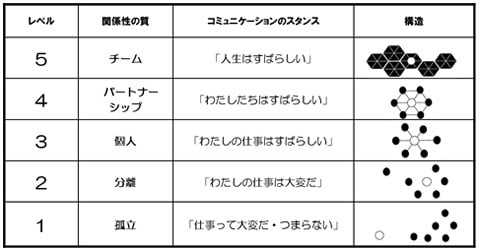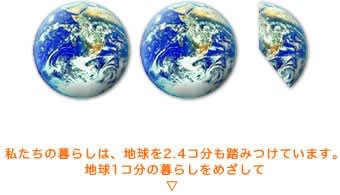有限会社人事・労務の20周年を記念して、弊社オリジナルブレンンドの紅茶をつくるにあたり、いつも大変お世話になっている世界のお茶の専門店 Y's tea の根本社長にお越しいただき、ブレストミーティングを実施いたしました。

いつも文字や言葉で理念を伝え、ファシリテーターとしてお客様に対応している私達ですが、今回は根本社長のファシリテーターの下、弊社の20周年の想いを紅茶という文字や言葉以外で表現するという試みです。

どんな紅茶になるか、私達も楽しみです。
さて、この日の前に、社内のメンバーに回答してもらっていたのがオリジナルブレンド紅茶をつくるにあたってのコンセプトシート。
まずは、各自ひとりひとり「うちの会社とは・・?」を考え、それがどのように紅茶に結び付くか、コンセプトをイメージしてから、この日のブレストミーティングに臨んでもらいました。
ブレストを進める上で、まずは3~4人のチームで自分の意見を出し合って、その後チームごとに発表し、出てきたキーワードをホワイトボードに羅列しながら、意見を出していきました。

うちを色で表すと何色?という質問に対して多く出た意見が
「オレンジ」。
色は同じでも理由がそれぞれ分かれ、
「あたたかさを感じる」
「太陽」「大地」「希望」
また、
「日光街道まるっと学び舎プロジェクトのジャンパーの色」という意見も!
理由をちゃんとつけて説明する、というのが大事だそうで、意見を出すうえで各自必ず添えて意見を出しました。

また、面白い!と思った色が「白」。
理由としては「変化できる。染まることができる。柔らかにする。」
コンサルする立場として、柔軟に、お客さんの色に染まることができる、というのは確かに弊社の強みのでもあるな、と思いました。
一方で、1色には決められない!オレンジとグリーンの“モザイク”で、ダイバーシティ―をイメージするメンバーも。
ダイバーシティ・多様性、という言葉は、うちらしさ、という点で共通したキーワードでもありました。

出てくる他のメンバーの意見を聞いていると、自分ひとりでイメージしていたものと違い、「あ~、なるほど」というもの、「え!!」というもの。
いろんな意見が出るも、想いの軸の部分は皆似ていて、それを共有できるのは、嬉しい瞬間でもありました。
その中からどの方向性でどのようにして紅茶というもので表現できるかを考えていくというのが難しいなと思いました。
ただ、まったく紅茶と結びつきそうもなかった私たちの意見が、徐々に根本社長のアドバイスにより、形が見えてきたように思えます。
田舎の縁側で日向ぼっこしているような雰囲気のフレーバー!太陽や土のにおい!など、到底紅茶とはイメージがかけ離れたフレーバーばかりあげてしまい根本社長を困らせてしまいつつも、そういった自由な意見が大事で、その背景にあるストーリーを深くしていって結び付けていく事が重要ということで、とにかく自由に意見交換を進めました。

今まで、フレーバーティーは香りと味を楽しんでいましたが、つくる上では、その果物がどこで採れたか、味や香りだけでなく、その果物が生まれた土地や環境についてまで考え、ストーリーにしていくということ。
例えば、リンゴであれば青森など寒い場所で採れるので北のイメージ、逆に南国で採れるものは暖かい、太陽を彷彿とさせる果物。
また、生姜やシナモンなどの“スパイス”とされるものを入れるとうちがイメージする“多様”とは逆に個性が強いので“個”のイメージとなり、単純にその味により好みが分かれやすいこともあり、万人受けしづらい、など、その素材やフレーバーの持つ力、というものも教えて頂きました。
そして、文字や言葉というのはもちろん大切ですが、大切なものやコトは、実は文字や言葉ではなかなかすべてを表現することはできない、五感で伝えていく大切さを今回の根本社長の芸術的なセンスで学びました。
弊社のクレドと共に大切な想いを紅茶で伝えたいと思います。
次のミーティングまでに宿題も課され、今度は味にフォーカスして意見をまとめていきます。
うちらしい紅茶、どんなフレーバーになるか??
皆さんもお楽しみに!!

いつも文字や言葉で理念を伝え、ファシリテーターとしてお客様に対応している私達ですが、今回は根本社長のファシリテーターの下、弊社の20周年の想いを紅茶という文字や言葉以外で表現するという試みです。

どんな紅茶になるか、私達も楽しみです。
さて、この日の前に、社内のメンバーに回答してもらっていたのがオリジナルブレンド紅茶をつくるにあたってのコンセプトシート。
まずは、各自ひとりひとり「うちの会社とは・・?」を考え、それがどのように紅茶に結び付くか、コンセプトをイメージしてから、この日のブレストミーティングに臨んでもらいました。
ブレストを進める上で、まずは3~4人のチームで自分の意見を出し合って、その後チームごとに発表し、出てきたキーワードをホワイトボードに羅列しながら、意見を出していきました。

うちを色で表すと何色?という質問に対して多く出た意見が
「オレンジ」。
色は同じでも理由がそれぞれ分かれ、
「あたたかさを感じる」
「太陽」「大地」「希望」
また、
「日光街道まるっと学び舎プロジェクトのジャンパーの色」という意見も!
理由をちゃんとつけて説明する、というのが大事だそうで、意見を出すうえで各自必ず添えて意見を出しました。

また、面白い!と思った色が「白」。
理由としては「変化できる。染まることができる。柔らかにする。」
コンサルする立場として、柔軟に、お客さんの色に染まることができる、というのは確かに弊社の強みのでもあるな、と思いました。
一方で、1色には決められない!オレンジとグリーンの“モザイク”で、ダイバーシティ―をイメージするメンバーも。
ダイバーシティ・多様性、という言葉は、うちらしさ、という点で共通したキーワードでもありました。

出てくる他のメンバーの意見を聞いていると、自分ひとりでイメージしていたものと違い、「あ~、なるほど」というもの、「え!!」というもの。
いろんな意見が出るも、想いの軸の部分は皆似ていて、それを共有できるのは、嬉しい瞬間でもありました。
その中からどの方向性でどのようにして紅茶というもので表現できるかを考えていくというのが難しいなと思いました。
ただ、まったく紅茶と結びつきそうもなかった私たちの意見が、徐々に根本社長のアドバイスにより、形が見えてきたように思えます。
田舎の縁側で日向ぼっこしているような雰囲気のフレーバー!太陽や土のにおい!など、到底紅茶とはイメージがかけ離れたフレーバーばかりあげてしまい根本社長を困らせてしまいつつも、そういった自由な意見が大事で、その背景にあるストーリーを深くしていって結び付けていく事が重要ということで、とにかく自由に意見交換を進めました。

今まで、フレーバーティーは香りと味を楽しんでいましたが、つくる上では、その果物がどこで採れたか、味や香りだけでなく、その果物が生まれた土地や環境についてまで考え、ストーリーにしていくということ。
例えば、リンゴであれば青森など寒い場所で採れるので北のイメージ、逆に南国で採れるものは暖かい、太陽を彷彿とさせる果物。
また、生姜やシナモンなどの“スパイス”とされるものを入れるとうちがイメージする“多様”とは逆に個性が強いので“個”のイメージとなり、単純にその味により好みが分かれやすいこともあり、万人受けしづらい、など、その素材やフレーバーの持つ力、というものも教えて頂きました。
そして、文字や言葉というのはもちろん大切ですが、大切なものやコトは、実は文字や言葉ではなかなかすべてを表現することはできない、五感で伝えていく大切さを今回の根本社長の芸術的なセンスで学びました。
弊社のクレドと共に大切な想いを紅茶で伝えたいと思います。
次のミーティングまでに宿題も課され、今度は味にフォーカスして意見をまとめていきます。
うちらしい紅茶、どんなフレーバーになるか??
皆さんもお楽しみに!!