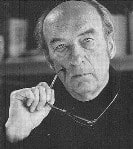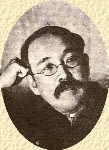「ある集団が禁欲的で高潔な理想に依拠している時代には、同時に激しい攻撃的傾向が高まり、それが内部、あるいは外部の敵(《反革命派の人びと》)に投射されるのが観察される。ひとたび偏見によって、敵の上に危険な連中だというレッテルが貼りつけられると、自分がもっている攻撃性は、合法的な正当防禦とされ、公然と発揮されることになる。」
(『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』)
A. ミッチャーリッヒ(Alexander Mitscherlich, 1908 - 82)
ドイツの心理学者。ハイデルベルク大学精神分析学・精神身体医学教授、フランクフルト大学心理学教授を歴任。1960年以来フロイト研究所所長を兼任。
戦後ドイツの精神分析学の中心的存在だが、心理学のみならず、社会学や動物行動学も議論の展開に応用するなど、幅広い観点を持っている。1969年には、ドイツ出版協会から平和賞を受賞した。
夫人は、心理学者のマーガレーテ・ミッチャーリッヒで、『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』は彼女との共著。
「ミッチャーリッヒ曲線」で知られるドイツ人化学者の A. ミッチャーリッヒ (1836 - 1918) とは同姓同名の別人。
上記引用の『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』は、ファシズムの社会心理学的考察。
過度に抑圧された「前社会的な状態に留まっている過剰な衝動の残余」が、時として、代償作用としてスケープ・ゴート(「犠牲の山羊」)を求めることになる、と説く。ここでは、ナチ体制下におけるユダヤ人排斥が主なテーマであるが、それ以外にさまざまな社会現象を、この原理で説明することができる。
前近代における日本社会では、「村八分」「憑き物筋」など、西洋においては「魔女狩り」など
また、現代においては、アメリカでの「赤狩り=マッカーシー旋風」、ソ連での「トロツキスト狩り」など。
外国人排斥(ゼノフォビア)などは、ほとんど、このパターンということができるだろう。
しかし、「禁欲的で高潔な理想に依拠している時代」ならざる現代においても、異質なものを排撃する傾向は、同じパターンを踏むようだ。
E. フロムの『自由からの逃走』と併せて読まれることをお勧めする。
参考資料 A .& M. ミッチャーリッヒ著、 林峻一郎/馬場謙一訳『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』(河出書房新社)
アレクサンダー・ミッチャーリヒ著、竹内豊治訳『攻撃する人間』(法政大学出版局)
A.ミッチャーリヒ著、小見山実訳『父親なき社会―社会心理学的思考―』(新泉社)
(『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』)
A. ミッチャーリッヒ(Alexander Mitscherlich, 1908 - 82)
ドイツの心理学者。ハイデルベルク大学精神分析学・精神身体医学教授、フランクフルト大学心理学教授を歴任。1960年以来フロイト研究所所長を兼任。
戦後ドイツの精神分析学の中心的存在だが、心理学のみならず、社会学や動物行動学も議論の展開に応用するなど、幅広い観点を持っている。1969年には、ドイツ出版協会から平和賞を受賞した。
夫人は、心理学者のマーガレーテ・ミッチャーリッヒで、『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』は彼女との共著。
「ミッチャーリッヒ曲線」で知られるドイツ人化学者の A. ミッチャーリッヒ (1836 - 1918) とは同姓同名の別人。
上記引用の『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』は、ファシズムの社会心理学的考察。
過度に抑圧された「前社会的な状態に留まっている過剰な衝動の残余」が、時として、代償作用としてスケープ・ゴート(「犠牲の山羊」)を求めることになる、と説く。ここでは、ナチ体制下におけるユダヤ人排斥が主なテーマであるが、それ以外にさまざまな社会現象を、この原理で説明することができる。
前近代における日本社会では、「村八分」「憑き物筋」など、西洋においては「魔女狩り」など
また、現代においては、アメリカでの「赤狩り=マッカーシー旋風」、ソ連での「トロツキスト狩り」など。
外国人排斥(ゼノフォビア)などは、ほとんど、このパターンということができるだろう。
しかし、「禁欲的で高潔な理想に依拠している時代」ならざる現代においても、異質なものを排撃する傾向は、同じパターンを踏むようだ。
E. フロムの『自由からの逃走』と併せて読まれることをお勧めする。
参考資料 A .& M. ミッチャーリッヒ著、 林峻一郎/馬場謙一訳『喪われた悲哀 : ファシズムの精神構造』(河出書房新社)
アレクサンダー・ミッチャーリヒ著、竹内豊治訳『攻撃する人間』(法政大学出版局)
A.ミッチャーリヒ著、小見山実訳『父親なき社会―社会心理学的思考―』(新泉社)