今年もはじまりました。Harvard松下村塾。
ケネディスクール、ビスネススクール(Harvard Business School)、教育大学院(Harvard Graduate School of Education)、公衆衛生大学院(Harvard School of Public Heath)等、ハーバードの各プロフェッショナルスクールや、MITそしてTufts大学院、Boston大学の学生として、あるいは研究者として「知のクラスター」といえるここボストン、ケンブリッヂで学ぶ日本人約30名が、今年もエズラ・ボーゲル(Ezra Vogel)先生の指導のもと、組織や立場の枠にとらわれることなく、世界の中の日本についてともに考え、議論を戦わせていくことになります。
夕方過ぎ、3か月ぶりにお邪魔した先生のご自宅。まずは恒例のお寿司とピザの夕食を楽しみながら、自己紹介や今年のHarvard松下村塾の進め方について、話がはずみます。
昨年はボーゲル先生が年明けまで中国で研究活動に従事されていたため、先生を交えての本格的な勉強会は年明けからとなりましたが、今年は秋口からフル・スタートが切れそうです。
そして、2007年度Harvard松下村塾の第1回となる今日の会合は、塾生一人一人からの自己紹介と自分のキャリア・経験を踏まえての「今後10年間に、日本が直面することとなる最大の課題は何か?」という点について簡単にプレゼンテーションをする形で進められました。
塾生からの自己紹介に先立ち、ボーゲル先生は相変わらず堪能な日本語でこんなメッセージ僕たちに贈ってくださいまいした。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
「毎年多くの日本人がHarvardで、あるいはMITやTuftsで非常に幅広い視点から多くのことを学び、様々な分野・国々で活躍する人材とのネットワークをつくっている。ただ、残念ながら彼らの多くは日本に戻ってしばらくすると、自分の所属する省庁や会社の一部署の狭い視野にどうしても捕らわれがちになってしまう。」
「しかし、この地で学んだことを活かし、日本をより良い国にしていくためには、幅広い視野から日本について考え、そしてそこで培った人脈を日本に戻ってからも深めていくことが大切だ。こんな想いでHarvard松下村塾を毎年開いている。」
「日本が抱える問題について、僕は英語での情報発信能力の弱さを懸念している。英語そのものの能力もそうだが、自分の立場や考えを、全くバックグラウンドが異なる人々や、あるいは日本をあまりよく思っていない国や人々に対して、納得してもらえるよう効果的に発信する能力を身につける訓練が足りないのではないか。」
「なので、この塾でもこれから可能な限り英語でディスカッション、意見発信をして、英語での発信能力を高める一つの機会としてもらいたいと思っている。」
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
日本人だけで構成されるHarvard松下村塾ですが、昨年後半からディスカッションでの使用言語は英語が主流となっています。ケネディスクールでも日本人の英語能力の低さは、ほかの留学生と比較しても際立っているため、あらゆる機会をとらえて英語能力を磨き続けることが必要だという先生の問題意識には強く共感します。
それにしても毎回、先生の日本語の自然さには舌を巻かざるを得ません。日常的には殆ど使う機会がないだろうに、どうやって維持しているのだろうか。そんな塾生たちの疑問に答えるかのように、ボーゲル先生はご自身の「日本語勉強法」の一端を紹介して下さいまいた。
「僕はね、よく日本の国会議員や大臣が演説しているのをテープにとって、彼らになった気分になってそのテープを繰り返し復唱していたんですよ。皆さんも、アメリカの政治家で誰かしゃべり方が気に入っている人、ヒラリー・クリントンでもバラック・オバマでも誰でもいいから、真似してみるとよいかもしれませんよ。」
なるほど、やはりシャードイングですね。
「ケネディスクール出願・合格への道(その2)」でも紹介したとおり、僕も日本で英語を勉強していた時から、そして今でもほぼ毎日欠かさずシャドーイングを続けています。日本語と「音の質」が異なる言語である英語をしっかりと捉え、またスムーズに発していくためには、やはりネイティブのスピーチを自分の耳と口を使って追っかけて行く訓練を継続的に続けるのがもっとも効果的であるように思います。
ボーゲル先生からメッセージをいただいた後は、塾生一人一人が自己紹介と「今後10年で日本が直面する最大の課題」について発表していきます。
話を聞いていると本当に多様なフィールドからユニークな人たちが集まっていると、改めて思わざるを得ません。関心事項も日本経済や金融・財政、安全保障、応用物理学、マスコミのあり方、エネルギー問題、環境問題、途上国支援等、実に様々。
一方で、この多様性がHrvard松下村塾で勉強会を効果的に進めていくうえでの難しさでもあります。何しろ各人の興味分野が専門がバラバラであるため、大所高所の問題設定をしつつも、しっかりと方向を定めて議論を進めていかないと、議論が発散するばかりとなったり、個別の専門領域が関連なく羅列されるだけで終わってしまう惧れがあるからです。
今後、今年取り組む4つの研究テーマを決めていくことになりますが、昨年度の「日本のソフトパワー」と同じくらい、いやそれ以上に魅力的で深く、今後の日本が進むべき道を考える上で示唆を与えてくれる課題について、集まった多様な仲間たちと議論し、理解を深めていきたいと思っています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆ 『人気Blogランキング』に参加しています。「ケネディスクールからのメッセージ」をこれからも読みたい、と感じられた方は1クリックの応援をお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆













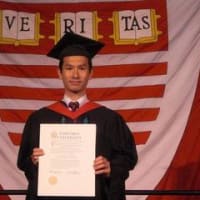






Japan As Number Oneの著者として有名なかたでした。
しかし、日本の専門家でライシャワー大使のようなかたかと思っておりましたが、学者としての関心は日本ではなく中国にあるという趣旨のことをおっしゃっていらっしゃったので残念に感じた記憶があります。
日本語は本当に堪能ですよね。
ボーゲル先生はご指摘の通り、現在は研究の軸足を日本から中国に移されています。ただ日本への強い関心は持ち続けられていて、先生がこの塾を毎年開催される一つの動機づけとして、塾での議論や資料を通じて日本の最新の情報をアップデートしたいということもあるようです。
今年の研究テーマも決定し、僕は昨年に引き続きグループの取りまとめ役ともなったので、また色々記事にしていきたいと思っています。