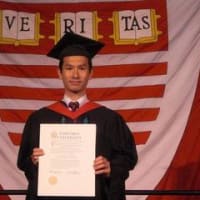小雨が降ったりやんだりのやや蒸し暑い土曜日の午後。中間試験やレポート真っ盛りの時期ですが、僕の足はHarvard Squareから地下鉄Red Lindでふたつ目のところにあるMIT(マサチューセッツ工科大学)に向かっていました。
今日は月1回のペースで開催される「ボストン日本人研究者交流会」の日。
「知のクラスター」であるここボストン・ケンブリッヂで、医療や物理、化学、遺伝子工学、ビジネスから法律などなど、様々な分野で活躍する人々が集まるこの交流会は、自分がこれまで全く知識も関心もなかった(特に理系の)分野の最先端の動きに触れ、自分の視野を広げるには絶好の場です。
というのも、この場は単にお酒等を飲みながら「人と人とが交流する場」だけではなく、毎月二人の研究者が、それぞれの専門分野について1時間程度のプレゼンテーションをし、その後、会場に集まった他分野の研究者からさまざまな質疑応答が30分程度行われるという、活発な「知の交流が行われる場」だからです。
そんな魅力に惹かれて、これまで何度か参加者として足を運んできましたが、今日は会場へ向かう際の動悸の高まりがいつもの何倍も違います。なぜなら、今日は僕のほうから各分野から集まった大勢の研究者の皆さんに対して、「知」を提供する側、つまりプレゼンテーション役を務めることになっているからです。
これまで一生懸命準備をした成果物であるパワーポイント40枚の資料のテーマは、
「財政を通じて考える日本の未来」
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
世界第二の経済大国である一方で、政府の台所事情に目を向ければ、世界一の借金大国となってしまった日本。
「大増税は避けられない!」、「狂乱インフレがやって来る!」あるいは「こんな日本に誰がしたのか?」とセンセーショナルで人々の不安と怒りを煽るキャッチフレーズとともに語られがちな日本の財政赤字の問題ですが、一方で
「誰が国にお金を貸しているのか?」
「今の日本の財政赤字は本当に危機的なのか?」
「国が借金を返せなくなる=“倒産”することが本当にあるのか。」
「万が一国が“倒産”したら私たちの暮らしはどうなるのか?」
などの根本的な問題について、正確に理解している人は意外に少ないのではないでしょうか?
今回の勉強会では、5年間、日本の財政を縦横斜め、上下左右から見てきた経験を通じて踏まえ、日本の財政の現状について、国際比較の視点も交えながら示すとともに、問題解決のために必要な“処方箋”と“根本的な価値観の転換”について、議論を深めていきたいと思います。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
・・・という大風呂敷を広げたような文章を事前に会員に送付される紹介文に載せてしまったのですが、果たしてプレゼン資料の作成は非常にむずかしい。
というのも、この勉強会に参加される皆さんは、それぞれ(特に理系の)の分野で大活躍されている、そう言う意味ではモノスゴク頭の鋭い研究者の方々が多い一方で、財政についての興味や問題意識は必ずしも持っていない方が多いからです。
しかし、ここが研究者会のプレゼンテーションの肝だと思っています。
世の中がますます専門分化する一方で、それぞれの分野が抱える問題が、一般の人々の日常生活やビジネス・研究活動に与える潜在的な影響力が増している昨今の状況の中、各分野の専門家に求められるのが、その分野に興味・知識を持たない一般の人々の意識を喚起し、問題解決に向けて、分野の垣根を越えて共に考え、行動するきっかけとなるような、分かりやすくて正確で、そして情熱的なプレゼンテーション能力なのだとすれば、様々な分野から人が集うこの研究者会は、正にそのような課題にチャレンジするのに格好の場所だからです。
という訳で悩みました。ブレゼンテーションを引き受けてから約1か月、暇を見つけては、自分の中でブレーン・ストーミングを続けました。
そして当日。
集まった約70名の参加者に対して、僕はまず自分自身の話から始めました。僕が何故ケネディスクールで学ぼうと思ったのか。何故、財政について考える場を職業選択の際選んだのか。その思いはどこから来ているのか。
なぜなら、僕自身、毎回この研究者会に参加するたび、あるいは自分が馴染みのない分野の話を聞く度に、「そもそもこの人は、なぜこの分野に興味を持ったのだろう?」「なぜこの分野に人生を賭けようと思ったのだろうか?」という疑問がまず第一に湧いてくるからです。また、自分の原点を参加者と共有することで、話し手と聞き手がより一層、同じ出発点に立てやすくなるのではないか、とも思っているからです。
次に、いきなり国の財政状況の話をするのではなく、月収40万円のサラリーマン一家の家計の話からはじめました。
莫大な借金があるこの家庭。何故この家計の借金が「マズイ」ものであるか、一つ一つの数字が物語る意味を考えながら、論点を洗い出していきます。この段階では参加者の皆さんにはお伝えしていませんでしたが、実はこの家計の数字は全てそっくりそのまま日本の財政状況を反映したものなのです。
そして、サラリーマン一家と日本の財政状況との対にしたスライド。こうして順を追ってみることで兆円単位の国の財政をより身近に感じることができ、結果、現在の日本の財政が直面する深刻な状況をより具体的に捉える事ができると考えました。なお、家計と国の財政とを単純比較することについては、専門家の間でもミスリーディングだとして批判する人もいますが、
① 月々返済するお金よりも、月々借りるお金のほうが多ければ絶対に借金は減らない、
② 適正金利を払い、担保があってはじめて、マーケットでお金を貸してくれる人が見つかる、
という金を借りる側、貸す側に係る二つの原理原則に変わりないと思っています。
そして、プレゼンテーションの最初の山場。「実際誰が国にお金を貸しているのか?」という問題。ここをどう説明するかは非常に頭を悩ませました。というのは、この問題の答えを突き詰めていくと、「実は国の借金は国民の借金で、現役世代の国民が次世代に負っている借金なのだ」という答えに結びついてしまうのですが、それをいきなり説明しても、「なんだ、国の借金は政治家・官僚が作った国の借金だろう。国民に責任を押しつけなさんな!」という憤った、しかし当然の反応が帰ってくるだけだからです。
そこで作ったのが財政という機能を介して繋がっている国と国民との関係を図示したスライド。
ポイントは政府の支出は基本的には公共サービスとして国民の誰かしらの懐に戻っている、より正確には、僕たち一人一人が、例えば町の治安のように、市場では提供されにくい商品やサービスを政府という「お店」から税金を払って買っているという、財政を介した国と国民との基本的な関係です。
それを踏まえれば、現在の財政赤字は、僕たち国民が「差額は後で払うから~」ということで、本来支払うよりも安い値段で政府から公共サービスを買い、その結果、政府は赤字が増えている、というのが実態であり、最終的には、受益者である僕たち国民が、自分たちの預貯金等を使って、貸し手(=金融機関)にお金を返さなければならない状況にある、ということが見えてきます。
ここで問題なのが、借金をする時には当然求められる「いつまでに返します」という約束事が事実上ないこと。
返済期日に関する約束事がなければ、人は先送りをするに決まっています。そして見えてくる財政赤字の最大の問題点は、「現在の公共サービスの受益者である現代世代の国民が、応分の負担をしないため、その負担が将来の子供たち世代の方にのしかかる」という世代間の不公平に他なりません。
今ひとつの問題は、現時点で、一年間の借金の返済額が借入額よりも少ないため、このままのペースが続けば、絶対に借金の額は減らない。むしろ増え続ける一方の構造にある、つまり財政の持続可能性に対する懸念。
「日本には1600兆円の個人金融資産があるから大丈夫だ!」という専門家もいますが、日本の総貯蓄は、高齢者層の増大に伴って減少傾向にある(一般的に高齢者の方は収入(例えば年金等)を日々の消費ではなく貯蓄に回す比率が少ない)ことも踏まえると、「大丈夫だ」と言いきれるか、甚だ疑問です。
こうして日本の財政の現状にかかわる問題点を共有したところでまずは小休止。質問コーナーに移りますが、既に会場からは質問の嵐。特に貯蓄率低下の傾向については、多くの質問が寄せられたほか、「国の借金は実は、国民の借金。より正確には現役世代が次世代に負っている借金」といった説明や、「国の“収入”である税金」といった表現には少なからず戸惑いや不快感を覚えた方もいらっしゃったようで、厳しい内容の質問もありました。
最初は「フーン。財政ね。」という雰囲気だった会場も段々と熱気を帯び始め、そしてプレゼンテーションは解決策の提示に移りました。(続く)
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆ 『人気Blogランキング』に参加しています。「ケネディスクールからのメッセージ」をこれからも読みたい、と感じられた方は1クリックの応援をお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆