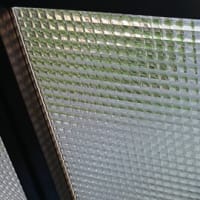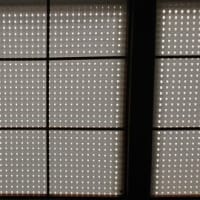昨日は、鈴木大拙館を訪れるため金沢まで行って来ました。あいにく天候は雨でしたが、雨の日の鈴木大拙館もいいかな・・それに人も少ないかも・・と思いつつ行って来ました。(最近、仕事が忙しくないので遊びまくっています・・・。)、鈴木大拙館は、金沢が生んだ仏教哲学者である鈴木大拙の考えや足跡を広く国内外の人々に伝えることによって、大拙についての理解を深めると共に、来館者自らが思索する場として利用することを目的に開設された建物で、建築家の谷口吉生氏の設計によるものです。以前から、友人に名建築だと聞いていたので、この機にと思い訪れて来ました。
 〈往路となる外部回廊から水鏡の庭に浮かぶ思索空間棟を見る〉
〈往路となる外部回廊から水鏡の庭に浮かぶ思索空間棟を見る〉
鈴木大拙館は、「玄関棟」「展示棟」「思索空間棟」を回廊で繋ぐと共に、「玄関の庭」「水鏡の庭」「露地の庭」によって構成されていて、3つの棟と3つの庭からなる空間を回遊することによって、来館者が鈴木大拙について知り、学び、考えることが意図されています。建築は、動線に沿って展開する内部空間の連鎖と関連して移り変わる外部への眺望を強調するために、極力単純な意匠とされていて、まさしくモノクロームの自然素材による「無の意匠」となっています。
 〈思索空間棟から水鏡の庭超しに展示棟と外部回廊を見る〉
〈思索空間棟から水鏡の庭超しに展示棟と外部回廊を見る〉
画家などのための記念館や美術館であれば、作家の作品を展示することによって、それらの建築は性格づけられます。しかし、日本文化の根源を説く哲学者にふさわしい空間をどう構成するかという難題について、設計者である谷口氏は「床」や「床の間」といわれる空間に答えを求めました。「床」や「床の間」といわれる空間は、軸が掛けられ、縁の品が置かれ、季節の花が添えられるまでは、全く機能を持たない無の空間です。最小の設えによって姿を変える家の中の小美術館とも言える「床」は、日本の文化の一面を顕著に象徴するものであって、鈴木大拙館の計画を構成する要素としてふさわしいものと谷口氏は考えました。
 〈昨日も、思索空間に空けられた開口部には、秋の朱に染まる彩りが添えられていました〉
〈昨日も、思索空間に空けられた開口部には、秋の朱に染まる彩りが添えられていました〉
水鏡の庭に浮かぶ思索空間は、全体が設えによって変化する「床」の空間そのものであり、壁面に空けられた開口部からは、四季によって移り変わる周囲の景観が切り取られて見えるようになっています。訪れた昨日も、谷口氏が目指した「無の意匠」に秋の朱に染まる彩りが添えられていました・・・。