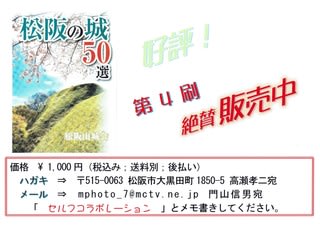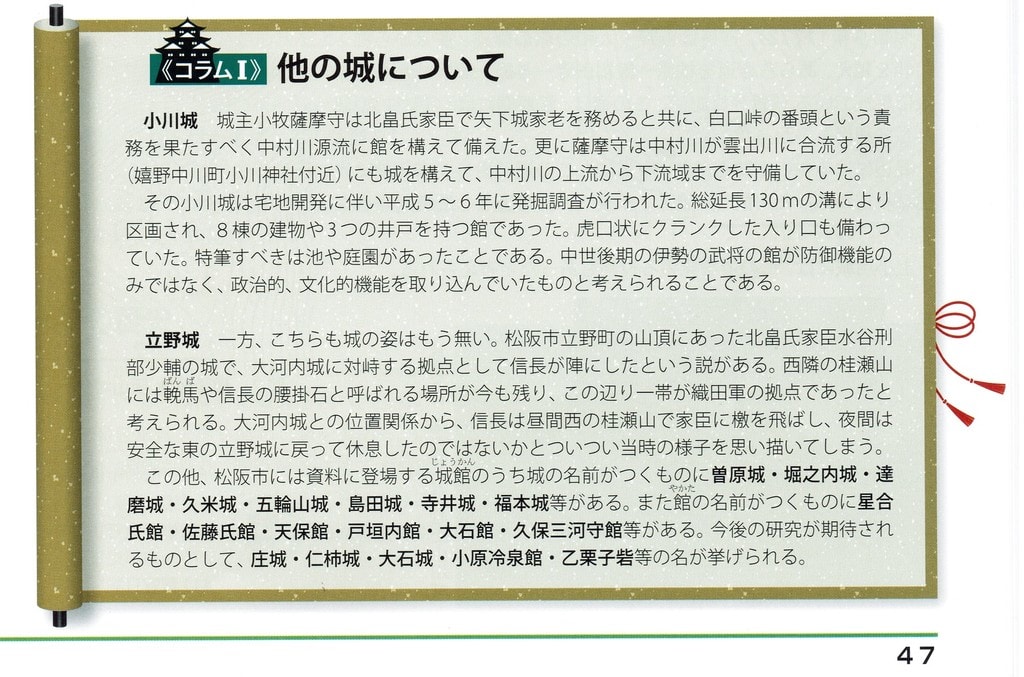松ケ島城
まつがしまじょう
| 城名 | 松ケ島城 | |
| 別名 | 細首城 | |
| 住所 | 松阪市松ヶ島町字城の腰 | |
| 築城年 | 安土桃山時代 | |
| 築城者 | 日置大膳亮、織田信雄、滝川勝利、蒲生氏郷 | |
| 形式 | 平城 | |
| 遺構 | 無し、金箔瓦が出土している | |
| 規模 | 南北180m×東西110m | |
| 城主 | 織田信雄、津川冬彦、滝川勝利、蒲生氏郷 | |
| 標高 | 1m | |
| 歴史 | 永禄10年(1567) 北畠具教、細首城築城 | |
| 永禄12年(1569) 織田信長侵攻により北畠具教-日置大膳亮らは城に火をつけお大河内城に籠城する。 | ||
| 天正4年(1576) 田丸城で北畠氏謀殺、三瀬の変で一族壊滅 | ||
| 天正8年(1580) 信雄、田丸城消失により細首に新たに城を築き松ヶ島城とする。5層天守、金箔瓦であった。 | ||
| 天正10年(1582) 信雄は清州城に移ったので津川玄蕃充に松ヶ島城を預け、南方の奉行とした。 | ||
| 天正12年(1584) 津川玄蕃充ら3人は秀吉の策略で信雄に殺害された。変わって滝川勝利-日置大膳亮が松が島城を守った。このあと小牧長久手の戦いになる。 | ||
| ついに、松ケ島城天正12年の戦いである。徳川家康の送った服部正成の援軍を得て、羽柴秀長の包囲に対し40日にわたって篭城した。 | ||
| 羽柴側は2万余りの兵で松ケ島城を包囲。蒲生氏郷も加わっていたと思われる。九鬼嘉隆と田丸直息の両名に松ヶ島城の近くまで船を寄せて海路から逃げられないように指示。 | ||
| 松ヶ島城落城。滝川雄利は助命され退城した。富田一白と八重羽左衛門尉を在城させる。 | ||
| 天正16年(1588) 蒲生氏郷は松ケ島城が狭かったので四五百森(よいほのもり)に松坂城を築城して町人や社寺全てを強制移住させて松ヶ島は瞬時にしてもとの一漁村に戻った。20年程の細頸ー細首-松ヶ島の城の歴史は終わった。 | ||
| 書籍 | 三重の中世城館 伊勢国司記略 | |
| 環境 | 海陸の要衝 櫛田川、坂内川、三渡川、雲出川、愛宕川、金剛川、以上6川が集まる松阪東部 | |
| 現地 | 備考 昭和32.12.5県指定 一辺20m余りのほぼ台状地(天守山)がのこり、この周囲も水田面より一段と高い畑となっている。 | |
| 現地は記念の塚と碑と説明看板があるだけ。訪れたとき傍で農作業をしていた人が「あなた来るのが遅かったわ。もう少し早く来ていたら良いものがたくさん見れたのに。」と声を掛けてきてくれた。何があったのかを聞くと「50年程前だがこのあたりから金箔瓦やなんやらようけ出たんよ」とのこと。50年前がもう少し早ければの間隔かと少し苦笑しながら話を聞かせてもらった。 | ||
| 感想 | たった20年程の間にいろいろな事柄が起こった細首城から松ケ島城への変遷。戦国時代の典型ともいえる日本の城の一つの姿。現在記念のものしか残っていない点もある意味日本の城の現状を表しているように思える。 | |
| 地図 | |
|