
ここ数日の朝晩の冷え込みの
お蔭で保津峡の木々もほのかに
赤く色づきはじめました。
いよいよ京都の秋本番近しですね。
嵐山にも観光客の姿は増えれてきました。
京都観光には欠かせない嵐山。
その象徴といえるのが‘渡月橋’でしょう。
渡月橋は、平安時代・承和3年(836)に空海の弟子、
道昌が大堰川を修築したおりに架橋されたもの
といわれ、川の対岸にある法輪寺にお参りする
為の橋として使われていました。
当時は「法輪寺橋」や「嵐橋」と呼ばれていたが、
亀山上皇が夜空に月がさながら橋を
渡る様に見えるときに「くまなき月の渡るに似る」
と語られたことで「渡月橋」と呼ばれる様になった
といわれています。

この写真は幕末・維新時の渡月橋です。都が東京に移って
人通りも少なく、ひなびた感じになっています。
細い丸太で橋脚と土台を造り、竹を敷き詰め、土で
固める構造です。
当時の渡月橋は洪水の度に流れていたそうです。

上の写真と同じところから撮った今の渡月橋です。
室町時代には嵯峨・天竜寺の勢力が強く、今架かっている場所から
約100m上流の天竜寺の門前に架けていたそうですが、
角倉了以が保津川開削の折、今の場所に戻したと云われています。
ちなみに角倉了以は莫大な天龍寺造営費用を捻出する為、
中国・元との貿易事業を進めたといわれ、その船は‘天龍寺船 ’
と呼ばれていました。

上の写真は明治時代の渡月橋の風景です。
橋の橋脚に筋交いが入れられ強固なものとなっています。
文明開化により土木技術も飛躍的に向上したの後が伺えます。

今の渡月橋です。
明治期の橋も洪水には勝てず、2度も流失したそうです。
今の橋は昭和9年に架けられた橋で、鋼鉄を使ってある
ので、平安の世からの流れ橋としての歴史には
終止符が打たれました。
今の橋は明治期の橋より少し下流に架かっています。
京都の人は子供が十三歳になると、京都嵐山の法輪寺にをお参りして、
知恵の仏様「 虚空蔵菩薩 」( こくうぞうぼさつ)に 、
知恵を授かりに行く風習がいまでも残っています。
知恵を授かる祭事を行った後は、渡月橋を渡りきるまで
「けっして振りかえらないように!」と約束させられます。
これは「約束を守る」という大人の自覚を持つという
意味があります。
たぶん丸太橋の頃は、下を見たら怖くて振りかえると
川へ落ちてしまうという意味もあったと思われます。
そんな言い伝えがいつしか
「カップルで渡る時、振り返ると別れる!」という
変な噂になっているのは面白い話ですね。
私達、保津川下りの船頭は毎日、この橋の下を
船で潜って、クレーン場まで片付けに行きます。
下から見る渡月橋の姿は・・・内緒にしておきますね。
お蔭で保津峡の木々もほのかに
赤く色づきはじめました。
いよいよ京都の秋本番近しですね。
嵐山にも観光客の姿は増えれてきました。
京都観光には欠かせない嵐山。
その象徴といえるのが‘渡月橋’でしょう。
渡月橋は、平安時代・承和3年(836)に空海の弟子、
道昌が大堰川を修築したおりに架橋されたもの
といわれ、川の対岸にある法輪寺にお参りする
為の橋として使われていました。
当時は「法輪寺橋」や「嵐橋」と呼ばれていたが、
亀山上皇が夜空に月がさながら橋を
渡る様に見えるときに「くまなき月の渡るに似る」
と語られたことで「渡月橋」と呼ばれる様になった
といわれています。

この写真は幕末・維新時の渡月橋です。都が東京に移って
人通りも少なく、ひなびた感じになっています。
細い丸太で橋脚と土台を造り、竹を敷き詰め、土で
固める構造です。
当時の渡月橋は洪水の度に流れていたそうです。

上の写真と同じところから撮った今の渡月橋です。
室町時代には嵯峨・天竜寺の勢力が強く、今架かっている場所から
約100m上流の天竜寺の門前に架けていたそうですが、
角倉了以が保津川開削の折、今の場所に戻したと云われています。
ちなみに角倉了以は莫大な天龍寺造営費用を捻出する為、
中国・元との貿易事業を進めたといわれ、その船は‘天龍寺船 ’
と呼ばれていました。

上の写真は明治時代の渡月橋の風景です。
橋の橋脚に筋交いが入れられ強固なものとなっています。
文明開化により土木技術も飛躍的に向上したの後が伺えます。

今の渡月橋です。
明治期の橋も洪水には勝てず、2度も流失したそうです。
今の橋は昭和9年に架けられた橋で、鋼鉄を使ってある
ので、平安の世からの流れ橋としての歴史には
終止符が打たれました。
今の橋は明治期の橋より少し下流に架かっています。
京都の人は子供が十三歳になると、京都嵐山の法輪寺にをお参りして、
知恵の仏様「 虚空蔵菩薩 」( こくうぞうぼさつ)に 、
知恵を授かりに行く風習がいまでも残っています。
知恵を授かる祭事を行った後は、渡月橋を渡りきるまで
「けっして振りかえらないように!」と約束させられます。
これは「約束を守る」という大人の自覚を持つという
意味があります。
たぶん丸太橋の頃は、下を見たら怖くて振りかえると
川へ落ちてしまうという意味もあったと思われます。
そんな言い伝えがいつしか
「カップルで渡る時、振り返ると別れる!」という
変な噂になっているのは面白い話ですね。
私達、保津川下りの船頭は毎日、この橋の下を
船で潜って、クレーン場まで片付けに行きます。
下から見る渡月橋の姿は・・・内緒にしておきますね。
















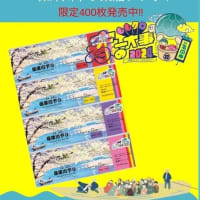

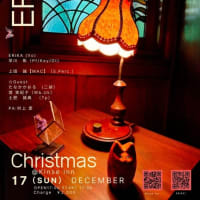


4日ほど前に船酔いの件で問い合わせさせて頂いたようこです。お返事ありがとうございました。
船酔いの心配はないようなので、安心しました☆実は京都旅行はもうすぐ出発で、11月1~3日の日程で行くのです。
そのいづれかの日に保津川に行けたらと思っています。
渡月橋も歩く予定です。だんだん旅行に行く実感がわいてきました♪
お仕事頑張ってくださいね!
下から見る渡月橋は、見れる人はそういないでしょう。
船頭さんだけの秘密ですか?
内緒って言われると、知りたくなるのよね。
東京にも、カップルで行くと破局する場所はいくつかあります。
井の頭公園でボートに乗る、ディズニーランドに行くとか…何処にでもあるのね。
渡月橋は知らなかったわ
ワクワクの京都旅行ですね。
どちらから来られるのですか?
時間があれば是非、保津川にもお越しくださいね。
もしかしたら3日は満員御礼札止めになる可能性も
あるので、一度問い合わせてくださいね。
今年は渡月橋にライトアップの灯篭が
設置されました。夜の嵐山も盛り上げようと
地元の保勝会が計画・実施しました。
天然温泉もあり、夜も賑やかな嵐山になることでしょう。
しかし、今年の京都の夜はライトアップが花盛りですね。
まあ~いいアイデアではあるけど・・・
昨晩の”土曜ワイド劇場”では、あの「渡月橋」の近くで日舞家元がお亡くなりになっておりましたね。(なんまいだ~ チ~ン)
はっちんさんは、あの撮影のことご存知でしたか?
はっちんさんがどこかに出演しておられるのではないかしら・・・などと、Honkoは無意識に探しておりましたよー。
今回、学生で例えるなら、「バッチリ!予習をしてから授業に臨んだ。」って感じです。(何だかすご~い!)
はっちんさんのおかげで、”京都サスペンス”が10倍楽しめたっ!そんな秋の夜長でございました・・・まる
すごいですね!昔の渡月橋ってこんなんだったんですね
しかしはっちんさんの記事は毎回楽しいですね
先々週の金曜日に運良くはっちんさんの漕ぐ舟で川下りを堪能することが出来ました!
ずーっと乗ってみたいと思っていた保津川の船。
景色は良いわ、船は快適に進むわ、船頭さんの話は面白いわで
予想していた以上に満足度の高い1時間50分でした。
何より手漕ぎというのが本当に素晴らしいですね。
その分ご苦労も多いとは思いますが、
これからも今の形を守っていって欲しいと思います。
当日はドイツから来た友人と一緒に3人で
乗り、
彼も周囲の自然の静かな佇まいと船頭の皆さんの技術に感心して、
大満足で帰国しました。
また友人と京都を訪ねた際には保津川下りを
したいと思ってます。
その時はまたよろしくお願いします☆
あの番組の撮影は3週間ほど前に
やっていたと思いますね。
今は年末時代劇もあるので、保津川でも
多くの撮影がなされています。
私をブラウン管の中に探して頂いてようで、
ありがとうございます(笑)でも、俳優ではないので
出演はしていないです。
もうTVに出ることはないと思います。
以前、TVのドキュメント番組に4件ほど
出演したことがあります。
それ以来、東京のバラエティー番組数件から
出演依頼がありましたが、品が良くないので
お断りしました。
TVメディアももう少し考えほしいですね。
今、保津川では年末の歴史大作「風林火山」
を撮っています。北大路欣也さんがいつも
遊船にトイレを借りに来られます。
今、保津川の400年記念事業を進めて
いますので、古い写真がいっぱい発掘されています。
また、機会があればブログに載せますね。
楽しみしておいてください。
私の船にご乗船いただいてとのこと、
ありがとうござます。
はっちん号は満足して頂けましたか?
しっかり説明できていたかな~
私の船に乗ったことのある方に、気が付いたところ
とか意見を聞かせてほしいですね。
ドイツの友人さんにもよろしくお伝えください。
自国でも宣伝しておいてくださいね。