A.戦争について考えていなかった?
1945年8月に日本が手痛い敗北を喫した戦争について、戦後いくども「戦争責任論」が問われ、「なぜ負けたのか」についても多くの論説が現われた。しかし、その戦争を身をもって経験した人びとが考えていたことと、戦後に生れた人間では、いうまでもなく戦争に対する感覚が異なる。ただそれを「戦中派」「戦後派」と分けてしまうと、戦中派にも戦争を軍中枢にいて指導した人たちと、ただの兵士として戦った人たち、空襲で逃げ惑った庶民ではかなり違うだろうし、未成年の軍国少年だったか、朝鮮や満州にいたか、沖縄にいたか、疎開地にいたかでも体験はさまざま異なるのは当然だ。いずれにせよ生き残って戦後を生きたという点では、ぼくたち戦後生まれだって、戦後焼け跡闇市育ちもあれば、地方農村が人にあふれていた時代に育った人もあれば、もっと後の高度経済成長期に育った人もいるわけで、ひとまとめに戦後派、戦中派などと分類してもあまり意味はない。むしろ、ある時点で多数の人々が考え感じていたことが、なにかをきっかけに大きく転換していく時期があり、戦争という大きな出来事についても、日本人の歴史意識には20年から25年くらいの幅で見ると、かなりの変動があるというのが歴史家の見方だろう。
吉田裕『日本人の戦争観』第一章の「歴史意識と政治――90年代における政策転換――」は、20世紀最後の10年に注目する。まず細川連立政権での首相発言「侵略戦争であった」から始め、それを国民世論も過半数が認めるという、侵略戦争論が一見1993年時点の国民の多数派であるかにみえていた状況が、実は戦争責任や戦争への真摯な反省や理解からではなかったこと、経済大国日本がアジア諸国にリーダーシップを確保し、国連常任理事国入りを目指したいという政治家の願望から、過去の清算を必要とした政治的辻褄合わせに発していたことを指摘する。この本は1995年前後に書かれていて、その時期はバブル経済は破綻していたものの、日本はまだ中国より経済力は優越し、戦後50年記念という節目にあった。自民党一党支配が行き詰り、国民新党、新生党、社会党などが連立して「非自民、非共産」の細川政権ができた。支持率は空前の71%、なにかこれまでとは違う新しい政治への期待が一瞬国民をとらえたともいえるが、細川政権は1年ももたず、自民党を割って出た新生党の羽田孜が後継になるが2カ月しかもたず、小沢一郎の画策が失敗して分裂し、自民党が政権の一角に戻って自社さ連立の村山政権になったのが1994年の政治劇だった。
保守政治家は言うに及ばず、中道リベラル派を自任する政治家も、基本的には過去の戦争について明確な歴史像をもたず、周辺諸国から非難されると謝り、内向けには「結果としての侵略行為」をなるべく都合よく無責任に考えておく、という態度は共通していたと考える。国民もまた、戦争責任についてあまり真剣に考えてはいなかった。
「かつての戦争を侵略戦争であると明確にに意識している人々が多数派を形成しているのであれば、羽田首相の「侵略行為」発言に対してもう少し厳しい反発があってもよさそうなものだが、世論の反応はほとんど見られないし、マスコミもこの発言をあまり問題にしていない。
この点で、この問題を考える際の手がかりになるのは、82年10月にNHK放送世論調査所が行なった、「日本人の平和観」に関する世論調査である。この調査で注目に値するのは、明治以降の日本の対外的膨張を、「侵略の歴史だ」と見なす人が51.4%に達する一方で、「資源の少ない貧しい日本が、他国に軍事進出して行ったのは、生きるためのやむを得ない行為だった」とする人が44.8%にも達している事実である。「やむを得ない」「しかたのない」戦争であるのなら、そこには「責任」という観念が生じるはずもない。恐らくは、そのことの直接の結果として、「一般国民の戦争責任」についての質問では、「国民に責任はない」とする人が36.3%で、第一位を占めている。また、太平洋戦争が「アジア諸国の独立回復を早めて点は、評価すべきだ」としている人が45.5%に達している事実も見逃すことができない。
表2 「日本人の平和観」調査
全国16歳以上の国民を対象、有効回収数2623人(回収率72.9%、単位%)
・日本は、明治から昭和20年の敗戦まで、数多くの戦争や領土拡張を行ってきましたが、あなたは、これを、どのように評価していますか。〔回投票〕のAからDまでのそれぞれについて、〔回答票〕の1,2,3の中からお答えください。
(A) 日清戦争から太平洋戦争までの50年の日本の歴史は、アジア近隣諸国に対する侵略の歴史だ
(B) 資源の少ない貧しい日本が、他国に軍事進出して行ったのは、生きるためのやむを得ない行為だった
(C) 朝鮮・韓国人や中国人に対する、明治以来のひどい差別・迫害や忌まわしい虐殺事件については、日本人として、心から反省すべきだ
(D) 太平洋戦争が、欧米諸国の圧政に苦しんでいたアジア諸国の独立回復を早めた点は、評価すべきだ
(A) (B) (C) (D)
そう思う 51.4 44.8 82.5 45.5
そうは思わない 21.9 38.7 5.2 25.1
昔のことだから、自分には関係ない 10.4 4.7 4.2 5.5
わからない、無回答 16.3 11.9 8.2 23.9
・あなたは、昭和6年から15年に及んだ日中戦争・太平洋戦争について、一般国民の戦争責任を、どのようにお考えでしょうか.〔回投票〕のように分けると、あなたのお考えは、どれに近いでしょうか.
一般の国民は、軍国主義の教育や情報にだまされ、ひどい目にあった被害者であって、国民に責任はない 36.3%
当時の国民は、大部分が軍国主義の讃美者・協力者であって、少なくともアジアの人々に対しては、加害者である 29.5%
あの戦争は、日本の自衛とアジアの平和のためにやったものであって、軍国主義だとか、被害者だ 加害者だというような問題ではない 17.6%
その他 0.5%
わからない、 無回答 16.1% 計 100.0
(内閣総理大臣官房広報室篇『全国世論調査の元凶・昭和58年版』大蔵省印刷局、1984年)
つまり、ここには、羽田首相の「結果としての侵略戦争」論とひびきあうような意識の構造がくっきりと現われている。後に詳しくみるように、このような国民意識のありようは、その後、現在に至るまで基本的には変わっていない。羽田首相の「結果としての侵略戦争」論に対する世論の沈黙の背景には、こうした意識構造が横たわっているとみるべきだろう。
また、先にふれた朝日新聞社の戦後補償問題に関する世論調査でも、確かに若い世代ほど補償について肯定的という注目すべき傾向が現われている。具体的に見てみると、補償要求に対する政府の対応についての回答では世代間の差がいちじるしく、二、三〇代では70%近くが、「事柄によっては応じるべきだ」としているが、50歳以上の戦争体験世代では「応じる必要はない」が40%をこえ「応じるべきだ」を上まわっている。しかし、この世論調査のより詳しいデータを収録した朝日新聞戦後補償問題取材班『戦後補償とは何か』(朝日新聞社、1994年)を見てみると、設問によっては微妙な結果が出ているのがわかる。表3は戦後補償問題への関心を聞いたものだが、若い世代の方が「あまり関心はない」と答える人の割合が高いことに気がつく。つまり、若い世代ほど戦時中の価値観や思想にとらわれていない分だけ自由で柔軟な対応が可能になるとは必ずしもいえず、むしろ、無関心層が少なくないのである。世代がさがるほど戦争に関する当事者意識が希薄であり、また学校教育の場で戦争の生々しい実態について教えられることがほとんどないことを考えるならば、これはある意味では当然の結果だといえよう。
太平洋戦争は「侵略戦争」か否かを聞いた毎日新聞社の先の世論調査でもほぼ同様の傾向が現われており、「若い世代では『わからない・無回答』の多さが目立ち、六〇代以上の五人に一人が、二〇代では三人に一人に上る」と指摘されている。
以上のような諸事実を考慮に入れるならば、世論の変化が意味しているのは、戦争責任や戦後処理の問題をめぐって厳しい対日批判が厳然として存在していることを自覚し、これに現実的に対応していこうとする人々が増えているという事実であって、そのことはそのまま日本人の歴史観や歴史意識の深まりを意味していないとみることもできる。
反米ナショナリズムの陥穽
ところで、世論の動向に関連して、ここで注意を払う必要があるのは、八〇年代から九〇年代にかけて、日本人の中に台頭してきた「嫌米感情」という名の反米ナショナリズムの問題である。外務省は、日米安保条約改定三〇周年の事業の一環として、「米国の内外情勢の日米安保体制に及ぼす影響」と題する研究を佐藤清三郎東大教授を中心にした学者グループに委託していたが、その中間報告は、「日本で反米意識という形のナショナリズムが高まりつつあり、日米安保体制を動揺させる可能性が出てきた」と警告を発していると報じられている(『朝日新聞』91年3月19日付)。事実、毎日新聞社が同年10月に日米両国で同時に実施した世論調査によると、日米安保条約については米国で「強化」「維持」を主張する人が45%で、「縮小・将来廃棄」「ただちに廃棄」の33%を大きく上回ったのに対し、日本では「縮小・将来廃棄」が42%でトップを占めている(『毎日新聞』91年11月16日付)。その後も、同様の傾向を示した世論調査がいくつか現われており、日本人の意識の深い所で、ある変化が生じつつあることを予感させる。
問題は、このような反米ナショナリズムが日本人の戦争観にも微妙な影響を及ぼしつつあるようにみえることである。この反米ナショナリズムと戦争観の関係を最も端的な形で示しているのは、自民党の石原慎太郎衆院議員の場合だろう。石原議員は93年10月5日の衆院予算委員会で、41年12月に開始されたアジア・太平洋戦争の性格を、日本の対中国戦争、東南アジアに植民地を保有する欧米列強と日本との戦争、戦争末期のソ連の対日参戦によって開始された日ソ戦争の三つに区分した上で、日ソ戦争がソ連の対日侵略戦争であったことを強調しながら、「日本と同じ植民地主義でアジアにも出張ってきた列強」との戦争である二番目の戦争の性格について、次のように細川首相を追求した。
私たちが戦争に敗れはしたけれども、敗者としてオランダやフランスやアメリカやイギリスに謝罪する、……今改めてそういう謝意を抱く必要はどこにもない。全くこっけいなことで、同罪ではあっても、どちらの罪が重い、軽いという問題は、比較にならない。
だから私は、先ほど言った太平洋戦争の第二の要因である、つまり植民地主義の列強と日本がこの太平洋地域で相まみえた、その戦争に破れた責任というものを、この時点で改めて謝罪するという形で国民が胸にする必要は毛頭ない、私はそう思いますけれど、いかがですか。
欧米列強に対する戦争の性格を、戦争の他の性格と区別して把握しようとする発想自体は、竹内好が、「近代の超克」(『近代日本思想史講座7』筑摩書房、1959年)や「戦争責任について」(『現代の発見3』)などの論文の中で早くから主張していたことである。特に後者の論文の中で竹内は、自説について、「日本の行なった戦争の性格を、侵略戦争であって同時に帝国主義対帝国主義の戦争であり、……侵略戦争の側面に関しては日本人は責任があるが、対帝国主義戦争の側面に関しては、日本人だけが一方的に責任を負ういわれはない、という論」と明解に説明している。
石原議員の質問は、日本が朝鮮を併合しなければ、「あのときの朝鮮の混乱からいえば、隣の清国なりロシアに併合されていたことは間違いがない」という言い方や、「国際法の上では合法的に獲得したシナ大陸の権益というものをめぐっての紛争が、結局は日中間の長い戦争になった」という言い方に示されるように、竹内ほど明確にアジアとの戦争の侵略性を認めているわけではない。とはいえ、石原議員の議論がその基本的発想を竹内から借りているのは、ほぼ間違いない。
もちろん、アジア・太平洋戦争が東南アジアの植民地の争奪をめぐる帝国主義国相互の戦争という一つの側面を持っていたことに関しては、誰しも異論がない。しかし、アジア諸国に対する戦争と欧米諸国との戦争を機械的に分離し、この二つの側面を対立させる議論の仕方については、すでに家永三郎が『戦争責任』(岩波書店、1985年)の中で、次のように批判していたことを想起する必要がある。
日本は中国侵略戦争を継続するために、これを中止させようとするアメリカ・イギリス・オランダと開戦することになったのであって、中国侵略戦争の延長線上に対米英蘭戦争が発生したのであり、中国との戦争と対米英蘭戦争とを分離して、別個の戦争と考えることはできないのである。
このアジア・太平洋戦争と日中戦争との連続性については、戦後、比較的早い時期のもっともポピュラーな戦記の一つである、伊藤正徳『帝国陸軍の最後 侵攻篇』(文藝春秋社、1959年)が、今日の段階からみてもきわめて重要な問題提起を行っていることを指摘しておきたい。すなわち、伊藤によれば、「もし日支事変がなかったら、日米戦争は之を欲しても戦い得なかった」。なぜなら、日本が開戦段階で英米に対抗できるだけの戦力を保持できていたのは、日中戦争中に、「兵力動員の上から、軍事産業大拡張の上から、武器の大蓄積の上から、日本はかつて夢想もしなかったような戦力を蓄えるのに至った」からであり、そのために必要な巨額の予算の獲得は、日中戦争の戦費として計上された臨時軍事費からの「流用」によって可能となった。つまり、伊藤によれば、軍は「日支事変を利用して、平時は予算的に不可能であった弱点の補修から基本戦力の増力まで仕上げて了ったのである」。
この臨時軍事費特別会計は、戦争の終結までの全期間を一会計年度とする特別会計である。予算編成に際しては大蔵省の審査も不十分な形でしか行われず、また、議会の審議でも、予算の細目が知らされないため、申し訳程度の秘密会でそのまま可決された。それだけに、軍にとってはきわめて旨味のある予算であり、日中戦争勃発時の「拡大派」の政治的な狙いの一つは、戦争を口実にした臨時軍事費の獲得にあった(拙稿「『国防国家』の構築と日中戦争」『一橋論叢』1984年7月号)。
この臨時軍事費のうちで、どれだけの予算が実際に軍備の拡充に転用されていたのかは判然としない。ただ、参謀本部篇『杉山メモ(上)』(原書房、1967年)によれば、41年2月3日の大本営政府連絡会の席上で、中国戦線の縮小によって戦費の節減をはかるべきだと主張する松岡洋右外相の発言に対して、海軍の代表が、「海軍ノ第一線消耗ハ一年ニ六千万円程度他ハ全部貯蔵ナリ」と答え、陸軍の代表も「陸軍ノ消耗ハ十七、八億検討他ハ貯蔵ナリ」と答えているのが参考になる。1940年度の臨時軍事費のうちで陸海軍省所管のものは、大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史4』(東洋経済新報社、1955年)によれば、57億2254万円だから、日中戦争の直接経費は全体の31~33%程度ということになる。
また、東条英機陸相も、41年4月5日の陸軍省内の会議の席上で、「又例えば数十億の軍費といっても実際第一線で使用するのはせいぜい二〇億で、他のすべては国家百年のための経費である」と発言していて(陸上自衛隊衛生学校偏『大東亜戦争陸軍衛生史1』非売品、1971年)、先の『杉山メモ』の記述を裏づけている。
ちなみに、この臨時軍事費の中から多額の機密費が支出され、それがまた軍の「政治資金」にもなっていたようである。陸軍省軍務局軍事課予算班長の経歴を持つ加登川幸太郎は、この点について、「何に使ったかわからんけど、東条さんが総理大臣になった時、…‥三百万円という機密費三口を内閣書記官長に渡せ、と来るんだね。…‥あの頃二百万円あったら飛行機の工場が一つ建ったんだから」ときわめて率直に回想している(若松会編『陸軍経理部よもやま話』非売品、1982年)。
臨時軍事費の話が少し長くなってしまったようだ。ただ、ここで満州事変・日中戦争とアジア・太平洋戦争の連続性という問題にこだわりたかったのは、反米ナショナリズムと結びついた形での戦争観が日本人の関心を日米関係という狭い問題領域に押し込めることによって、結局はアジアとのかかわりを見失わせるという点を強調したかったからである。
同時に、石原議員の追求の仕方をみていて気がつくのは、彼が戦後処理の問題を全く視野に入れていないことである。そして、戦後処理のあり方という問題を考慮に入れるならば、一見鋭くみえる石原議員の追求も俄然色あせたものとなる。なぜなら、冷戦の激化という状況の下でアメリカは、日本を対ソ包囲網の中に組み入れるために、アジア・太平洋戦争の戦後処理に関しては基本的に宥和的な対日政策をとった。サンフランシスコ講和条約でアメリカが対日賠償の請求権を放棄している事実が端的に示しているように、対日講和はあくまで「寛大な講和」だったのである。こうした中で日本政府は、サンフランシスコ講和条約の第11条で東京裁判の判決を受諾するという形で最小限度の戦争責任を認めることによって、アメリカの同盟者としての地位を獲得したのであり、その点では日本は冷戦体制の受益者だった。
このことが示唆しているのは、日本人のアジア・太平洋戦争観はこうしたアメリカ主導の戦後処理のあり方と密接に関連しながら形成されてきたのではないかということである。だとするならば、アメリカとの協力・協働によって築きあげてきた自らの戦後史そのものを問い直すことなしに、アメリカに対して責任を負う必要がないという議論だけを一方的に主張するのは、率直に言ってやはり欺瞞的だと思う。」吉田裕『日本人の戦争観 戦後史の中の変容』岩波現代文庫、2005.pp.12- 22.
戦後の保守政治家の多くは、日米安保と講和条約と東京裁判で組上げられたアメリカに首根っこを押さえられた体制を、自分たちの権力と天皇制存続のために承認し、ことあるごとにアメリカの意向を最優先することで生きのびる他ないと考えていた。「侵略戦争論」についても、それを国民が日本の支配権力が国民の犠牲において遂行したと考えるとき、非難と攻撃がアメリカと密着した日本保守政治に向かうのだけは避けたかった。60年安保で噴出した「反米」意識はまさに、そうした危険を顕在化したものと意識したであろう。だから本音は再軍備や改憲を企みながらも、憲法の平和主義、非軍事的な商人国家の旗は降ろせなかった。しかし、80年代になると、経済大国の自負とアジアへの進出という誘惑に駆られて、ふたたび周辺国との関係を再構築する必要にかられ、侵略戦争への反省・謝罪を口にする。しかしこれは中途半端で保守派の中から少しも反省していない発言が沸き出すやぶ蛇でもあり、それが韓国・中国から反発を招く事態になる。結局過去の汚点を隠蔽や蒸し返し、やったやらないの非難の応酬合戦になってしまった。まことに不幸ななりゆきだが、歴史意識へのじゅうぶんな理解と配慮を欠いた憎悪の掛け合いは、なにひとつお互いの利益をもたらさない。では、日本の左翼リベラル派(そういうものがあればの話だが)は、これに対してどうふるまったのか?実はこっちの方も、戦争責任や侵略戦争論について明確なスタンスをもっているといえないのではないか。ただ9条を守れ、反戦平和というお題目を唱えていただけではないか。昔のことはもういいから、未来指向で仲よくしましょうよ、では安倍晋三と変わらない。少なくとも敗戦直後には、昭和天皇の戦争責任はもっと真剣に問われていたはずだ。
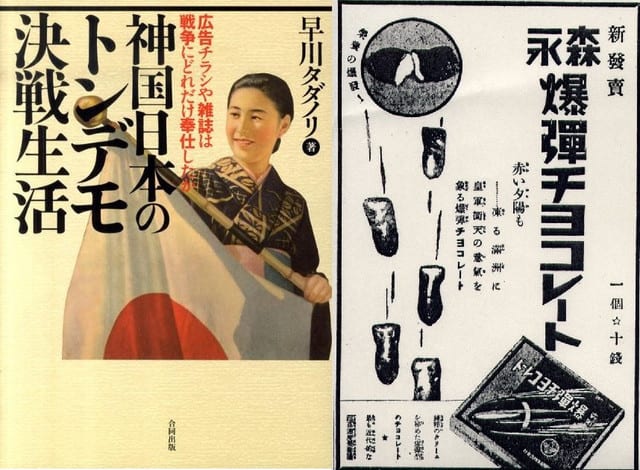
B.軍国の母、はどうして「母」でしかないのか?
靖国主義というイデオロギーがあるとすると、それは天皇の国家のために命を捧げるほど崇高な行為はなく、兵士として名誉の戦死をした息子を英雄として褒めてあげなければ、母が悲しみ霊は浮かばれない、というものだろう。言い換えれば、軍隊を持つ国家の支配者にとって、自分の意のままに兵士に喜んで死んでもらうためには、その死を意義付け、悲しむ母に栄誉と納得を与えなければならない、という心理にもとづく。特攻隊員の遺書などにみられるように、戦前の皇国教育を受けて育った日本の男の子たちにとって、父親よりも兄弟よりも何よりも、愛着と郷愁の象徴は母だった。息子の眼からみて、三世代同居のイエ制度の中で、ひたすら夫のため家族のために汗水たらして苦労していた母の姿は、国家や天皇陛下というシンボル以上に、命を捧げるに値した。でも、そういう「軍国の母」というイメージこそ、教育とジャーナリズムが手を変え品を変え作り上げた虚像ではなかったか。
「日本婦道の暗黒――軍国の母ぶり競争
当時、もっともよく読まれていた婦人雑誌である『主婦の友』が、敗戦に至るまで何度も何度も繰り返した軍国の母顕彰キャンペーン「日本婦道の光」シリーズは、回を重ねるごとにより強烈に・より陰惨なものとなっていった。何もそれは戦局が悪化したからというわけではなく、より刺激の強い・より泣ける物語を求めて主婦の友編集部が走り回ったからにほかならない。やがて連載は、お国に捧げた子/生んだ子の数の比率競争と化した。
例えば「大空の母」なる称号が与えられた住原モトさんのばあい(『主婦の友』昭和十八年三月号)、愛児五人はことごとく飛行兵となり、
二男は夜間飛行演習中に墜落死
三男は吉林省で墜落し
四男は練習生を乗せての訓練飛行中に墜落死
五男はビルマ北部国境攻撃に機長として出動中に倒れ戦死
……という有様。記事が掲載された時点で生存していたのは長男の住原正一航空大尉ただの一人で、まさに映画『プライベート・ライアン』(S・スピルバーグ監督、1998年)さながらの状態である。彼女の長男氏も戦争が終わるまで生き残れたのかどうかは定かでない。
こういうばあい、大日本帝国は周到にメディアを動員して、同情を集めるのに抜かりはなかった。「四児殉国の栄光」を大々的に発表し、東条英機夫人は弔電をおくり、女学生からは「お母様のような日本の母に私もなります」という手紙が寄せられ、福岡県のある鉄工所従業員一同からは「三百五十円」もの醵金が……と「国民の感激と敬悼は、刀自〔年配の女性への敬称〕の一身に集められた」のだそうだ。靖国神社を統治システムに組み込んだ神国・日本は、死者の利用法にかけては昔から高度な技術を有していたわけだ。
ほかにも、「五人の子どもをことごとく海軍軍人に育て上げた母」(昭和十九年四月号)、「二児を大東亜戦争に捧げ六人の孫の養育に営々土と戦ふ岩淵ゆり刀自」(昭和二十年一月号)「四男児を海軍軍人に育てた軍国の母 岩田ヒモ刀自」(昭和二十年二月号)など枚挙にいとまがない。少子化の現代から見れば、よくもまあこれだけ子どもを産んで兵隊に差しだしたものよ…‥と思う。ともあれ、「産めよ殖やせよ」スローガンを忠実に履行すれば、どんな「軍国の母」になれるのか、そんな“期待される〈産む機械〉像”は、このような軍国美談とともに形成されたのだろう。
〈靖国の妻〉たちの貞操問題
父親が戦死した後も健気に生きる遺児たちが、国を挙げて称揚される一方、残された未亡人たちには、立派な〈靖国の妻〉でありつづけることが厳しく要求された。
昭和十四年に、帝国在郷軍人会本部が刊行した『軍国家庭読本 締めよ、こころ』は、タイトルからして端的なように、〈靖国の妻〉たちの生活態度を思いっきり引き締めるために作成されたパンフレットで、「期待される軍国婦人像」をストレートにあらわしている。その中でも、かなりの量が割かれているのが〈靖国の妻〉たちの「貞操問題」だった。同パンフレットの最終章は「日本婦徳に還れ」と題され、未亡人の貞操をどう守るのかに費やされている。
婦人本然の美徳であります徹底的な愛は、兎角一面において盲目的であり、熱狂的であり、偏狭である恐れがあるのであります。一時的の愛に溺れて、永遠の幸福を忘れたり、或はあるものを偏愛するとかいふような事例がないではないのであります。……つまらぬ劣情や、一時的の感情に左右されての事が多いのであります。此の偏狭な熱狂的な愛は、婦人として最も慎まなければならぬ所であります。
彼らは、女=つまらぬ劣情に左右されるものという徹底した女性蔑視観に基づいて、「靖国の妻」の大義名分を振りかざし、女性たちにタガをはめようとしたのである。こうした「道徳」の強制は、「理想としては、一生独身生活を送るのが至当」「親兄弟や社会が、何等要求する事がないに拘はらず、その身の勝手や、情欲の為に、再婚するやうな事は許すべからざる罪悪である」(ともに同書)などという人な結論をもたらした。まったく大きなお世話である。婦人の「劣情」「情欲」に注目しこだわっているところに、帝国在郷軍人会のいやらしいオヤジ目線を感じるのは私だけではあるまい。
結局のところ「日本婦道」とは、すべて「男」「夫」そして彼らを預かる「軍」の男根的三位一体サイドからの身勝手な注文で埋め尽くされていたのである。」早川タダノリ『神国日本のトンデモ決戦生活』ちくま文庫、2014.pp.50-54.
夫や息子を軍隊で死なせ、悲しみに暮れる母に、日本婦道は再婚を禁じ、最後までイエに尽くして二夫にまみえてはいけない、とはどういう心情から出てきた思想だろう。女は一生、一人の男、つまり夫だけに仕え、身も心も捧げて夫のイエに骨を埋めることが唯一の正義だという思想。それは早川氏もいうように、自分はいくらでも娼婦を買ったり浮気をしても、妻だけは貞操を守って自分にだけ尽くすべきであり、そういう妻であってこそ国家に命を捧げたとしても満足できる、という非常に自分勝手な思想である。こんな思想に殉じる女性が「軍国の母」だとしたら、日本って最低の国家だったな。
1945年8月に日本が手痛い敗北を喫した戦争について、戦後いくども「戦争責任論」が問われ、「なぜ負けたのか」についても多くの論説が現われた。しかし、その戦争を身をもって経験した人びとが考えていたことと、戦後に生れた人間では、いうまでもなく戦争に対する感覚が異なる。ただそれを「戦中派」「戦後派」と分けてしまうと、戦中派にも戦争を軍中枢にいて指導した人たちと、ただの兵士として戦った人たち、空襲で逃げ惑った庶民ではかなり違うだろうし、未成年の軍国少年だったか、朝鮮や満州にいたか、沖縄にいたか、疎開地にいたかでも体験はさまざま異なるのは当然だ。いずれにせよ生き残って戦後を生きたという点では、ぼくたち戦後生まれだって、戦後焼け跡闇市育ちもあれば、地方農村が人にあふれていた時代に育った人もあれば、もっと後の高度経済成長期に育った人もいるわけで、ひとまとめに戦後派、戦中派などと分類してもあまり意味はない。むしろ、ある時点で多数の人々が考え感じていたことが、なにかをきっかけに大きく転換していく時期があり、戦争という大きな出来事についても、日本人の歴史意識には20年から25年くらいの幅で見ると、かなりの変動があるというのが歴史家の見方だろう。
吉田裕『日本人の戦争観』第一章の「歴史意識と政治――90年代における政策転換――」は、20世紀最後の10年に注目する。まず細川連立政権での首相発言「侵略戦争であった」から始め、それを国民世論も過半数が認めるという、侵略戦争論が一見1993年時点の国民の多数派であるかにみえていた状況が、実は戦争責任や戦争への真摯な反省や理解からではなかったこと、経済大国日本がアジア諸国にリーダーシップを確保し、国連常任理事国入りを目指したいという政治家の願望から、過去の清算を必要とした政治的辻褄合わせに発していたことを指摘する。この本は1995年前後に書かれていて、その時期はバブル経済は破綻していたものの、日本はまだ中国より経済力は優越し、戦後50年記念という節目にあった。自民党一党支配が行き詰り、国民新党、新生党、社会党などが連立して「非自民、非共産」の細川政権ができた。支持率は空前の71%、なにかこれまでとは違う新しい政治への期待が一瞬国民をとらえたともいえるが、細川政権は1年ももたず、自民党を割って出た新生党の羽田孜が後継になるが2カ月しかもたず、小沢一郎の画策が失敗して分裂し、自民党が政権の一角に戻って自社さ連立の村山政権になったのが1994年の政治劇だった。
保守政治家は言うに及ばず、中道リベラル派を自任する政治家も、基本的には過去の戦争について明確な歴史像をもたず、周辺諸国から非難されると謝り、内向けには「結果としての侵略行為」をなるべく都合よく無責任に考えておく、という態度は共通していたと考える。国民もまた、戦争責任についてあまり真剣に考えてはいなかった。
「かつての戦争を侵略戦争であると明確にに意識している人々が多数派を形成しているのであれば、羽田首相の「侵略行為」発言に対してもう少し厳しい反発があってもよさそうなものだが、世論の反応はほとんど見られないし、マスコミもこの発言をあまり問題にしていない。
この点で、この問題を考える際の手がかりになるのは、82年10月にNHK放送世論調査所が行なった、「日本人の平和観」に関する世論調査である。この調査で注目に値するのは、明治以降の日本の対外的膨張を、「侵略の歴史だ」と見なす人が51.4%に達する一方で、「資源の少ない貧しい日本が、他国に軍事進出して行ったのは、生きるためのやむを得ない行為だった」とする人が44.8%にも達している事実である。「やむを得ない」「しかたのない」戦争であるのなら、そこには「責任」という観念が生じるはずもない。恐らくは、そのことの直接の結果として、「一般国民の戦争責任」についての質問では、「国民に責任はない」とする人が36.3%で、第一位を占めている。また、太平洋戦争が「アジア諸国の独立回復を早めて点は、評価すべきだ」としている人が45.5%に達している事実も見逃すことができない。
表2 「日本人の平和観」調査
全国16歳以上の国民を対象、有効回収数2623人(回収率72.9%、単位%)
・日本は、明治から昭和20年の敗戦まで、数多くの戦争や領土拡張を行ってきましたが、あなたは、これを、どのように評価していますか。〔回投票〕のAからDまでのそれぞれについて、〔回答票〕の1,2,3の中からお答えください。
(A) 日清戦争から太平洋戦争までの50年の日本の歴史は、アジア近隣諸国に対する侵略の歴史だ
(B) 資源の少ない貧しい日本が、他国に軍事進出して行ったのは、生きるためのやむを得ない行為だった
(C) 朝鮮・韓国人や中国人に対する、明治以来のひどい差別・迫害や忌まわしい虐殺事件については、日本人として、心から反省すべきだ
(D) 太平洋戦争が、欧米諸国の圧政に苦しんでいたアジア諸国の独立回復を早めた点は、評価すべきだ
(A) (B) (C) (D)
そう思う 51.4 44.8 82.5 45.5
そうは思わない 21.9 38.7 5.2 25.1
昔のことだから、自分には関係ない 10.4 4.7 4.2 5.5
わからない、無回答 16.3 11.9 8.2 23.9
・あなたは、昭和6年から15年に及んだ日中戦争・太平洋戦争について、一般国民の戦争責任を、どのようにお考えでしょうか.〔回投票〕のように分けると、あなたのお考えは、どれに近いでしょうか.
一般の国民は、軍国主義の教育や情報にだまされ、ひどい目にあった被害者であって、国民に責任はない 36.3%
当時の国民は、大部分が軍国主義の讃美者・協力者であって、少なくともアジアの人々に対しては、加害者である 29.5%
あの戦争は、日本の自衛とアジアの平和のためにやったものであって、軍国主義だとか、被害者だ 加害者だというような問題ではない 17.6%
その他 0.5%
わからない、 無回答 16.1% 計 100.0
(内閣総理大臣官房広報室篇『全国世論調査の元凶・昭和58年版』大蔵省印刷局、1984年)
つまり、ここには、羽田首相の「結果としての侵略戦争」論とひびきあうような意識の構造がくっきりと現われている。後に詳しくみるように、このような国民意識のありようは、その後、現在に至るまで基本的には変わっていない。羽田首相の「結果としての侵略戦争」論に対する世論の沈黙の背景には、こうした意識構造が横たわっているとみるべきだろう。
また、先にふれた朝日新聞社の戦後補償問題に関する世論調査でも、確かに若い世代ほど補償について肯定的という注目すべき傾向が現われている。具体的に見てみると、補償要求に対する政府の対応についての回答では世代間の差がいちじるしく、二、三〇代では70%近くが、「事柄によっては応じるべきだ」としているが、50歳以上の戦争体験世代では「応じる必要はない」が40%をこえ「応じるべきだ」を上まわっている。しかし、この世論調査のより詳しいデータを収録した朝日新聞戦後補償問題取材班『戦後補償とは何か』(朝日新聞社、1994年)を見てみると、設問によっては微妙な結果が出ているのがわかる。表3は戦後補償問題への関心を聞いたものだが、若い世代の方が「あまり関心はない」と答える人の割合が高いことに気がつく。つまり、若い世代ほど戦時中の価値観や思想にとらわれていない分だけ自由で柔軟な対応が可能になるとは必ずしもいえず、むしろ、無関心層が少なくないのである。世代がさがるほど戦争に関する当事者意識が希薄であり、また学校教育の場で戦争の生々しい実態について教えられることがほとんどないことを考えるならば、これはある意味では当然の結果だといえよう。
太平洋戦争は「侵略戦争」か否かを聞いた毎日新聞社の先の世論調査でもほぼ同様の傾向が現われており、「若い世代では『わからない・無回答』の多さが目立ち、六〇代以上の五人に一人が、二〇代では三人に一人に上る」と指摘されている。
以上のような諸事実を考慮に入れるならば、世論の変化が意味しているのは、戦争責任や戦後処理の問題をめぐって厳しい対日批判が厳然として存在していることを自覚し、これに現実的に対応していこうとする人々が増えているという事実であって、そのことはそのまま日本人の歴史観や歴史意識の深まりを意味していないとみることもできる。
反米ナショナリズムの陥穽
ところで、世論の動向に関連して、ここで注意を払う必要があるのは、八〇年代から九〇年代にかけて、日本人の中に台頭してきた「嫌米感情」という名の反米ナショナリズムの問題である。外務省は、日米安保条約改定三〇周年の事業の一環として、「米国の内外情勢の日米安保体制に及ぼす影響」と題する研究を佐藤清三郎東大教授を中心にした学者グループに委託していたが、その中間報告は、「日本で反米意識という形のナショナリズムが高まりつつあり、日米安保体制を動揺させる可能性が出てきた」と警告を発していると報じられている(『朝日新聞』91年3月19日付)。事実、毎日新聞社が同年10月に日米両国で同時に実施した世論調査によると、日米安保条約については米国で「強化」「維持」を主張する人が45%で、「縮小・将来廃棄」「ただちに廃棄」の33%を大きく上回ったのに対し、日本では「縮小・将来廃棄」が42%でトップを占めている(『毎日新聞』91年11月16日付)。その後も、同様の傾向を示した世論調査がいくつか現われており、日本人の意識の深い所で、ある変化が生じつつあることを予感させる。
問題は、このような反米ナショナリズムが日本人の戦争観にも微妙な影響を及ぼしつつあるようにみえることである。この反米ナショナリズムと戦争観の関係を最も端的な形で示しているのは、自民党の石原慎太郎衆院議員の場合だろう。石原議員は93年10月5日の衆院予算委員会で、41年12月に開始されたアジア・太平洋戦争の性格を、日本の対中国戦争、東南アジアに植民地を保有する欧米列強と日本との戦争、戦争末期のソ連の対日参戦によって開始された日ソ戦争の三つに区分した上で、日ソ戦争がソ連の対日侵略戦争であったことを強調しながら、「日本と同じ植民地主義でアジアにも出張ってきた列強」との戦争である二番目の戦争の性格について、次のように細川首相を追求した。
私たちが戦争に敗れはしたけれども、敗者としてオランダやフランスやアメリカやイギリスに謝罪する、……今改めてそういう謝意を抱く必要はどこにもない。全くこっけいなことで、同罪ではあっても、どちらの罪が重い、軽いという問題は、比較にならない。
だから私は、先ほど言った太平洋戦争の第二の要因である、つまり植民地主義の列強と日本がこの太平洋地域で相まみえた、その戦争に破れた責任というものを、この時点で改めて謝罪するという形で国民が胸にする必要は毛頭ない、私はそう思いますけれど、いかがですか。
欧米列強に対する戦争の性格を、戦争の他の性格と区別して把握しようとする発想自体は、竹内好が、「近代の超克」(『近代日本思想史講座7』筑摩書房、1959年)や「戦争責任について」(『現代の発見3』)などの論文の中で早くから主張していたことである。特に後者の論文の中で竹内は、自説について、「日本の行なった戦争の性格を、侵略戦争であって同時に帝国主義対帝国主義の戦争であり、……侵略戦争の側面に関しては日本人は責任があるが、対帝国主義戦争の側面に関しては、日本人だけが一方的に責任を負ういわれはない、という論」と明解に説明している。
石原議員の質問は、日本が朝鮮を併合しなければ、「あのときの朝鮮の混乱からいえば、隣の清国なりロシアに併合されていたことは間違いがない」という言い方や、「国際法の上では合法的に獲得したシナ大陸の権益というものをめぐっての紛争が、結局は日中間の長い戦争になった」という言い方に示されるように、竹内ほど明確にアジアとの戦争の侵略性を認めているわけではない。とはいえ、石原議員の議論がその基本的発想を竹内から借りているのは、ほぼ間違いない。
もちろん、アジア・太平洋戦争が東南アジアの植民地の争奪をめぐる帝国主義国相互の戦争という一つの側面を持っていたことに関しては、誰しも異論がない。しかし、アジア諸国に対する戦争と欧米諸国との戦争を機械的に分離し、この二つの側面を対立させる議論の仕方については、すでに家永三郎が『戦争責任』(岩波書店、1985年)の中で、次のように批判していたことを想起する必要がある。
日本は中国侵略戦争を継続するために、これを中止させようとするアメリカ・イギリス・オランダと開戦することになったのであって、中国侵略戦争の延長線上に対米英蘭戦争が発生したのであり、中国との戦争と対米英蘭戦争とを分離して、別個の戦争と考えることはできないのである。
このアジア・太平洋戦争と日中戦争との連続性については、戦後、比較的早い時期のもっともポピュラーな戦記の一つである、伊藤正徳『帝国陸軍の最後 侵攻篇』(文藝春秋社、1959年)が、今日の段階からみてもきわめて重要な問題提起を行っていることを指摘しておきたい。すなわち、伊藤によれば、「もし日支事変がなかったら、日米戦争は之を欲しても戦い得なかった」。なぜなら、日本が開戦段階で英米に対抗できるだけの戦力を保持できていたのは、日中戦争中に、「兵力動員の上から、軍事産業大拡張の上から、武器の大蓄積の上から、日本はかつて夢想もしなかったような戦力を蓄えるのに至った」からであり、そのために必要な巨額の予算の獲得は、日中戦争の戦費として計上された臨時軍事費からの「流用」によって可能となった。つまり、伊藤によれば、軍は「日支事変を利用して、平時は予算的に不可能であった弱点の補修から基本戦力の増力まで仕上げて了ったのである」。
この臨時軍事費特別会計は、戦争の終結までの全期間を一会計年度とする特別会計である。予算編成に際しては大蔵省の審査も不十分な形でしか行われず、また、議会の審議でも、予算の細目が知らされないため、申し訳程度の秘密会でそのまま可決された。それだけに、軍にとってはきわめて旨味のある予算であり、日中戦争勃発時の「拡大派」の政治的な狙いの一つは、戦争を口実にした臨時軍事費の獲得にあった(拙稿「『国防国家』の構築と日中戦争」『一橋論叢』1984年7月号)。
この臨時軍事費のうちで、どれだけの予算が実際に軍備の拡充に転用されていたのかは判然としない。ただ、参謀本部篇『杉山メモ(上)』(原書房、1967年)によれば、41年2月3日の大本営政府連絡会の席上で、中国戦線の縮小によって戦費の節減をはかるべきだと主張する松岡洋右外相の発言に対して、海軍の代表が、「海軍ノ第一線消耗ハ一年ニ六千万円程度他ハ全部貯蔵ナリ」と答え、陸軍の代表も「陸軍ノ消耗ハ十七、八億検討他ハ貯蔵ナリ」と答えているのが参考になる。1940年度の臨時軍事費のうちで陸海軍省所管のものは、大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史4』(東洋経済新報社、1955年)によれば、57億2254万円だから、日中戦争の直接経費は全体の31~33%程度ということになる。
また、東条英機陸相も、41年4月5日の陸軍省内の会議の席上で、「又例えば数十億の軍費といっても実際第一線で使用するのはせいぜい二〇億で、他のすべては国家百年のための経費である」と発言していて(陸上自衛隊衛生学校偏『大東亜戦争陸軍衛生史1』非売品、1971年)、先の『杉山メモ』の記述を裏づけている。
ちなみに、この臨時軍事費の中から多額の機密費が支出され、それがまた軍の「政治資金」にもなっていたようである。陸軍省軍務局軍事課予算班長の経歴を持つ加登川幸太郎は、この点について、「何に使ったかわからんけど、東条さんが総理大臣になった時、…‥三百万円という機密費三口を内閣書記官長に渡せ、と来るんだね。…‥あの頃二百万円あったら飛行機の工場が一つ建ったんだから」ときわめて率直に回想している(若松会編『陸軍経理部よもやま話』非売品、1982年)。
臨時軍事費の話が少し長くなってしまったようだ。ただ、ここで満州事変・日中戦争とアジア・太平洋戦争の連続性という問題にこだわりたかったのは、反米ナショナリズムと結びついた形での戦争観が日本人の関心を日米関係という狭い問題領域に押し込めることによって、結局はアジアとのかかわりを見失わせるという点を強調したかったからである。
同時に、石原議員の追求の仕方をみていて気がつくのは、彼が戦後処理の問題を全く視野に入れていないことである。そして、戦後処理のあり方という問題を考慮に入れるならば、一見鋭くみえる石原議員の追求も俄然色あせたものとなる。なぜなら、冷戦の激化という状況の下でアメリカは、日本を対ソ包囲網の中に組み入れるために、アジア・太平洋戦争の戦後処理に関しては基本的に宥和的な対日政策をとった。サンフランシスコ講和条約でアメリカが対日賠償の請求権を放棄している事実が端的に示しているように、対日講和はあくまで「寛大な講和」だったのである。こうした中で日本政府は、サンフランシスコ講和条約の第11条で東京裁判の判決を受諾するという形で最小限度の戦争責任を認めることによって、アメリカの同盟者としての地位を獲得したのであり、その点では日本は冷戦体制の受益者だった。
このことが示唆しているのは、日本人のアジア・太平洋戦争観はこうしたアメリカ主導の戦後処理のあり方と密接に関連しながら形成されてきたのではないかということである。だとするならば、アメリカとの協力・協働によって築きあげてきた自らの戦後史そのものを問い直すことなしに、アメリカに対して責任を負う必要がないという議論だけを一方的に主張するのは、率直に言ってやはり欺瞞的だと思う。」吉田裕『日本人の戦争観 戦後史の中の変容』岩波現代文庫、2005.pp.12- 22.
戦後の保守政治家の多くは、日米安保と講和条約と東京裁判で組上げられたアメリカに首根っこを押さえられた体制を、自分たちの権力と天皇制存続のために承認し、ことあるごとにアメリカの意向を最優先することで生きのびる他ないと考えていた。「侵略戦争論」についても、それを国民が日本の支配権力が国民の犠牲において遂行したと考えるとき、非難と攻撃がアメリカと密着した日本保守政治に向かうのだけは避けたかった。60年安保で噴出した「反米」意識はまさに、そうした危険を顕在化したものと意識したであろう。だから本音は再軍備や改憲を企みながらも、憲法の平和主義、非軍事的な商人国家の旗は降ろせなかった。しかし、80年代になると、経済大国の自負とアジアへの進出という誘惑に駆られて、ふたたび周辺国との関係を再構築する必要にかられ、侵略戦争への反省・謝罪を口にする。しかしこれは中途半端で保守派の中から少しも反省していない発言が沸き出すやぶ蛇でもあり、それが韓国・中国から反発を招く事態になる。結局過去の汚点を隠蔽や蒸し返し、やったやらないの非難の応酬合戦になってしまった。まことに不幸ななりゆきだが、歴史意識へのじゅうぶんな理解と配慮を欠いた憎悪の掛け合いは、なにひとつお互いの利益をもたらさない。では、日本の左翼リベラル派(そういうものがあればの話だが)は、これに対してどうふるまったのか?実はこっちの方も、戦争責任や侵略戦争論について明確なスタンスをもっているといえないのではないか。ただ9条を守れ、反戦平和というお題目を唱えていただけではないか。昔のことはもういいから、未来指向で仲よくしましょうよ、では安倍晋三と変わらない。少なくとも敗戦直後には、昭和天皇の戦争責任はもっと真剣に問われていたはずだ。
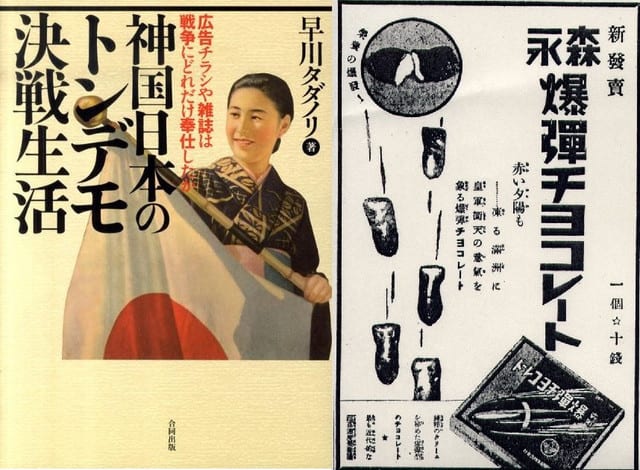
B.軍国の母、はどうして「母」でしかないのか?
靖国主義というイデオロギーがあるとすると、それは天皇の国家のために命を捧げるほど崇高な行為はなく、兵士として名誉の戦死をした息子を英雄として褒めてあげなければ、母が悲しみ霊は浮かばれない、というものだろう。言い換えれば、軍隊を持つ国家の支配者にとって、自分の意のままに兵士に喜んで死んでもらうためには、その死を意義付け、悲しむ母に栄誉と納得を与えなければならない、という心理にもとづく。特攻隊員の遺書などにみられるように、戦前の皇国教育を受けて育った日本の男の子たちにとって、父親よりも兄弟よりも何よりも、愛着と郷愁の象徴は母だった。息子の眼からみて、三世代同居のイエ制度の中で、ひたすら夫のため家族のために汗水たらして苦労していた母の姿は、国家や天皇陛下というシンボル以上に、命を捧げるに値した。でも、そういう「軍国の母」というイメージこそ、教育とジャーナリズムが手を変え品を変え作り上げた虚像ではなかったか。
「日本婦道の暗黒――軍国の母ぶり競争
当時、もっともよく読まれていた婦人雑誌である『主婦の友』が、敗戦に至るまで何度も何度も繰り返した軍国の母顕彰キャンペーン「日本婦道の光」シリーズは、回を重ねるごとにより強烈に・より陰惨なものとなっていった。何もそれは戦局が悪化したからというわけではなく、より刺激の強い・より泣ける物語を求めて主婦の友編集部が走り回ったからにほかならない。やがて連載は、お国に捧げた子/生んだ子の数の比率競争と化した。
例えば「大空の母」なる称号が与えられた住原モトさんのばあい(『主婦の友』昭和十八年三月号)、愛児五人はことごとく飛行兵となり、
二男は夜間飛行演習中に墜落死
三男は吉林省で墜落し
四男は練習生を乗せての訓練飛行中に墜落死
五男はビルマ北部国境攻撃に機長として出動中に倒れ戦死
……という有様。記事が掲載された時点で生存していたのは長男の住原正一航空大尉ただの一人で、まさに映画『プライベート・ライアン』(S・スピルバーグ監督、1998年)さながらの状態である。彼女の長男氏も戦争が終わるまで生き残れたのかどうかは定かでない。
こういうばあい、大日本帝国は周到にメディアを動員して、同情を集めるのに抜かりはなかった。「四児殉国の栄光」を大々的に発表し、東条英機夫人は弔電をおくり、女学生からは「お母様のような日本の母に私もなります」という手紙が寄せられ、福岡県のある鉄工所従業員一同からは「三百五十円」もの醵金が……と「国民の感激と敬悼は、刀自〔年配の女性への敬称〕の一身に集められた」のだそうだ。靖国神社を統治システムに組み込んだ神国・日本は、死者の利用法にかけては昔から高度な技術を有していたわけだ。
ほかにも、「五人の子どもをことごとく海軍軍人に育て上げた母」(昭和十九年四月号)、「二児を大東亜戦争に捧げ六人の孫の養育に営々土と戦ふ岩淵ゆり刀自」(昭和二十年一月号)「四男児を海軍軍人に育てた軍国の母 岩田ヒモ刀自」(昭和二十年二月号)など枚挙にいとまがない。少子化の現代から見れば、よくもまあこれだけ子どもを産んで兵隊に差しだしたものよ…‥と思う。ともあれ、「産めよ殖やせよ」スローガンを忠実に履行すれば、どんな「軍国の母」になれるのか、そんな“期待される〈産む機械〉像”は、このような軍国美談とともに形成されたのだろう。
〈靖国の妻〉たちの貞操問題
父親が戦死した後も健気に生きる遺児たちが、国を挙げて称揚される一方、残された未亡人たちには、立派な〈靖国の妻〉でありつづけることが厳しく要求された。
昭和十四年に、帝国在郷軍人会本部が刊行した『軍国家庭読本 締めよ、こころ』は、タイトルからして端的なように、〈靖国の妻〉たちの生活態度を思いっきり引き締めるために作成されたパンフレットで、「期待される軍国婦人像」をストレートにあらわしている。その中でも、かなりの量が割かれているのが〈靖国の妻〉たちの「貞操問題」だった。同パンフレットの最終章は「日本婦徳に還れ」と題され、未亡人の貞操をどう守るのかに費やされている。
婦人本然の美徳であります徹底的な愛は、兎角一面において盲目的であり、熱狂的であり、偏狭である恐れがあるのであります。一時的の愛に溺れて、永遠の幸福を忘れたり、或はあるものを偏愛するとかいふような事例がないではないのであります。……つまらぬ劣情や、一時的の感情に左右されての事が多いのであります。此の偏狭な熱狂的な愛は、婦人として最も慎まなければならぬ所であります。
彼らは、女=つまらぬ劣情に左右されるものという徹底した女性蔑視観に基づいて、「靖国の妻」の大義名分を振りかざし、女性たちにタガをはめようとしたのである。こうした「道徳」の強制は、「理想としては、一生独身生活を送るのが至当」「親兄弟や社会が、何等要求する事がないに拘はらず、その身の勝手や、情欲の為に、再婚するやうな事は許すべからざる罪悪である」(ともに同書)などという人な結論をもたらした。まったく大きなお世話である。婦人の「劣情」「情欲」に注目しこだわっているところに、帝国在郷軍人会のいやらしいオヤジ目線を感じるのは私だけではあるまい。
結局のところ「日本婦道」とは、すべて「男」「夫」そして彼らを預かる「軍」の男根的三位一体サイドからの身勝手な注文で埋め尽くされていたのである。」早川タダノリ『神国日本のトンデモ決戦生活』ちくま文庫、2014.pp.50-54.
夫や息子を軍隊で死なせ、悲しみに暮れる母に、日本婦道は再婚を禁じ、最後までイエに尽くして二夫にまみえてはいけない、とはどういう心情から出てきた思想だろう。女は一生、一人の男、つまり夫だけに仕え、身も心も捧げて夫のイエに骨を埋めることが唯一の正義だという思想。それは早川氏もいうように、自分はいくらでも娼婦を買ったり浮気をしても、妻だけは貞操を守って自分にだけ尽くすべきであり、そういう妻であってこそ国家に命を捧げたとしても満足できる、という非常に自分勝手な思想である。こんな思想に殉じる女性が「軍国の母」だとしたら、日本って最低の国家だったな。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます