A.批評という事
『季刊藝術』という雑誌があった。1967年に創刊され79年まで続いた。同人として江藤淳(文芸評論)、遠山一行(音楽評論)、高階秀爾(美術研究)が名を連ね、古山高麗雄(作家)が編集人となって、さまざまな寄稿者の論稿を載せた。学生だったぼくは、この『季刊藝術』を毎号購入して読んでいた。音楽、美術、文学それぞれの第一人者が力のある論稿を載せ、ここからデビューした若い才能もあった。いわゆる論壇誌とは一線を画したレベルの高い芸術論を中心にした雑誌は読みごたえがあった。80年代以降の柄谷行人らの『批評空間』や『現代思想』につながる側面もあるが、ポストモダンのフランス現代思想がブームになって以後の、観念的な論文の山に比べ、『季刊藝術』ははるかに幅広くゆるやかに、どのような立場にせよ一般読者が抵抗なく読める文章が多かったと思う。
福田恆存といえば、旧仮名遣いを主張したり左翼文化人を批判した保守派の重鎮の一人として知られていた。しかし、彼がもっとも力を注いでいた仕事は、演劇であり、戯曲であり、自ら劇団を主宰して公演を行い、俳優、演出家、演劇人に幅広い影響を与えていた、ということを今頃知った。吉田秀和のオペラ論の中に、福田恆存が書いていた演劇評論のことがでてきて、ちょっと気になって福田恆存の本をいくつか読んでみた。とくに演劇論が具体的で非常に面白いので、しばらくとりあげてみようと思う。
「ここに一つ読者の了解を得ておきたい事がある・問題は私は財団法人現代演劇協会の理事長であるが、その私が翻案者、翻訳者、あるいは原作者として、しかも同時にその演出者として参加した、同協会附属劇団昴(すばる)の公演、すなはちコルネイユの『嘘つき男』の翻案に近い『嘘から出た嘘』や自作の『解ってたまるか!』などもまたこの劇評の対象として、看過する訳にはいかず、その場合、果たして公正を期し得るかどうか、たとへそれが可能であるにしても、内外にそれが認めてもらへるかどうかといふ事である。たまたま今月は観た芝居の数が少いので、その問題について日頃からの私の考へ方を述べてみようと思ふ。結果としてはそれは劇評論とでもいふべきものにならう。第一に、至極単純な事だが、劇評に限らず、人は絶対に公正たり得ない。公正であらうと務める事、客観的であらうと務める事、それと公正であり客観的であるといふ事とは捌事である。私達は公正であり客観的であらうと務めながら、また最善を尽くしてさうあらうと務めながら、そこには必ず私心が立入り、私達は絶対に主観から逃れられない。だからといって、居直って公正を無視し、主観、私心に安住してよいといふ事にはならない。公正とは何か、客観性とは何か。それは私心や主観を排する事でもなければ、自分はいつもさう行動してゐると自己欺瞞をする事でもない。むしろ、私心や主観に筋を通し、一貫性を持たせ、その「偏向」に責任を持つ事、それ以外に公正や客観性への手掛かりを私達は持ち得ない。
第二に、それにしても、自づと程度の差といふものがある。科学技術やスポーツの場合、問題はすこぶる簡単である。いかにフロックであれ、投手の頭上を越えたホームランをファウルと見なしたり、九十メートル以上跳んだスキーのジャンパーを九十メートルしか跳べなかったものの次位に評価したりする様な「主観」「私心」の入込む余地は、スポーツでは決してあり得ない。科学技術においても欠陥車の方が優れてゐるといふ論議は成り立たない。たとへ人類滅亡の具と言はれる核兵器でも、殺傷力の劣ってゐる物の方が高く評価されるといふ事はない。それがもしあるとすれば、それは科学的基準ではなく、道徳的基準による場合である。スポーツでもあまり強くない貴乃花が強い北の湖より人気があるとしても、その人気によって貴乃花が横綱になり、北の湖が関脇に落とされるといふ事は起り得ない。が、藝能界ではしばしばさういふ事が起る。世界中で芝居が一番隆盛を極めてゐる英国においても、たとえば、ペギー・アシュクロフト、デボラ・カー、イングリッド・バーグマンの三人を較べれば、役者=技術者としては、スポーツ界と同様、この順位は誰が見ても絶対に狂はない。役者の技能にしても、そこには主観や私心の入込む余地のない客観的基準と称し得るものがある。が、人気となれば、右の順位は明かに逆転する。その場合、バーグマンをカーより高く買ふ人がゐれば、それは好みといふ主観、私心によるものだといふ、大げさに言へば「うしろめたさ」「はばかり」の意識がどこかに働いてゐる。もしさうではなく、舞台藝術においては、人気もまた役者にとつて必須条件だといふ、劇評家として、彼自身の演劇観があるなら、その理想=主観に筋を通さねばならず、さうなると、単なる演技の技術家たる役者だけでなく、戯曲の評価にも関わって来る。劇評家としての彼はカワードやモームの作品の方が、ワイルド、ショウ、あるいはシェイクスピアより偉大な作品だといふ論議、少なくともさう言い切る責任を持たなければならなくなる。
第三に、今、英国の三女優を例に挙げ、この順位は誰が見ても狂はないと言った。その程度の客観性は役者、演劇藝術にもある。四百年の伝統を持つた国には当然の事である。が、日本にはそれすら全く無い。少なくとも新劇には未だかつてそれらしきものは一度も確立された事は無い。その結果として起る現象は、演劇は、あるいは演技は、いかにあるべきかについてはもちろん、その現状がどうなつてゐるのか、どうしてかうなつてゐるのが、このままではどうなるのか、さういふ事を一切考へず、またそれを考へる必要があるといふ事すら考へず、それを考へる能力も手立も知らない人間が、自分の好みのままに、しかもその好みが演劇に対する好みではなく、何か他のもの、たとへば、女なら細面より丸顔の方が好きだとか、すしにはわさびよりからしの方が、いや、場合によつてはあんこの方面より丸顔の方が旨いとか、その種の好みの系列に準じ、自分の主観、私心をそれと意識する事さへせず、意識しない以上、居直ることもせず、聊かの「うしろめたさ」も無くはなはだ素直に劇評の筆を取る、さういふ事になる。
第四に、さういふ人達に限つて、独りよがりな、自分達業界にしか通用しない、時には自分だけにしか通用しない、といふ事は自分自身にも解ってはゐない、むづかしい言葉を使ふ。前にも言った様に思ふが、私には「演劇空間」といふ言葉の意味が解らない。さういふ言葉を使ってゐる人で、それが普通の日常言語では表現し得ない重要な意味を持つてゐる事を知ってゐる事を知つてゐる人がゐたら、是非説明して戴きたい。その他にも、「劇状況をふくらまし」などと文章にぶつかると、私など狐に摘ままれた思ひをする。まづ「劇状況」といふ言葉の意味が解らない。またそれが何にせよ、「状況をふくらます」といふ事の意味が解らない。「ふくらます」と言はれると、懐、腹、胸、風船などを連想してしまふのだが、それを抽象的な「状況」に適用した場合、一体どういふ状況になるのかさつぱり見当が付かなくなる。その筆者は同じ文章の中で「劇状況を濃密に醸成しえなかった」と書いてゐる、それから察すると、私には訳の解らない。殊に「外質的演技が先行し、内的行動が処理しきれてゐない」などと言はれると、高が芝居じゃないか、カントが料理の味に文句を付ける様な言ひ草はやめてくれと怒鳴りたくなる。いや、カントだって、料理に文句を付ける時は、「塩がききすぎた」とか、「焼きが足りない」とか、極く普通の、具体的な言葉を使つたに違い無い。料理には料理の、芝居には芝居の、それぞれ具体的な注文の出し方がある筈である。私は演出家として、まだまだ未熟だと思つてゐるが、「外質的演技が先行してゐる」とか「内的行動が処理しきれていない」とか、そんな「哲学的」抽象語でダメ出しをした事は一度も無い。ダメはすべて日常言語で事足りる。劇評も同様である。具体的な日常言語で事足りるばかりでなく、その方が有効であるのにも拘らず、自らも定義不可能な難しい抽象語を使ふのは、ごまかしであり、逃避であり、責任回避であり、責任回避である。たとへ平易でも「好演」「力演」などといふ言葉も具体的ではなく、それだけでは無意味、不可解である。「素晴らしい」から「まあまあの出来」まで、その間のどれをも蔽ひ得る様な曖昧なごまかしでお茶を濁してまで劇評家の権威といふ仲間内の虚栄心を保たうとする事はあるまい。
藤木敬士宛
昨年の『嘘から出た嘘』(昭和五十二年九月・三百人劇場)のあなたは「好演」かつ「力演」でした。あなたの演じたドラントは文字通りの主役らしい主役であり、あなたが私達の劇団に入って以来、これほどの訳を与へられた事は無かった。それだけにあなたは全力を挙げてこれに当った。私もその為に最善を尽し、相手のクラリス役の田島令子がなまなか器用なだけに、結果的にはその方が手抜きになつてしまひ、田島には気の毒だつたと反省してをります。正直に言って、あなたは役者=技術家としては未熟です。歩き方とか、階段の降り方とか、身の翻し方とか、尻餅の付き方とか、さういふ極く初歩的、基本的な動作すらまだ身に付けてゐません。さういふと決定的な否定の様に聞えるかも知れませんが、もしあなたがこの書をはじめから読んできたなら、大きな顔をして一枚看板を掲げ、大興行主に支へられてゐる役者といふ名の素人が、同じような批判を、それこそ具体的に、綿密に、この私によつて受けてゐる事を御存じの筈ですし、また稽古中、準演技員や演劇学校専科在学中の役者の卵は勿論の事、あなたの先輩格に当る一人前と思はれてゐる役者色腕さへ、同じ憂き目に遭ってゐるのを見てゐるのでせうから、別に屈辱感に打ちのめされるといふ事もありますまい。
初日以来、劇団の内外を問はず、かなり沢山の人達から、ドラント役のあなたに対する褒め言葉を耳にしました。が、私の根性が曲ってゐるせいか、この場合に限らず、自分、および自分の関係者に対する褒め言葉といふものを、折角褒めてくれた人には失礼かも知れませんが、私は容易に信じる気になれないのです。私は常に自分自身の手応へしか信じられない性だからでせう。「藤木はよくやつた」といふのは、「藤木があそこまでもやれるとは思はなかった」といふ事に過ぎず、文字通り「力演」だつたといふ事でしかありません。「力演」といふ言葉を強ひて定義すれば、「自分の力以上の仕事をしようと純粋な情熱を持ちながら、その為に技術の力不足と格闘する情熱の余剰が客の目に快く感じられる演じ方」といふ事になりませうか。言換えれば、それは自己陶酔でしかない。この作品は、幾ら私が翻案の手を加へてあっても、やはりコルネイユの古典劇であります。自己陶酔、あるいは私の定義した「力演」といふ興奮剤のみに頼って、命脈を保つといふのでは、前衛劇のお家藝と少しも変わるところがありません。
実際、あなたの芝居に対する純粋、誠実な態度には頭が下がります。天下の婦女子を湧かせた往年のロック歌手藤木孝の面影は、少なくとも今日、劇団内で接触する限り、あなたのどこにも見出せない。が、自由、奔放なロックの先駆者が芝居となると、どうしてああ硬直するのか、歌手、踊手に限らない、人気を一身に集めた人間といふものは、その人気を支えてくれてゐると頼り切ってゐるファンの前では、幾らでも自由、奔放になり得るものです。時には宮田輝の様に厚かましくもなり得る。言換へればファンに甘え、ファンを舐めているゐるのです。彼は何をしても許されるどころか、文士劇同様、失敗をすれば、かへつて愛される。芝居に対しても、友人に対しても、日頃から常に謙虚なあなたではありますが、やはりあのロック歌手時代の甘えがどこかに残ってゐるのではないか、その甘えと謙虚は紙一重の差、あるいは一枚の紙の裏表ではないか、これは私の思ひ過しでせうか。
あなたがドラントで「成功」したのは、あの役が比較的独り芝居で相手を無視しても、ほとんどぼろが出ないからです。しかし、芝居である以上、独り芝居に等しい芝居であっても、いや、さういふ役であればあるほど、相手役に対して慎重に付合はなければなりません。相手に主役の機会を与へなければなりません。が、あなたのドラントは「力演」のきりきり舞をすればするほど、誰もその中に入込めない円周を描き、相手をその外に弾き出してしまふ。その責任は演出家の私の中にもあります。が、そのあなたの独り芝居を抑えれば、主役としてのあなたが死ぬ。私はさう判断し、クラリスやクリトンを犠牲にしたのです。さういふ弁解めいた事は言ひたくないし、まして自分まであなたの犠牲者になつたなどと言ふ積りはありません。私はあへてあなたに賭けたのです。その責任は私にあります。ですから『解ってたまるか!』では付合ひと受けを主とする役、しかも、古典劇ではごまかせるが、写実のごまかしがしにくい現代日本の新聞記者という役をやってもらつた。他人事の様に言ふのが気が退けますが、その時のあなたはつひにぼろを出してしまひました。が、恐らく謙虚なあなたは独り芝居の「力演」の限界を思ひ知ったと思ひます。できる事なら、あなたの成長の為には、ドラントと新聞記者との間に『動物園物語』のジュリーかピーターの様な役を演じる機会があれば、これに越した事は無かったのですが、万事、物事はさう巧く運ぶものではありません。しかし、ドラントとはとにかくあなたとしては一応「成功」だったのですから、以上の私の忠言を反芻して、まづはせりふの遣取りのタイミングはもちろんの事、なほ今まで何人かの役者諸氏に忠言してきたごとく、相手のせりふを聴く力、自分のせりふが相手の心を動かしてゐるのを見る能力を、稽古中のみならず、日常生活において身に付けるように努めて下さい。」福田恆存『せりふと動き 役者と観客のために――』玉川大学出版部、pp.69-75.
この劇評はそのまま演劇論であり俳優演技論になっているが、とりあげる芝居や俳優に対する批評は実に辛辣で罵倒に近い。藤木孝さんは、歌手として「2万4千回のキッス」などで売れた人だったが、俳優を志して福田の劇団欅などに所属して、この頃から舞台で活躍を始めていた。福田にとってはいわば身内なので、厳しいが育てようとする視線がある。しかし、いわゆる新劇系の俳優座やもともとそこから分裂してきた文学座などの芝居への批判は、ここまで言っちゃうかというほどの厳しさである。
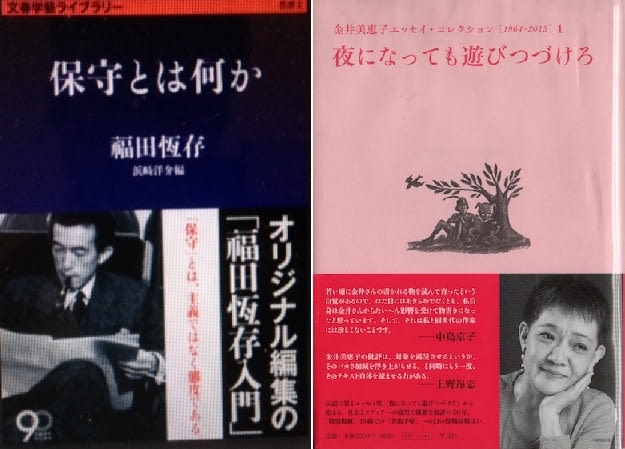
B.はしゃぎすぎ
急に5月1日から令和元年だからと、10連休もボーナスのように祝賀をはやすメディアには辟易してしまう。こうなりそうな予想はあったが、こういう雰囲気に異を唱えるのは表立っては難しいのかもしれない。でも、控えめなアイロニーくらいは出てくる。
「平成は終わる うやうやしく [令和に寄せて] 小説家 金井美恵子(寄稿)
「慶祝」ムード はしゃぐメディア
明治・大正・昭和と続いた個人の死による元号の変化が、近現代史を語るときに使用されはするものの、今日ほとんどの者は、日常的にも歴史を考えるときにも元号を使うことはないはずである。
この原稿が掲載されている紙面の情報を見れば、太ゴチック体の西暦の年数の後のカッコ内に、とりあえず、一応といった目だたなさで元号が記されていることからも、使用頻度がわかるというものだろう。元号を使用した時間的感覚のわかりづらいニュースを伝えるのは、NHKと産経新聞のニュースだけではないだろうか。
天皇の生前退位と即位による「慶祝」ムードは、十連休を政府が作ったせいで、あらゆるメディア(町の看板から広告、チラシ、テレビ、新聞、SNS)に子供っぽい、誰はばかることのないはしゃぎぶりが広がって、「平成の最後の※※」という、すべりっぱなしのギャグのような言い方が蔓延している。
もちろん「文化人」や「知識人」の間にはギャグではなしに、「平成」という時代を知的に分析し総括しなければならないという「義務」があるのだから、あらゆる文芸雑誌や総合誌や新聞では特集が組まれ、そういった「歴史的」場面のたびに登場して何事かを語る学者や小説家や批評家が、このいかにも「不安定」で「不透明」な時代の「時代精神」を語っている。
三十年前の改元時はどうだったのかと、手もとにある数少ない資料の『新潮社100年』(2005年)という社史の年表を見ると、一九八九年(昭和64年、平成1年)の文芸誌「新潮」は二月に「この一冊でわかる昭和の文学」という、身も蓋もなく軽薄な臨時増刊号を組み(井上ひさし、高橋源一郎、島田雅彦の座談会を掲載)、三月号では「文学者の証言 昭和を送る」という特集を編んでいる。
しかし、「昭和」は簡単に「送れる」ものなのだろうか。戦前と戦後に不自然な形で二分されている昭和天皇の「天皇の生まれてはじめての記者会見というテレビ番組」(昭和五十年)を見た小説家の藤枝静雄は「文芸時評」に「実に形容しようもない天皇個人への怒りを感じた」と書き、それは、戦争責任について質問された昭和天皇が、そういった文学的問題はわからない、という意味のことを答えたことに対する戦争体験者であり文学者でもある者の怒りだった。
長い戦争の後、人間宣言をして途中から「象徴天皇」になったのとは違って、「象徴天皇」というものを「国民の安寧と幸せを祈る」だけではなく「人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添」う存在として行動した「平成」の天皇は、平成最後というか在位中最後の誕生日会見に、「平成が戦争のない時代として終ろうとしていることに、心から安堵しています」と語ったのだが、もちろん「平成」という日本だけの元号で歴史の年代を数える「国」の内部だけのことである。
一九五八年の婚約、翌年の成婚馬車パレード以後、天皇・皇后は、普及しはじめた白黒テレビと創刊されたばかりの女性週刊誌によって国民に超スター的存在として親しまれ愛されてきたのだった。「平成」は世界最悪規模の原発事故をはじめ様々な大災害を何度も経験した時代だったが、その度に被災地を訪れる天皇夫妻の映像をテレビで見る機会が驚くほど多かったし、今年の四月に入ってからはさらに懐古的な映像が流され、訪問地の沿道では日の丸の小旗を振って迎える女性が、皇后について「拝むといったらなんだけど、やっぱり、拝みたい気持ち」と感極まって語り、「有難い」、「ただただ感謝です」と口々に言う。感謝?
小旗を持った女性たちだけではなく、「天皇陛下御即位三十年奉祝感謝の集い」では、北野武もお二人からお声をかけていただいた感激と感謝を語り、日本を代表する現代詩人は、美智子皇后の美しさと知性について、心底からの感嘆の言葉を書く。(「文芸春秋」五月号)
「私たち日本国民はなんという優雅で深切な国母を持ち、皇室を持っていることか、と幸福な思いに満たされ」(高橋陸郎)、もう一人の詩人は、女たちが蚕のそばで暮らしてきた何千年もの歴史をふまえて「蚕の命にまで耳を澄ませ」「万物の立てる響きにお心をお寄せになる皇后陛下の詩心はとても深い」(吉増剛造)と讃美する。それは詩人の言語的批評意識をこえた存在なのだろう。
そして、こうした心底からの讃美は生前退位で終わった「平成」が二度、いや三度、うやうやしい言葉の大群と共に終わることを暗示しているのだろう。」朝日新聞2019年5月2日朝刊19面、文化・文芸欄。
北野武はともかく、高橋陸郎、吉増剛造という詩人の名は、どちからといえば政治や時局とは無縁で高踏的な前衛詩人というイメージだったが、ここで皇室礼賛の詩を書いたというなら、やっぱり歴史は繰り返しているのかと暗澹たるものがある。
『季刊藝術』という雑誌があった。1967年に創刊され79年まで続いた。同人として江藤淳(文芸評論)、遠山一行(音楽評論)、高階秀爾(美術研究)が名を連ね、古山高麗雄(作家)が編集人となって、さまざまな寄稿者の論稿を載せた。学生だったぼくは、この『季刊藝術』を毎号購入して読んでいた。音楽、美術、文学それぞれの第一人者が力のある論稿を載せ、ここからデビューした若い才能もあった。いわゆる論壇誌とは一線を画したレベルの高い芸術論を中心にした雑誌は読みごたえがあった。80年代以降の柄谷行人らの『批評空間』や『現代思想』につながる側面もあるが、ポストモダンのフランス現代思想がブームになって以後の、観念的な論文の山に比べ、『季刊藝術』ははるかに幅広くゆるやかに、どのような立場にせよ一般読者が抵抗なく読める文章が多かったと思う。
福田恆存といえば、旧仮名遣いを主張したり左翼文化人を批判した保守派の重鎮の一人として知られていた。しかし、彼がもっとも力を注いでいた仕事は、演劇であり、戯曲であり、自ら劇団を主宰して公演を行い、俳優、演出家、演劇人に幅広い影響を与えていた、ということを今頃知った。吉田秀和のオペラ論の中に、福田恆存が書いていた演劇評論のことがでてきて、ちょっと気になって福田恆存の本をいくつか読んでみた。とくに演劇論が具体的で非常に面白いので、しばらくとりあげてみようと思う。
「ここに一つ読者の了解を得ておきたい事がある・問題は私は財団法人現代演劇協会の理事長であるが、その私が翻案者、翻訳者、あるいは原作者として、しかも同時にその演出者として参加した、同協会附属劇団昴(すばる)の公演、すなはちコルネイユの『嘘つき男』の翻案に近い『嘘から出た嘘』や自作の『解ってたまるか!』などもまたこの劇評の対象として、看過する訳にはいかず、その場合、果たして公正を期し得るかどうか、たとへそれが可能であるにしても、内外にそれが認めてもらへるかどうかといふ事である。たまたま今月は観た芝居の数が少いので、その問題について日頃からの私の考へ方を述べてみようと思ふ。結果としてはそれは劇評論とでもいふべきものにならう。第一に、至極単純な事だが、劇評に限らず、人は絶対に公正たり得ない。公正であらうと務める事、客観的であらうと務める事、それと公正であり客観的であるといふ事とは捌事である。私達は公正であり客観的であらうと務めながら、また最善を尽くしてさうあらうと務めながら、そこには必ず私心が立入り、私達は絶対に主観から逃れられない。だからといって、居直って公正を無視し、主観、私心に安住してよいといふ事にはならない。公正とは何か、客観性とは何か。それは私心や主観を排する事でもなければ、自分はいつもさう行動してゐると自己欺瞞をする事でもない。むしろ、私心や主観に筋を通し、一貫性を持たせ、その「偏向」に責任を持つ事、それ以外に公正や客観性への手掛かりを私達は持ち得ない。
第二に、それにしても、自づと程度の差といふものがある。科学技術やスポーツの場合、問題はすこぶる簡単である。いかにフロックであれ、投手の頭上を越えたホームランをファウルと見なしたり、九十メートル以上跳んだスキーのジャンパーを九十メートルしか跳べなかったものの次位に評価したりする様な「主観」「私心」の入込む余地は、スポーツでは決してあり得ない。科学技術においても欠陥車の方が優れてゐるといふ論議は成り立たない。たとへ人類滅亡の具と言はれる核兵器でも、殺傷力の劣ってゐる物の方が高く評価されるといふ事はない。それがもしあるとすれば、それは科学的基準ではなく、道徳的基準による場合である。スポーツでもあまり強くない貴乃花が強い北の湖より人気があるとしても、その人気によって貴乃花が横綱になり、北の湖が関脇に落とされるといふ事は起り得ない。が、藝能界ではしばしばさういふ事が起る。世界中で芝居が一番隆盛を極めてゐる英国においても、たとえば、ペギー・アシュクロフト、デボラ・カー、イングリッド・バーグマンの三人を較べれば、役者=技術者としては、スポーツ界と同様、この順位は誰が見ても絶対に狂はない。役者の技能にしても、そこには主観や私心の入込む余地のない客観的基準と称し得るものがある。が、人気となれば、右の順位は明かに逆転する。その場合、バーグマンをカーより高く買ふ人がゐれば、それは好みといふ主観、私心によるものだといふ、大げさに言へば「うしろめたさ」「はばかり」の意識がどこかに働いてゐる。もしさうではなく、舞台藝術においては、人気もまた役者にとつて必須条件だといふ、劇評家として、彼自身の演劇観があるなら、その理想=主観に筋を通さねばならず、さうなると、単なる演技の技術家たる役者だけでなく、戯曲の評価にも関わって来る。劇評家としての彼はカワードやモームの作品の方が、ワイルド、ショウ、あるいはシェイクスピアより偉大な作品だといふ論議、少なくともさう言い切る責任を持たなければならなくなる。
第三に、今、英国の三女優を例に挙げ、この順位は誰が見ても狂はないと言った。その程度の客観性は役者、演劇藝術にもある。四百年の伝統を持つた国には当然の事である。が、日本にはそれすら全く無い。少なくとも新劇には未だかつてそれらしきものは一度も確立された事は無い。その結果として起る現象は、演劇は、あるいは演技は、いかにあるべきかについてはもちろん、その現状がどうなつてゐるのか、どうしてかうなつてゐるのが、このままではどうなるのか、さういふ事を一切考へず、またそれを考へる必要があるといふ事すら考へず、それを考へる能力も手立も知らない人間が、自分の好みのままに、しかもその好みが演劇に対する好みではなく、何か他のもの、たとへば、女なら細面より丸顔の方が好きだとか、すしにはわさびよりからしの方が、いや、場合によつてはあんこの方面より丸顔の方が旨いとか、その種の好みの系列に準じ、自分の主観、私心をそれと意識する事さへせず、意識しない以上、居直ることもせず、聊かの「うしろめたさ」も無くはなはだ素直に劇評の筆を取る、さういふ事になる。
第四に、さういふ人達に限つて、独りよがりな、自分達業界にしか通用しない、時には自分だけにしか通用しない、といふ事は自分自身にも解ってはゐない、むづかしい言葉を使ふ。前にも言った様に思ふが、私には「演劇空間」といふ言葉の意味が解らない。さういふ言葉を使ってゐる人で、それが普通の日常言語では表現し得ない重要な意味を持つてゐる事を知ってゐる事を知つてゐる人がゐたら、是非説明して戴きたい。その他にも、「劇状況をふくらまし」などと文章にぶつかると、私など狐に摘ままれた思ひをする。まづ「劇状況」といふ言葉の意味が解らない。またそれが何にせよ、「状況をふくらます」といふ事の意味が解らない。「ふくらます」と言はれると、懐、腹、胸、風船などを連想してしまふのだが、それを抽象的な「状況」に適用した場合、一体どういふ状況になるのかさつぱり見当が付かなくなる。その筆者は同じ文章の中で「劇状況を濃密に醸成しえなかった」と書いてゐる、それから察すると、私には訳の解らない。殊に「外質的演技が先行し、内的行動が処理しきれてゐない」などと言はれると、高が芝居じゃないか、カントが料理の味に文句を付ける様な言ひ草はやめてくれと怒鳴りたくなる。いや、カントだって、料理に文句を付ける時は、「塩がききすぎた」とか、「焼きが足りない」とか、極く普通の、具体的な言葉を使つたに違い無い。料理には料理の、芝居には芝居の、それぞれ具体的な注文の出し方がある筈である。私は演出家として、まだまだ未熟だと思つてゐるが、「外質的演技が先行してゐる」とか「内的行動が処理しきれていない」とか、そんな「哲学的」抽象語でダメ出しをした事は一度も無い。ダメはすべて日常言語で事足りる。劇評も同様である。具体的な日常言語で事足りるばかりでなく、その方が有効であるのにも拘らず、自らも定義不可能な難しい抽象語を使ふのは、ごまかしであり、逃避であり、責任回避であり、責任回避である。たとへ平易でも「好演」「力演」などといふ言葉も具体的ではなく、それだけでは無意味、不可解である。「素晴らしい」から「まあまあの出来」まで、その間のどれをも蔽ひ得る様な曖昧なごまかしでお茶を濁してまで劇評家の権威といふ仲間内の虚栄心を保たうとする事はあるまい。
藤木敬士宛
昨年の『嘘から出た嘘』(昭和五十二年九月・三百人劇場)のあなたは「好演」かつ「力演」でした。あなたの演じたドラントは文字通りの主役らしい主役であり、あなたが私達の劇団に入って以来、これほどの訳を与へられた事は無かった。それだけにあなたは全力を挙げてこれに当った。私もその為に最善を尽し、相手のクラリス役の田島令子がなまなか器用なだけに、結果的にはその方が手抜きになつてしまひ、田島には気の毒だつたと反省してをります。正直に言って、あなたは役者=技術家としては未熟です。歩き方とか、階段の降り方とか、身の翻し方とか、尻餅の付き方とか、さういふ極く初歩的、基本的な動作すらまだ身に付けてゐません。さういふと決定的な否定の様に聞えるかも知れませんが、もしあなたがこの書をはじめから読んできたなら、大きな顔をして一枚看板を掲げ、大興行主に支へられてゐる役者といふ名の素人が、同じような批判を、それこそ具体的に、綿密に、この私によつて受けてゐる事を御存じの筈ですし、また稽古中、準演技員や演劇学校専科在学中の役者の卵は勿論の事、あなたの先輩格に当る一人前と思はれてゐる役者色腕さへ、同じ憂き目に遭ってゐるのを見てゐるのでせうから、別に屈辱感に打ちのめされるといふ事もありますまい。
初日以来、劇団の内外を問はず、かなり沢山の人達から、ドラント役のあなたに対する褒め言葉を耳にしました。が、私の根性が曲ってゐるせいか、この場合に限らず、自分、および自分の関係者に対する褒め言葉といふものを、折角褒めてくれた人には失礼かも知れませんが、私は容易に信じる気になれないのです。私は常に自分自身の手応へしか信じられない性だからでせう。「藤木はよくやつた」といふのは、「藤木があそこまでもやれるとは思はなかった」といふ事に過ぎず、文字通り「力演」だつたといふ事でしかありません。「力演」といふ言葉を強ひて定義すれば、「自分の力以上の仕事をしようと純粋な情熱を持ちながら、その為に技術の力不足と格闘する情熱の余剰が客の目に快く感じられる演じ方」といふ事になりませうか。言換えれば、それは自己陶酔でしかない。この作品は、幾ら私が翻案の手を加へてあっても、やはりコルネイユの古典劇であります。自己陶酔、あるいは私の定義した「力演」といふ興奮剤のみに頼って、命脈を保つといふのでは、前衛劇のお家藝と少しも変わるところがありません。
実際、あなたの芝居に対する純粋、誠実な態度には頭が下がります。天下の婦女子を湧かせた往年のロック歌手藤木孝の面影は、少なくとも今日、劇団内で接触する限り、あなたのどこにも見出せない。が、自由、奔放なロックの先駆者が芝居となると、どうしてああ硬直するのか、歌手、踊手に限らない、人気を一身に集めた人間といふものは、その人気を支えてくれてゐると頼り切ってゐるファンの前では、幾らでも自由、奔放になり得るものです。時には宮田輝の様に厚かましくもなり得る。言換へればファンに甘え、ファンを舐めているゐるのです。彼は何をしても許されるどころか、文士劇同様、失敗をすれば、かへつて愛される。芝居に対しても、友人に対しても、日頃から常に謙虚なあなたではありますが、やはりあのロック歌手時代の甘えがどこかに残ってゐるのではないか、その甘えと謙虚は紙一重の差、あるいは一枚の紙の裏表ではないか、これは私の思ひ過しでせうか。
あなたがドラントで「成功」したのは、あの役が比較的独り芝居で相手を無視しても、ほとんどぼろが出ないからです。しかし、芝居である以上、独り芝居に等しい芝居であっても、いや、さういふ役であればあるほど、相手役に対して慎重に付合はなければなりません。相手に主役の機会を与へなければなりません。が、あなたのドラントは「力演」のきりきり舞をすればするほど、誰もその中に入込めない円周を描き、相手をその外に弾き出してしまふ。その責任は演出家の私の中にもあります。が、そのあなたの独り芝居を抑えれば、主役としてのあなたが死ぬ。私はさう判断し、クラリスやクリトンを犠牲にしたのです。さういふ弁解めいた事は言ひたくないし、まして自分まであなたの犠牲者になつたなどと言ふ積りはありません。私はあへてあなたに賭けたのです。その責任は私にあります。ですから『解ってたまるか!』では付合ひと受けを主とする役、しかも、古典劇ではごまかせるが、写実のごまかしがしにくい現代日本の新聞記者という役をやってもらつた。他人事の様に言ふのが気が退けますが、その時のあなたはつひにぼろを出してしまひました。が、恐らく謙虚なあなたは独り芝居の「力演」の限界を思ひ知ったと思ひます。できる事なら、あなたの成長の為には、ドラントと新聞記者との間に『動物園物語』のジュリーかピーターの様な役を演じる機会があれば、これに越した事は無かったのですが、万事、物事はさう巧く運ぶものではありません。しかし、ドラントとはとにかくあなたとしては一応「成功」だったのですから、以上の私の忠言を反芻して、まづはせりふの遣取りのタイミングはもちろんの事、なほ今まで何人かの役者諸氏に忠言してきたごとく、相手のせりふを聴く力、自分のせりふが相手の心を動かしてゐるのを見る能力を、稽古中のみならず、日常生活において身に付けるように努めて下さい。」福田恆存『せりふと動き 役者と観客のために――』玉川大学出版部、pp.69-75.
この劇評はそのまま演劇論であり俳優演技論になっているが、とりあげる芝居や俳優に対する批評は実に辛辣で罵倒に近い。藤木孝さんは、歌手として「2万4千回のキッス」などで売れた人だったが、俳優を志して福田の劇団欅などに所属して、この頃から舞台で活躍を始めていた。福田にとってはいわば身内なので、厳しいが育てようとする視線がある。しかし、いわゆる新劇系の俳優座やもともとそこから分裂してきた文学座などの芝居への批判は、ここまで言っちゃうかというほどの厳しさである。
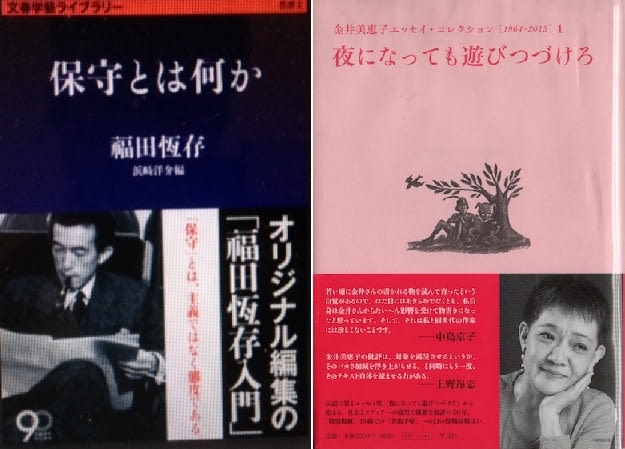
B.はしゃぎすぎ
急に5月1日から令和元年だからと、10連休もボーナスのように祝賀をはやすメディアには辟易してしまう。こうなりそうな予想はあったが、こういう雰囲気に異を唱えるのは表立っては難しいのかもしれない。でも、控えめなアイロニーくらいは出てくる。
「平成は終わる うやうやしく [令和に寄せて] 小説家 金井美恵子(寄稿)
「慶祝」ムード はしゃぐメディア
明治・大正・昭和と続いた個人の死による元号の変化が、近現代史を語るときに使用されはするものの、今日ほとんどの者は、日常的にも歴史を考えるときにも元号を使うことはないはずである。
この原稿が掲載されている紙面の情報を見れば、太ゴチック体の西暦の年数の後のカッコ内に、とりあえず、一応といった目だたなさで元号が記されていることからも、使用頻度がわかるというものだろう。元号を使用した時間的感覚のわかりづらいニュースを伝えるのは、NHKと産経新聞のニュースだけではないだろうか。
天皇の生前退位と即位による「慶祝」ムードは、十連休を政府が作ったせいで、あらゆるメディア(町の看板から広告、チラシ、テレビ、新聞、SNS)に子供っぽい、誰はばかることのないはしゃぎぶりが広がって、「平成の最後の※※」という、すべりっぱなしのギャグのような言い方が蔓延している。
もちろん「文化人」や「知識人」の間にはギャグではなしに、「平成」という時代を知的に分析し総括しなければならないという「義務」があるのだから、あらゆる文芸雑誌や総合誌や新聞では特集が組まれ、そういった「歴史的」場面のたびに登場して何事かを語る学者や小説家や批評家が、このいかにも「不安定」で「不透明」な時代の「時代精神」を語っている。
三十年前の改元時はどうだったのかと、手もとにある数少ない資料の『新潮社100年』(2005年)という社史の年表を見ると、一九八九年(昭和64年、平成1年)の文芸誌「新潮」は二月に「この一冊でわかる昭和の文学」という、身も蓋もなく軽薄な臨時増刊号を組み(井上ひさし、高橋源一郎、島田雅彦の座談会を掲載)、三月号では「文学者の証言 昭和を送る」という特集を編んでいる。
しかし、「昭和」は簡単に「送れる」ものなのだろうか。戦前と戦後に不自然な形で二分されている昭和天皇の「天皇の生まれてはじめての記者会見というテレビ番組」(昭和五十年)を見た小説家の藤枝静雄は「文芸時評」に「実に形容しようもない天皇個人への怒りを感じた」と書き、それは、戦争責任について質問された昭和天皇が、そういった文学的問題はわからない、という意味のことを答えたことに対する戦争体験者であり文学者でもある者の怒りだった。
長い戦争の後、人間宣言をして途中から「象徴天皇」になったのとは違って、「象徴天皇」というものを「国民の安寧と幸せを祈る」だけではなく「人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添」う存在として行動した「平成」の天皇は、平成最後というか在位中最後の誕生日会見に、「平成が戦争のない時代として終ろうとしていることに、心から安堵しています」と語ったのだが、もちろん「平成」という日本だけの元号で歴史の年代を数える「国」の内部だけのことである。
一九五八年の婚約、翌年の成婚馬車パレード以後、天皇・皇后は、普及しはじめた白黒テレビと創刊されたばかりの女性週刊誌によって国民に超スター的存在として親しまれ愛されてきたのだった。「平成」は世界最悪規模の原発事故をはじめ様々な大災害を何度も経験した時代だったが、その度に被災地を訪れる天皇夫妻の映像をテレビで見る機会が驚くほど多かったし、今年の四月に入ってからはさらに懐古的な映像が流され、訪問地の沿道では日の丸の小旗を振って迎える女性が、皇后について「拝むといったらなんだけど、やっぱり、拝みたい気持ち」と感極まって語り、「有難い」、「ただただ感謝です」と口々に言う。感謝?
小旗を持った女性たちだけではなく、「天皇陛下御即位三十年奉祝感謝の集い」では、北野武もお二人からお声をかけていただいた感激と感謝を語り、日本を代表する現代詩人は、美智子皇后の美しさと知性について、心底からの感嘆の言葉を書く。(「文芸春秋」五月号)
「私たち日本国民はなんという優雅で深切な国母を持ち、皇室を持っていることか、と幸福な思いに満たされ」(高橋陸郎)、もう一人の詩人は、女たちが蚕のそばで暮らしてきた何千年もの歴史をふまえて「蚕の命にまで耳を澄ませ」「万物の立てる響きにお心をお寄せになる皇后陛下の詩心はとても深い」(吉増剛造)と讃美する。それは詩人の言語的批評意識をこえた存在なのだろう。
そして、こうした心底からの讃美は生前退位で終わった「平成」が二度、いや三度、うやうやしい言葉の大群と共に終わることを暗示しているのだろう。」朝日新聞2019年5月2日朝刊19面、文化・文芸欄。
北野武はともかく、高橋陸郎、吉増剛造という詩人の名は、どちからといえば政治や時局とは無縁で高踏的な前衛詩人というイメージだったが、ここで皇室礼賛の詩を書いたというなら、やっぱり歴史は繰り返しているのかと暗澹たるものがある。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます