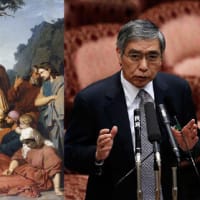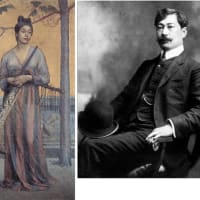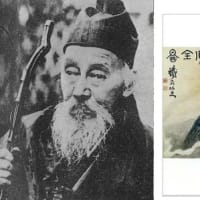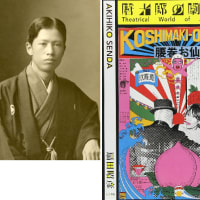A.語源の探索ではなく訳語の創作
近代以前の日本に「恋愛」はあったのだろうか?と考えてみると、たとえば近松の「曽根崎心中」という浄瑠璃作品がある。これは近松が創作した物語だが、元禄16年に大坂で実際にあった心中、内本町の醤油屋手代の徳兵衛(25)と堂島新地天満屋の女郎はつ(21)が西成の曽根崎村、露天神の森で情死した事件に取材している。浄瑠璃芝居が大人気を呼び、情死心中事件がその後も起きたという。さて、これは「恋愛」だろうか?若い男女が惚れ合って、想いを遂げるため一緒に死ぬという心理は、情熱恋愛に似ているようにも思える。「未来成仏うたがひなき恋の手本となりにけり」と来世でのかたい契りとして観客の涙を誘うわけだが、近松の物語構造のねらいは、「恋愛」にあるわけではない。徳兵衛は主人が勧める縁談や、それに絡む金銭のトラブルを抱えて追いつめられ、絶望して死ぬしかないという状況でお初は道連れに心中するのである。
「ロミオとジュリエット」であれば、結末は二人が死ぬ悲劇という形は同じでも、恋の成就を阻む状況を打開し新しい地へ脱出する計画のもとに二人は示し合わせ、手違いで死んでしまう。ロミオとジュリエットの目的は「恋愛の成就」であるが、お初徳兵衛の目的は「来世の契り」つまり「この世の苦からの逃亡」になる。明治以降の西洋輸入の近代化では、loveとかamourとかにどう訳語を充てるか、近松的な「恋」ではどうも暗く反社会的な匂いがして具合が悪かった。
「恋愛」は日本にはなかった
「『恋愛』とは何か。「恋愛」とは、男と女が互いに愛しあうことである、とか、その他いろいろの定義、説明があるであろうが、私はここで、「恋愛」とは舶来の観念である、ということを語りたい。そういう側面から「恋愛」について考えてみる必要があると思うのである。
なぜか。「恋愛」もまた「美」や「近代」などと同じように翻訳語だからである。この翻訳語「恋愛」によって、私たちはかつて、一世紀ほど前に、「恋愛」というものを知った。つまり、それまでの日本には、「恋愛」というものはなかったのである。
しかし、男と女というものはあり、互いに恋しあうということはあったではないか。万葉の歌にも、それは多く語られている。そういう反論が当然予想されよう。その通りであって、それはかつて私たちの国では、「恋」とか「愛」とか、あるいは「情」とか「色」とかいった言葉で語られたのである。が、「恋愛」ではなかった。
1890(明治23)年十月、近代日本初期の女性教育を担当した『女学雑誌』で、この雑誌を主宰していた巌本善治は、翻訳小説『谷間の姫百合』(クレイ・バルサ原作、千葉宣一氏のご教示による)の批評を書き、そこでこう述べている。
訳本を評するには文章の外(ほ)か言ふべき所あらず。更に一事の感服する所(とこ)ろ及び承知しがたき所ろを挙れば、訳者がラーブ(恋愛)の情を最(もっ)も清く正しく訳出し、此の不潔の連感(アッソシエーション)に富める日本通俗の文字を、甚(はな)はだ潔(いさ)ぎよく使用せられたるの手ぎはにあり。
例(れい)せば、
私の命は其(その)恋で今まで持てゝ居ります。恋は私の命(いの)ちで私に取りても此外には何の楽(たのしみ)も願いもありませぬ。‥‥‥あなたは実に男一人の腸(はらわた)を寸々(ずたずた)にしました。一生を形(かたち)なしにしました。
の如き、英語にては‟You have ruined my life”など云ふ極めて適当の文字あれど、日本の男子が女性に恋愛するはホンノ皮肉の外にて、深く魂(ソウル)より愛するなどの事なく、随ってかゝる文字を最も厳粛に使用したる遺伝少なし。
ここで、「ラーブ(恋愛)」ということばが登場しているのだが、筆者は、これを「恋」などのような「不潔の連感に富める日本通俗の文字」とは違う、と考えている。loveと「日本通俗」の「恋」とは違う。そこで、そのloveに相当する新しいことばを造り出す必要があった。それが「恋愛」ということばだったわけである。
この「恋愛」をもとにして考えてみると、「恋愛」は、「不潔の連感に富める」「恋」などと違って、上等である。価値が高い、とされている。その違いは、「恋愛」の方が「清く正しく」「深く魂(ソウル)より愛する」ような意味を持っているからである。
そして、このlove=恋愛ということばの意味することがらは、西欧にはもちろんあったわけだが、日本にはなかった。あるいはほとんどなかった、と考えられている。「日本の男子が女性に恋愛するのはホンノ皮肉の外にて、深く魂(ソウル)より愛するなどの事なく」、また、「かゝる文字をもっとも厳粛に使用したる遺伝少なし」と言うのである。
つまり、「恋愛」は価値が高い、が、このことばの意味することがらは日本にはない、と当時の先進的知識人巌本善治は考えていたわけである。
巌本善治のこの「恋愛」感は、かなりもっともなところがあった、と私は考える。「恋愛」ということばの伝える意味内容が日本にはなかったということ、これは、「恋愛」ということばが当時の新造語であって、それ以前にはなかったのだから、それに対応する意味もなかったのは当然である。このことは、「社会」ということばを知る以前に、「社会」の意味はなく、「美」を知る以前に「美はなかったのと同様である。
それから、「恋愛」は価値が高く、日本に従来あった「恋」などは、これに対して価値が低いということ、冷静に考えれば、こういう考え方は、もちろんあやまりである。が、これは、先進国の事物が、翻訳語ということばを介して理解されるとき、私たちがいつでも陥りがちな思考法なのである。
しかし、「恋愛」と「恋」とが、価値が高い、低いということで違うのではなく、とにかく違っているということ、これはもっともであろうと思う。そしてその違いについては、巌本がここで言うように、「恋愛」とは「深く魂(ソウル)より愛する」ことだ、という考えには、かなりうなずける所があるように思うのである。
英語で、loveに大変近いことばに、romanceがある。Romanceとは恋物語のことであり、その源は、中世騎士物語である。『アーサー王と円卓の騎士』のような物語がその典型であって、たとえば一人の騎士がお城の近くを通りかかると、彼方のバルコニーに美しい女性の姿が見える。女性がスカーフを投げる。騎士はそれを受け取ると、冒険の旅に出る。旅の途中の森の中で、巨漢と出会って決闘となる。騎士は巨漢を打負かす。だが殺さない。降参させた上で、あのお城の女性のもとへおもむいて私のことを伝えてこい、と命ずるような筋のパターンである。
はじめに美しい女性がいる。遠くの方から現われる。男は、直ちにそれに近づいていこうとしないで、かえって遠ざかる。しかも生命を賭けた危険の方に向かっていく。男は、冒険の果てに、やがてその美しい存在のもとへ帰ってくるのだが、そのloveの始まりの形にとくに注目したい。このような物語の背景には、マリア崇拝や、十字軍の遠征がある。つまりキリスト教が根本にある。
「永遠の女性」とは、ゲーテが『ファウスト』で語っているように、遠い彼方から男を導く存在である。導く存在は、身近ではありえない。遠い彼方にいるから、男はそれにあこがれるわけだが、たとえ身近にあっても、あえてそれを遠い彼方に置こうとする。男は恋する女性を、もちろん身近に引きつけたいと願う。が、それだけでは西欧の「恋愛」の型は生まれなかった。騎士はお姫様の住む城から冒険に旅立つのであり、こうして遠い彼方の女性というものをあえてつくりだすのである。やがて肉体の恋はやってくるとしても、それとは別に、遠い彼方にあこがれる「魂(ソウル)」の恋がある。
ところで、私たちの国には、こういうパターンの恋物語は、まずなかった。『万葉集』の恋歌は、ほとんどすべて、二人がいったん結ばれて後の悲しみや喜びを歌っている。『万葉集』の恋する男にとって、恋する人は、遠い彼方ではない。肉体を離れた魂だけの存在ではない。『万葉集』の中にも、一度会っただけの人にあこがれる、というような歌もまれにはあるが、これにしてもよく注意して読むと、一度会った、とは一度結ばれた、という意味であるらしいことが多い。
巌本の理解した、loveとは「深く魂(ソウル)より愛する」ことだ、という考えについて、私はこのような事情を考えざるをえないのである。Loveとは、決して「魂」だけのできごとではない。しかし、魂と肉体とを区別して理解しようとする考え方、ものの見方がそこにはある。私たちの伝統的な「恋」や「愛」が、心と肉体とを常に切離さず、一つに扱ってきたのと対照的である。したがって、loveの解釈として、「魂」だけをとくに強調する「恋愛」観も、当然あっておかしくなかった、と考えられるのである。
「恋愛」ということばは、いつごろから使われるようになったのだろうか。ここで、loveや、これに相当する西欧語の翻訳の歴史をふり返ってみよう。
日本語の辞書ではないが、幕末から明治初期の人びとによく使われた各種の「英華字典」では、古くから「恋愛」ということばが出てくる。ただし、動詞のloveの訳語で、名詞のloveの方ではない。メドゥーストの『英華字典』(1847-48年)では、to loveの訳語が、「愛、好」で始まって、「哀惜」「恋愛」などがある。名詞のloveの項では、「愛情、寵、仁」などだが、「恋愛」はない。ロブシャイドの『英華字典』(1866-69年)でも、だいたい同じである。
日本語の辞書では、『和蘭字彙』(1855-58年)が、liefdeの訳語に、「寵愛又愛敬」「仁」とある。『仏語明要』(1864年)が、amourの訳語を、「恋○愛○恋神」としている。『英和対訳袖珍辞書』(1862年)では、loveが、「愛、恋、財宝」である。日本語の辞書に「恋愛」が現れるのは、仏学塾の『仏和辞林』がたぶんもっとも早く、1887年版でamourの訳語が、「恋愛。鐘愛。好愛。愛。愛セラル、所ノ者」となっている。
「恋愛」という翻訳語の実際の用例は、前記の巌本善治以前では、非常に少ない。おそらく最初の用例は、1870-71(明治3-4)年に出た中村正直の翻訳、『西国立志編』における例であったろう。そこで、
李嘗(リイかつ)テ村中ノ少女ヲ見テ、深ク恋愛シ、
と使われている。原文(S. Smiles: Self-help,1859)では、ここのところは、
to have fallen deeply in love with a young ledy of the village,
となっている。中村の訳文には「英華字典」の影響が大きいので、これもそうであろう。「恋愛シ」という言い方では、この「恋愛」の部分は、サ変動詞の語幹である。この点も、「英華字典」で「恋愛」が動詞として扱われていたことと似ている。
巌本善治のあの「恋愛」の紹介も、系譜をたどれば「英華字典」の訳語を受け継いでいた、と考えられる。が、巌本のこの「恋愛」論は、私たちの「恋愛」史上、画期的な出来事であった、と思うのである。
第一に、巌本はあそこで、「恋愛」を真正面から肯定した。それは、とりわけ、あの前後の時代的背景の中で、画期的なのである。
「恋愛」は、とくに小説の中心テーマであるが、幕末から明治初期の頃、西欧の書物がいろいろと翻訳され、紹介された中で、小説は少なかった。あったとしても、『ロビンソン・クルーソー』のような冒険小説、あるいは政治小説などがおもであった。要するに、男の時代だったのである。国造りの仕事の忙しい男たちにとって、「小説」や「恋愛」は、二の次、三の次だった。『西国立志編』におけるあの「恋愛」にしても、これはこの書物でただ一ヵ所現われている「恋愛」だが、少年李は、「恋愛」したものの、女は靴下を編む仕事に忙しくて相手にしてくれない。そこで、それなら靴下を機械で編む自動織機を発明してやろうと思い立った、というのである。
巌本善治の『女学雑誌』は、この男の時代の中で、精一杯、一つの抵抗の拠点をつくっていたのである。「恋愛」は、あの紹介の頃以後、巌本の指導と支持で、『女学雑誌』の一つの中心テーマとなっていく。「恋愛」論の投書がしきりにとりあげられ、北村透谷が、それを引き継ぐ。そしてやがて、日本におけるロマン主義の時代を花開かせたのである。
ところで、問題は、「恋愛」という翻訳語、つまりことばの問題である。巌本から透谷を経て、日本の一時期の文芸へと受け継がれていく「恋愛」の思想を、その特徴を、時代とか歴史という視点から眺めることはもちろん重要である。が、それとは一応別に、翻訳語ということばの視点からとらえることができる。それを考察してみたい。」柳父章『翻訳語成立事情』岩波新書、1882.pp.89-97.
『女学雑誌』以来、教養ある良家の少女にとって「恋愛」という観念は、甘い蜜の貯水池になった。親の決めた許婚といずれ嫁入りする運命にあるとしても、もし可能なら、すぐれた資質と洗練された趣味をもつイケメン男とイイ関係になり、情熱恋愛がしてみたいと願う娘があちこちに現れた。もちろん彼女たちの夢は、ほとんど幻のうちに消えたのだが、それを実践してしまったお嬢様もたしかにいて、やがて「新しい女」と呼ばれることになる。

B.既成事実に慣らされている?
自衛隊という存在をめぐる安全保障論議を、その「再軍備」といわれた創設期から振返ると、憲法9条との斉合性を問う自衛隊違憲論は、ときの保守政権によって次々なしくずしにされて今に至っている。相次ぐ災害で救援に活躍する自衛隊の姿は、ごく当たり前の光景になり、国民の大多数が自衛隊の存在を頼もしいもの、悪くないものと感じていると安倍首相は満足げである。でも、災害復旧や市民生活への支援が主要任務なら、アメリカの州兵みたいな地域救援部隊でいいわけで「国軍」的な装備や機能は要らない。自衛隊は、当初の役割からだいぶ違うものになり、5年前の「安保法制」成立で、日本の領土と国民を守る、という範囲を超えて米軍の行なう戦争の応援部隊にまで変質してしまった。そのことをあんなに危惧したのに、いつのまにか日本国民有権者は、なんだか別に問題ねえんじゃね?みたいに、無感覚になってしまってヤバくね。
「安保法成立5年 「専守防衛」踏み外すな
安全保障関連法の成立から三年。いま、私たちの眼前にあるのは戦後日本が貫いてきた「専守防衛」を踏み外し、憲法九条が蔑ろにされている現実だ。
安倍晋三首相率いる内閣が「平和安全法制」と称し、強行した安保関連法の成立から、今日九月十九日で三年を迎えた。
安倍氏は、連続三選を目指す自民党総裁選の演説会などで、安保法について「日米はお互いに助け合うことのできる同盟になった。助け合うことのできる同盟は、その絆を強くするのは当然だ」と、その意義を強調し続け、支持を呼び掛けている。
違憲性は拭い去れない
「助け合う同盟」とは、集団的自衛権を部分的ながら日本も行使できるようになったことを指す。
おさらいになるが、集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず実力で阻止する権利のことだ。
日本の歴代内閣は憲法九条に基づいて、集団的自衛権について、主権国家として有してはいるが、その行使は憲法上、許されないとの解釈を堅持してきた。
この解釈を変え、集団的自衛権の行使を一部容認したのが二〇一四年七月一日、安倍内閣の閣議決定であり、安保法はこの閣議決定を基に策定された。
戦争放棄と戦力不保持の憲法九条が、日本国民だけで三百十万人の犠牲を出し、交戦国にとどまらず、近隣諸国にも多大な犠牲を強いた先の大戦に対する痛切な反省に基づくのは論をまたない。
日本防衛のための必要最小限の実力組織として自衛隊が発足したが、専守防衛に徹し、他国同士の戦争には加わらない九条の精神を一内閣の判断で独善的に変えていいわけがない。安保法の違憲性は引き続き問われるべきだろう。
活動拡大で既成事実化
にもかかわらず、国会での追及は手ぬるいと言わざるを得ない。安保法成立当時の最大野党、民主党は分裂し、野党共闘にも影を落としている。安保法廃止を求める野党各党はいま一度結束して、憲法論争に果敢に挑むべきである。
安倍政権が成立後の三年間に進めたのは、安保法の既成事実化と自衛隊の活動領域の拡大、その裏付けとなる防衛費増額である。
ここ数日、自衛隊をめぐる報道が相次いだ。その一つが、政府が秋田、山口両県への配備を計画する地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」について、だ。
北朝鮮が、米空軍が戦略爆撃機を配備する米領グアム島に弾道ミサイルを発射した場合、日本の地上イージスが迎撃することもあり得ると、防衛省が認めたという。
日本を守る名目で導入される防衛装備品が、米国を防衛する集団的自衛権の行使にも使われて当然という、安保法に基づく日米の軍事的一体化を象徴する事例だ。
安倍内閣はまた、エジプト・シナイ半島でイスラエル、エジプト両軍の停戦監視活動をする「多国籍軍・監視団」(MFO)に、陸上自衛隊の幹部自衛官数人を、司令部要員として派遣することを検討しているという。
国際平和への貢献は必要だとしても、国連が統括しない米国中心の軍事的活動だ。参加打診は以前からあったとされるが、なぜ今、という疑問は拭い去れない。
国連以外の国際機関の要請でも自衛隊を派遣できるようになった安保法の適用事例拡大に主眼があるのでは、と疑わざるを得ない。
海上自衛隊の潜水艦とヘリコプター搭載型護衛艦が十三日に、南シナ海で対潜水艦の訓練を初めて実施したことも看過できない。
南シナ海は、日本にとっても重要な海上交通路であり、中国が一方的に権利を主張し、軍事拠点化を進めることは、高校の安全確保の観点からも認められない。
首相は「特定の国を想定したものではない」とするものの、中国けん制の意図があるのだろう。
かといって中国をはじめ各国が領有権を主張し合う「係争地」に乗り込んでの訓練が緊張を高めるのは当然だ。それが、武力による威嚇を、国際紛争解決の手段としては放棄した日本の役割なのか。
自衛隊明記で9条変質
自民総裁選で優位が伝えられる安倍氏は自衛隊の存在を明記する九条改憲を訴え、連続三選を果たした後、今秋の臨時国会に自民党改憲案を提出し、二〇年中の改正憲法施行を目指すと明言した。
しかし、集団的自衛権の行使など安保法の違憲性を問わず、その活動を行う自衛隊の存在を憲法に明記すれば、他国同士の戦争には参加しない九条の精神を、さらに変質させることになりかねない。
眼前で起きる安保法の既成事実化や自衛隊の活動拡大を放置していいのか。平和国家の道を歩んできた戦後日本の試練でもある。」東京新聞2018年9月19日朝刊5面、社説。
安倍晋三の提起する改憲の、いちばんの眼目は9条に自衛隊を明記し、正規軍を持つ国家という場所に日本を置きたい、という思想だろう。「国軍」と呼びたい心情を抑えて「自衛隊」でもまあいい、とにかく軍事力を自由に行使して国益のために場合によっては戦争もできるようにしておきたい、という意思。いま自民党総裁選を安倍氏と争う石破氏も、基本的に同じ考えで、できれば戦力不保持もとっぱらうのが筋だと言っている。どっちもそこまで言っても、国民多数から支持を得られると読んでいる。まったく、戦後70年、「9条の平和主義」は敗け続けてしまったわけで、本丸落城まえの豊臣秀頼みたいなところにいる。
近代以前の日本に「恋愛」はあったのだろうか?と考えてみると、たとえば近松の「曽根崎心中」という浄瑠璃作品がある。これは近松が創作した物語だが、元禄16年に大坂で実際にあった心中、内本町の醤油屋手代の徳兵衛(25)と堂島新地天満屋の女郎はつ(21)が西成の曽根崎村、露天神の森で情死した事件に取材している。浄瑠璃芝居が大人気を呼び、情死心中事件がその後も起きたという。さて、これは「恋愛」だろうか?若い男女が惚れ合って、想いを遂げるため一緒に死ぬという心理は、情熱恋愛に似ているようにも思える。「未来成仏うたがひなき恋の手本となりにけり」と来世でのかたい契りとして観客の涙を誘うわけだが、近松の物語構造のねらいは、「恋愛」にあるわけではない。徳兵衛は主人が勧める縁談や、それに絡む金銭のトラブルを抱えて追いつめられ、絶望して死ぬしかないという状況でお初は道連れに心中するのである。
「ロミオとジュリエット」であれば、結末は二人が死ぬ悲劇という形は同じでも、恋の成就を阻む状況を打開し新しい地へ脱出する計画のもとに二人は示し合わせ、手違いで死んでしまう。ロミオとジュリエットの目的は「恋愛の成就」であるが、お初徳兵衛の目的は「来世の契り」つまり「この世の苦からの逃亡」になる。明治以降の西洋輸入の近代化では、loveとかamourとかにどう訳語を充てるか、近松的な「恋」ではどうも暗く反社会的な匂いがして具合が悪かった。
「恋愛」は日本にはなかった
「『恋愛』とは何か。「恋愛」とは、男と女が互いに愛しあうことである、とか、その他いろいろの定義、説明があるであろうが、私はここで、「恋愛」とは舶来の観念である、ということを語りたい。そういう側面から「恋愛」について考えてみる必要があると思うのである。
なぜか。「恋愛」もまた「美」や「近代」などと同じように翻訳語だからである。この翻訳語「恋愛」によって、私たちはかつて、一世紀ほど前に、「恋愛」というものを知った。つまり、それまでの日本には、「恋愛」というものはなかったのである。
しかし、男と女というものはあり、互いに恋しあうということはあったではないか。万葉の歌にも、それは多く語られている。そういう反論が当然予想されよう。その通りであって、それはかつて私たちの国では、「恋」とか「愛」とか、あるいは「情」とか「色」とかいった言葉で語られたのである。が、「恋愛」ではなかった。
1890(明治23)年十月、近代日本初期の女性教育を担当した『女学雑誌』で、この雑誌を主宰していた巌本善治は、翻訳小説『谷間の姫百合』(クレイ・バルサ原作、千葉宣一氏のご教示による)の批評を書き、そこでこう述べている。
訳本を評するには文章の外(ほ)か言ふべき所あらず。更に一事の感服する所(とこ)ろ及び承知しがたき所ろを挙れば、訳者がラーブ(恋愛)の情を最(もっ)も清く正しく訳出し、此の不潔の連感(アッソシエーション)に富める日本通俗の文字を、甚(はな)はだ潔(いさ)ぎよく使用せられたるの手ぎはにあり。
例(れい)せば、
私の命は其(その)恋で今まで持てゝ居ります。恋は私の命(いの)ちで私に取りても此外には何の楽(たのしみ)も願いもありませぬ。‥‥‥あなたは実に男一人の腸(はらわた)を寸々(ずたずた)にしました。一生を形(かたち)なしにしました。
の如き、英語にては‟You have ruined my life”など云ふ極めて適当の文字あれど、日本の男子が女性に恋愛するはホンノ皮肉の外にて、深く魂(ソウル)より愛するなどの事なく、随ってかゝる文字を最も厳粛に使用したる遺伝少なし。
ここで、「ラーブ(恋愛)」ということばが登場しているのだが、筆者は、これを「恋」などのような「不潔の連感に富める日本通俗の文字」とは違う、と考えている。loveと「日本通俗」の「恋」とは違う。そこで、そのloveに相当する新しいことばを造り出す必要があった。それが「恋愛」ということばだったわけである。
この「恋愛」をもとにして考えてみると、「恋愛」は、「不潔の連感に富める」「恋」などと違って、上等である。価値が高い、とされている。その違いは、「恋愛」の方が「清く正しく」「深く魂(ソウル)より愛する」ような意味を持っているからである。
そして、このlove=恋愛ということばの意味することがらは、西欧にはもちろんあったわけだが、日本にはなかった。あるいはほとんどなかった、と考えられている。「日本の男子が女性に恋愛するのはホンノ皮肉の外にて、深く魂(ソウル)より愛するなどの事なく」、また、「かゝる文字をもっとも厳粛に使用したる遺伝少なし」と言うのである。
つまり、「恋愛」は価値が高い、が、このことばの意味することがらは日本にはない、と当時の先進的知識人巌本善治は考えていたわけである。
巌本善治のこの「恋愛」感は、かなりもっともなところがあった、と私は考える。「恋愛」ということばの伝える意味内容が日本にはなかったということ、これは、「恋愛」ということばが当時の新造語であって、それ以前にはなかったのだから、それに対応する意味もなかったのは当然である。このことは、「社会」ということばを知る以前に、「社会」の意味はなく、「美」を知る以前に「美はなかったのと同様である。
それから、「恋愛」は価値が高く、日本に従来あった「恋」などは、これに対して価値が低いということ、冷静に考えれば、こういう考え方は、もちろんあやまりである。が、これは、先進国の事物が、翻訳語ということばを介して理解されるとき、私たちがいつでも陥りがちな思考法なのである。
しかし、「恋愛」と「恋」とが、価値が高い、低いということで違うのではなく、とにかく違っているということ、これはもっともであろうと思う。そしてその違いについては、巌本がここで言うように、「恋愛」とは「深く魂(ソウル)より愛する」ことだ、という考えには、かなりうなずける所があるように思うのである。
英語で、loveに大変近いことばに、romanceがある。Romanceとは恋物語のことであり、その源は、中世騎士物語である。『アーサー王と円卓の騎士』のような物語がその典型であって、たとえば一人の騎士がお城の近くを通りかかると、彼方のバルコニーに美しい女性の姿が見える。女性がスカーフを投げる。騎士はそれを受け取ると、冒険の旅に出る。旅の途中の森の中で、巨漢と出会って決闘となる。騎士は巨漢を打負かす。だが殺さない。降参させた上で、あのお城の女性のもとへおもむいて私のことを伝えてこい、と命ずるような筋のパターンである。
はじめに美しい女性がいる。遠くの方から現われる。男は、直ちにそれに近づいていこうとしないで、かえって遠ざかる。しかも生命を賭けた危険の方に向かっていく。男は、冒険の果てに、やがてその美しい存在のもとへ帰ってくるのだが、そのloveの始まりの形にとくに注目したい。このような物語の背景には、マリア崇拝や、十字軍の遠征がある。つまりキリスト教が根本にある。
「永遠の女性」とは、ゲーテが『ファウスト』で語っているように、遠い彼方から男を導く存在である。導く存在は、身近ではありえない。遠い彼方にいるから、男はそれにあこがれるわけだが、たとえ身近にあっても、あえてそれを遠い彼方に置こうとする。男は恋する女性を、もちろん身近に引きつけたいと願う。が、それだけでは西欧の「恋愛」の型は生まれなかった。騎士はお姫様の住む城から冒険に旅立つのであり、こうして遠い彼方の女性というものをあえてつくりだすのである。やがて肉体の恋はやってくるとしても、それとは別に、遠い彼方にあこがれる「魂(ソウル)」の恋がある。
ところで、私たちの国には、こういうパターンの恋物語は、まずなかった。『万葉集』の恋歌は、ほとんどすべて、二人がいったん結ばれて後の悲しみや喜びを歌っている。『万葉集』の恋する男にとって、恋する人は、遠い彼方ではない。肉体を離れた魂だけの存在ではない。『万葉集』の中にも、一度会っただけの人にあこがれる、というような歌もまれにはあるが、これにしてもよく注意して読むと、一度会った、とは一度結ばれた、という意味であるらしいことが多い。
巌本の理解した、loveとは「深く魂(ソウル)より愛する」ことだ、という考えについて、私はこのような事情を考えざるをえないのである。Loveとは、決して「魂」だけのできごとではない。しかし、魂と肉体とを区別して理解しようとする考え方、ものの見方がそこにはある。私たちの伝統的な「恋」や「愛」が、心と肉体とを常に切離さず、一つに扱ってきたのと対照的である。したがって、loveの解釈として、「魂」だけをとくに強調する「恋愛」観も、当然あっておかしくなかった、と考えられるのである。
「恋愛」ということばは、いつごろから使われるようになったのだろうか。ここで、loveや、これに相当する西欧語の翻訳の歴史をふり返ってみよう。
日本語の辞書ではないが、幕末から明治初期の人びとによく使われた各種の「英華字典」では、古くから「恋愛」ということばが出てくる。ただし、動詞のloveの訳語で、名詞のloveの方ではない。メドゥーストの『英華字典』(1847-48年)では、to loveの訳語が、「愛、好」で始まって、「哀惜」「恋愛」などがある。名詞のloveの項では、「愛情、寵、仁」などだが、「恋愛」はない。ロブシャイドの『英華字典』(1866-69年)でも、だいたい同じである。
日本語の辞書では、『和蘭字彙』(1855-58年)が、liefdeの訳語に、「寵愛又愛敬」「仁」とある。『仏語明要』(1864年)が、amourの訳語を、「恋○愛○恋神」としている。『英和対訳袖珍辞書』(1862年)では、loveが、「愛、恋、財宝」である。日本語の辞書に「恋愛」が現れるのは、仏学塾の『仏和辞林』がたぶんもっとも早く、1887年版でamourの訳語が、「恋愛。鐘愛。好愛。愛。愛セラル、所ノ者」となっている。
「恋愛」という翻訳語の実際の用例は、前記の巌本善治以前では、非常に少ない。おそらく最初の用例は、1870-71(明治3-4)年に出た中村正直の翻訳、『西国立志編』における例であったろう。そこで、
李嘗(リイかつ)テ村中ノ少女ヲ見テ、深ク恋愛シ、
と使われている。原文(S. Smiles: Self-help,1859)では、ここのところは、
to have fallen deeply in love with a young ledy of the village,
となっている。中村の訳文には「英華字典」の影響が大きいので、これもそうであろう。「恋愛シ」という言い方では、この「恋愛」の部分は、サ変動詞の語幹である。この点も、「英華字典」で「恋愛」が動詞として扱われていたことと似ている。
巌本善治のあの「恋愛」の紹介も、系譜をたどれば「英華字典」の訳語を受け継いでいた、と考えられる。が、巌本のこの「恋愛」論は、私たちの「恋愛」史上、画期的な出来事であった、と思うのである。
第一に、巌本はあそこで、「恋愛」を真正面から肯定した。それは、とりわけ、あの前後の時代的背景の中で、画期的なのである。
「恋愛」は、とくに小説の中心テーマであるが、幕末から明治初期の頃、西欧の書物がいろいろと翻訳され、紹介された中で、小説は少なかった。あったとしても、『ロビンソン・クルーソー』のような冒険小説、あるいは政治小説などがおもであった。要するに、男の時代だったのである。国造りの仕事の忙しい男たちにとって、「小説」や「恋愛」は、二の次、三の次だった。『西国立志編』におけるあの「恋愛」にしても、これはこの書物でただ一ヵ所現われている「恋愛」だが、少年李は、「恋愛」したものの、女は靴下を編む仕事に忙しくて相手にしてくれない。そこで、それなら靴下を機械で編む自動織機を発明してやろうと思い立った、というのである。
巌本善治の『女学雑誌』は、この男の時代の中で、精一杯、一つの抵抗の拠点をつくっていたのである。「恋愛」は、あの紹介の頃以後、巌本の指導と支持で、『女学雑誌』の一つの中心テーマとなっていく。「恋愛」論の投書がしきりにとりあげられ、北村透谷が、それを引き継ぐ。そしてやがて、日本におけるロマン主義の時代を花開かせたのである。
ところで、問題は、「恋愛」という翻訳語、つまりことばの問題である。巌本から透谷を経て、日本の一時期の文芸へと受け継がれていく「恋愛」の思想を、その特徴を、時代とか歴史という視点から眺めることはもちろん重要である。が、それとは一応別に、翻訳語ということばの視点からとらえることができる。それを考察してみたい。」柳父章『翻訳語成立事情』岩波新書、1882.pp.89-97.
『女学雑誌』以来、教養ある良家の少女にとって「恋愛」という観念は、甘い蜜の貯水池になった。親の決めた許婚といずれ嫁入りする運命にあるとしても、もし可能なら、すぐれた資質と洗練された趣味をもつイケメン男とイイ関係になり、情熱恋愛がしてみたいと願う娘があちこちに現れた。もちろん彼女たちの夢は、ほとんど幻のうちに消えたのだが、それを実践してしまったお嬢様もたしかにいて、やがて「新しい女」と呼ばれることになる。

B.既成事実に慣らされている?
自衛隊という存在をめぐる安全保障論議を、その「再軍備」といわれた創設期から振返ると、憲法9条との斉合性を問う自衛隊違憲論は、ときの保守政権によって次々なしくずしにされて今に至っている。相次ぐ災害で救援に活躍する自衛隊の姿は、ごく当たり前の光景になり、国民の大多数が自衛隊の存在を頼もしいもの、悪くないものと感じていると安倍首相は満足げである。でも、災害復旧や市民生活への支援が主要任務なら、アメリカの州兵みたいな地域救援部隊でいいわけで「国軍」的な装備や機能は要らない。自衛隊は、当初の役割からだいぶ違うものになり、5年前の「安保法制」成立で、日本の領土と国民を守る、という範囲を超えて米軍の行なう戦争の応援部隊にまで変質してしまった。そのことをあんなに危惧したのに、いつのまにか日本国民有権者は、なんだか別に問題ねえんじゃね?みたいに、無感覚になってしまってヤバくね。
「安保法成立5年 「専守防衛」踏み外すな
安全保障関連法の成立から三年。いま、私たちの眼前にあるのは戦後日本が貫いてきた「専守防衛」を踏み外し、憲法九条が蔑ろにされている現実だ。
安倍晋三首相率いる内閣が「平和安全法制」と称し、強行した安保関連法の成立から、今日九月十九日で三年を迎えた。
安倍氏は、連続三選を目指す自民党総裁選の演説会などで、安保法について「日米はお互いに助け合うことのできる同盟になった。助け合うことのできる同盟は、その絆を強くするのは当然だ」と、その意義を強調し続け、支持を呼び掛けている。
違憲性は拭い去れない
「助け合う同盟」とは、集団的自衛権を部分的ながら日本も行使できるようになったことを指す。
おさらいになるが、集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず実力で阻止する権利のことだ。
日本の歴代内閣は憲法九条に基づいて、集団的自衛権について、主権国家として有してはいるが、その行使は憲法上、許されないとの解釈を堅持してきた。
この解釈を変え、集団的自衛権の行使を一部容認したのが二〇一四年七月一日、安倍内閣の閣議決定であり、安保法はこの閣議決定を基に策定された。
戦争放棄と戦力不保持の憲法九条が、日本国民だけで三百十万人の犠牲を出し、交戦国にとどまらず、近隣諸国にも多大な犠牲を強いた先の大戦に対する痛切な反省に基づくのは論をまたない。
日本防衛のための必要最小限の実力組織として自衛隊が発足したが、専守防衛に徹し、他国同士の戦争には加わらない九条の精神を一内閣の判断で独善的に変えていいわけがない。安保法の違憲性は引き続き問われるべきだろう。
活動拡大で既成事実化
にもかかわらず、国会での追及は手ぬるいと言わざるを得ない。安保法成立当時の最大野党、民主党は分裂し、野党共闘にも影を落としている。安保法廃止を求める野党各党はいま一度結束して、憲法論争に果敢に挑むべきである。
安倍政権が成立後の三年間に進めたのは、安保法の既成事実化と自衛隊の活動領域の拡大、その裏付けとなる防衛費増額である。
ここ数日、自衛隊をめぐる報道が相次いだ。その一つが、政府が秋田、山口両県への配備を計画する地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」について、だ。
北朝鮮が、米空軍が戦略爆撃機を配備する米領グアム島に弾道ミサイルを発射した場合、日本の地上イージスが迎撃することもあり得ると、防衛省が認めたという。
日本を守る名目で導入される防衛装備品が、米国を防衛する集団的自衛権の行使にも使われて当然という、安保法に基づく日米の軍事的一体化を象徴する事例だ。
安倍内閣はまた、エジプト・シナイ半島でイスラエル、エジプト両軍の停戦監視活動をする「多国籍軍・監視団」(MFO)に、陸上自衛隊の幹部自衛官数人を、司令部要員として派遣することを検討しているという。
国際平和への貢献は必要だとしても、国連が統括しない米国中心の軍事的活動だ。参加打診は以前からあったとされるが、なぜ今、という疑問は拭い去れない。
国連以外の国際機関の要請でも自衛隊を派遣できるようになった安保法の適用事例拡大に主眼があるのでは、と疑わざるを得ない。
海上自衛隊の潜水艦とヘリコプター搭載型護衛艦が十三日に、南シナ海で対潜水艦の訓練を初めて実施したことも看過できない。
南シナ海は、日本にとっても重要な海上交通路であり、中国が一方的に権利を主張し、軍事拠点化を進めることは、高校の安全確保の観点からも認められない。
首相は「特定の国を想定したものではない」とするものの、中国けん制の意図があるのだろう。
かといって中国をはじめ各国が領有権を主張し合う「係争地」に乗り込んでの訓練が緊張を高めるのは当然だ。それが、武力による威嚇を、国際紛争解決の手段としては放棄した日本の役割なのか。
自衛隊明記で9条変質
自民総裁選で優位が伝えられる安倍氏は自衛隊の存在を明記する九条改憲を訴え、連続三選を果たした後、今秋の臨時国会に自民党改憲案を提出し、二〇年中の改正憲法施行を目指すと明言した。
しかし、集団的自衛権の行使など安保法の違憲性を問わず、その活動を行う自衛隊の存在を憲法に明記すれば、他国同士の戦争には参加しない九条の精神を、さらに変質させることになりかねない。
眼前で起きる安保法の既成事実化や自衛隊の活動拡大を放置していいのか。平和国家の道を歩んできた戦後日本の試練でもある。」東京新聞2018年9月19日朝刊5面、社説。
安倍晋三の提起する改憲の、いちばんの眼目は9条に自衛隊を明記し、正規軍を持つ国家という場所に日本を置きたい、という思想だろう。「国軍」と呼びたい心情を抑えて「自衛隊」でもまあいい、とにかく軍事力を自由に行使して国益のために場合によっては戦争もできるようにしておきたい、という意思。いま自民党総裁選を安倍氏と争う石破氏も、基本的に同じ考えで、できれば戦力不保持もとっぱらうのが筋だと言っている。どっちもそこまで言っても、国民多数から支持を得られると読んでいる。まったく、戦後70年、「9条の平和主義」は敗け続けてしまったわけで、本丸落城まえの豊臣秀頼みたいなところにいる。