■牟田和恵『部長、その恋愛はセクハラです!』(集英社新書、2013年)
頁109──
たとえば電車で痴漢に遭った女性がどういう言葉を発するか考えてみてください。現実には不快感を押し殺し、黙って身体をずらしてなんとか逃れようとするだけ、という女性が多数派ですが、声を出すことができたとしても、か細い声で「やめてください」「やめて」というのが関の山でしょう。でも、「やめてください」は、決して「ノー!」「やめなさい!」ではありません。命令ではなく依頼、礼儀正しいお願いです。小さな可愛らしい声でそうした「女らしい」反応をされれば、痴漢はあわてて手をひっこめるどころか、むしろ喜ぶかもしれません。
男性がもし同じような目に遭ったら、「やめろ!」と怒鳴ることもできますが、女性にはそれはできません。女性が電車の中で「やめろ!」とドスの利いた声で怒鳴ったら、周囲は、女性の被害に同情するよりも、なんと非常識な女性かと呆れるに違いありません。
ここから見えてくるのは、日ごろは気付かない、ジェンダーによる言葉の縛りです。日本語では、とくに女性は、断定・言い切りの言葉を使いません。女性は会話ではいつも、「~かも」と語尾を曖昧にし、相手の意図を窺いながら頻繁に相槌をうってコミュニケーションをします。相手に何かを要求したり禁止をしたりする場合ですら、女性の言葉がストレートな命令のかたちを取ることはほとんどありません。あるとすればせいぜい犬に「お手」「伏せ!」と言うときくらい。子供にも、父親なら「勉強しろ」と言うところを、「勉強しなさい」「しなくちゃだめよ」と言うのですから。
そんな女性たちには、不快な、意に反した性的接近をされ、セクハラや痴漢に遭う場合ですら、はっきりとノーを伝える言葉がありません。報復されるのではないかと考える以前に、戸惑いやおびえ、あるいは相手への配慮から女性が「ノー」を言えない事情をこれまで縷々ご説明してきましたが、その奥に、そもそも「ノー」の言葉がないとは、なんとも悲劇的なことではないでしょうか。
しかしもちろん、言葉や表現は変化します。女性がしゃべる日本語に「ノー」がないのは女性が置かれた社会状況の反映です。歴史をたどれば、階層・地方によっては、男女の言葉遣いにさほどの性差はなく、女性の今の感覚からすればもっとぞんざいで乱暴な言葉遣いをしていました。今でも地方によっては、「オレ」と自分を呼ぶおばさんがいたりします。
■国家と儀礼研究会編『雅子の真実』社会評論社、1993年初版第1刷
頁10──
マサコ略奪の噂
天野恵一
頁19──
この間いろいろ情報を分析していて、ぼくらが長いことだまされていたことに気がついたことがあります。それはミチコのドラマです。ミチコが陰惨な皇室に民間の女としてマサコを引きずりこむ役割をしたことの裏には、おそらく自分が負った人生の悲惨さに対する復讐があったのかもしれない(笑)。ミッチーブームの時に出ていた週刊誌に、彼女も一度逃げて、国外旅行をしていたという記事が載っていました。そして帰ってきた時か、それ以前かに断りの手紙なんかを書いた。皇室に宛てたものですから、婉曲にいうしかなく、だからそれを断りというふうにとらなかった向こう側(笑)が、もう一回すごいアッタクをする。最終的にはこれで落ちちゃったらしいのです。ミチコの母親が──今度のようにグロテスクな話は相対的には少ないかもしれませんが、マサコの母と同じように最後まで反対していたらしいのですが──最後の言葉として「小泉信三にだまされた」といっていたことが、彼女が死んだ時、週刊誌に載った。あれも一種の政略強奪結婚ふうのものだったと思うんです。国家が国家の事業として民間から女を入れるという方針を決め、かなり強制的に囲い込んでいろいろやった。最後まで反対した母親は、いろいろな条件を出して娘をさし出したのですが、その約束が守られなかった。ミッチーブームの、「テニスコートの恋」のイメージ操作の裏側にもこういうドラマがあったわけです。
■WiMN『マスコミ・セクハラ白書』文藝春秋、2020年
頁12──
聞く──望月衣塑子さん(40代・東京新聞記者)の場合
頁19──
・・・セクハラを受けたのは、それとは別の時だった。
「新しい支局に異動して2週間ほど経った頃のこと。支局時代は自分で車を運転して取材先に行きますが、所轄のある副署長さんのところへ車で夜回りに行った時、『ここじゃ話せないから車の中で』と言われ、自分の車に移動したんです。自分が運転席に座り、相手を助手席に座らせて話を聞いていたら、いきなり抱き着かれてキスされそうになった。払いのけてすぐに車から飛び出しました。
それまでに人間的な交流がいろいろあって好意を持たれた、というならまだ理解できますが、会って夜回りは1回目です。車に誘い込んだのもそういう意図があったんだな、と思いました。
あんまり頭に来たので、支局に戻って上司に相談したんですね。そうしたら、『もうそこには行かなくていい』。それで、これはこういう場合に上司からよく言われるようなことかなと思いますけど、『まだこの支局に来て2週間足らず。事を荒立てて相手が処分されるようなことになると、相手は傷つくが、それ以上に『あいつは取材先を売る女だ』、と言われて望月自身がバッシングされ、その後取材しにくくなる可能性がある。よく考えてほしい』と」
上司にそう諭されてしまうと、悔しかったけれど、これからガンガン取材したいと思っていた時期だった望月さんは、「取材ができなくなるのは自分にとってもきついな」と、その場は我慢し、納得した。でも、どうしても黙って泣き寝入りするのは納得が行かない。
「翌日、その副署長のところにもう一度でかけました。副署長室だと他に人がいるから、1対1になろうと思って、夜回りに行ったのかな。とにかく他に人がいないところで面と向かって、『昨日は何であんなことをしたんだ!ふざけんじゃねぇ、女性記者をナメてんのか』って、めっちゃオッサン言葉で怒鳴りまくって怒りをぶつけたんです。
その人、びっくりしてました。それで、『いや、軽はずみで申し訳なかった』とひたすら謝罪をしてくれました。それ以降、そういう行為は一切しなくなったし、腹を割った仕事の話ができるようになりました。今でも連絡のやり取りがあります。
その時に感じたのは、やっぱり怒りをきちんと伝えないと相手はつけ上がるし、もしかしたらこれまでずっと、女性記者にそういうことをして許されてきたのかもしれない、ということ。














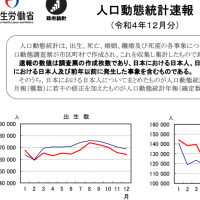








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます