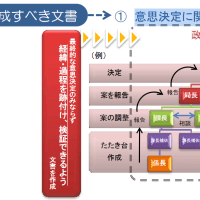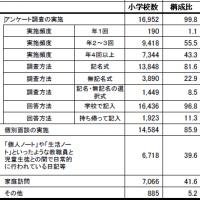八方美人尾木直樹が夫婦別姓についてどんな考えを持っているのだろうかとネット検索を掛けてみたら、本人のブログ、「尾木ママオフィシャルブログ」の2015年12月17日の記事、《夫婦別姓なんて当たり前なのに、最高裁って古いんですね》(尾木ママオフィシャルブログby AMEBA/2015-12-17 23:11:42)に当たった。
水増しするために行間隔を大きく開けているが、勝手に狭めることにした。以下、全文を紹介する。
〈再婚規定の違憲判断
当たり前!!
でも
夫婦別姓?
おかしくないのに…
・男女平等の原則に違反
・個人の幸福権追求の侵害
に明らかにひかかりますね!!
古い
古い
最高裁にがっかりの
尾木ママです…〉――
この記事記載の前日、2015年12月16日、二つの最高裁判決が示された。一つは女性の再婚禁止期間6ヶ月のうち100日を超える部分を違憲とする判断と、夫婦同姓を義務付ける民法750条を合憲とする判断が示され、夫婦別姓結婚への憲法容認は門前払いとなった。
特に後者の場合は夫婦同氏の強制は憲法第24条の要請、個人の尊厳と両性の本質的平等の侵害に当たるとの訴えに合理性を欠くとは認められないと裁決している。
勿論、尾木直樹の上記記事はこの両最高裁判決を受けた自身の評価であって、再婚規定の違憲判断に賛成であり、夫婦同姓のみの義務付けに対する合憲判断に反対であることが分かる。
だが、再婚規定の違憲判断がどう「当たり前!!」なのか、夫婦別姓がどう「おかしくない」のか、同じく夫婦別姓結婚について憲法上認められなかったことが男女平等の原則にどう「違反している」のか、個人の幸福権追求をどう「侵害」し、どう「ひかかる」のか、今回の夫婦別姓を認めない最高裁の判断がどうして「古い」のか、尾木直樹自身がそれぞれに理由とするところの具体的な解釈や根拠を何も示さずに片付けていることの自身の無責任に何も気づいていない。
なぜなら、教育者として社会的に広く活動している以上、教育問題に限らずに社会や政治の問題に関しても自分自身にとって理想とするあるべき姿を取っていないことに対してこうあるべきだと理想を口にすることは、好むと好まざるとに関わらず、世論を自身が理想とする方向に導く役割を同時に果たしていることになるのだから、「当たり前!!」、「おかしくない」、「侵害」、「ひかかる」、「古い」等々の発言に対して理由、あるいは根拠を述べた上で著名な教育者としてのこうあるべきだとする自らの言葉を発信しないのは自らが担うことになる世論形成の役割を放棄していることになり、教育者として発言する資格を失うことになるからだ。
この夫婦別姓婚の憲法容認を求める東京地方裁判所への告発は2011年5月25日となっている。当然、その当時から関心を持って注目していただろうし、2015年末の最高裁判決まで4年が経過しているが、こういった事情に反して一家言を持って行うべき世論形成を置き忘れたほんのちょっとした感想、あるいは印象の類いしか発信できないことと最高裁判決の翌日の尾木直樹の記事であることとの関係から新聞記事のつまみ食いに過ぎないと断定できる。
要するに教育者として進歩的なところを見せるために何か一言言う必要が生じたが、世論を導くだけのこうあるべきだとする考えを持っていなかったために新聞記事をつまみ食いした程度の感想や印象の類いで終わることになったといったところなのだろう。
このように断定できる理由は他にもある。イジメ解決の書物を数多く出版しているが、提言はするが、その具体的な方法論には触れずじまいで終える無責任を多々見るからだ。
以前ブログに取り上げたことだが、その特徴的な例を一つ示してみる。
2013年2月1日に発売した『尾木ママの「脱いじめ」論 子どもたちを守るために大人に伝えたいこと』という教育本の第5章は、「本気でいじめをなくすための愛とロマンの提言」と謳っていて、その中で、「どの子にも居場所と出番のある学級づくりの実現」を掲げている。
だが、実現の必要性を言うだけで、実現の具体策には何一つ触れていない。「居場所と出番」を別の言葉で言い換えると、「可能性追求の機会と場」となる。何らかの活動に基づいた可能性追求の機会を手にすることによって、機会発揮の場が居場所となり、発揮すること自体を出番とすることになる。
勿論、どのような可能性であってもいいわけではない。誰かをイジメることが自身の楽しい活動となり、最悪、活躍しているという思い込みに駆られた場合、イジメを自身の飛び切りの可能性追求の機会とすることになって、楽しいばかりの出番とすることになる。
結果、一度イジメると、なかなか抜け出せないのは思うようにいくという成功体験が自分にとっての精神的、あるいは肉体的躍動を利益とするようになるからだろう。
当然、何かの趣味に没頭するといった自分一人の可能性の追求ではなくて、第三者が関わる可能性の追求の場合は自分だけが何らかの利益を得るものはなく、相手にとっても何らかの利益となる可能性の追求でなければならないことになる。
尾木直樹が「本気でいじめをなくすための愛とロマンの提言」だ、「どの子にも居場所と出番のある学級づくりの実現」だなどと口にする以上、お互いが精神的にも肉体的にも利益となる「可能性追求の機会と場」を見い出すことのできる手助けをして、そのことを以ってそれぞれの「居場所と出番」にできるように持って行く方法を示し、その方法を広めていく世論形成が教育者としての役目だろうが、言うだけ言って、役目を果たさず、その責任を放棄したままでいる。
この無責任は、先に挙げた最高裁判断に関して著名な教育者として発言していながら、自分が理想とする方向に世の声を少しでも向けようと自らの考えを述べるべき務めを果たすこともしない無責任と通底している。
この点からも上記最高裁判断に関わる記事内容は新聞記事のツマミ食いに過ぎないと断定できる。