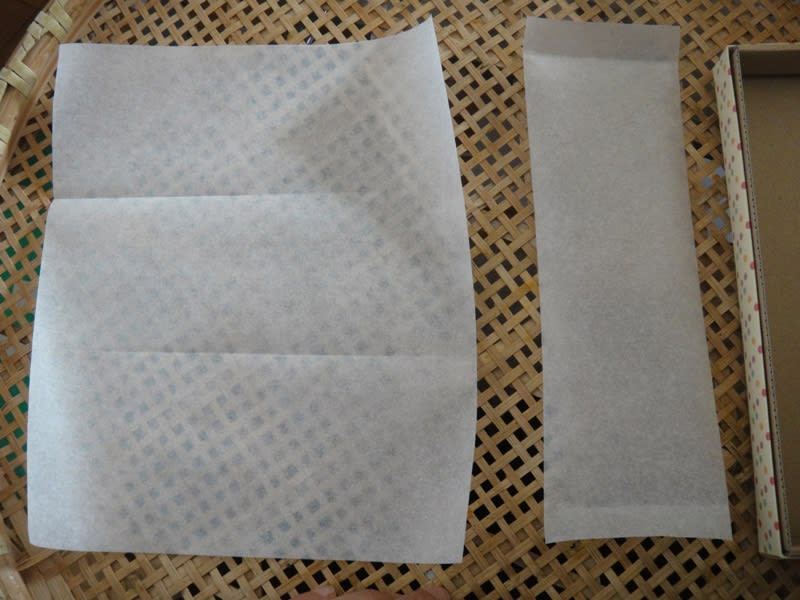フィンランドの陶磁器メーカー、アラビアの展覧会が笠間でやっているということなので、行ってみることにしました。
国立科学博物館のチョコレート展は結局行けず仕舞いだったので、せめてこちらだけでも、と元気をふりしぼりました。
 |
場所は茨城県陶芸美術館。
陶芸のまち笠間(茨城県)にあります。
同じく陶芸のまち益子(栃木県)には何度も行ったことがありますが、笠間は初めて。
ダンナサマに運転してもらったせいもあるかもしれませんが、結構近いです。
|
 |
今でもデパートで見かけるデザインが、歴史を追って色々見られました。
意外だったのはこちら。蛍手のもの。
こんなものもアラビアで作っていたとは。
中国の磁器を真似て、1942~1974年に作られていたのだそうです。「ライス・ポーセリン」というシリーズ名。
中国の技法だけれどデザインはどことなく北欧風です。
調べてみると、日本でもビンテージ品が買えるところもあるようですが、ひとつ数万円はするようです(値段まで見たってことは、ちょっと欲しかったのね?ええまあその・・)。
|
 |
アラビアで最も重要なデザイナーの一人、カイ・フランク。
用途ごとにそれぞれ複雑な形状の食器が必要な従来のテーブルウェアに意義を唱えました。
「ディナーセットをぶっ壊せ」というスローガンを掲げ、マルチユース、積み重ね易さなどの機能を追求して発表されたのが「キルタ」シリーズ。
6人分の食器が、綺麗にスタッキングできる雑誌広告が展示してありました。
(僧侶の使う入れ子状の器、応量器に通じるところがあるようにも思います)
|
 |
電子レンジ対応など、いくつか改良点を加えたキルタの後継シリーズがこのティーマ。
今でも製作されているようです。
素敵にしよう、とするとつい、何か付け足したくなってしまうところですが、カイ・フランクはアレもコレも取り去って、シンプルさを追求したところがすごいです。(不安になるほどにシンプル)
|
 |
カイ・フランク氏は日本にも来たことがあるようです。
北大路魯山人など有名陶芸家の作品を見ていったとか。
白山陶器の醤油さし(森正洋デザイン)を高く評価したそうです。
なるほど、カイ・フランクデザインに通じるものがあります。
(画像は白山陶器からの借り物です)
|
 |
こちらは、カップから取っ手を取り去って、リング状の突起にしてしまえば、スタッキングも容易だし、場合によっては別の用途にも使えるし・・・という発想です。
40年ほど前のデザインですが、モノトーンのヒース柄はシックで、今でもどこかで売っていそうな感じ。
|
 |
一方、ほぼ同じ時期、1965-1975年製作なのに、この「ポモナ」シリーズは何だか懐かしい「昭和」な感じ。
この時代、こういう流行があったのでしょうか。類似のデザインが、鍋やらガラス器やら沢山あったような気がします。
|
 |
アラビアといえば、というもののひとつ。「ヴァレンシア」シリーズ。
スペインの陶磁器を参考に作られたハンドペイントのものだとか。(つまり高級シリーズ)
1960~2002年というロングセラーでしたが、現在はもう作られていないようです。
|
 |
アラビアには芸術家部門があって、いわゆる陶芸作家を数人雇っていたとか。
これはその中の1人、ビルガー・カイピアネンによる作品。
(いわゆる手作りの1点もの、というものだと思う)
作家は、基本的には自分の作品を追求していたようですが、人によっては大量生産部門のデザインを手がけることもあったとか。
|
 |
それがこちら。
アラビアといえば、という程馴染みがある「パラディッシ」(天国という意味)シリーズ。上と同じビルガー・カイピアネンによるデザイン。
ハンドペイントの工程があり、アラビアでも最高級クラスのシリーズだったそうです。
1969年から1973年という比較的短期間で一旦生産が終わっていたようですが、2000年からリバイバルしています(ミュージアムショップにもあった)。
|
どこの陶磁器メーカーもそうなのかもしれませんが、電子レンジや食洗機の普及に伴い、洗いやすい形や堅牢で色の変わりにくい釉薬などの研究も進められていたそうです。
工業デザインという制約の中、機能と美とを追求していたプロ集団の作品は、「作家もの」とは全く別のベクトルです。
大衆のため、用の美を追究していたカイ・フランクの時代、一つの頂点に達していたのかもと思いました。
常設展で笠間の作家さんの、これはこれで美麗な作品を見たので尚更印象深かったです。
展示品の数はさほど多くありませんが、興味深い展覧会でした。
現物だけでなく、カタログの拡大コピーをタイプ別に年表に貼り付けて並べるなど、もっと二次資料も使って色々展示すればいいのにな、と思いました。
アラビア以前/以外のフィンランドデザインの流れみたいなものも知りたかったな・・。
テキスタイルメーカーのマリメッコの展覧会もどこかでやらないかしらん・・・。
さて、お楽しみのミュージアムショップ。
最近は、企画展の内容に合わせた業者が出店していることも多いですよね。
(チョコレート展だったらチョコレートが売っていたりなど)
アラビアの陶磁器がいっぱい並んじゃっているのかしら☆と思ったら、それほどでもなくて・・・。
 |
(パラディッシなど)新品いくつかのほか、北欧デザインのビンテージ品がいくつかありました。
このポットには見覚えが・・・。
業務連絡:お母さんへ
うちにあるあのポット、結構なお宝かもしれませんよ~。
|
 |
アラビア以外の陶芸作品も置いてあります。
このうさぎ、可愛い・・。
|
 |
冬眠中のヤマネさんたち。
(ダンナサマに撮っておいてと言われた)
|
 |
真ん中の、スヤスヤ寝ているフクロウの子がダンナサマのお気に入り。
|
美術館を出ると、別館でコーヒーやソフトクリームが売っているようです。
折角だからちょっと休憩しようかと立ち寄ったら、 中はかなり大規模な売店!
おおう! 単なるコーヒーショップではなかったのね!
(「笠間工芸の丘 KASAMAクラフトヒルズ」という施設だったようです)
 |
夏みかんピール。
左はなんと、粉唐辛子がまぶしてあります。
どんな味なんだろう。
|
 |
ヘタ付近をスライスした、夏みかんピール。
緑のものは、何かで色をつけてあるのだろうか?
(原料表示は見そびれました)
|
 |
食品だけでなく、陶芸作品、食器類も大量に置いてありました。
このうさぎも可愛い・・・。
|
 |
あんまり可愛いのでもう1枚。
|
 |
ここで一番印象深かったのはこの変なお魚かな。
直径50cmくらいあり、周囲は裏側に反り返って高くなっており、鉢を裏返しにしたような形状です。
「廣田芳樹 盤皿 とと 23100円」
使うものなのかな?それとも飾るためだけのものかな?
どこに飾るかはともかく、欲しくなってしまいました。
|
お豆腐屋さんと産直で買い物をして、高速に乗って帰りました。
ダンナサマへ:
また行きましょうね。
笠間稲荷とか、本命の観光スポットがまだですし。 いなり寿司も名物みたいです。
■参考情報
アラビア窯の有名デザイナーの解説 (日本語)
アラビアシリーズ名一覧