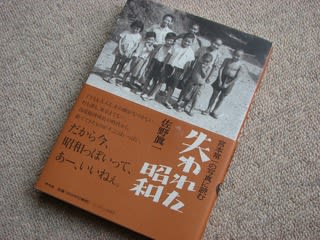先日、久しぶりにこの本を入手した。「抜粋のつづり・その六十五」。
津島町岩松商工会(宇和島市)にあるものを頂戴した。
これは知る人ぞ知るもの凄い本である。片手に納まるハンディタイプの冊子であるが、私にはこの本にちょっと思い入れがある。
かつて、「あけぼの」という地元建設会社の広報担当だった頃、私はこの冊子と出会いとても驚き感銘を受けた。発行元は株式会社熊平製作所。広島の宇品に本社のある金庫の会社である。今はどうか、確か以前は熊倉和雄?(人形劇「ひょっこりひょうたん島」の声優)を起用したCMがテレビで流れていたような。
ともかく、これは質実な金庫のメーカーから年一回発行されている冊子であり、つまり「その六十五」ということは、昭和6年からの発行(戦中戦後の混乱期を除く)で、今も続けられていてその歴史は75年に及ぶ。これは小・中学校や図書館を中心に全国8万ヶ所に無料配布されており、その部数ナンと45万部。
内容は、その年の新聞各紙や雑誌などから、人々の為になると思われる文章の抜粋で構成されている。この号では、新井満氏の「千の風と千の花」(読売新聞より)から田辺聖子氏の「お酒と口別嬪」(日本経済新聞より)まで新玉のエッセーが33編。
前述の「あけぼの」は、営業マンが地域へ無料配布するという形式を取っていたので、その編集にあたっては企業メセナやフィランソロフィーなどといった、企業の地域貢献について、それは仕事柄とても大切な関心事だった。20年ほど前にこの「抜粋のつづり」の存在を知った私は、戦前から既にそんなことをしていた企業があったことに驚愕した。しかもクマヒラの金庫。
私事にはなるが、本社のある広島の宇品には、学校を卒業して就職したジャスコ時代に住んでいたので(在住当時は知らなかった)、早速私は愛媛から連絡を取って熊平製作所を訪問した。そうすると、やはりと言うべきか、比較的地味な佇まいの工場から地味な感じで年配の方が出てこられ、応対していただいた。
聞けば、たった一人で編集し、全国に送り続ける作業をされているとのこと。信用第一の金庫製作会社で、連綿と続く企業メセナの真髄を見た瞬間だった。
因みにこの会社、今年で創業108年を迎えるという。ライプドアではないが、時代という厳しい経済変動の中で企業が生き残り、長きにわたって存続することの難しさを思うと、その長さは国内でも希少な企業の一つである。
「抜粋のつづり」は、その創業記念日(1月29日)を期して全国に配送される。
巻頭にある創業者の「創刊のことば」を記してみる。
『日頃の御好意に対して感謝の意を致したいと存じてをりますので、その一端として、このパンフレットを発行したしました。
積極的消費論と学校教育の普及と改善、又宗教に現世の浄土化思想の必要は私の持説とする所で御座いますが、私の陳弁よりも、近頃読みましたものの内で、こうした方面における諸名士の御意見を紹介してみたいと存じまして編纂いたしました。 昭和六年霜月 熊平源蔵』