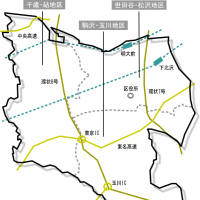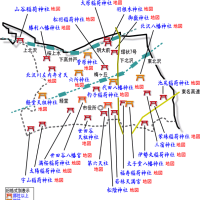下高井戸八幡神社
鎮座地 下高井戸4-39
祭神 応神天皇(おうじんてんのう)
旧格式 村社
別当寺 宗源寺
例大祭 9月第四日曜
解説
下高井戸宿の鎮守。
長禄元年(1457)太田道灌が江戸城を築く際に、
家臣柏木左衛門が工事の安全を祈願して、鎌倉鶴岡八幡宮のご分霊を遷したという。
江戸時代には甲州道中下高井戸宿の鎮守となった。
本殿は弘化4年(1847)築。明治25年(1892)四ツ割の稲荷神社が合祀された。
神職は斉藤氏が務める。
現在では絶たれているが、昭和初期まで「面芝居」という神楽が伝わり、
当時の斉藤守高宮司は「中村縫之助」という芸名を持つ元締であった。
ホームページ http://www.shimotakaido.org/
鎮座地 下高井戸4-39
祭神 応神天皇(おうじんてんのう)
旧格式 村社
別当寺 宗源寺
例大祭 9月第四日曜
解説
下高井戸宿の鎮守。
長禄元年(1457)太田道灌が江戸城を築く際に、
家臣柏木左衛門が工事の安全を祈願して、鎌倉鶴岡八幡宮のご分霊を遷したという。
江戸時代には甲州道中下高井戸宿の鎮守となった。
本殿は弘化4年(1847)築。明治25年(1892)四ツ割の稲荷神社が合祀された。
神職は斉藤氏が務める。
現在では絶たれているが、昭和初期まで「面芝居」という神楽が伝わり、
当時の斉藤守高宮司は「中村縫之助」という芸名を持つ元締であった。
ホームページ http://www.shimotakaido.org/