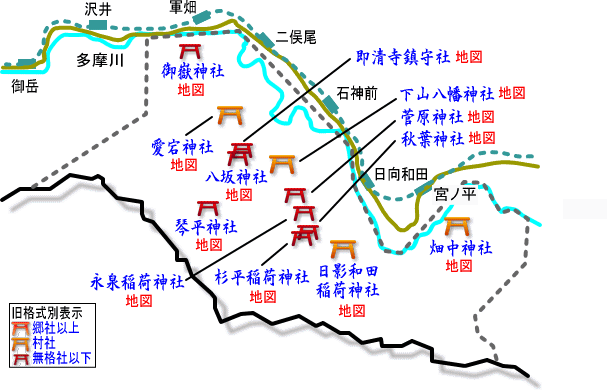氷川愛宕神社
鎮座地 氷川795
祭神 火産霊神 (ほのかぐつちのみこと)
塩土翁命 (しおつおうのみこと)
手名槌神 (てなつちのかみ)
足名槌神 (あしなつちのかみ)
旧格式 無格社?
別当寺 登計・長畑両村持ち
例大祭 7月下旬の日曜
解説
愛宕山山頂に鎮座する。
明治41年(1908)登計の阿羅波婆岐神社と長畑の白髭神社が合祀され現在の祭神となった。
境内に戦没者を慰霊する五重塔がある。
愛宕神は火除けの神様だが、
伝説によると、当地に火事がある時はその前兆として愛宕山の上に火柱が上がり、
その倒れた方に火事が起こるという。
またこういう伝説もある。
長畑村のある後家の家の柱を金色の蛇が登っていくのが見られた。
何の事かと村人たちが愛宕神社に伺いをたててみると、
社殿の中で男女の心中死体が見つかった。
神様が不浄を嫌い、村人に知らせたのであろうという。
鎮座地 氷川795
祭神 火産霊神 (ほのかぐつちのみこと)
塩土翁命 (しおつおうのみこと)
手名槌神 (てなつちのかみ)
足名槌神 (あしなつちのかみ)
旧格式 無格社?
別当寺 登計・長畑両村持ち
例大祭 7月下旬の日曜
解説
愛宕山山頂に鎮座する。
明治41年(1908)登計の阿羅波婆岐神社と長畑の白髭神社が合祀され現在の祭神となった。
境内に戦没者を慰霊する五重塔がある。
愛宕神は火除けの神様だが、
伝説によると、当地に火事がある時はその前兆として愛宕山の上に火柱が上がり、
その倒れた方に火事が起こるという。
またこういう伝説もある。
長畑村のある後家の家の柱を金色の蛇が登っていくのが見られた。
何の事かと村人たちが愛宕神社に伺いをたててみると、
社殿の中で男女の心中死体が見つかった。
神様が不浄を嫌い、村人に知らせたのであろうという。