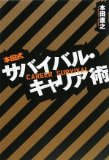
意外に思われやすいのですが、私は、「サバイバル」という言葉が好きです。
というかむしろ、どんな状況でもなるべく自分で対応できるように、とわりと小さい小学5年生くらいのころから、明確に「サバイバル」という意識を持って生きてきたので、レバレッジシリーズで有名な本田氏のこの「サバイバル・キャリア術」は、とてもおもしろく読めました。
中でも特に興味深かったページがあったので引用しておきます。
「自己啓発セミナーなどに参加している人からポジティブシンキングをしても仕事もプライベートもうまくいかないという話をよく耳にします。セミナーを何回も繰り返して受講する人もいるようです。
効果がない理由を私なりに分析すれば、そういったセミナー、その人の置かれる現状を改善することよりも、現状を肯定することにウエイトを置くので受講者の解決能力を高められないのだと思います。
「暗くなったら人から元気をもらってメンタリティを前向きにし、効き目が切れたら、一度元気をもらってメンタリティを前向きに」という回路は、壊れたエンジンにガソリンを注ぎ続けているのと同じです。その場合ガソリンを注ぐより、壊れたエンジンをなおすのが先決なのは、明らかです。
あくまで行動を伴ってこそのポジティブ・シンキング。
サバイバル時代に求められるのはポジティブ・シンキングではなく、ポジティブ・アクションです。」
最後の方に書いてあったこのページを読んで、自分の中のちょっとした疑問が解決できたような気がしました。
私は、「元気をもらった」という最近よく聞くフレーズを耳にするととても気持ちが悪くなってしまうのです。元気はもらうものじゃないでしょ?ちょっと病的な表現なのではないか?とずっと疑問に思っていたのです。
また、そのようなフレーズを好む方の多くは、「ポジティブ」や「前向き」というのをこれまた悲壮感漂わせて求めているようなところも疑問でした。
さらに私が不思議だったのは、そういう方々の元気をもらった後の燃費の悪さです。
次々元気をもらわないと前に進めないなんて、なんでなんだろう?
パソコンのOSではないけれど、自分のバージョンそのものをあげないと、現状に対処できないのではないかな?と薄々は気がついていたことが、本田氏の「壊れたエンジンにガソリンを注いでいる」という表現ですごく納得がいった。
やはりそういうのは正しい状態ではないんだな。
自分が普通にできることを誰か他の人ができない場合、もしくは他の人ができるのに自分ができない場合、私だったら自分の中のOSのバージョン(考え方、行動のしくみ)そのものを変えなければきっとうまくいかないだろうと考えて、自分の感じ方を変え現状に合わせたスキルアップをすることで現実的に対処します。
そうしないと生き残ってはいけない。
生き残っていけないというは大げさな表現と思われるかもしれませんが、現状、今の世の中は本当にサバイバルです。ゆっくり休んで、癒されたいという人は多分今後状況に対応できずに本当に生きていけなくなるくらい大変な世の中なんだと思います。
右肩下がりのライフプランだからこそ、生活レベルを上げないこと、コーポレートキャリアを積んだ後でパーソナルキャリアを積むこと。
大事なことだと思います。
最新の画像[もっと見る]
-
 あんたたちって…と思う瞬間
9年前
あんたたちって…と思う瞬間
9年前
-
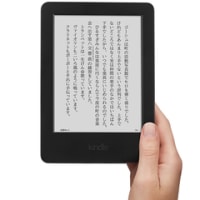 Kindleを注文してみる。
9年前
Kindleを注文してみる。
9年前
-
 ミスター飲茶、スーラタンメン
9年前
ミスター飲茶、スーラタンメン
9年前
-
 牧のうどん本店の肉うどんキムチトッピング
9年前
牧のうどん本店の肉うどんキムチトッピング
9年前
-
 ノマド感ハンパなし、バッグのなかみ。
9年前
ノマド感ハンパなし、バッグのなかみ。
9年前
-
 釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
-
 釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
-
 釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
-
 釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
-
 釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前
釜山食べ歩き「ソファバンでお茶」
15年前









