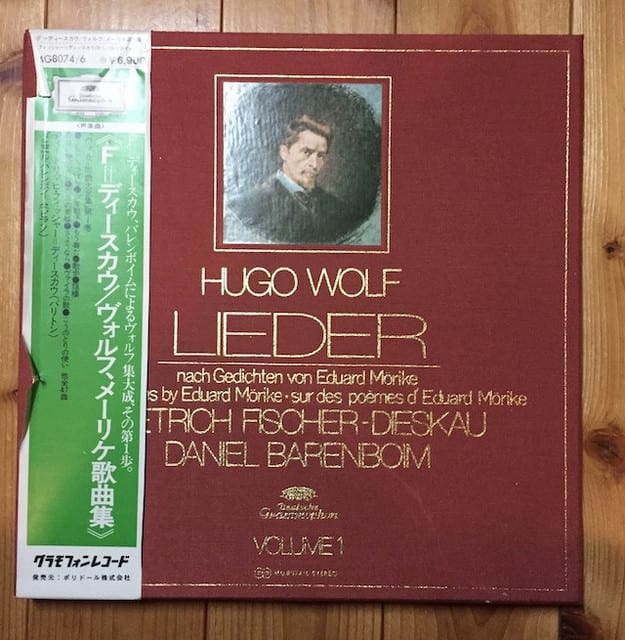やはり「すげーな!」と声が出た
どう表現したら良いのかわからないが、とにかく「すげーな」という感覚だけは強烈に残る
フルトヴェングラー指揮、ウィーンフィルの「エロイカ」1944年録音を昨晩聴いた
記憶に残っているはずなのに、そしてわかっているはずなのに、またまた圧倒されてしまった
でも以前と感じるところは少し違う
前は熱気の凄まじさに驚いたが、昨日はなぜこんな音が出るのだろう?
と不思議に思えた(例えば弦楽器主体のフォルテの音色)
指揮者は自分で音を出すわけではないのに、なぜ音が違うのだろう
気合が入った音と感じられるのは何故なんだろう
クラシック音楽をよく聴く人は、このようなことがあるのは理解している
だから多くの聴き比べをして楽しむのだろうが
何故音色が違うのかは、どうもスッキリと納得できる解説を聞いたことがない
量子力学は確率で表される
何故それが使われるかは、使うと結果とうまく繋がって便利だからで
演繹法による必然的な道具ではないらしい
これと同じで、何故音の印象が違うかはわからないが、音が違うという事実を
認めて話を進めたほうが生産的になっているので、既成事実として使われる
でも好みは時代背景で、そして聞き手の育った時代とか環境によって変わってくる
フルトヴェングラーを知らないで、その後のカラヤンがスーパースターだったころ
感受性のピークを迎えた人は、カラヤンが判断の基準になる
時の経過は恐ろしいもので今ではカラヤンでさえオールドスターになりつつある
そして少しばかり残酷な批評もちょくちょく見かける
それにしても、フルトヴェングラー、、
ほんと何が違うのだろう
不思議で仕方ない
彼の演奏が唯一無比とまでは言わないが、他の演奏と比べて体に残る何かの総量は違う
どこが、なにが違うのだろう