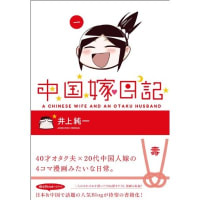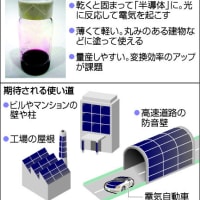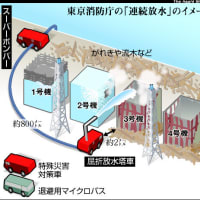環境は改善されている
地球環境問題への関心は、1990年代以降グローバルな広がりを見せ、特に温暖化問題は、97年の京都会議にも見られるように世界のNGO(非政府組織)のもっとも愛好する話題となった。それはまた単に公害を防止するという域を超え、ある時は文学や芸術のテーマとなり、ある時は哲学的な文明論にまで昇格する。たとえば「環境倫理」を提唱する加藤尚武氏(鳥取環境大学学長)は、その著書を「ガイアを救え」という言葉で結んでいる(*1)。だが、果たしてガイア(地球)は救いを求めているのだろうか?
私は1990年に、ガイア仮説を提唱した英国の発明家ジェイムズ・ラヴロック氏にインタビューしたことがある。「ガイアを守れという議論をどう思うか」という質問に、彼は「ナンセンス」と答えた。「ガイアは、40億年前からずっと生き続け、地球の大気の成分は少なくとも7億年前から一定です。その生命力は強靭で、人類に守ってもらう必要などありません」。
彼は地球温暖化や大気汚染についても大して心配していなかった。「大気の組成を変えて生物に悪影響を与えることを大気汚染と呼ぶなら、地球の歴史上最悪の大気汚染は植物の誕生による酸素の発生です」。植物の祖先となった光合成バクテリアの出す酸素は、初期の生物の大部分を占めていた嫌気性生物には有毒で、ほとんどの生物が滅亡したと考えられている。
つまり「地球環境問題」といわれているのは、地球の問題ではなく人間の問題にすぎないのである。ラヴロック氏は「人類はガイアの保護なしには生きられないが、ガイアにとって人類はゴミのようなものです。温暖化によって地球が砂漠化し、人類が死滅したとしても、バクテリアは生き残ってガイアを維持するでしょう」といって笑った。
では人間が住みやすいかどうかを基準にするとして、地球環境は悪化しているだろうか?熱心な環境保護主義者として知られる米国の元副大統領アル・ゴア氏は「地球全体が破局に向かって進んでいる」(*2)と強調しているが、環境についての公式統計を検討したデンマークの統計学者ビョルン・ロンボルグ氏は、「環境は基本的には改善している」という結論を出した。ゴア氏の論拠は、主として個別の環境破壊の例だが、ロンボルグ氏によれば、そうした突出した事件は例外で、地球全体としては環境問題は改善している。
たとえば図のように、ロンドンで大気汚染がもっともひどかったのは19世紀で、現在の大気汚染は16世紀よりましだ(*3)。この他の大気汚染も20世紀後半に劇的に改善しており、先進国で圧倒的に重要な「大気汚染」の原因はタバコである。開発途上国の汚染は深刻だが、これも所得水準の向上につれて改善している。海の汚染は、もともとあまりにも広くて問題にならないし、川の水質汚染も顕著に改善している。

(図)ロンドン市内の亜硫酸ガス(SO_2)と煤煙の濃度 出所:OECDほか
環境保護団体やメディアが好んで取り上げる「危機」の多くも根拠がない。かつて大気汚染による酸性雨が森林を滅ぼすという話が騒がれ、米国政府はNAPAP(全米酸性雨評価計画)という組織を作って調査を行ったが、その結論は「雨のpH値(酸性度)と森林の植生との間には関連は見られない」というものだった。
また「ここ50年でヒトの精子が半減した。その原因は、農薬にエストロゲン(女性ホルモン)に似た物質が含まれているためだ」というBBCのドキュメンタリーをきっかけとして「環境ホルモン」が大きな問題となった。しかし50年前の精子の数については客観的なデータがなく、1970年以降の調査では変化は見られない。エストロゲンは小麦やキャベツにも農薬よりはるかに多量に含まれており、それが有害なら、ほとんどの穀物や野菜を禁止しなければならない。
嘘ではないが、誇張されている問題も多い。1985年、南極にオゾン・ホールが発見され、紫外線の増加によって皮膚ガンが増えるとして、オゾン層破壊の原因とされるフロン(CFC)は全面禁止された。だがオゾン層が完全に破壊されたとしても、紫外線の量は北緯35度の地域で平均6%増えるだけで、これは東京と福岡の違いぐらいだ。先進国で皮膚ガンが増えている最大の原因は、海水浴と日光浴である。
現代文明は「維持不可能」ではない
かつて環境問題といえば、大気汚染や水質汚染などの公害問題だったが、1990年代から主役になってきたのが地球温暖化問題である。これは「供給側」の要因も大きい。先進国では、公害対策によって古典的な環境問題は終わり、環境保護の仕事は減ってゆくだろう。ところが政府予算の中で環境対策の占める比重は一貫して上がっており、日本では環境庁は行政改革の中で唯一、省に昇格した。こうした「需給ギャップ」を埋めるためには、新しい問題を作り出すしかないのである。
メディア(特にテレビ)にとっても、地球環境問題は「絵になる」素材だ。環境保護に反対する人はいないので政治的に安全で、ヒューマニズムに訴えて「物質文明」を批判するというストーリーが立てやすい。
しかし地球環境はグローバルな問題だから、経済問題が解決して環境問題が気になる先進国は二酸化炭素(CO_2)の規制を要求するが、途上国では環境よりも経済成長のほうが大事だ。それに今までCO_2を排出してきたのは先進国ではないか――というわけで、もっとも環境汚染の深刻な途上国を除外して先進国だけが2012年までに温室効果ガスを5.2%削減するという「京都議定書」ができてしまった。
地球温暖化は、主として途上国の問題である。国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第3次報告書も認めるように、高緯度地域では農業生産を増やし、極地にも人が住めるようになるので、温暖化は先進国にとってはメリットも多い。海面が数十cm上がる程度は堤防で解決でき、そのコストは全世界で数百億ドルである。しかし熱帯の途上国では、気温が上がると住みにくくなり、堤防を作る経済力もない。
つまり京都議定書は、結果としては先進国が途上国の温室効果ガス排出のコストを負担するという開発援助の一種なのである。ところが、この「間接援助」はきわめて効率が悪い。京都議定書を実施するコストは最悪の場合、先進国全体で1兆ドルにのぼると推定される。これは全世界の開発援助の総額の20年分だが、その効果は海面を数cm下げるだけだ。途上国にとっては、食糧や医療のほうがはるかに切実な問題である。温暖化対策は、健康の気になる金持ちが毎日の食事にも事欠くホームレスに健康器具をプレゼントするようなものだ。
地球温暖化を論じる人々は、壮大な「地球文明論」を語るのが好きらしい。たとえば佐和隆光氏(京都大学教授)は、「地球温暖化問題が発信する『大量廃棄を伴う工業文明は持続不可能である』との警告に、私たちは真摯に耳を傾けねばなるまい」として「今日ある文明の改編」を主張する(*4)。これは文明論以前に、事実認識として誤りである。これまで見たように、工業文明の発達した先進国ほど環境は改善しており、現在の経済システムは持続可能である。
もちろん環境が改善されているということは、現状のままでよいということを意味しない。必要なのは内容空疎な文明論ではなく、政策の費用対効果を客観的に評価して優先順位をつけることである。たとえば京都議定書の1/5のコストで、全世界に衛生的な水を供給して毎年200万人の命を救うことができる、とロンボルグ氏は論じている。
環境問題の中でも、温暖化より深刻な問題は多い。たとえば途上国では、焼畑などの「略奪農業」によって大規模な森林破壊が行われ、すでに熱帯雨林の20%は消滅した。このまま破壊が続くと、熱帯が砂漠化するばかりでなく、熱帯雨林にある地球上の生物種の半分が絶滅の危険にさらされる。森林破壊の最大の原因は貧困であり、先進国がナチュラル・トラストのような方法で経済的に支援する必要があろう。
ラヴロック氏のあと、文化人類学者レヴィ=ストロース氏にインタビューしたとき、彼は「熱帯雨林とともにわれわれが失うのは快適な環境ではなく、生命の謎です。熱帯雨林という地球上で最大の謎が解明されないまま失われてゆくことが最大の損失なのです」と語った。生命の中には、まだ人間が学ぶべき「知性」が無限に残されている。遺伝子工学と呼ばれるものは、自然界にある遺伝子を解読し、組み替える技術にすぎない。互いに独立に生きる植物やバクテリアがどのようにして地球の平衡を維持しているのかもよくわからない。
レヴィ=ストロース氏は、「地球を守る」というエコロジストの発想こそ、人間が自然を征服し改造する近代西洋文明の傲慢の典型だと指摘した。問題は、人間が地球を守ることではなく、そこから学ぶことである。生物の遺伝子は、絶滅したら二度と作り出すことのできない「歴史的遺産」である。それを守るのは、地球のためでも持続可能性のためでもなく、人間にとって必要な知的なコモンズ(共有地)を残すためなのである。
*1 『ヘーゲルの「法」哲学』(青土社)264ページ。ガイア仮説とは、地球の大気に化学的に不安定な酸素が20%も含まれる原因を光合成などの生物の活動に求め、地球全体が一定の環境を維持する「生きたシステム」だとするもの。