栄村は前号で紹介した通り、長野県の最北端に位置し、東西19.1キロメートル、南北33.7キロメートル。南部に苗場山など2000メートル級の山岳がつらなり、92.8%を山林原野が占める山村。平地は少なく山すそを切り開いた棚田で稲作。年間積雪は130日から160日という日本有数の豪雪地帯で人口は2,203人、65歳以上高齢者が45.6%(24年)を占めています。
農家人口は平成17年度調査で2,160人といいますから村民は全員農家と言ってよい。しかし事業所分類によると農林漁業は6事業所しかない。事業所で多いのは卸・小売・飲食が64事業所、サービス業68事業所、これに建設業26が続く。飲食、サービス業が多いのは秘境で有名な秋山郷や栄村の風景を見に來村する観光客が多いから。
千曲川沿線は年間9万3千人が訪れ、秘境・秋山郷には2万6千人が訪れる。しかし観光客数は年々減少。経営耕作地も減少している。
その中でいかに村民が元気に生涯を栄村で過ごすか。その理念をあらわしたのが栄村民憲章 その村民憲章をはじめに紹介します。
その村民憲章をはじめに紹介します。
栄村民憲章
一、自然を愛し、環境を整え、美しい村を作ります。
二、生産をすすめ、豊かな、くらしよい村をつくります。
三、子どもをはぐくみ、おとしよりを敬う、温かい村をつくります。
四、体をきたえ、大自然の中で躍動する、活力ある村をつくります。
五、心のふれ合いを深め、礼儀に厚い、連帯感にみちた村をつくります。
六、教育を尊び、知識を求め、創意にあふれた村をつくります。
こうした憲章を持つ栄村。独自事業を展開した村づくりを紹介します。次回
 栄村の村づくりを話してくれた鈴木敏彦村議
栄村の村づくりを話してくれた鈴木敏彦村議
農家人口は平成17年度調査で2,160人といいますから村民は全員農家と言ってよい。しかし事業所分類によると農林漁業は6事業所しかない。事業所で多いのは卸・小売・飲食が64事業所、サービス業68事業所、これに建設業26が続く。飲食、サービス業が多いのは秘境で有名な秋山郷や栄村の風景を見に來村する観光客が多いから。
千曲川沿線は年間9万3千人が訪れ、秘境・秋山郷には2万6千人が訪れる。しかし観光客数は年々減少。経営耕作地も減少している。
その中でいかに村民が元気に生涯を栄村で過ごすか。その理念をあらわしたのが栄村民憲章

栄村民憲章
一、自然を愛し、環境を整え、美しい村を作ります。
二、生産をすすめ、豊かな、くらしよい村をつくります。
三、子どもをはぐくみ、おとしよりを敬う、温かい村をつくります。
四、体をきたえ、大自然の中で躍動する、活力ある村をつくります。
五、心のふれ合いを深め、礼儀に厚い、連帯感にみちた村をつくります。
六、教育を尊び、知識を求め、創意にあふれた村をつくります。
こうした憲章を持つ栄村。独自事業を展開した村づくりを紹介します。次回




















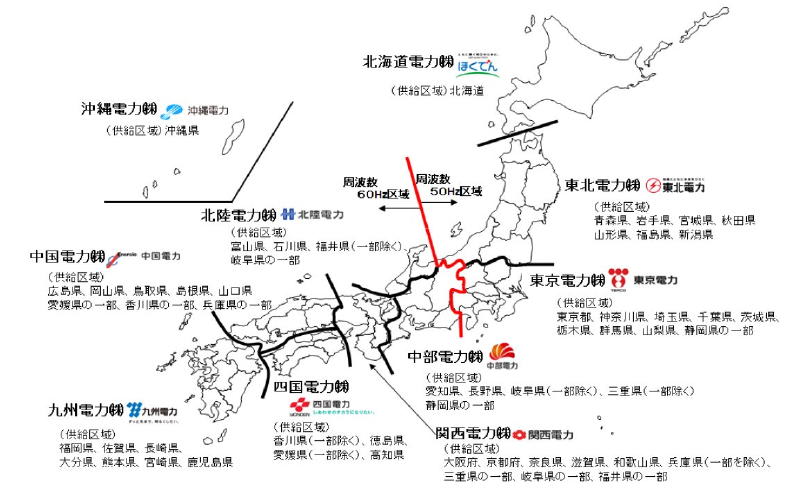
 (表「コスト等検討委員会」)
(表「コスト等検討委員会」)