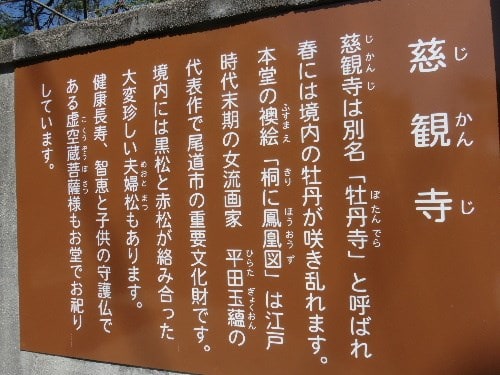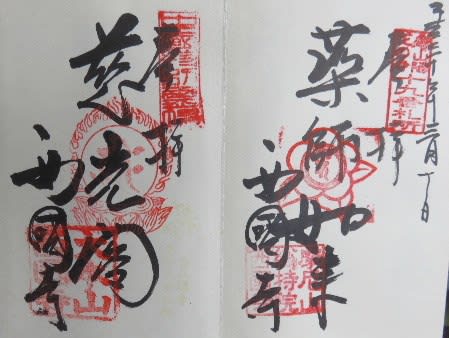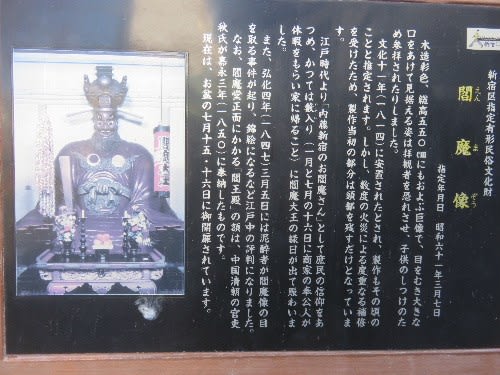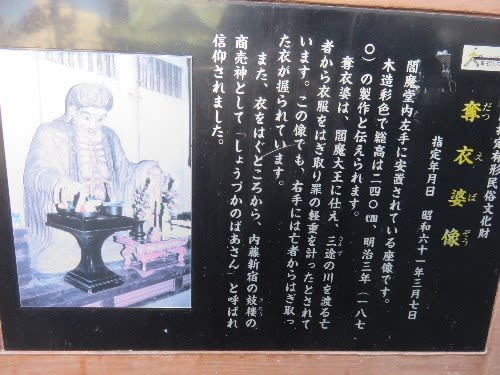慈観寺の隣には妙宣寺と艮神社がありますが、
早く千光寺に参拝したかったので後回しにして、
千光寺山ロープウェイ乗り場へ。
艮神社の前に乗り場があります。
所在地:広島県尾道市東土堂町20-1
料金:(片道)大人320円、小児160円(往復)大人500円、小児250円

片道だけロープウェイを利用。
帰りは歩きという観光客が多いようですね。

天寧寺の三重塔が見えます。
後で行くので楽しみ。

艮神社の本殿が真下に。
ドローンならともかく、
本殿の上を自分の目で見れるのは貴重です。


ゆっくりロープウェイは頂上へ近づく。


千光寺の象徴である玉の岩が見えてきました。
この角度から見るのがロープウェイならではですね。(^^
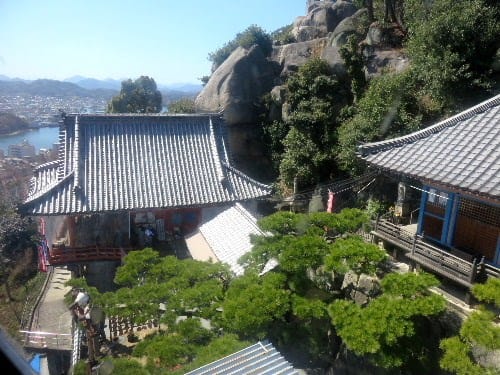
千光寺の本堂を通り過ぎていきます。

鎖場があるくさり山という巨石群が見えます。
鎖場を登りたい気持ちはあるが、
実は一週間前に酷い寝違いを起こしてしまい、
ついには右肩まで痛めてしまったんですよね。
まだまだ完調では無いので回避した方が無難だな。

よくこんな場所に建てるよね。
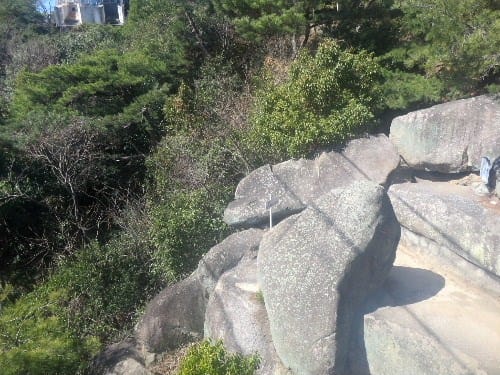
文学のこみちの岩場のようです。

山頂駅に到着。
楽チンでいいわ。(^^
頂上は千光寺公園となっており、
展望台や売店があり観光客が多い。

確かに素晴らしい風景です。
尾道に来たなら必ず訪れなければならないと断言する。
とはいえ、目的が千光寺参拝なので、
公園は2分程で退散し、文学のこみちを歩き千光寺へ。
文学のこみちは道沿いの自然の巨石に尾道ゆかりの作家・詩人等、
文化人らによる作品を刻んだ25基の石碑があり、
それらを見ながら進むと千光寺に行けます。
ただ、千光寺までの案内板はあるけど、
この先を進んでいいのかイマイチよく分からない。
このあたりはもうちょっと改善して欲しい。
【正岡子規】


【十返舎一九】


【文学のこみち】


このような巨石の間をくぐる所もあります。
ロープウェイが近いです。
【志賀直哉】

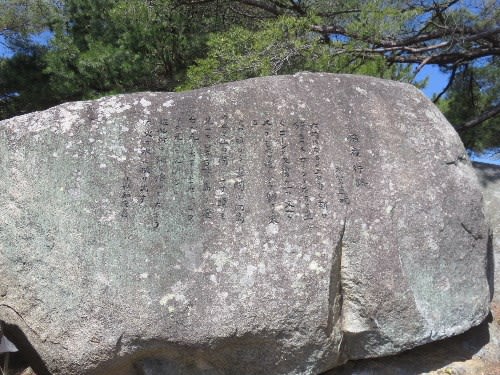
とりあえず有名どころはパシャリ。
あと松尾芭蕉があるようですが見つけられず。
【尾道水道】

休憩がてら景色を楽しむ。(^^
【大明神】

勝七大明神等三つの大明神が祀られていました。
【石段】

どうやら千光寺に着いたようです。
続きは後ほど。
早く千光寺に参拝したかったので後回しにして、
千光寺山ロープウェイ乗り場へ。
艮神社の前に乗り場があります。
所在地:広島県尾道市東土堂町20-1
料金:(片道)大人320円、小児160円(往復)大人500円、小児250円

片道だけロープウェイを利用。
帰りは歩きという観光客が多いようですね。

天寧寺の三重塔が見えます。
後で行くので楽しみ。

艮神社の本殿が真下に。
ドローンならともかく、
本殿の上を自分の目で見れるのは貴重です。


ゆっくりロープウェイは頂上へ近づく。


千光寺の象徴である玉の岩が見えてきました。
この角度から見るのがロープウェイならではですね。(^^
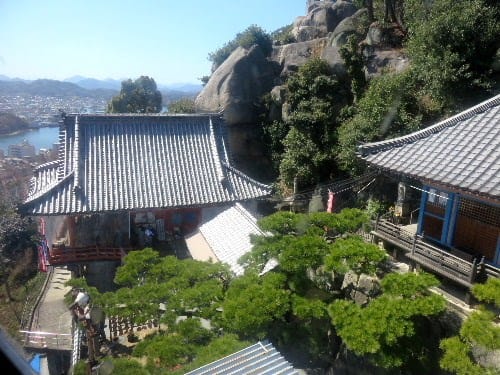
千光寺の本堂を通り過ぎていきます。

鎖場があるくさり山という巨石群が見えます。
鎖場を登りたい気持ちはあるが、
実は一週間前に酷い寝違いを起こしてしまい、
ついには右肩まで痛めてしまったんですよね。
まだまだ完調では無いので回避した方が無難だな。

よくこんな場所に建てるよね。
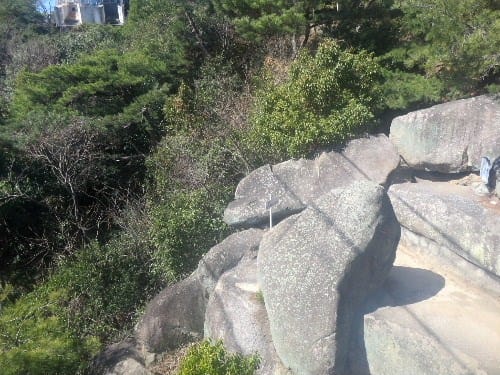
文学のこみちの岩場のようです。

山頂駅に到着。
楽チンでいいわ。(^^
頂上は千光寺公園となっており、
展望台や売店があり観光客が多い。

確かに素晴らしい風景です。
尾道に来たなら必ず訪れなければならないと断言する。
とはいえ、目的が千光寺参拝なので、
公園は2分程で退散し、文学のこみちを歩き千光寺へ。
文学のこみちは道沿いの自然の巨石に尾道ゆかりの作家・詩人等、
文化人らによる作品を刻んだ25基の石碑があり、
それらを見ながら進むと千光寺に行けます。
ただ、千光寺までの案内板はあるけど、
この先を進んでいいのかイマイチよく分からない。
このあたりはもうちょっと改善して欲しい。
【正岡子規】


【十返舎一九】


【文学のこみち】


このような巨石の間をくぐる所もあります。
ロープウェイが近いです。
【志賀直哉】

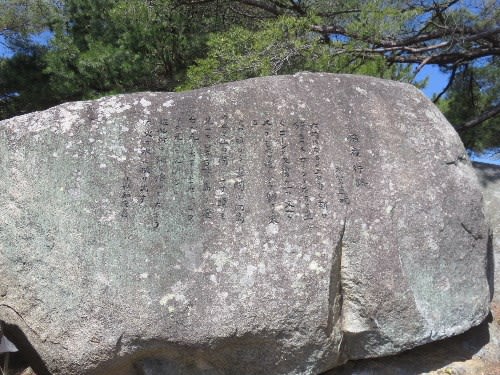
とりあえず有名どころはパシャリ。
あと松尾芭蕉があるようですが見つけられず。
【尾道水道】

休憩がてら景色を楽しむ。(^^
【大明神】

勝七大明神等三つの大明神が祀られていました。
【石段】

どうやら千光寺に着いたようです。
続きは後ほど。