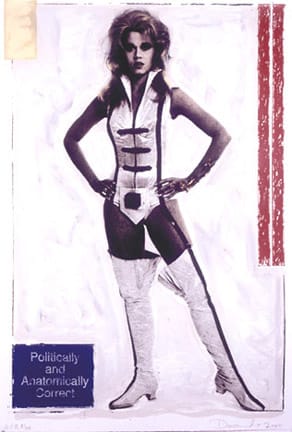持っているのに持っていない。
永遠にそれを持つことは出来ない。
物は生き続け、
人はその前に無力だ。
物は問う。人よ、私はあなたの物なのか。
否。
物よ、あなたは自由だ。
私ごときが所有できるものではない。
私はあなたの永遠を瞬時でも感じたくて、
あなたを腕に囲っているだけだ。
持っている錯覚にしばし満たされているだけだ。
だから、あなたは限りなく自由だ。
(画像:瓢池園。ノリタケがnoritakeとなる前のノリタケ。その美しさは大倉へと受け継がれたか。)あんまり別嬪に撮れておりません。上手に撮れたら差し替え予定です。
余談。今日よりお仕事。「I have」の雑感はいつかまた。
永遠にそれを持つことは出来ない。
物は生き続け、
人はその前に無力だ。
物は問う。人よ、私はあなたの物なのか。
否。
物よ、あなたは自由だ。
私ごときが所有できるものではない。
私はあなたの永遠を瞬時でも感じたくて、
あなたを腕に囲っているだけだ。
持っている錯覚にしばし満たされているだけだ。
だから、あなたは限りなく自由だ。
(画像:瓢池園。ノリタケがnoritakeとなる前のノリタケ。その美しさは大倉へと受け継がれたか。)あんまり別嬪に撮れておりません。上手に撮れたら差し替え予定です。
余談。今日よりお仕事。「I have」の雑感はいつかまた。