厚生労働省が全国のハローワークに寄せられた求人票に関する苦情約9000件を調べたところ、約4割で実際の労働条件が記載内容と異なっていたことがわかった。
(中略)
その結果、「土日は休みと書いてあったのに出勤させられた」「賃金が20万円と書かれていたのに、2万円低かった」など、3815件(41%)で求人票の内容と実態が異なっていた。求人票には「正社員募集」と書かれていたのに、契約社員として雇われたケースもあったという。
まぁ、ハローワークが詐欺の温床なのは随分と昔からの話です。ハローワークは公然と嘘を掲載し、その嘘に公的機関として折り紙を付け、職を失って困窮している人を欺いては陥れる悪の組織ですから。読売報道の文面上は「ウソ」4割と緩いことが書いてありますけれど、実際に内訳を見るとどうでしょうか。「企業側の説明不足」だって要は求人票に誤解させるようなことを書いて求職者を罠にかけたということですし、「求職者側の要望で事実確認できず」というのも結局は「求職者側の泣き寝入り」ですよね。そもそもが苦情に発展しているケースが氷山の一角であろうとも推測されるところ、ハローワークのせいで酷い目に遭った人は山のようにいるのでしょう。

ハローワークが掲載する嘘偽りにまみれた求人広告によってもたらされた被害は、ハローワーク側にもしかるべく責任が負わされるべきではないかと思います。実際とは異なる労働条件の仕事を斡旋されたことによって求職者は当然ながら不利益を被っているわけです。ハローワークは求人を出す側の不正には目こぼしを続けるばかり、そのせいで泣きを見る求職者が相次いでもハローワーク側には何のお咎めもナシですけれど、この辺は流石にバランスを欠いているのではないでしょうか。ハローワークで紹介された就職先で金銭を騙し取られた、ハローワークで紹介された先が詐欺グループで、ハローワークが公認する職場で働いていただけなのに逮捕されたなんてケースすらあります。あまりにも悪質なハローワークには、責任者の刑事訴追や営業停止処分などが下されるべきです。
「英語」は本当に必要なのか 早期教育化の流れの中で大学関係者から漏れる「英語不要論」(産経新聞)
一部の教育関係者からは、「英語教育は必要」としながらも、差し迫った課題ではないとの意見も聞かれた。
全国公立短期大学協会副会長の中村慶久委員も英語教育の改革を「えらく遠い話のように感じる」と話した。短大教育が医療や福祉、保育などの分野の比重を高める中で、英語教育の推進に対する教育者側の感覚的な違和感ともいえる。
(中略)
12月2日の文科省の有識者会議では「(英語教育の)必然性はない」と述べた委員らに対し、財界側から出席した日本経済団体連合会(経団連)の教育問題委員会企画部会長の三宅龍哉委員が「ビジネスにおいては必然性は高い。社員を海外駐在などへ送り出す際、(企業が)語学教育をせざるを得ない現状だ」と正反対の意見を述べた。
こうした実用的な英語力の必要性は、昭和30年に当時の日本経営者団体連盟(日経連、現経団連)が「会話力を身につける」などと要望を出すなど、これまで幾度も繰り返されてきている。なぜ、英語力は身につかないのか。
……で、今度は産経新聞の報道ですが、英語教育を巡って意見が分かれているようです。実績から鑑みれば財界筋の要求することは常に誤っていましたので、この逆張りに徹しておけば間違いはない、性急な英語教育の絶対視は避けておくのが無難ではないかと考えられます。経団連の言うことの反対のことをやれば、だいたいは良い結果が得られるものです。
なお引用元では「英語をめぐる中高生の意識」と称して就学・高校生相手のアンケート結果を掲載しています。う~ん、中高生ではなく実際に会社で働いている人々にこそ「仕事で英語を使う機会があったか」を聞くべきではないでしょうか。しばしば会社を危機的状況に陥らせる実情を理解できない経営者達に尋ねれば、挙って「英語教育は必要」と断言するのかも知れません。しかし、実際に第一線で働いている人々にとって英語はどれだけ必要なものなのか、そこは理解されなければならないはずです。
この辺もまた求人票詐欺と似たようなものがあって、就職活動の時点では必須レベルになりつつある英会話能力も、実際に入社した後は活かす機会がないことが普通なのではないでしょうか。求職者に英会話能力を要求しておきながら、その能力を発揮する場所を与えない、それもまたタチの悪い話ですよね。でも後ろ半分は仕方がないとも思います、国内企業で働く中で英語力が必要になる場合なんて、本当にレアケースですから。ほんの一握り、英語に堪能な人がいれば十分に足りてしまうのが現状でしょう。そんなに英語の上手い人が多くても、それを使う場面は決して多くないのですから。
ただ畑違いの異動を好む日本的人事において、人事権を持つ人々から見れば「英語力は必要」になってしまうものなのかも知れません。いかに英語力を必要とする部署が少なかろうとも、社内に英語の堪能な人材が少数であれば、その少数者を海外向けの部門に配置せざるを得なくなってしまいます。それは適材適所と言えるかも知れませんが、日本的人事ではないでしょう。日本の人事たるもの、上の人間の意のままであることこそが重要です。○○は英語ができるから海外事業部、△△は英語がダメだから国内向けの部署限定――そういう縛りが人事に加わることを日本の経営者は嫌うわけです。会社側にとって望ましいのは「誰でも海外に飛ばせる」状況であること、そのためには「誰もが英会話に堪能であること」が必須となります。
私の昔の勤務先の上司は海外志向が強く、もちろん英語力に自信ニキ、毎年のように海外部への異動願いを提出していたそうですが、10年以上も国内の企業グループ相手の営業部門に縛り付けられていました。一方で望みもしないのに海外部へ異動させられる人もいる、新卒で正社員として採用されるのも英会話ができる人ばかり、「だったら俺を海外に行かせてくれれば良いのに、なぁ?」と言われたものです。しかし会社は海外志向の強い私の上司の望みを叶えることはなく、会社側が望んだ人だけを英語力の必要な部署に付けていきました。日本の人事とは、そういうものなのでしょう。やれやれ、日本の会社が求める人材になるのは本当に大変だと思います。











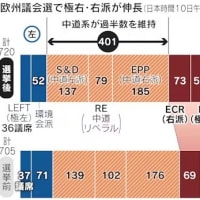


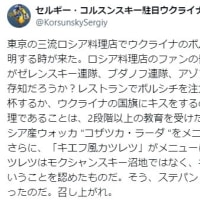

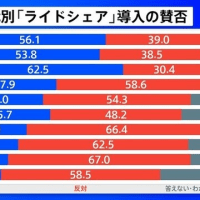
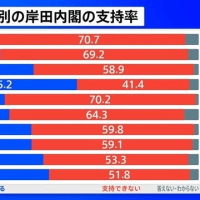
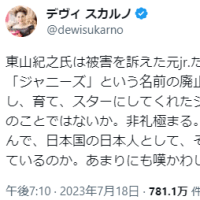
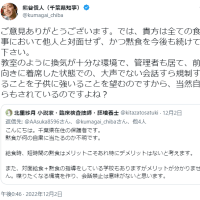
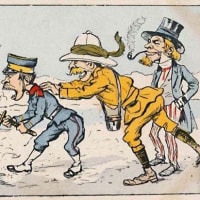






ハローワークですか。私も10代の頃に苦い思いをさせられました。
『スタジオ○×』とかいう写真館の求人だったのですが、面接では私が高校を一度辞めている点を散々責め立てられた挙句、なぜか親類が経営すると見られる印刷工場を見学して来いと言われ、そちらに行かされたことがあります。
偶然にも工場の方が自宅から近かったので言う通りにしましたが、結局不採用でした。
それから、あの端末は使い辛いことこの上ないですね。
今はどうだか知りませんが、一昔前の端末は勤務地と業種だけで分類されているので、学歴別や雇用形態別等で検索できないんですよ。
私のような低学歴の人間は仕事など選んでられませんから、求人(と言っても非正規が多く、ロクなのがありませんが)が多くても却って困るのです。
利用者の利便性なんて何も考えてくれないんですから(呆)
ハローワークの端末、使いづらいですよねぇ。それでも利用者が殺到しているから、管理する側は好評だとでも勘違いしているのでしょうか。まぁ会社の端末も悲惨なケースが多いので、どこも購入を決める人のセンスは似たようなものなのかも知れませんが……
まあ、これらの企業はゼンショーやワタミのように、労働力をなるべく安く買い叩き続けている上に、昇給が一切ないところばかりですから、労働条件のより良い職場に行くのも無理はないと思いますね。