そこに集団ヒステリーがくわわると、事態は悪化の一途をたどった――その悪質な例としてあげられるのが、合衆国におけるマッカーシズム現象である。わたしのようにマッカーシズムが猛威をふるった1950年代に中東から合衆国にやってきて少年時代をすごした人間には、その後、このマッカーシズムから妙に陰険な知識人層が生まれてきたという思いが強いし、彼らは今日にいたるまで、内憂外患に対して危機感をあおりたいだけあおっている。この種の現象はすべて、自家中毒的に生み出された辟易する危機意識にもとづくものであり、それはまた、事故批判的分析はいうまでもなく合理的分析すらも踏みにじるような、無知蒙昧なマニ教的二元論の勝利でもあった。
――E.サイード『知識人とは何か』
かの週刊金曜日が掲げた「原発文化人」のリストを見たとき、私の脳裏をかすめたのはマッカーシズムと赤狩りでした。そうでなくとも選挙報道などでは、○○は原発推進派、○○は原発反対派などと明確な色分けが好まれる昨今です。元より我々の社会では曖昧さは好まれず(ゆえに「日本人は曖昧だからダメだ」と常に自らを戒め続けているのでしょう)、白黒はっきり付けたがる、二元論的なものが好まれるところがあったように思いますが、その傾向は強まるばかりです(例えば「直ちに影響がない」ものを「直ちに影響がない」と説明するのは正しいことですが、しかるに日本で求められているのは影響があるのか無いのか、その明白な二元論なのです)。一方で過熱する報道やネット世論とは裏腹に発端となった原発事故そのものは意外に落ち着いており、少なくとも事故前までは反原発側の主張に一定の信頼を置いていた私にとっては「聞かされていたほど酷くはないな」と安堵すると共に拍子抜けした思いを感じる状況が続いているわけで、崩壊しているのは原発危険神話ではないかという気がします。「放射能で首都圏消滅!」みたいなことすら聞かされてきたものですが、あれはきっと、ずっとウソだったのでしょう。
社会主義革命や、それに続く社会主義政権、社会主義国の誕生には少なからぬ実例がありますが、それが社会主義の進展に貢献したかどうかは甚だ怪しいところです。果たして社会主義国は社会主義を実現させたのでしょうか? 今となっては社会主義政権の大多数が崩壊したり、社会主義を事実上放棄している国も多いわけです。社会主義もしくは共産主義の実現にとって、相次いだ社会主義革命と社会主義国の誕生はプラスだったのか、それともマイナスだったのか、その辺を省みることは何をなすべきか、あるいは何をなすべきでないかを考える上で一つのヒントにはなるでしょう。そもそもマルクスは資本主義が発展して資本が蓄積した次の段階として共産主義を想定していたはずで、現に裕福な福祉国家でこそ部分的ではあれ共産主義的な理想は実現されているように見えます。しかるに社会主義革命は例外なく、資本の蓄積が「ない」国で起こりました。社会主義を実現させるための要件と、社会主義革命を起こすための条件とは相異なるようです。そして資本の不足する国でこそ革命が起きたのと同様に、電力供給に不足が見込まれるようになった今、日本では脱原発論が盛り上がりを見せているわけです。
それは社会的な必然性から発生したというより、一時の熱狂から生まれた、ある種の「流行」なのかも知れません。政治家でも軽薄なポピュリストほど嬉々としてこの「流行」に加わり始めています。そして流行である以上は、ノリと勢い重視と言いますか、もう何でもありみたいになっているフシもあるわけです。反原発でさえあれば、デマもトンデモも陰謀論も怪文書も何でもあり、原発や東電を罵っておけば嘘も許される、混乱に乗じた差別や風評被害すら「正当な防衛行動」の名の下に容認されてしまう、一方で科学的根拠に沿った話をすれば御用学者と罵られ、あるいは原発文化人、原発推進派に括られてパージされるとあらば、もはや脱原発論は自浄能力を失いカルト化した、かつ空想的社会主義ならぬ空想的脱原発論によって科学的脱原発論は放逐されたとすら言えます。私にはむしろ昨今の状況は、脱原発論の深刻な劣化とエネルギー政策の退行をもたらすものでしかないように思えるのですが。
・・・・・
当然のことながら発電所には寿命がありますから、将来的には原発を含めた既存の発電方式が、より新しく秀でた方式によって置き換えられていくであろうことは普通に想定されます。一方で、これを「今すぐ」やれと迫る人々もいるわけです。あるいは「今すぐ」可能であるかのごとく語る人も。まぁ、安全で安定した電力供給のために最良の手段を探すのではなく、ひたすらに脱原発という「目的」を追い求めるのなら、そういう論調にもなるのでしょう。世間の熱狂が背を押してくれる今こそ、最大の好機に見えているものなのかも知れません。
しかるに、それが簡単かつ短いスパンで実現できるかのように語る人は、往々にして背信するものです。票を集めることは出来ても、有権者との約束を果たすことは出来ない――民主党への政権交代は、それを教えてくれはしなかったでしょうか? 例えば政権交代前に沖縄米軍基地の県外移設に関して、当時の民主党代表だった鳩山がどういう態度を取っていたかを思い出してください。政権交代を果たせば=民主党が政権の座に着けば、それはすぐにでも実現できるかのように語られてはいなかったでしょうか? 結果は言うまでもありません。約束を果たせず、かえって失望を呼ぶばかりでした……
民法改正とか取り調べ可視化とか、あくまで国内レベルの問題であり予算を要しないことであれば政権与党が「本気」でさえあれば容易に実現できたはずですが、一方で米軍基地問題は相手のいる話です。仮に日本政府が本気であったとしても相手国の同意を得ないことにはどうにもならないわけで、ましてや前政権との間の取り決めもあるとなれば話が簡単に進むはずはありません。そうである以上は、難しさを認めた上で地道に進めていくしかないのですが――あたかも簡単に出来ることであるかのごとく有権者に約束し、しかる後に簡単にはできないと判断して投げ出してしまったのが実際のところです。そしてこの例は、単に鳩山の資質の問題として片付けられるべきものではないでしょう。
まぁ、自信満々に「出来る」と言い切れるタイプの方が、どこでも好まれるものなのかも知れません。就職活動だってそうです。「それは難しいですので、善処はしますが結果については保証できかねます」みたいな受け答えは、それが真実であっても許されないですから。加えて「簡単にできる」かのように語れば「現政権は簡単にできるはずのことすらやろうとしない(or前政権は簡単に出来るはずのことをやってこなかった)」として、一層の攻撃を加えられるというものです。逆に難しさを認めてしまえば「現政権がそれを実現できないことにも同情の余地はある」みたいになりかねないですし。ともあれ米軍基地の県外移設は簡単にできることのように語られ、そして約束は見事に裏切られる結果となりました。では流行りの脱原発論はどれほどのものでしょうか? 脱原発が今すぐにでも可能と語る人々が今以上に幅を利かせることがないことを願うほかありませんが、万が一そうなってしまえば到り着く先は鳩山と同じようなものにしかならないように思います。そうして脱原発論は一時の盛り上がりを見せつつも、結局は甚大な混乱を撒き散らし、しわ寄せを受けやすい立場の弱い人を犠牲にするだけで終わるでしょう。難しさを認めた上で地道に取り組んでいくのか、それとも簡単にできると口約束して世間の歓心を買おうとするのか、どちらに意味があるかは冷静に考えて欲しいところです。
・・・・・
顔の見えない無名の有権者達の頭はネット世論程には沸騰していないと思いますが、どこでも媚びる政治家は幅を利かせがちです。お調子者が流行に媚びだして昨今の空想的脱原発論に追従し多数派を構成するとなれば、いったい何が起こるでしょうか。脱原発は「簡単にできる」かのごとく語って票を集めたところで、おとぎ話を実現させることが10年や20年のスパンであっても難しいことは言うまでもありません(結局、電力の純輸入国に逆戻りしたドイツの例を直視すべきです)。有権者への約束は果たされることがないでしょう。そこで空手形を切った政治家が信を失うだけに止まるならば、まだ許せる範囲です。しかるに空疎なイデオロギーのために現実への対策が蔑ろにされ、経済分野で続いたことがエネルギー供給の面でも、住民の生活インフラの面でも起こってしまう可能性があります。
例えば「電力は足りている」という虚妄に沿って、代替手段の実用化を待たずに原発の停止が続けば当然ながら電力不足という危機にさらされることになるわけです(安全で安定した電力供給を重視するなら当然、代替手段の確保が先行しなければならないはずですが、電力は足りているという「設定」によって代替手段の必要性は蔑ろにされてしまうのでしょう。脱原発を加速させるためなら何でも許されるようですから)。まぁ震災後に評価が高まったというソフトバンクのケースを鑑みれば、本業での責任を果たせずとも(被災地で電話が繋がらなくとも/電力供給に不足を生じさせても)美談さえ構築できれば世間は許すものなのかも知れません。もっとも電力会社が本業(必要なときに必要な電力を供給すること=インフラを支えること)に責任を持っているのであれば、そのような事態を避けるべく全力を尽くすでしょう。ただ、その足を行政や世論が引っ張るだけのことです。
原子力の時代終了ではなく、復活させるべき時 FT社説(フィナンシャル・タイムズ)
不幸なことに、今の原子力発電のほとんどの設備は古いままだ。なぜかというと1979年のスリーマイル島事故に続いたチェルノブイリ事故のせいで、新規原子炉の承認と建設が何年も凍結されたからだ。世界の原発施設の相当数は、20世紀半ばの防衛産業で生まれた設計に基づき20年以上前に建設されたものだ。
アレバの欧州加圧水型炉(EPR)やウェスティングハウスの軽水炉AP1000など、現在の「第3世代」原子炉は、受動冷却システムなどの安全装置を備えた設計になっている。こうした装置があれば、津波の後に福島第一原発を破壊した深刻な温度上昇をほぼ確実に防げたはずだ。
原子力発電に変わる代替手段が短いスパンで実用化されずとも、それを誰かの利権や陰謀のせいにすることで政治家なり空想的脱原発論なりが地位を守りきる可能性は十分にあります。しかるに原発の新造には枷が掛けられる一方で新たな発電手段が現実のものとなるまでは長い月日を要することでしょう。こうした苦境の中でも電力会社が責任を果たそうとすれば、現行の老朽化した旧世代型の原発を延々と引っ張り続けることにもなりかねません。旧世代型の原発を引っ張り続けざるを得ないことで、カテゴリこそ同じ原発であろうとも設備が新しければ、あるいは設計が新しいものであれば防げたはずのリスクを今後とも抱え込むことになるわけです。加えて情緒的な理由から(「不安がある」「理解が得られない」等々)点検後の運転再開を阻まれる原発も増える中で電力会社が責任を果たそうとすれば、必然的に点検を最小限に止めようという方向にも動かざるを得なくなるでしょう。
結局のところ問われるのは、安全で安定した電力供給のために「その時点で可能なものから」最善の発電手段を選ぶのか、あるいは何が何でも脱原発なのか、その空想的脱原発論によって生じる犠牲を「なかったこと」にすべく代替手段が実現されないのを利権なり陰謀なりのせいにして自説の正当化を図るのか、ということです。前者の立場に立つのであれば、電力供給に不足が生じようとする時期に脱原発論が急進化するのは、はっきり言ってあり得ない話です(上でも触れましたが、まず原発に代わる発電手段の確保が先に来なければなりません)。しかるに火力発電所を倍増させようなんて話はさっぱり出てきませんし、燃料確保の面で不安視されてもいる、加えて「クリーン」なイメージのある発電手段の中では最も実用化されている風力発電などでも課題は山積みで、不安定性や立地の問題もさることながら、建設時には想定していなかった低周波被害の訴えも相次いでいます(この辺も、その筋の人に言わせれば原発推進派の陰謀のようですが! 取りあえず「原発の近くに住んでみろ」とか言って得意になっている連中には風力発電機の近くに住んでみることをお勧めしたいですね)。それでも原子力に代わるエネルギーへの転換の「難しさ」を認めず、「簡単にできる」かの如き幻想に沿って非現実的な政策を振りかざして現実を蔑ろにするのなら、それは何も解決できないばかりか、原発事故などの比ではない甚大な被害を我々の社会にもたらすことでしょう。それと同時に空想的脱原発論が萎んだとしても、全ては後の祭りです。











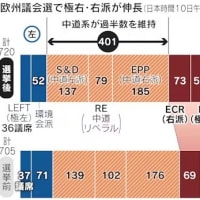


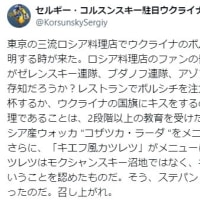

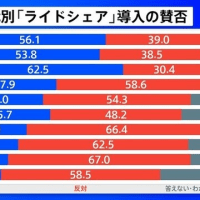
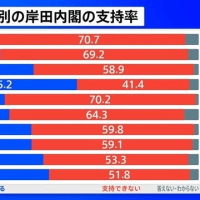
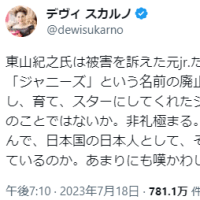
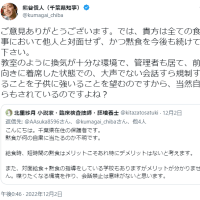
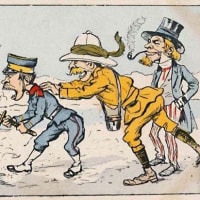






ところでそんな無知の私に教えていいただきたいのですが
あなたさまは革命についてどう考えますか?
というのも僕は今のこの国に絶望していて政府の仕組みそのものをがらりと変えないといけないところにあると思ってます。
ですが国を内部から変えれる人は仕組みの中の要人であり仕組みを変えようとしないとしない。
それなら法に則った形、具体的には国民単位での抗議運動を行えばいいのでは?と考えているのです。
これだけ国民同士の連携がとりやすい世の中で何故皆そうしないかとあなたが日本をよくするために考える理想論を聞かせていただけたらうれしいです。
まず、国のどの段階に対して絶望しているかにもよるのではないでしょうか。私が見る限り、政府の仕組みと呼ぶべきものは小泉純一郎登場以来、(悪い方に)大きく変えられたように思います(その方向性は民主党政権にも忠実に引き継がれています)。むしろ変わらないことではなく、その時々の社会が「敵」として認定したものに対する憎悪によって(族議員であったり、官僚であったり、原発だったり)振り回され、その結果に責任を負おうとしない、こういう部分を改める必要があると考えています。