ちょっと映画や本の紹介が続いているが、前に予告してある「高校授業料無償化問題」を少しまとめて論ずることにする。自民党はいわゆる「4K」と言って、子ども手当、高速道路無料化、農家の戸別所得補償制度と並び、高校授業料無償化制度をバラマキと批判している。本日まとまったとされる「民自公3党合意」では、「政策効果を検証して、12年度予算で必要な見直しを検討する」となったらしい。しかし、この政策は今後も堅持されなくてはならない、と強く思っている。
勘違いしている人(あるいは「無知」な人)が多いのだが、他の3件と高校授業料無償化はその本質が全く違う。子ども手当(あるいは児童手当)をどういう制度にするかは、純粋に制度設計の問題である。(しかし、今回の合意が果たしてよいものかどうかは疑問も多いが。)高速道路無料化も戸別所得補償制度も同じで、日本にとってより良い制度を見つけていくための検討はして当然である。津波被害と原発事故という国難というべき時期に高速道路無料化は延期になっても仕方ない。(ただし、この政策をとんでもないバラマキと思ってる人がいるが、高速道路というものはいずれ建設費の償還が終わったら無料にするという約束で作ったものなのである。デーブ・スペクターだったかな、アメリカで日本語の勉強に歌を聞きまくり、「中央フリーウェイ」と言ってたのに、日本で実際に通ったらやけに高くて詐欺かと思ったという話を聞いたことがあるけど、高速道路無料化自体は至極まともな発想なのである。)
前置きが長くなったけど、では高校授業料無償化の本質とは何か、と言えばそれは「人権問題」なのである。1948年12月8日、国際連合は世界人権宣言を採択した。宣言は言いっ放しだから、それを何とか規制力のあるルール化することが目指され、1966年12月に国連で採択されたのが、国際人権規約である。社会権を定めたA規約と自由権を定めたB規約に分かれる。日本は1979年にいたってABともに批准した。(なお、A規約には第一選択議定書=個人通報制度と第二選択議定書=死刑廃止が後から成立したが、日本はご承知の通り、どちらも批准していない。)
さて、その国際人権規約の中に、(小学校はもちろん無償であり)中学や高校もだんだんと無料にするのだと明確に書いてある。外務省訳を一応あげておくと「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」
中等教育というのは中学と高校のことで、日本は中学は無償だが、高校は授業料があった。では、1979年にこの規約になぜ入れたのか。実は、日本も仲間に入るけど、三つだけ特例を認めてねという荒業を使ったのである。他にも解釈の問題も二つ、注文を付けている。
その三つとは、「中・高等教育の無償化」「労働者への休日の報酬の支払い」「ストライキ権の保障」だった。最後のスト権というのは、もちろん民間労働者にはあるわけだが、「公務員にスト権がない」ことが国際水準からすれば人権無視のとんでもない事態なのである。
高校授業料を取っていた国は、だから世界にほとんどない。国によっては大学まで無償である。これは国民の教育権を保障する人権上の措置だと、どの国も判っているからだ。ウィキペディアによれば、この条項を保留扱いしていたのは、日本とマダガスカルだけだという。民主党政権になり、高校が無償になり、国連にこの保留通知の撤回を行った。やっと世界の常識が日本に通じたのである。どこがバラマキなのか、そういうことを言う人の常識を疑う。
ところで、実際は各地方で貧困家庭には学費減免措置があった。みんなタダになれば、金持ちの家庭はその授業料分のお金で塾や予備校に行けるから、かえって教育格差を広げるという人もいる。教科書代や制服代や修学旅行費はタダにはならない以上、家庭の負担はやはり大きくて、授業料だけの問題ではないという人もいる。そいう議論の一つ一つはもっともなのだが、本質を外している。金持ちだろうが、貧乏だろうが、それは子供に選べない。高校や高校にあたる専門学校等の授業料そのものをなくすというのは、社会の側で若い世代に与えることができるチャンスであって、それを維持するのは当然だ。(教科書や修学旅行への援助制度もあるので、他の問題は別建てで考えればいいことだ。)
ところで、この問題を調べていて、今のことに気付いたのは数年前である。僕でさえ、「人権」という授業を作って、国際人権規約なんてものをちゃんと調べて知った。多分多くの先生は、国際人権規約で高校授業料無償化と公務員のスト権が定められているが、日本政府がそれはやらないよと通知していたんだということを知らない人が多いと思う。自分の権利を侵害されていて、それで教育を行っていたのか。このことは、もっともっと知られなくてはならない。教育と労働に関して、日本の水準は国際的に見て低いということを。
「キューポラのある街」という映画がある。1962年。伝説の名匠浦山桐郎監督のデビュー作。17歳の吉永小百合が主演女優賞を取った。早船ちよの児童文学の映画化。キューポラとは鉄の溶解炉で、鋳物の街として知られた埼玉県川口市を舞台にした傑作である。「北朝鮮帰国問題」も重要なテーマになっており、貴重な場面も多い。さて、そんなことではなく、中学生の吉永の父、東野英治郎が失職する。学力はあるが経済的に全日制高校へ行けなさそうになり、悩む。その時に担任の先生役の加藤武が諄々と説く。働きながら定時制高校へ行ってもいいのだ。通信制高校というのもあるのだ。人間は一生ちゃんと勉強しなければいけなんだ。ここでくじけてはダメだ、と。吉永小百合は工場で働きながら夜は定時制高校で学ぶ女子工員たちの見学に行く。そのような感動的なシーンがあるのだが、その場面を見ていて、日本の庶民にとって子供をなんとか高校までは出してやりたいということがどんなに大変なことだったかが痛切に伝わってきたのである。本当は日本がまだまだ貧しかった60年代に、少なくとも高度成長を達成した70年代にこの政策が実現できていたらどんなに良かったろうにと強く思う。
勘違いしている人(あるいは「無知」な人)が多いのだが、他の3件と高校授業料無償化はその本質が全く違う。子ども手当(あるいは児童手当)をどういう制度にするかは、純粋に制度設計の問題である。(しかし、今回の合意が果たしてよいものかどうかは疑問も多いが。)高速道路無料化も戸別所得補償制度も同じで、日本にとってより良い制度を見つけていくための検討はして当然である。津波被害と原発事故という国難というべき時期に高速道路無料化は延期になっても仕方ない。(ただし、この政策をとんでもないバラマキと思ってる人がいるが、高速道路というものはいずれ建設費の償還が終わったら無料にするという約束で作ったものなのである。デーブ・スペクターだったかな、アメリカで日本語の勉強に歌を聞きまくり、「中央フリーウェイ」と言ってたのに、日本で実際に通ったらやけに高くて詐欺かと思ったという話を聞いたことがあるけど、高速道路無料化自体は至極まともな発想なのである。)
前置きが長くなったけど、では高校授業料無償化の本質とは何か、と言えばそれは「人権問題」なのである。1948年12月8日、国際連合は世界人権宣言を採択した。宣言は言いっ放しだから、それを何とか規制力のあるルール化することが目指され、1966年12月に国連で採択されたのが、国際人権規約である。社会権を定めたA規約と自由権を定めたB規約に分かれる。日本は1979年にいたってABともに批准した。(なお、A規約には第一選択議定書=個人通報制度と第二選択議定書=死刑廃止が後から成立したが、日本はご承知の通り、どちらも批准していない。)
さて、その国際人権規約の中に、(小学校はもちろん無償であり)中学や高校もだんだんと無料にするのだと明確に書いてある。外務省訳を一応あげておくと「種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」
中等教育というのは中学と高校のことで、日本は中学は無償だが、高校は授業料があった。では、1979年にこの規約になぜ入れたのか。実は、日本も仲間に入るけど、三つだけ特例を認めてねという荒業を使ったのである。他にも解釈の問題も二つ、注文を付けている。
その三つとは、「中・高等教育の無償化」「労働者への休日の報酬の支払い」「ストライキ権の保障」だった。最後のスト権というのは、もちろん民間労働者にはあるわけだが、「公務員にスト権がない」ことが国際水準からすれば人権無視のとんでもない事態なのである。
高校授業料を取っていた国は、だから世界にほとんどない。国によっては大学まで無償である。これは国民の教育権を保障する人権上の措置だと、どの国も判っているからだ。ウィキペディアによれば、この条項を保留扱いしていたのは、日本とマダガスカルだけだという。民主党政権になり、高校が無償になり、国連にこの保留通知の撤回を行った。やっと世界の常識が日本に通じたのである。どこがバラマキなのか、そういうことを言う人の常識を疑う。
ところで、実際は各地方で貧困家庭には学費減免措置があった。みんなタダになれば、金持ちの家庭はその授業料分のお金で塾や予備校に行けるから、かえって教育格差を広げるという人もいる。教科書代や制服代や修学旅行費はタダにはならない以上、家庭の負担はやはり大きくて、授業料だけの問題ではないという人もいる。そいう議論の一つ一つはもっともなのだが、本質を外している。金持ちだろうが、貧乏だろうが、それは子供に選べない。高校や高校にあたる専門学校等の授業料そのものをなくすというのは、社会の側で若い世代に与えることができるチャンスであって、それを維持するのは当然だ。(教科書や修学旅行への援助制度もあるので、他の問題は別建てで考えればいいことだ。)
ところで、この問題を調べていて、今のことに気付いたのは数年前である。僕でさえ、「人権」という授業を作って、国際人権規約なんてものをちゃんと調べて知った。多分多くの先生は、国際人権規約で高校授業料無償化と公務員のスト権が定められているが、日本政府がそれはやらないよと通知していたんだということを知らない人が多いと思う。自分の権利を侵害されていて、それで教育を行っていたのか。このことは、もっともっと知られなくてはならない。教育と労働に関して、日本の水準は国際的に見て低いということを。
「キューポラのある街」という映画がある。1962年。伝説の名匠浦山桐郎監督のデビュー作。17歳の吉永小百合が主演女優賞を取った。早船ちよの児童文学の映画化。キューポラとは鉄の溶解炉で、鋳物の街として知られた埼玉県川口市を舞台にした傑作である。「北朝鮮帰国問題」も重要なテーマになっており、貴重な場面も多い。さて、そんなことではなく、中学生の吉永の父、東野英治郎が失職する。学力はあるが経済的に全日制高校へ行けなさそうになり、悩む。その時に担任の先生役の加藤武が諄々と説く。働きながら定時制高校へ行ってもいいのだ。通信制高校というのもあるのだ。人間は一生ちゃんと勉強しなければいけなんだ。ここでくじけてはダメだ、と。吉永小百合は工場で働きながら夜は定時制高校で学ぶ女子工員たちの見学に行く。そのような感動的なシーンがあるのだが、その場面を見ていて、日本の庶民にとって子供をなんとか高校までは出してやりたいということがどんなに大変なことだったかが痛切に伝わってきたのである。本当は日本がまだまだ貧しかった60年代に、少なくとも高度成長を達成した70年代にこの政策が実現できていたらどんなに良かったろうにと強く思う。










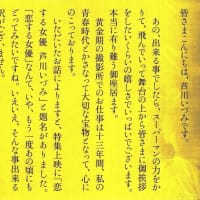
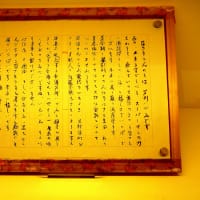








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます