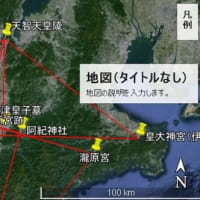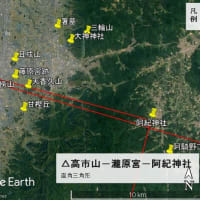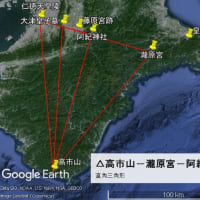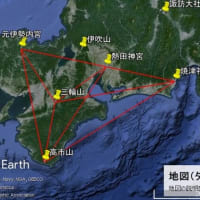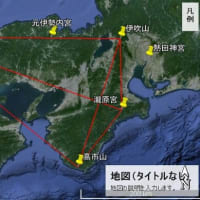新羅にも王朝の変化があったのではないか、と推測しました。
新羅が伽倻を併合し伽倻諸国(または加羅諸国)は滅んだことになっています。
しかし、金庾信(きむゆしん)が金官伽倻の出身だということで、もしかすると、考えたからです。
日本が新羅の歴史を取り入れるとすると、全くありえないような話ですが、もし、新羅の王家が伽倻、すなわち任那と関連するであろう国の王家につながる金庾信(きむゆしん)の系統に変化していたならば、あるかな・・・ 中断。
まるっきりまとまりませんので、苦しまぎれに太白山の位置関係をやります。
仙台に太白山があります。
また、諸塚山も太白山と名づけられました。
白頭山ももともとは太白山のはずです。
これらは何度もみてきました。
さらに、韓国にもテペク(太白)山があります。
このテペク(太白)山の位置は、はっきりしなかったこともあり、新羅関係だから関係ないと思い込んでいたために、検討したことはあった気がするのですが、気に留めなかったようです。
しかし、新羅の歴史記述と日本の歴史記述が重なることがあるならば、関連付けられてもおかしくありません。





仙台・太白山
北緯38度14分08.25秒、東経140度48分07.61秒
大韓民国・テペク(太白)山
北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒(たぶん、ここではないかと・)
諸塚山
北緯32度38分04.06秒、東経131度17分14.06秒
仙台・太白山→大韓民国・テペク(太白)山
Ⅰ266°47′20.09″ Ⅱ79°30′32.95″ Ⅲ1,055,537.537(m)
仙台・太白山→諸塚山
Ⅰ237°06′43.71″ Ⅱ51°34′49.90″ Ⅲ1,063,279.506(m)
諸塚山→大韓民国・テペク(太白)山
Ⅰ337°01′00.99″ Ⅱ155°39′37.31″ Ⅲ540,332.432(m)
仙台・太白山での角度
266°47′20.09″-237°06′43.71″=29°40′36.38″≒29.6768度
諸塚山での角度
360°-337°01′00.99″+51°34′49.90″=74°33′48.91″≒74.5636度
大韓民国・テペク(太白)山での角度
155°39′37.31″-79°30′32.95″=76°09′04.36″≒76.1512度
頂角30度、底角75度の二等辺三角形になるのではないでしょうか。
でも写真はあまり二等辺三角形には見えないです。球面のせいでしょうか。
新羅が伽倻を併合し伽倻諸国(または加羅諸国)は滅んだことになっています。
しかし、金庾信(きむゆしん)が金官伽倻の出身だということで、もしかすると、考えたからです。
日本が新羅の歴史を取り入れるとすると、全くありえないような話ですが、もし、新羅の王家が伽倻、すなわち任那と関連するであろう国の王家につながる金庾信(きむゆしん)の系統に変化していたならば、あるかな・・・ 中断。
まるっきりまとまりませんので、苦しまぎれに太白山の位置関係をやります。
仙台に太白山があります。
また、諸塚山も太白山と名づけられました。
白頭山ももともとは太白山のはずです。
これらは何度もみてきました。
さらに、韓国にもテペク(太白)山があります。
このテペク(太白)山の位置は、はっきりしなかったこともあり、新羅関係だから関係ないと思い込んでいたために、検討したことはあった気がするのですが、気に留めなかったようです。
しかし、新羅の歴史記述と日本の歴史記述が重なることがあるならば、関連付けられてもおかしくありません。





仙台・太白山
北緯38度14分08.25秒、東経140度48分07.61秒
大韓民国・テペク(太白)山
北緯37度05分46.75秒、東経128度54分58.26秒(たぶん、ここではないかと・)
諸塚山
北緯32度38分04.06秒、東経131度17分14.06秒
仙台・太白山→大韓民国・テペク(太白)山
Ⅰ266°47′20.09″ Ⅱ79°30′32.95″ Ⅲ1,055,537.537(m)
仙台・太白山→諸塚山
Ⅰ237°06′43.71″ Ⅱ51°34′49.90″ Ⅲ1,063,279.506(m)
諸塚山→大韓民国・テペク(太白)山
Ⅰ337°01′00.99″ Ⅱ155°39′37.31″ Ⅲ540,332.432(m)
仙台・太白山での角度
266°47′20.09″-237°06′43.71″=29°40′36.38″≒29.6768度
諸塚山での角度
360°-337°01′00.99″+51°34′49.90″=74°33′48.91″≒74.5636度
大韓民国・テペク(太白)山での角度
155°39′37.31″-79°30′32.95″=76°09′04.36″≒76.1512度
頂角30度、底角75度の二等辺三角形になるのではないでしょうか。
でも写真はあまり二等辺三角形には見えないです。球面のせいでしょうか。