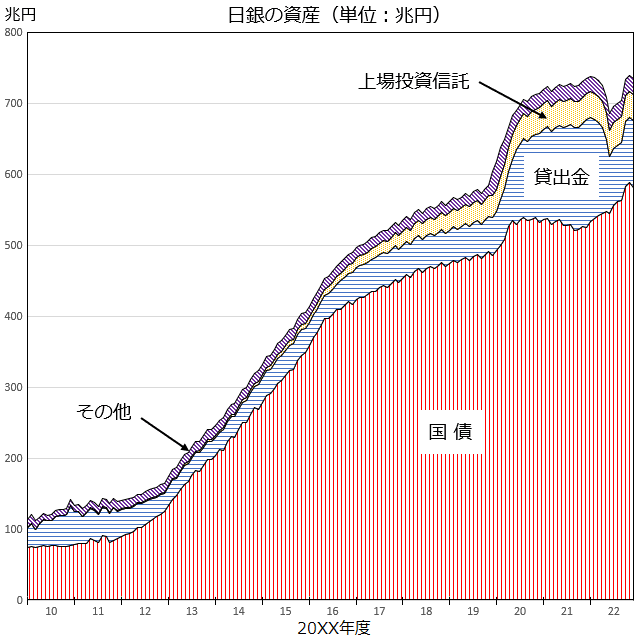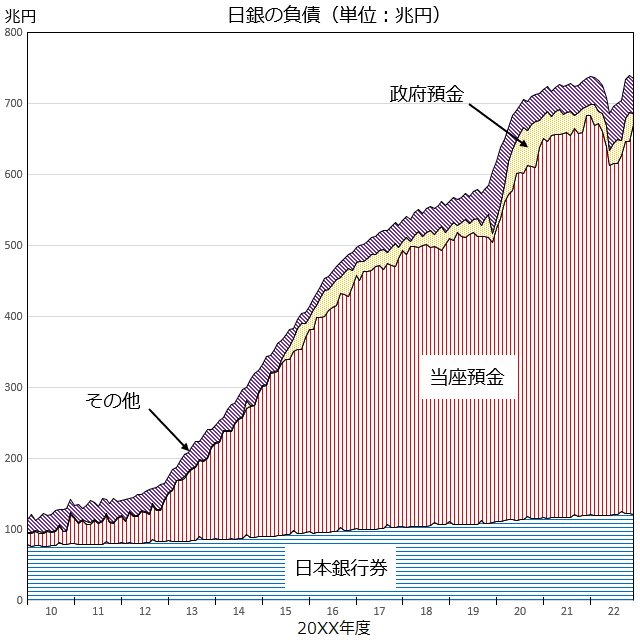前回は、国立がん研究センターが多くの「がん難民」を生み出してきたということをお伝えしましたので、今回は「がん難民」となった人々を数多く救った人物をご紹介しましょう。
それは、健康再生会館の館長・加藤清氏で、彼は医師ではないのですが、指圧と粉ミルク断食によって重症のがん患者を数多く治療したそうです。
『婦人生活』(婦人生活社:刊、1982年1月号)という雑誌によると、この人はもともと指圧と断食で病人を治療していたようですが、あるとき、彼のところに医者に見放されたがん患者が訪ねてきたそうです。
そこで、加藤氏はそのがん患者を入院させて断食を開始したのですが、その患者がどうしても水を飲まないため、脱水症状を起こさないよう、水の代わりに粉ミルクを与えたところ、やっと飲んでくれたそうです。
ところが、驚いたことに、やがてその患者のがんが影も形もなくなってしまったため、それ以来、「がんは粉ミルクと整体指圧でよくなる」ということを公表して、多くのがん患者を治療するようになったそうです。
また、この雑誌には、この治療法を習得した医師による治療例も掲載されています。
その医師は、神奈川県平塚市の十全病院副院長・石神正文氏で、彼は加藤氏の講演を聞き、これはインチキではないと確信し、病院のマッサージの先生2人とともに大阪の健康再生会館で治療のやり方を教わったそうです。
その後、石神氏の知人で、某大学病院でS字状部結腸がんと診断され、患部を切除して人工肛門を作る手術をしなければならないという症状の人がいたのですが、その人は手術を拒否して石神氏のところに来たため、粉ミルク断食と整体指圧で治療することにしたそうです。
【粉ミルク断食療法の治療例】
1981年6月27日 粉ミルク断食開始。薬は一切使わず。がんの大きさは触診で10x10センチ。
粉ミルク大さじ5杯、五健草1グラム、バイエム酵素小さじ1杯を朝昼2回、夕食はその5分の2。
6月28日 マッサージ開始、午前11時と午後3時の2回、以後毎日。粉ミルクは2杯ずつ。
6月29日 粉ミルクは朝2杯、昼3杯、夕4杯。
6月30日 この日から粉ミルク5杯、五健草2グラム、バイエム酵素1杯を1日3回。
7月2日 この日から排便中にがんの剥離したものが混じってきた。
7月4日 排便に血液のかたまりが出た。
7月7日 親指頭大のがんのかたまりが出てきた。魚の腹わたの腐ったようなものすごい悪臭。
7月10日 触診でのがんは3x4センチ。出血はないが、潜血反応あり(11月まで継続)。
7月17日 がん様の触診全くなし。驚くべきスピードでがんが消失した。
8月15日 昼だけおもゆ。この日以降、ゆっくりと復食。
11月1日 この日から普通のごはん(昼食だけ)。月末に退院の予定。
以上です。それにしても、10x10センチのがんがわずか20日で完治したというのは驚きですね。
加藤氏は、『ガンは助かる』(主婦の友社:1980年刊)などの8冊の著書を出版しているので、この治療法にご興味のある方は図書館等で探してみてください。
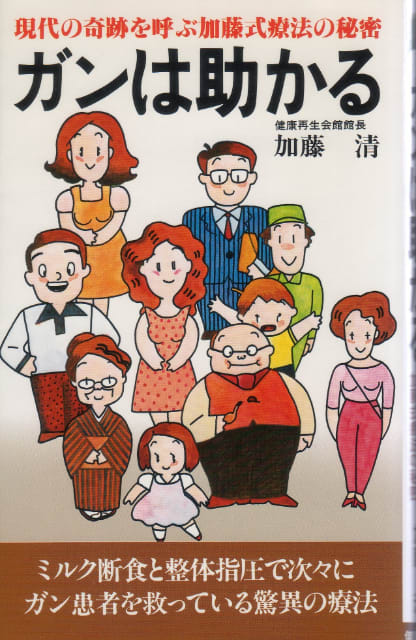
【加藤清:著『ガンは助かる』】(画像はAmazon通販サイトより拝借)
なお、『知識』(彩文社:刊、1988年7月号)という雑誌によると、加藤氏は無資格で七千人を治療したため、1988年2月に医師法違反で逮捕されたそうです。(朝日新聞が一面トップで報道)
私は、こういった素晴らしい治療法を考案した人は表彰されるべきだと思うのですが、本人は逮捕され、粉ミルク断食療法は医学界から黙殺されてしまったわけですから、日本は本当に救いのない国ですね。
その一方で、多くの医師が標準治療(手術、抗がん剤、放射線)という名の有害無益な処置によってがん患者を不具者にし、死に追いやっているのに、彼らが医師免許を持っているというだけの理由で野放しにされている現状には、本当に驚かされます。