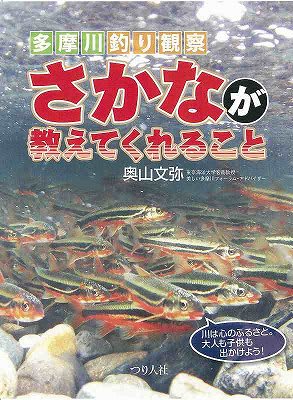後ろを振り返ってみたらそこにいたのはヒグマ!!!
ウヮオ! 近すぎる! その距離3m。
以前、バビーンリバーのロッジの庭先でのグリズリーとの遭遇より近いじゃん!
あの時はお互いがびっくりして逃げていったけど、こいつは全然逃げないのです。
人間に慣れているとすぐわかりました。
私はすぐにカメラを出し、シャッターを切りましたがまだ暗いのでブレブレ。
そこでデジカメの特徴であるISO感度をすぐに上げて撮影開始。ってそんな余裕かましている場合じゃないだろうと自分でも不思議でした。

番屋の主がロケット花火を当ててもクマは驚きません。投げた石は手(前足)ではじき返しました。ゴジラ対エビラのようでした。
クマは後ろに置いてあるカラフトマスをほとんど食いつくしてから森に消えて行きました。
さてどうします?遠藤さんと望月さん、村山さんはまず食事をしながら考えましょうと、朝食に取り掛かります。
他の人たちはみんな帰り始めました。
残ったのは私たちだけ。
クマが森に戻ってしばらくしてからまた釣りを開始しました。今度は後方をチラチラ見ながらの釣りです。
で、何匹かのカラフトマスを釣ったらまた現れました。見てるんでしょうね。村山さんはさっと魚を隠して番屋の方に持って行きました。
クマは川で遡上した魚を狙ってます。不思議に今度は危険を感じませんでした。
写真もいっぱい撮って、、、。動画も撮ってから私たちはその場を去りました。
今回の件は釣り人も愚かでした。釣った魚の内臓を、カモメに食べさせるか、も使えればいいものを、河原に放置する人が多すぎたのです。
また番屋に泊った人がデカクーラーに前日釣ったカラフトマスを入れておいたら全部食べられたとか、、、。奴はクーラーの留め具を外すことを知っています。
またこのエリアでクマに襲われた釣り人はいません。
でも、今回、私が一人目になった可能性は十分あったのです。
帰還したから言えることですが、今回の釣りはグランドスラム。
エゾジカ、キタキツネ、そしてヒグマでした。




ウヮオ! 近すぎる! その距離3m。
以前、バビーンリバーのロッジの庭先でのグリズリーとの遭遇より近いじゃん!
あの時はお互いがびっくりして逃げていったけど、こいつは全然逃げないのです。
人間に慣れているとすぐわかりました。
私はすぐにカメラを出し、シャッターを切りましたがまだ暗いのでブレブレ。
そこでデジカメの特徴であるISO感度をすぐに上げて撮影開始。ってそんな余裕かましている場合じゃないだろうと自分でも不思議でした。

番屋の主がロケット花火を当ててもクマは驚きません。投げた石は手(前足)ではじき返しました。ゴジラ対エビラのようでした。
クマは後ろに置いてあるカラフトマスをほとんど食いつくしてから森に消えて行きました。
さてどうします?遠藤さんと望月さん、村山さんはまず食事をしながら考えましょうと、朝食に取り掛かります。
他の人たちはみんな帰り始めました。
残ったのは私たちだけ。
クマが森に戻ってしばらくしてからまた釣りを開始しました。今度は後方をチラチラ見ながらの釣りです。
で、何匹かのカラフトマスを釣ったらまた現れました。見てるんでしょうね。村山さんはさっと魚を隠して番屋の方に持って行きました。
クマは川で遡上した魚を狙ってます。不思議に今度は危険を感じませんでした。
写真もいっぱい撮って、、、。動画も撮ってから私たちはその場を去りました。
今回の件は釣り人も愚かでした。釣った魚の内臓を、カモメに食べさせるか、も使えればいいものを、河原に放置する人が多すぎたのです。
また番屋に泊った人がデカクーラーに前日釣ったカラフトマスを入れておいたら全部食べられたとか、、、。奴はクーラーの留め具を外すことを知っています。
またこのエリアでクマに襲われた釣り人はいません。
でも、今回、私が一人目になった可能性は十分あったのです。
帰還したから言えることですが、今回の釣りはグランドスラム。
エゾジカ、キタキツネ、そしてヒグマでした。