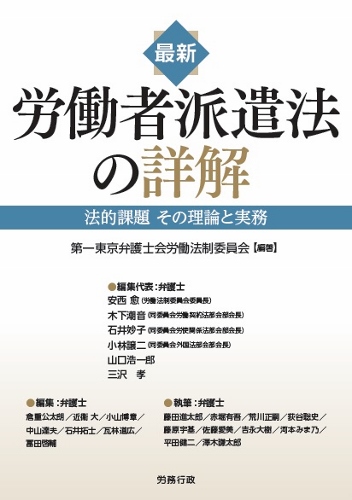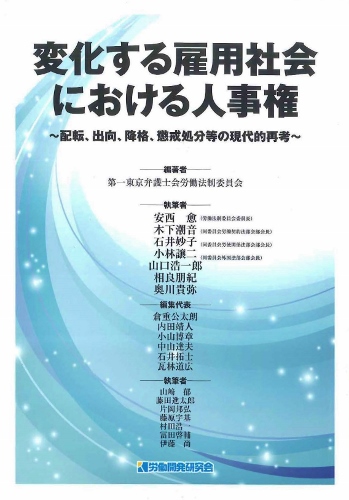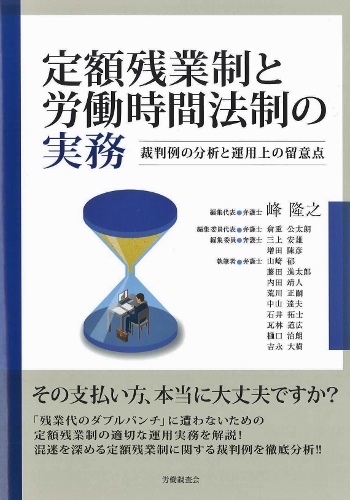1 賃金減額の方法
賃金減額の方法としては,①労働協約,②就業規則の変更,③個別同意によることが考えられます。
2 労働協約による賃金減額
労働組合との間で賃金に関する労働協約を締結した場合,それが組合員にとって有利であるか不利であるか,当該組合員が賛成したか反対したかを問わず,労働協約で定められた賃金額が労働契約で定められた賃金額に優先して適用されるのが原則です(労組法16条)。
したがって,労働者が賃金減額に反対していたとしても,当該労働者が加入している労働組合との間で賃金を減額することを内容とする労働協約を締結すれば,賃金を減額することができます。
労働協約の規範的効力が及ぶ範囲は原則として組合員との範囲と一致し,労働協約締結後に組合員となった者にも組合加入時から労働協約の規範的効力が及びますが,労働組合を脱退した場合には離脱の時点から労働協約の規範的効力は及ばなくなります。
労働協約が締結されるに至った経緯,当時の会社の経営状態,同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らし,同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたものである場合には,その規範的効力を否定され(朝日海上火災保険(石堂・本訴)事件最高裁第一小法廷平成9年3月27日判決),賃金減額の効力が生じません。
具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約により処分又は変更することは許されません。
賃金減額の効力が及ぶのは,原則として労働協約を締結した労働組合の労働組合員に限られることになりますが,労働協約には,労組法17条により,一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは,当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められており,この要件を満たす場合には,賃金減額に反対する未組織の同種労働者に対しても労働協約の効力を及ぼし,賃金を減額することができます。
ただし,労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容,労働協約が締結されるに至った経緯,当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし,当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは,労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼし,賃金を減額することはできません(朝日海上火災保険(高田)事件最高裁第三小法廷平成8年3月26日判決)。
少数組合に加入している組合員に対しては,労組法17条の一般的拘束力は及びません。
したがって,少数組合に加入している組合員の賃金を減額するためには,当該少数組合と労働協約を締結するか,就業規則を変更するか,個別同意を取る必要があります。
未組織組合員に一般的拘束力が及ばない場合に賃金を減額するためには,就業規則を変更するか,個別同意を取る必要があります。
3 就業規則による賃金減額
就業規則により賃金を減額する場合は,就業規則の不利益変更に該当するため,就業規則の変更が有効となるためには,以下のいずれかの場合である必要があります。
① 労働者と合意して就業規則を変更したとき(労契法9条反対解釈)
② 変更後の就業規則を周知させ,かつ,就業規則の変更が,労働者の受ける不利益の程度,労働条件の変更の必要性,変更後の就業規則の内容の相当性,労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき(労契法10条)
①に関し,「就業規則の不利益変更は,それに同意した労働者には同法9条によって拘束力が及び,反対した労働者には同法10条によって拘束力が及ぶものとすることを同法は想定し,そして上記の趣旨からして,同法9条の合意があった場合,合理性や周知性は就業規則の変更の要件とはならないと解される。」(協愛事件大阪高裁平成22年3月18日判決)との見解が妥当と思われますが,労働者の同意があれば合理性や周知性は就業規則の変更の要件とはならないとの見解に立ったとしても,合意の認定は慎重になされるのが通常であるため,最低限,書面による同意を取る必要があります。
労働者が就業規則の変更を提示されて異議を述べなかったといったことだけでは足りません。
合理性に乏しい就業規則の規定の変更については,書面による同意を取ったとしても,労働者の同意があったとは認定されないリスクが高いものと思われます。
②に関し,賃金,退職金など労働者にとって重要な権利,労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については,当該条項が,そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において,その効力を生じます(大曲市農協事件最高裁昭和63年2月16日判決)。
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されません。
4 個別合意による賃金減額
個別合意よりも労働者に有利な労働条件を定めた労働協約,就業規則が存在する場合には,それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条,労契法12条),労働協約,就業規則を変更しない限り,個別合意により賃金を減額することはできません。
個別合意よりも労働者に有利な労働条件を定めた労働協約,就業規則が存在しない場合は,個別合意により賃金を減額することができますが,賃金減額に対する同意の認定は慎重になされることが多いので,「書面」で同意を取っておくべきです。
「既発生の」賃金債権の減額に対する同意は,既発生の賃金債権の一部を放棄することにほかなりませんから,それが有効であるというためには,それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであることが明確である必要があります(シンガーソーイングメシーン事件最高裁第二小法廷昭和48年1月19日判決)。
「未発生の」賃金債権の減額に対する同意についても「賃金債権の放棄と同視すべきものである」とする下級審裁判例もありますが,「未発生の」賃金債権の減額に対する同意は,労働者と使用者が合意により将来の賃金額を変更した(労契法8条参照)に過ぎず,賃金債権の放棄と同視することはできないのですから,通常の同意で足りると考えるべきであり,それが労働者の自由な意思に基づいてなされたものであることが明確であることまでは要件とされないものと考えます。
北海道国際空港事件最高裁第一小法廷平成15年12月18日判決(労判866号14頁)が,「原審は,上告人が平成13年7月25日に減額された賃金を受け取り,その後同年11月まで異議を述べずに減額された賃金を受け取っていた事実によれば,同年7月1日にさかのぼって賃金が減額されることも,上告人はやむを得ないものとしてこれに応じたものと認めることができると認定した。すなわち,原審は,上告人が平成13年7月25日に同月1日以降の賃金減額に対する同意の意思表示をしたと認定したのであるが,この意思表示には,同月1日から24日までの既発生の賃金債権のうちその20%相当額を放棄する趣旨と,同月25日以降に発生する賃金債権を上記のとおり減額することに同意する趣旨が含まれることになる。しかしながら,上記のような同意の意思表示は,後者の同月25日以降の減額についてのみ効力を有し,前者の既発生の賃金債権を放棄する効力は有しないものと解するのが相当である。」と判示し,未発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示を肯定しているのは,既発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示の効力を肯定するための要件と未発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示を肯定するための要件を明確に区別し,未発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示を肯定するための要件としては,それが労働者の自由な意思に基づいてなされたものであることが明確でなければならないことを要求していないからであると考えられます。
5 各論
(1) 定期昇給凍結
就業規則に一定額・割合以上の定期昇給を行う義務が定められている場合に定期昇給を凍結するためには,定期昇給を凍結する旨の労働協約を締結するか,定期昇給を凍結する旨就業規則の附則に定める等の就業規則の変更が必要となります。
労働協約を締結できず,定期昇給を凍結する旨の就業規則の変更に関し同意が得られない場合は,就業変更により一方的に労働条件の変更をせざるを得ませんが,その合理性(労契法10条)の有無が問題となります。
就業規則に一定額・割合以上の定期昇給を行う義務が定められておらず,使用者に定期昇給の努力義務が課せられているに過ぎない場合は,定期昇給をしなくても法的問題はありません。
(2) ベースアップ凍結
ベースアップは労使交渉により特段の決定がなされない限り行う必要はありません。
(3) 賞与不支給
個別労働契約,就業規則,労働協約で一定額・割合の賞与を支給する義務が定められていない場合には,使用者には賞与を支給する義務がないため,賞与不支給としても法的には問題はありません。
一定額以上の賞与支給が労使慣行になっているとして賞与請求がなされることがありますが,賞与支給額の決定権限を有している者が一定額以上の賞与支給が法的義務であると考えているケースはそれほど多くなく,労使慣行の成立が認められるケースは多くありません。
民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには,
① 同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行われていたこと
② 労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないこと
③ 当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていること
を要し,使用者側においては,当該労働条件についてその内容を決定しうる権限を有している者か,又はその取扱いについて一定の裁量権を有する者が規範意識を有していたことを要すると考えるのが一般です(商大八戸ノ里ドライビングスクール事件最高裁第一小法廷平成7年3月9日判決・労判679号30頁,同事件大阪高裁平成5年6月25日判決・労判679号32頁参照)。
他方,一定額・割合の賞与を支給する義務が定められている場合は,賞与を支給する義務があります。
就業規則の定めを変更して賞与不支給とする場合には,就業規則の不利益変更の問題となるため,その高度の合理性の有無が問題となります。
(4) 諸手当の廃止,支給停止
賃金規程で定められた諸手当の廃止,支給停止を行う場合は,賃金規程を変更したり,附則に支給を停止する旨定めたりする必要があり,就業規則の不利益変更の問題となります。
(5) 年俸額の引下げ
年俸制を採用した場合に,年度途中で年俸額を一方的に引き下げることができるか,次年度の年俸額引下げを求めたところ合意が成立しない場合における次年度の年俸額がどうなるかは,当該労働契約の解釈の問題です。
トラブルを予防するためにも,労働契約上明確にしておくことをお勧めします。
労働契約上明確でない場合は,年度途中で年俸額を一方的に引き下げることはできないケースが多いのではないかと思います。
次年度の年俸額引下げを求めたところ合意が成立しない場合における次年度の年俸額については,使用者の提示額を超えては請求できないとされた裁判例,前年度実績の年俸額を支給すべきものとされた裁判例等があります。
(6) 休業時の賃金カット
会社の業績が悪いことを理由とした休業がなされた場合は,通常は使用者の責めに帰すべき事由があると言わざるを得ないため,平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります(労基法26条)。
休業手当の支払義務は,労働協約,就業規則,個別合意により排除することはできません(労基法13条)。
民法536条2項の適用を排除し,平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨の労働協約が締結された場合には,当該労働組合の組合員については,平均賃金の60%の休業手当を支払えば足ります。
少数組合の組合員など,労働協約の効力が及ばない社員に対し,平均賃金の60%の休業手当を超えて賃金を支払う必要があるかどうかについては,従来,民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」の存否の問題として争われてきました。
例えば,いすゞ自動車事件宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定は,使用者が労働者の正当な(労働契約上の債務の本旨に従った)労務の提供の受領を明確に拒絶した場合(受領遅滞に当たる場合)に,その危険負担による反対給付債権を免れるためには,その受領拒絶に「合理的な理由がある」など正当な事由があることを主張立証すべきであり,その合理性の有無は,具体的には,使用者による休業によって労働者が被る不利益の内容・程度,使用者側の休業の実施の必要性の内容・程度,他の労働者や同一職場の就労者との均衡の有無・程度,労働組合等との事前・事後の説明・交渉の有無・内容,交渉の経緯,他の労働組合又は他の労働者の対応等を総合考慮して判断すべきものとしています。
民法536条2項は民法上の任意規定であり,特約で排除することもできるため,労働契約及び就業規則において休業期間中は平均賃金の60%の休業手当のみを支払う旨定めておけば,理論的にはこれを超える賃金を支払う義務はないはずですが,裁判所は,民法536条2項の適用除外について慎重に判断する傾向にあります。
例えば,いすゞ自動車(雇止め)事件東京地裁平成24年4月16日判決(労判1054号5頁)は,休業手当に関し,就業規則に「臨時従業員が,会社の責に帰すべき事由により休業した場合には,会社は,休業期間中その平均賃金の6割を休業手当として支給する。」と定められている事案において,「被告は,本件休業に係る休業手当額を平均賃金の6割にすることについては,第1グループ原告らとの間の労働契約及び臨時従業員就業規則43条により,その旨の個別合意が存在し,この合意は本件休業の合理性を基礎付ける旨主張する。しかし,上記の規定は,労働基準法26条に規定する休業手当について定めたものと解すべきであって,民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」による労務提供の受領拒絶がある場合の賃金額について定めたものとは解されないから,被告の上記主張は,その前提を欠くというべきである。」と判示しており,民法536条2項の適用除外を認めていません。
民法536条2項の適用を排除するためには,単に休業期間中は平均賃金の60%の休業手当を支払うとだけ就業規則に規定するのではなく,民法536条2項の適用を排除する旨明確に規定しておくべきでしょう。
また,就業規則が労働契約の内容となるための要件として合理性が要求されていることもあり(労契法7条),事案によっては適用が制限されるリスクがないわけではありません。
大多数の社員の理解を得られないまま休業を行った場合,会社経営に支障が生じる可能性が高いため,少なくとも多数派の同意を得ておくべきでしょう。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田進太郎