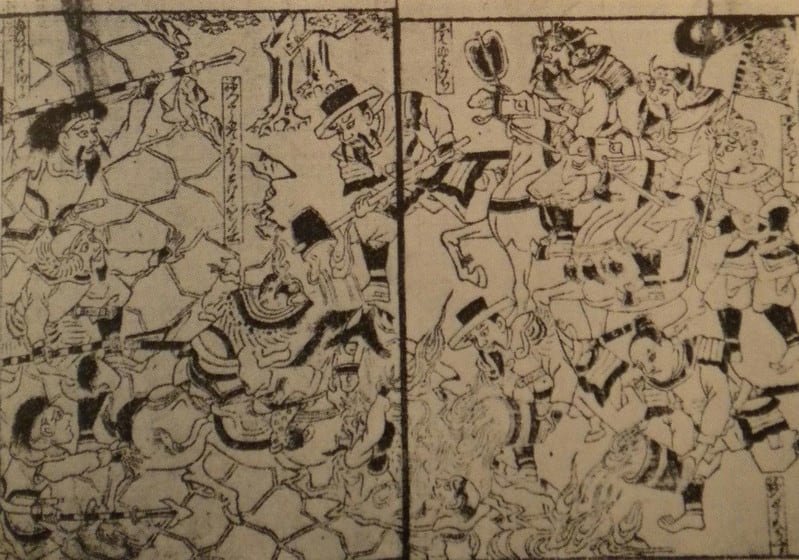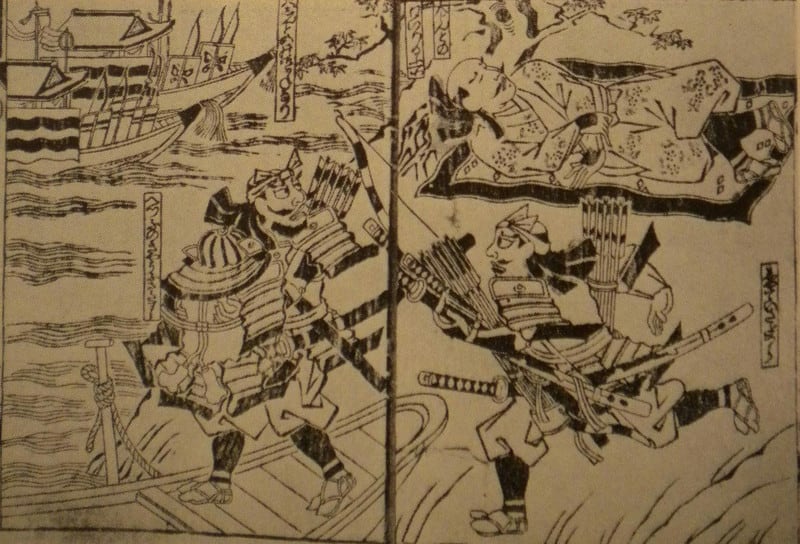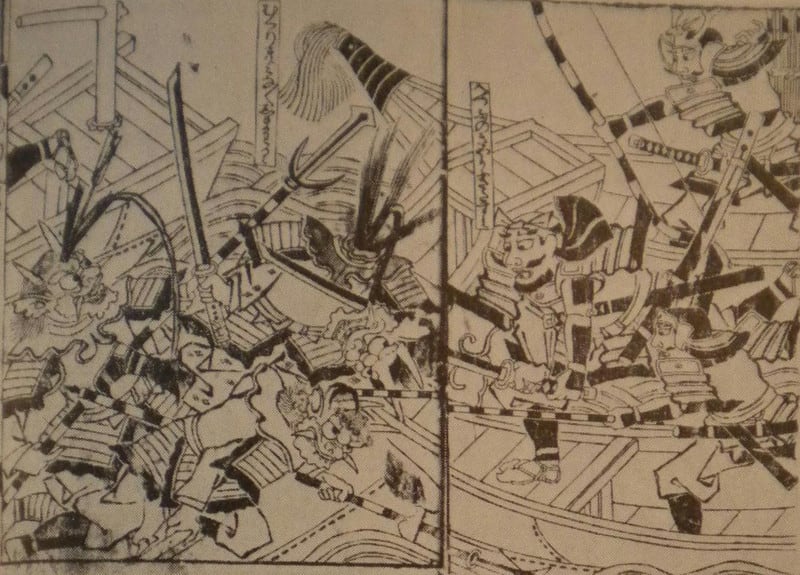弘知上人二段目 その2
さて、その頃館では、柳の前が、事の次第がどうなったと、そわそわとしていました。
柳の前は、千代若を抱いて、館を出たり入ったりしながら、義父秋弘が弘友を、無事に
連れて帰って来るのを待っていたのでした。居ても立っても居られなくなった柳の前は、
やがて、館を忍び出でました。そんなところを通りかかったのは、弘友の装束を着せら
れた馬子でした。馬子は、途中で秋弘に咎められていたので、びくびくしながら馬に乗
っていました。柳の前は、馬上の小袖羽織に夫の紋を見つけて、走り寄りました。
「のうのう、そこを行くのは、弘友殿ではありませんか。お待ち下さい。」
と言うと、馬の尾筒に縋り付きました。またまた呼び止められた馬子は、飛び上がって
驚くと、いきなり刀を抜いてばっさりときりつけました。そして、後ろも見ずに一目散
に走り去って行ったのでした。
労しいことに、柳の前は、肩先から脇腹に切り下げられて、そこにばったりと倒れ伏しました。
哀れな柳の前は、もう虫の息でしたが、千代若に乳を含ませると、微かな声で口説くのでした。
「ああ恨めしい、我が夫よ。五百生の奇縁によって夫婦となった私を、何でこのように
切り捨てるのですか。例え、私との縁が切れて、私を憎んでいたとしても、三歳のこの
子は、あなたの御子ではありませんか。母が死んで、誰が育てて行くのですか。
今になって言うことでもありませんが、
『五月雨かや不如帰 鳴り鳴く里の多ければ』(足利義輝辞世を引いて:涙のような五月雨がふる里で、沢山の不如帰が鳴いている:世の中の人々の弘友への嘲り)
『胸の炎(ほむら)を押さえつつ 色には出でぬ埋火(うずみび)の 底に焦がるる我が思い』(胸の炎を押さえて、見えない埋火のように焦げている私の思いがわかりませんか)
父上様との間に立って、陰となり仲立ちして、うまく行くようにと取りなしして来て、
この度、遣いを出したのも、恨みながらも我が夫を悪くは思っていないからこそ。陰な
がら、忠はしても、一度も仇になることをしていない私を、よくも刀に掛けて命を奪い
ましたね。
千代若よ。母の最期の言葉をよっく覚えて、もし生き延びて成人し、父に巡り会う時
は、母が思いを詳しく語って恨みなさい。千代若よ。成人したのなら出家となり、必ず
母が菩提を弔ってくださいね。ああ、名残惜しい我が子よ。」
と言うと、まだ十九歳だというのに、とうとう息絶えました。まったく哀れなことです。
すると突然、胎内の嬰児(みどりご)が、忽然と生まれ出てきて、産声を上げたのでした。
さて、弘友は、父から勘当されて面目も無く、知人へ頼ることもできずにおりました。
季節は長月(旧暦9月)の夕方、麻の単衣(ひとえ)も肌寒く、行く末も知れない心細
さのまま彷徨っていますと、草むらから幼い子供の泣き声が聞こえてきました。どうや
ら、一人ではなく、二人の子供が泣いているようです。いったい何事かと近づいて見て
みると、なんと一人は千代若、一人は生まれたばかりの産子(うぶこ)です。そして、
傍らに死んでいるのは、妻の柳の前ではありませんか。弘友は、これは夢か現かと、死
骸に取り付いて嘆き悲しみました。死骸を良く見てみると、左の肩より脇の下に切り捨
てられています。
「これは、いったい何者の仕業か。譬えこのように身を落としていても、敵(かたき)
を取らずに居られようか。ええ、千代若、幼いとはいえ、母の敵を教えられないとは恨
めしい。また、この生まれ出でた子は、どうして胎内において、湯とも水とも成らずに
生まれてきて、嘆きをさらに重ねるのだ。いったい何の因果の報いであるか。」
産子を懐に入れ、左手に千代若を抱き上げて、右手で妻の死骸を押し動かして、悶え苦
しむ弘友の有様は、まるで幽鬼のようです。弘友はつくづくと無常を感じて、
「これは、すべて自分の煩悩、色欲の迷いより起こった事だ。親子夫婦の嘆きの原因は、
何一つとして外から来たものは無い。煩悩即菩提とは、まさしくここだ。」
と悟ると、忽ちに発起すると、涙を押しとどめて、
「如何に妻よ。これを菩提の種として発心し、堅固に修業して、後世を弔うぞよ。おま
えは、私にとっては、法身仏(ほっしんぶつ)である。」
と、三度礼拝すると、穴を掘り、
「それでは、仮の色相を返すぞ。我妻よ。上の小袖は私に貸してくれ。」
と言うと、妻の小袖を羽織り、死骸を埋めて印を立てたのでした。
『さて、この子供達はどうしたものか。一人ならば何とか手立てもあるものを。二人も
居ては育て様も無い。仕方ない。やはり産子を捨てるしかない。』
と思った弘友は、産子を懐から取り出すと、道端に捨て置きました。しかし、嬰児の泣
き声に心引かれて、また戻っては抱き上げて、涙ながらに言い聞かすのでした。
「先に生まれた者を兄と言い、後から生まれた者を弟と言うが、いずれも同じ父の子で
あるから、差別があってはならないが、兄を取って弟を捨てることを、どうか恨まない
でくれよ。兄とても父の手で育てるわけでは無いからな。」
と、まるで知恵のある者に言う様に、嬰児に言い聞かす弘友の心の内は、いかばかりで
しょうか。嘆きながらも弘友は、懐中より鬢鏡(びんかがみ)を取り出すと二つに割り、
嬰児にその半分をくくりつけました。
「もし、仏神のご加護があり、人に拾われて成人して、兄と巡り会うことがあるのなら、
その時の印として、ここに添えておくぞ。」
と、弘友は言うと、その半分を千代若にくくりつけて、その場を離れました。ところが、
その時突然に巨大な狼が一匹現れ、嬰児を咥えると、忽然と山の中へと消え去ったのでした。
弘友は、驚いて走り戻りましたが、もう既に遅く、ただただ、呆れ果てているしかありません。
なんということでしょう。自分のせいで、幼い命が奪われたと悔やみながらも、南無阿
弥陀仏と回向するほかありません。千代若を抱いてその場から去っていく弘友の心の内
程、悲しいものはありません。
さて、その夜も既に丑三(午前2時頃)の頃のことです。弘友は、自宅の門外に、千
代若をそっと寝かすと、自分は、傍らに身を隠して様子を窺いました。
やがて、暁方になって、番犬がしきりに吠えるので、番の者が出てみると、捨て子が
あるではありませんか。抱き上げてみると、弥彦のお守りを身に付けています。はっと
思った番人は急いで、秋弘に伝えました。秋弘が門に出てみると、疑いも無い千代若です。
「どこへ連れて行ったのかと思っていたが、さては、この祖父に孫を育てよと、母が置
いて行き、母は、身を投げ死んだのであろう。むう、尤も尤も。どうして粗末にあつか
うことができようか。」
と秋弘は、御乳(おち)乳母(めのと)を沢山つけて、大切に育てるのでした。
弘友は、この様子を立ち聞いて安心すると、大変に喜びました。
この人々の有様は、哀れとも中々申すばかりはなかりけり
つづく