
テレビの番組を見ていると、最初から最後まで音が出っ放しである。
お喋りか奇声か音楽か擬音か終始音が出っ放しである。静と動もないし、強弱もないし、話と話の「間」もない。静寂を効果的に使う手法もあまり見ない。特に軽薄なバラエティー番組は早口でしゃべりまくり、終始騒ぎっぱなし、テンションあがりっぱなしであるが、その内容はほとんどない。おまけに、聴衆を模した笑い声やうなづきの言葉を効果音として入れているので、最初から最後まで音が途切れることがない。反対に音が途切れることがしらけることだと忌避して常に何かをしゃべりつづけようとしているようでもある。
最近の音楽もその傾向がある。
最初から最後まで同じ調子で同じリズムで歌詞も途切れることなく繰り出され、決して途切れることはない。間奏はあってもボーカルから楽器の独奏に変わるだけで音の太さは最初から最後まで寸胴でアップテンポの強烈な同じリズム(通常あわただしい8ビートか16ビート)で刻まれる。こんな曲は環境音楽にいいかもしれない。ちょっと年輩の人には騒がしいかもしれないが、BGMとして聞き流すにはもってこいである。急にピアニッシモになったりフォルテシモになったり、テンポが変わったり、曲間があったりでは気になってしまって落ち着かないことになる。ただし、反対の見方をすると誰も真剣に鑑賞しようとする人はいないことになる。
ずっと前に、コンサートに行ってレスピーギの「ローマの松」を聴いた。
昔、私は吹奏楽とオーケストラをやっていたので自分でも実際に演奏したことのある曲で懐かしかったが、最初のピアニシモから始まって最後に壮大なフォルテシモで盛り上がる感動は格別のものである。久しぶりに堪能した。会場は札幌のコンサートホール「キタラ」だったが、最後はパイプオルガンも加わって、思わず顔をステージから天井のほうに向けて上方から降り注ぐ音響のシャワーに聴き入ってしまった。同じような感動を呼ぶ作品でワグナーの「エルザの大聖堂への行進」というのもあるのも思い出して家へ帰ったらCDで聴き直してしまった。
最初から最後までガチャガチャと単調なリズムで流されるものは、
反対にすんなりと聞き流すことができる。単なる退屈や寂しさを紛らわせ静けさを打ち消して景気をつけるためだけのものになってしまう。何らかの主張があり単調を乱すものは気になってしまって聞き流すことができなくなってしまう。「鑑賞する」とは、何かを主張するものに対して行われるもので、何を主張しているのかを解き明かすために「鑑賞する」のである。
隙間を埋め尽くしてしまう現代の文化は、なんだか異常である。
全てを均質のものにしてしまう。何にもない空間を許さないし、凸凹や山谷や強弱や大小をも許さない。均質なものの中で個人が抵抗する唯一の手段は「独り言」であろうか。誰に語りかける訳でもなく不特定多数に「独り言」を言いつづける。この頃、テレビのコマーシャルにこんなのが多くなっている。時にはこの独り言が「呪文」のように響く。あたかも群集の真中で誰かに対して大声で携帯電話をかけているような異様な雰囲気をかもし出す。これもまた病的である。大衆に影響を与え感動を与え行動を起こさせるほどの力はないし、そのために努力する気概もない。当然その内容に賞賛に値する価値もない。
現代人は孤独感と疎外感に苛まれているが、
反対に周囲の人達と真剣に関わるのは嫌っているようである。それを満たすのが「隙間を埋め尽くす文化」かも知れない。静寂と孤独の中では耐えられなくて人間との交わりを熱望しているが、真正面から対峙すると顔をそらして逃げ出してしまう。そういう意味では隙間を埋め尽くす文化(テレビ番組や音楽)は癒しと安らぎを与えてくれるのではないかと思う。もしかしたら、このような「隙間を埋め尽くす文化」が反対に真剣な人間関係を避ける人達を生んでいるのかもしれない。そして今度はテレビの中でそのような人達が大衆に向かって独り言をつぶやいているような気がする。私には奇異な感覚を呼び起こしてしまう。

















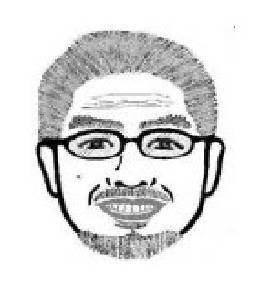





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます