新聞やテレビの報道を見ているとカタカナ用語が飛び交っている。
なぜカタカナにしなければならないのかを考えてみると、国外からの受け売りであることに気付く。「ある国がやっているから日本もやるべきである。」「世界で問題になっているから日本でも対策しなければならない。」「どこかの国でうまくやっているので日本でも取り入れるべきである。」と言うような感じであろうか?だから出発時点ではカタカナ用語で表現される。日本人が自分たちで案出したものではないからである。
そして、カタカナ用語が独り歩きを始める。
新しく取り込んだカタカナ用語には日本の国としての考え方は何もないのである。一生懸命にカタカナ用語のお勉強が始まり、ああでもないこうでもないといじくりまわし始める。そして、あらぬ方向に突っ走ってしまう。なにせカタカナ用語の中身が日本国内にないのだからどんな風に解釈しようとどんな風に使おうと勝手なのである。だいたいこんなもんだろうと思い込んで、周囲がこんな時にこんな風に使っているから私も使ってみようというような感じで気楽に口にしている。
何で日本語から出発しないのだろう。
それほど日本語が斬新性と信頼性と表現性に欠けているのであろうか?私はそう思わないし、カタカナ用語は日本語で何と言えばいいのだろうとまず最初に考えなければならないのだろう。日本語にもカタカナ用語に相当する意味を持った用語があるはずであり、日本的な発想を膨らませてカタカナ用語に匹敵する日本語の用語を使用すべきであり、そうであれば日本独特の伝統に基づいたしっかりとした考え方がその用語に備わっていくと思う。
借り物はあくまでも他人のものでこれを取り入れるのは物真似に過ぎない。
カタカナ用語が正にこれである。しかもカタカナ用語から出発しないと行動に移せないということは、最初から他人の物真似から出発しているのである。そこには新規性も独創性も独自性も全くない。どこからか他国のカタカナ用語を見つけてきて、さも最新のもののように流行させようとしているが、はっきり言って中身は全くない。言葉を先行させるのではなく、内容を先行させるべきであり、その内容は日本の文化に根差したものであるべきである。日本の文化として取り入れるべきなのである。
カタカナ用語の意味が解らないので用語の解説がある。
用語の解説は当該外国語からの翻訳である。このカタカナ用語はこんな意味であると定義している。なんだか笑い話である。それは日本語で何と言うんだと突っ込みたくなるし、本当に日本語にない概念であれば、いずれかはその概念に日本語としてふさわしい名前を付けてやらなければならない。昔の人達はしっかりとそれをやっていたのに何で現代の日本人はこれができなくなったのだろう。
何も考えないで受け売りしている弊害である。
どこからか見つけてきた知識を受け売りしているだけの文化になりつつある。自分達で独自に作り出して世界に発信していこうという気概に欠けているのである。だから政治も経済も科学技術も文化も教育も廃れるばかりである。日本は貿易立国として成り立ってきた。外国から原油・鉱石等の鉱産物、また原材料の類を輸入して国内で加工し、製品を輸出して得た利益で国の経済を維持してきた。輸入したものをそのまま横流しして輸出したのでは意味がないであろう。
カタカナ用語も同じである。
少なくとも取り入れたものは日本国仕様に作り直してこれらを組み合わせて新たな日本の考え方として世界に発信していかなければならない。また、世界に発信できるほどの価値のあるものを作り出してゆかなければならない。昔は具体的な物として原材料を輸入して具体的な物として製品を輸出していたが、これを考え方や知識や技術や思想・文化に置き換えて考える必要がある。昔の加工貿易の本質さえ無くしてしまった「カタカナ用語」である。是非猛省を促す。
今朝の新聞の一面に「フレイル」と言う言葉が躍っていた。
政府が公式に「フレイル」と言うカタカナ用語を使用しているようである。「フレイル」って何だ?カタカナ用語にしなければならないの?「フレイル」と言えば新しいことが始まると感じられるし、そのことを強調して政策として打ち出そうとしているのだろう。こんなところから勘違いが始まる。「寝たきり老人対策」でいいではないか。「寝たきり老人」の言葉が悪いのであればそれに代わる言葉を考えればいいのである。
私はフレイルと言えば別のことを思い浮かべる。
シェークスピアのハムレットの「弱き者よ汝の名は女なり(Frailty, thy name is woman)」である。ただの「フレイル」を用語として定義して何の意味があるのだろう。「フレイルとは加齢により心身が老い衰えた状態のことです。」とある。違うだろう。フレイルそのものにそんな意味はない。老年医学の分野で使用されているだけである。フレイルとは「壊れやすいもの」です。このようにして「Frail」そのものの意味さえ理解せずにカタカナ用語が独り歩き始める。ロコモシンドローム、ハラスメント、ストーカー、インバウンド、アセスメント、ヘイトスピーチなどなど挙げればきりがない。
75歳以上に来年からフレイル検診などを始めるという。
何のことだかフレイルだけではわからない。しかも内容は後ろ向きの意味が強い。もっと前向きに考えられないものだろうか。老人に美しく齢を取ってもらいたかったら「美齢検診」でもいいではないか。フレイルと言わなくても日本語に「老衰」と言う言葉もある。老衰防止対策でもいいではないか。年をとってもなおも健康である「老健」と言う言葉もある。老衰を防止して老健であって美齢を追及できれば十分にフレイル対策となるだろう。「健康寿命」と言う言葉は私的には素敵であり、久しぶりのヒット作だと思っている。
最新の画像[もっと見る]
-
 議員先生と学校の先生との違い
3年前
議員先生と学校の先生との違い
3年前
-
 SDGsともったいない精神
3年前
SDGsともったいない精神
3年前
-
 発想の転換
4年前
発想の転換
4年前
-
 発想の転換
4年前
発想の転換
4年前
-
 ワンニャン仲良し
18年前
ワンニャン仲良し
18年前
-
 ワンニャン仲良し
18年前
ワンニャン仲良し
18年前











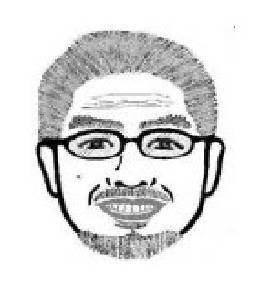






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます