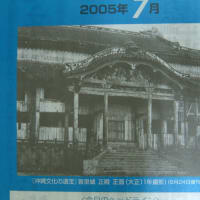レアアースなかりせばのカセットウォークマンにあちこちで訃報がが話題提供元。
もうカセットのウォークマンなんて生産終了しただろうと思ったけど、まだ続いていたんだと改めて実感した。日本では生産終了。アジアや一部欧米では生産を続けるとか。そもそもカセットウォークマンは1979年から発売開始。当時はかなり大きかったはずだ。これが、我が家にやってくるのは、10年はかかったはずである。実家で一番最初に買ったのは父親だった。かなり上位機種であったらしく、音楽を聴くという本来の機能のほかに、ラジオや集音型の録音装置を持っていた。ただし、結構壊れやすく、しょっちゅう修理に出していたように思う。
私は何かの景品で、ただ再生を行うだけのウォークマンをもらったことがある。高校に入ったくらいか。確か機能は再生と早送りだけ。繰り返し聞かなければならない時は、テープを取り出して鉛筆で巻き戻しを行ったいた。すでに周囲はそれなりのウォークマンを持っていたので、そんなものを見せたとたん、大笑いされた。
そんな父親の姿を見ていたというのもあるけど、私が本格的なウォークマンを欲しがったときに示した機種は、ワイヤレスタイプのウォークマンだった。(写真は「とあるソニー好きなエンジニアの日記」さんから)

あまり酷使しなかったというのもあるけど、結構耐久性があった。たしか故障してサービスセンターに持ち込んだのは、一回だけ。これを学校の行き帰りに聞いていたと思う。友人にも見せたが、「大きいね」と言われた。もうすでに、それなりの小型化(といっても今のiPodとは大違いだが)がウォークマンの中でも始まっていたが、その大きさは一回り以上大きかった。しかし、レシーバーと本体は分離していたので、そんなことはこの際関係ない。レシーバーを友人に貸して聞かせていることを忘れて、本体の鞄を持ってうろうろした時は、友人が怒りだした時がある。
それでも本体接続型のウォークマンは大きかった。もちろんだ。カセットテープよりも小さく作れないからだ。それでも結構聞いていたと思う。高校を卒業して二年浪人したが、その時も持ち歩いていた。当時、S台予備校に通っていたが、大阪南校は南の堀江にあったが、心斎橋筋の西側、さらにアメリカ村の西側にあって、今日でこそそれなりのブティックなどが建ち並んだおしゃれな街になっているが、当時はただの倉庫街だった。さらに言うとバブルがはじけた後だったから、なおさらうらぶれた感があった。
それでもかなり工事は遅れていたみたいだが、周辺の再開発が進んでいて、空き地ばっかりでもあって、都市が行き着くとこまでいったという印象があった。夕闇がおりたその風景を、永井真理子のChangeを聞きながら眺めるのが好きだった。
なんとか大学に入ったあとは、普通音楽との付き合いが深くなるはずなのに、逆に疎遠になっていった。家では痴呆の進んだ祖父が大変なことになっていたが、ラジカセをつけると決まって、ウロウロするのである。どれだけ音をしぼっても、ウロウロしだすのである。これが結構なストレスに転じた。そのために音楽を聴くことがなくなっていったのだと思う。
その他にも、レンタルで借りてきたCDをラジカセ経由でカセットに録音する。ただし、テープの時間は決まっていて、どこで切れるかはわからないので、一曲一曲計算しなければならない、録音してもタイトルの情報が残らないので、いちいち書き写さなければならない。下手したら、レンタルショップで歌詞カードすら貸してくれないこともある。
実は、こうした煩わしさをいっぺんに解消したのがインターネットとiTuneであった。今じゃインターネットでググればタイトルも歌詞も簡単に出すことが出来るし、iTuneにCDを取り込めば、たいていCDの情報をどこからか引っ張ってくるのだ。まして店先で聞いた曲の一部を検索サイトに入れれば、だいたいそれを見つけることができる。ただ、それはかなり後の話。
レンタルのショップも遠いわで、そりゃあかなり疎遠になっていく。バブルの頃にレンタルショプが流行ったのは、既にお金を出してCDを買うという行為が忌避されだしていたことを示している。たしかに今でこそ、CDを買うひとがいるし、当時もやたら持っている友人はいたけど、あのカネ余りの時代にしてみても、3000円少しのCDにカネを投じるのは、それなりに勇気がいったのだ。
学部2回のとき、電車の中でとなりに座った国文科の友人が、CDウォークマンを持っていた。しかし、私はこれがそれほど魅力的に写らなかった。というのも、既にカセットのウォークマンでそれなりに「大きすぎる」と感じていたところへ、あのCDの大きさである。もちろんワイヤレスではなく、本体とつないだコードがある。当時はカセット式のウォークマンでも携帯して音楽を聴くのには、それなりの工夫が必要だった。みんなは鞄からコードを出していたり、上着やズボンのポケットに放り込んでいたが、落としそうで、壊しそうでと言った具合だった。中には小さな巾着にいれてズボンのベルトにつけていたのもみたが、お義理にもカッコいいとは良いがたい。
結局、音楽をどんな形におさめてあるかで、大きさが変化してくる。そうこうしているうちにMDが出てきた。これがいったいいつ頃登場したのかさっぱりわからないので今回調べてみることにした。
・・・とはいっても、早いとこ書き終えて、部屋を掃除して勉強しなければならないのだが。
結果、またまた「ソニー」の名前を拝む結果になった。ウィキペディアの結果を編集してみよう。
ミニディスク (MiniDisc) とはソニーが1992年に発表したデジタルオーディオ記録用の光学ディスク媒体およびその規格である。略称はMD(エムディー)。アナログコンパクトカセットを代替するという目標が開発の背景にあった。しかしコンパクトカセットについては2010年現在でも根強い需要があり、市場では完全な代替には至らずコンパクトカセットとMDの両方を搭載したラジカセやミニコンポなどが販売されている。
CDが世界に広く普及したのに対し、MDは日本市場のみに普及した。事実上、MDは日本独自のメディアフォーマットであるといえる。
当初ソニーが日本国外向けにウォークマンのみならず据置型デッキ・ミニコンポ・カーオーディオ機器を開発・発売し、オーバーシーズモデルのカタログにも掲載されその中には完全な日本国外専用モデルも存在したが、ソニー以外の他メーカーの参入はほとんどなく現在はHi-MDウォークマン・MZ-M200が販売されているのみである。
その結果、現在販売されている日本国外向けオーディオ機器はCDとコンパクトカセットが主流である。
2010年現在、iPodやメモリータイプのウォークマンなどのデジタルオーディオプレーヤーの普及によりMD市場は衰退の一途をたどっている。特にポータブルMDプレーヤーに関しては2007年3月以降パナソニックを皮切りに各メーカーが次々と生産、販売から撤退し、ソニー製の録音・再生対応Hi-MDウォークマン、MZ-RH1が唯一現行機種としてカタログに残っているが、2009年10月頃に、一部の販売店では取り寄せ不可になった(SONYの直販サイト、ソニースタイルでは購入できる)。
実家でMDコンポを導入したのは妹だった。2000年頃だったと思う。それで彼女はいろいろレンタルで借りてきたCDをダビングしていたが、私自身は使いにくさを感じた。音楽は取り込めても、タイトルなどの周辺情報まではどうしても取り込めない。ましてMDの編集が効くから、こうした周辺情報はなおさら重要になるからだ。就職した年の2003年、私はMDウォークマンを買うことも考えたし、周囲は結構持っていたけど、結局買わなかった。
すでにiPodが登場していたが、当時はかなり高価に思えた。これを手に入れるのは少し先の話である。
もうカセットのウォークマンなんて生産終了しただろうと思ったけど、まだ続いていたんだと改めて実感した。日本では生産終了。アジアや一部欧米では生産を続けるとか。そもそもカセットウォークマンは1979年から発売開始。当時はかなり大きかったはずだ。これが、我が家にやってくるのは、10年はかかったはずである。実家で一番最初に買ったのは父親だった。かなり上位機種であったらしく、音楽を聴くという本来の機能のほかに、ラジオや集音型の録音装置を持っていた。ただし、結構壊れやすく、しょっちゅう修理に出していたように思う。
私は何かの景品で、ただ再生を行うだけのウォークマンをもらったことがある。高校に入ったくらいか。確か機能は再生と早送りだけ。繰り返し聞かなければならない時は、テープを取り出して鉛筆で巻き戻しを行ったいた。すでに周囲はそれなりのウォークマンを持っていたので、そんなものを見せたとたん、大笑いされた。
そんな父親の姿を見ていたというのもあるけど、私が本格的なウォークマンを欲しがったときに示した機種は、ワイヤレスタイプのウォークマンだった。(写真は「とあるソニー好きなエンジニアの日記」さんから)

あまり酷使しなかったというのもあるけど、結構耐久性があった。たしか故障してサービスセンターに持ち込んだのは、一回だけ。これを学校の行き帰りに聞いていたと思う。友人にも見せたが、「大きいね」と言われた。もうすでに、それなりの小型化(といっても今のiPodとは大違いだが)がウォークマンの中でも始まっていたが、その大きさは一回り以上大きかった。しかし、レシーバーと本体は分離していたので、そんなことはこの際関係ない。レシーバーを友人に貸して聞かせていることを忘れて、本体の鞄を持ってうろうろした時は、友人が怒りだした時がある。
それでも本体接続型のウォークマンは大きかった。もちろんだ。カセットテープよりも小さく作れないからだ。それでも結構聞いていたと思う。高校を卒業して二年浪人したが、その時も持ち歩いていた。当時、S台予備校に通っていたが、大阪南校は南の堀江にあったが、心斎橋筋の西側、さらにアメリカ村の西側にあって、今日でこそそれなりのブティックなどが建ち並んだおしゃれな街になっているが、当時はただの倉庫街だった。さらに言うとバブルがはじけた後だったから、なおさらうらぶれた感があった。
それでもかなり工事は遅れていたみたいだが、周辺の再開発が進んでいて、空き地ばっかりでもあって、都市が行き着くとこまでいったという印象があった。夕闇がおりたその風景を、永井真理子のChangeを聞きながら眺めるのが好きだった。
なんとか大学に入ったあとは、普通音楽との付き合いが深くなるはずなのに、逆に疎遠になっていった。家では痴呆の進んだ祖父が大変なことになっていたが、ラジカセをつけると決まって、ウロウロするのである。どれだけ音をしぼっても、ウロウロしだすのである。これが結構なストレスに転じた。そのために音楽を聴くことがなくなっていったのだと思う。
その他にも、レンタルで借りてきたCDをラジカセ経由でカセットに録音する。ただし、テープの時間は決まっていて、どこで切れるかはわからないので、一曲一曲計算しなければならない、録音してもタイトルの情報が残らないので、いちいち書き写さなければならない。下手したら、レンタルショップで歌詞カードすら貸してくれないこともある。
実は、こうした煩わしさをいっぺんに解消したのがインターネットとiTuneであった。今じゃインターネットでググればタイトルも歌詞も簡単に出すことが出来るし、iTuneにCDを取り込めば、たいていCDの情報をどこからか引っ張ってくるのだ。まして店先で聞いた曲の一部を検索サイトに入れれば、だいたいそれを見つけることができる。ただ、それはかなり後の話。
レンタルのショップも遠いわで、そりゃあかなり疎遠になっていく。バブルの頃にレンタルショプが流行ったのは、既にお金を出してCDを買うという行為が忌避されだしていたことを示している。たしかに今でこそ、CDを買うひとがいるし、当時もやたら持っている友人はいたけど、あのカネ余りの時代にしてみても、3000円少しのCDにカネを投じるのは、それなりに勇気がいったのだ。
学部2回のとき、電車の中でとなりに座った国文科の友人が、CDウォークマンを持っていた。しかし、私はこれがそれほど魅力的に写らなかった。というのも、既にカセットのウォークマンでそれなりに「大きすぎる」と感じていたところへ、あのCDの大きさである。もちろんワイヤレスではなく、本体とつないだコードがある。当時はカセット式のウォークマンでも携帯して音楽を聴くのには、それなりの工夫が必要だった。みんなは鞄からコードを出していたり、上着やズボンのポケットに放り込んでいたが、落としそうで、壊しそうでと言った具合だった。中には小さな巾着にいれてズボンのベルトにつけていたのもみたが、お義理にもカッコいいとは良いがたい。
結局、音楽をどんな形におさめてあるかで、大きさが変化してくる。そうこうしているうちにMDが出てきた。これがいったいいつ頃登場したのかさっぱりわからないので今回調べてみることにした。
・・・とはいっても、早いとこ書き終えて、部屋を掃除して勉強しなければならないのだが。
結果、またまた「ソニー」の名前を拝む結果になった。ウィキペディアの結果を編集してみよう。
ミニディスク (MiniDisc) とはソニーが1992年に発表したデジタルオーディオ記録用の光学ディスク媒体およびその規格である。略称はMD(エムディー)。アナログコンパクトカセットを代替するという目標が開発の背景にあった。しかしコンパクトカセットについては2010年現在でも根強い需要があり、市場では完全な代替には至らずコンパクトカセットとMDの両方を搭載したラジカセやミニコンポなどが販売されている。
CDが世界に広く普及したのに対し、MDは日本市場のみに普及した。事実上、MDは日本独自のメディアフォーマットであるといえる。
当初ソニーが日本国外向けにウォークマンのみならず据置型デッキ・ミニコンポ・カーオーディオ機器を開発・発売し、オーバーシーズモデルのカタログにも掲載されその中には完全な日本国外専用モデルも存在したが、ソニー以外の他メーカーの参入はほとんどなく現在はHi-MDウォークマン・MZ-M200が販売されているのみである。
その結果、現在販売されている日本国外向けオーディオ機器はCDとコンパクトカセットが主流である。
2010年現在、iPodやメモリータイプのウォークマンなどのデジタルオーディオプレーヤーの普及によりMD市場は衰退の一途をたどっている。特にポータブルMDプレーヤーに関しては2007年3月以降パナソニックを皮切りに各メーカーが次々と生産、販売から撤退し、ソニー製の録音・再生対応Hi-MDウォークマン、MZ-RH1が唯一現行機種としてカタログに残っているが、2009年10月頃に、一部の販売店では取り寄せ不可になった(SONYの直販サイト、ソニースタイルでは購入できる)。
実家でMDコンポを導入したのは妹だった。2000年頃だったと思う。それで彼女はいろいろレンタルで借りてきたCDをダビングしていたが、私自身は使いにくさを感じた。音楽は取り込めても、タイトルなどの周辺情報まではどうしても取り込めない。ましてMDの編集が効くから、こうした周辺情報はなおさら重要になるからだ。就職した年の2003年、私はMDウォークマンを買うことも考えたし、周囲は結構持っていたけど、結局買わなかった。
すでにiPodが登場していたが、当時はかなり高価に思えた。これを手に入れるのは少し先の話である。