東京地方裁判所 昭和46年(行ウ)158号 判決
原告 内藤一子
被告 農林漁業団体職員共済組合
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告に対し、昭和四五年一一月三〇日付でなした原告の農林漁業団体職員共済組合法に基づく組合員内藤三郎にかかる遺族給付請求を却下する決定を取消す。
2 被告は原告に対し、組合員内藤三郎にかかる農林漁業団体職員共済組合法に基づく遺族給付を全額支給せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 原告の請求原因
1(一) 原告は被告に対し、昭和四五年六月二日、農林漁業団体職員共済組合法(以下、「共済組合法」という)四六条、二四条に基づき組合員内藤三郎(以下、「三郎」という。)にかかる遺族給付の支給を求める申立をしたが、被告は原告に対し、同年一一月三〇日右遺族給付請求を却下する旨の決定(以下、「本件却下決定」という。)を行つた。
(二) 原告は農林漁業団体職員共済組合審査会(以下、「審査会」という。)に対し、昭和四六年一月二二日、右却下決定につき審査請求をしたが、同審査会は同年三月二二日、右審査請求棄却の裁決を行い、右裁決書は同月二四日、原告の代理人安西義明に送達された。
2 しかしながら、本件却下決定は、原告が以下のとおり遺族給付の支給要件を充足しているにもかかわらず、事実を誤認して原告の遺族給付請求を却下した違法があるから取消されるべきである。
(一)(組合員の死亡)
三郎は昭和四三年八月四日死亡したが、右死亡当時、農林漁業団体職員共済組合員であつた。
(二)(組合員の配偶者)
原告は三郎と昭和五年九月四日婚姻(同日届出)し、四人の子供(百合子、隆介、天津男、美智子)をもうけた。
しかるに三郎は、昭和四〇年七月五日、原告に無断で原告との間に協議離婚が成立した旨の内容虚偽の協議離婚届を偽造して静岡県袋井市役所戸籍係に提出し、同係は同日付で右離婚届を受理した。
次に、三郎は同月二〇日付で中嶋とみ子と婚姻した旨の届出をし、同月二四日右中嶋の子、中嶋信夫、中嶋香代子を養子とする旨の養子縁組の届出をした。
その後、原告は右の事実を知り、直ちに、三郎等を相手方として昭和四一年七月一四日、東京地方裁判所八王子支部に「協議離婚届出の無効確認及び三郎と中嶋とみ子(当時戸籍上は内藤とみ子)間の婚姻取消を求める調停申立」をし、次いで三郎死亡後の昭和四三年八月二九日、東京地方裁判所に検察官及び右とみ子らを被告として、協議離婚無効確認及び三郎ととみ子間の婚姻の取消、三郎と前記信夫、香代子間の養子縁組無効確認の訴訟を提起し、右事件は昭和四三年(タ)第二九三号、同三一四号、同三一五号として係属し、審理の結果、昭和四五年三月一七日原告全部勝訴の判決があり、控訴なく確定した。
したがつて、原告は三郎と婚姻した昭和五年九月四日以降、同人が死亡した昭和四三年八月四日に至るまで、同人の配偶者であつた。
なお、本件遺族給付は昭和四五年一一月三日以降、中嶋とみ子に支給されているが、三郎ととみ子の間は法の保護に値しない重婚ないし重婚的内縁関係にあり、ことに公的性格をもつ遺族給付を、法が否定する関係にある者に末長く支給し、他方、法の認めた配偶者であり、三郎生存中は扶養請求権、死後は相続権を有する原告の遺族給付請求権を否定することは、法の根本理念に反し吾人の道徳観からも認めがたいところである。共済組合法二四条は反論理的に解釈されるべきではない。
(三)(組合員の収入による生計の維持)
(1) 遺族給付を受けるべき遺族が組合員の配偶者である場合は、農林漁業団体職員共済組合法二四条の改正経過及び死亡した組合員(夫)の地位、収入は配偶者(妻)の協力によつて得られたものであること等に照らし、同条に規定する「組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたもの」との要件は不要であるというべきである。すなわち、昭和三三年四月二八日公布(以下、「当初の法」という。)当時の条文は、次のとおりである。
「遺族年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員であつた者の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」
そして、配偶者については「死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者」(以下、単に「生計維持」という。)という要件は不要であつたのである。蓋し、もし配偶者にも「生計維持」を要件とするのであれば、右条文中の「並びに」という文言は不要な筈であり、このことは同法二五条(昭和三九年削除)の文理からも首肯できるところであつた。然るに、昭和三九年六月二三日法律第一一二号による同法の改正(以下第一次改正という)の結果、二四条は「遺族年金」を「遺族給付」に、「並びに子」を「子」と改められ、二五条は削除された。従つて、右第一次改正による二四条は次のとおりとなつた。
「遺族給付を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」
次いで、昭和四六年五月二九日法律第八五号による同法の改正(以下「第二次改正」という)によれば、同条は以下のとおりである。
「遺族給付を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫及び祖父母でその者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする」
ところで、右第一次改正により、同条中の「並びに」が削除された為、配偶者につき「生計維持」を要件とするか否かが不明となつたのであるが、右第二次改正の条文によれば、当初の法の意味にもどつていることは文理上明白である。本件は、右第一次改正法が適用される案件であるが、前記のとおり、同条を配偶者には「生計維持」を要件としていないと解するのが正当である。仮りに右の点を要件とするのであれば、従前配偶者について右の要件を必要としなかつたのに、第一次改正法で何故必要とするに至つたのか、その合理的根拠はなく、かような解釈は相互に協力扶助の義務を負う夫婦関係の本質からも首肯しがたく、第二次改正法で当初の法と同一の文言形式となつた点の説明にも窮することとなるであろう。従つて、共済組合法二四条は形式文理的に解釈してはならないのであつて、本件に適用されるべき第一次改正法も当初の法及び第二次改正法と同様に解するのが相当である。そうでなくして「当初の法から第一次改正法までの間」及び「第二次改正法以後」と、「第一次改正法条文存続中」とで取扱いを異にする如きは、結局法の下の平等に反し、憲法一四条に違反する不合理な解釈である。
(2) 仮に遺族が組合員の配偶者である場合にも右の要件が必要であるとしても、原告は以下のとおり、その要件を充足しているというべきである。
三郎は原告との結婚以前から女性関係の出入りが多く結婚後も素行の悪さは改まらず、原告(妻)以外の女性としばしば関係を持ち、家庭を省みなかつた。そのため家庭内における紛争が絶えなかつたところ、昭和二八年七月一三日、原告と三郎との間で、二人は別居すること、子供は原告が引きとること、三郎は養育費として子供が一八才になるまで月額六、〇〇〇円原告に支払うこと等を内容とする協約書を作成し、三郎は家を出たが同年一二月に原告の許にもどつた。そして、昭和三一年一一月末頃、三郎は家族のとめるのを振り切つて再び家を出たが、その時、原告に対し、警察庁恩給を受領させること、子供達には養育費を支払う旨を約した。これは、その名目は恩給、養育費であつても実体は原告とその子供達の生活費であつた。その後、原告は三郎から別紙(一)記載のとおり、昭和三九年三月に至るまで毎月五、〇〇〇円から八、〇〇〇円の送金を受けていたが、これでは足りないので、原告が三郎の勤務先を訪れ一、〇〇〇円とか二、〇〇〇円をもらい受け、ボーナス時には八、〇〇〇円ないし一五、〇〇〇円位を生活費として三郎が持参する等して受け取つていたが、その最終は三郎死亡の直前の昭和四三年六月のボーナス時で、その折、三郎は八、〇〇〇円を持参し原告に手渡した。その他、原告が受け取つたもので原告の記憶にあるのは別紙(二)記載のとおりであり、また、原告は三郎の前記警察恩給を引続き受け取つており、その金額は別紙(三)記載のとおり、昭和三七年一二月までは年額三五、二〇八円の割合であつたが、その後、逐次増額され、同四二年一二月からは年額九八、九二八円の割合となつた。また、昭和四三年八月四日、三郎の死亡後は恩給はなくなり、その代り恩給の約五分の三に当る額が原告に対する扶助料として現在も引き続き支給されている。
このようにして、三郎は家族を省みることなく女性関係において放埓な生活を送つていたが、他方、原告は子供達の養育のため筆舌に尽くしがたい程の苦労と努力をし、あるいは一介の労働者として、あるいは内職により、あるいは子供達と共に商売を営んだりして得た収入と、前記夫の収入の一部とによつて辛じて糊口を凌いでいたのであるから、原告は三郎の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたものというべきである。また、共済組合法二四条の「主としてその収入によつて生計を維持していた者」には不法な内縁関係者は含まないものというべきであり、その解釈基準は金額の大小に関係なく、かつ、現実に主としてその収入によつて生計を維持していた者に限らず、「法の理念や社会規範からみて主として生計を維持していたと解される場合」を含むものというべきである。
3 よつて原告は被告に対し、本件却下決定の取消と、共済組合法に基づく遺族給付の全額の支給を求める。
二 請求原因に対する被告の認否及び主張
(認否)
1 請求原因1の事実は全て認める。
2(一) 同2の(一)の事実は認める。
(二) 同2の(二)の事実は全て認めるが、原告が三郎の死亡した昭和四三年八月四日に至るまで、共済組合法二四条にいう「配偶者」であつたとの点は争う。なお、中嶋とみ子に対する遺族給付は原告の受給資格の有無に直接関係がないことである。
(三) 同2の(三)の(1)の主張は争う。但し、条文改正の経過は認める。同(2)の事実中、原告と三郎との間に昭和二八年七月一三日、原告主張のような協約書が作成されたこと、三郎はその時、家を出たが同年一二月には原告の許にもどつたこと、昭和三一年一一月末頃再度、三郎が家を出たこと、その際三郎が原告に対し原告主張のような約束をしたこと、その後、原告は三郎から別紙(一)記載のとおり送金を受けていたほか、ボーナス時には若干の仕送りを受けていたこと、別紙(二)記載のうち、原告が昭和三七年一二月下旬に一七五、〇〇〇円の次女の交通事故に関する補償金を受領したこと、原告が別紙(三)記載の割合で恩給を受け取つていたことは認めるが、その余の事実は不知。原告が三郎の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたとの主張は争う。
3 同3は争う。
(主張)
1 原告は自己が共済組合法二四条一項にいう「遺族」中の「配偶者」であると主張するが、これに該当するには組合員である三郎の「配偶者」であると共に、「組合員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた」ことを必要とするところ、原告は、以下のとおり、右二つの要件のいずれも具備していない。
2(組合員の配偶者)
(一) 共済組合法二四条一項にいう「配偶者」には「婚姻の届出をしているが事実上婚姻関係にないのと同様の事情にある者」いいかえれば、「届出による婚姻関係の実体が失われ固定化している者」は含まれないものというべきである。
すなわち、農林漁業団体職員共済組合(以下、「組合」という。)は、農林漁業団体の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて事業の円滑な運営に資することを目的とするものである(共済組合法一条)。したがつて、共済組合法に基づき支給される遺族給付は、組合員の死亡により生計の資を失う者に対する社会保障的性格を有する公的給付(その故に非課税とされる)であり、かつ、それはまた、組合員の収入によつて生計を維持している家族の生活が、組合員の死亡後においても保障されることによつて、在職中安んじて職務に専念しうることに役立たしめる趣旨で設けられたものである。
共済組合法に基づく遺族給付の性格及び趣旨は右に述べたとおりであるから、同法二四条一項にいう「配偶者」は、組合員の生活の実態に即応して判断すべきであつて、同条項が「配偶者」に「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(いわゆる「内縁関係」にある者)を含むことを明文で認めているのはこの趣旨に出るものである。したがつて、婚姻の届出はされていても、婚姻生活の実体が失われ、その状態が固定化しているような関係にある者は、同法二四条一項の「配偶者」には含まれないと解するのが制度の趣旨、目的に照らして正当である。
仮に、婚姻生活の実体が失われている者も婚姻の届出がある以上右の「配偶者」に含まれると解するとしても、組合員が他に内縁関係を形成しているときは、内縁の妻(又は夫)も「配偶者」に該当し、その場合遺族給付を受ける者は、組合員の死亡当時実際に共同生活を営んでいた者とするのが法が定める遺族給付の趣旨に照らし正当な解釈である。
(二) そこで、これを本件についてみると、三郎の死亡した昭和四三年八月四日当時、原告と三郎との婚姻生活は以下のとおりその実体を失つて形骸化していた。
すなわち、原告は昭和二〇年八月、三郎と共に中国より引揚げてきたが、引揚後の夫婦仲はいたつて悪く、昭和二六年頃には原告が子供を連れて家出し、実家に帰つたこともあつた。その後も夫婦の間にはいざこざが絶えず、昭和二八年七月頃、三郎の女性関係のため夫婦の仲は険悪となり、三郎の上司であつた荒川源三郎の仲介で夫婦別居の話合いが成立し、子供達は原告が引きとること、当時幼少であつた末娘の美智子(昭和二〇年四月四日生)の養育費として同女が一八才になるまで月額六〇〇〇円の仕送りをすること、三郎が原告に対しその取得する警察恩給の二分の一を与えること等を内容とする協約書(乙第四号証の一二)が作成されるに至つた。そして、右協約書の前文には「愛情の破綻」した旨を明示し、その趣旨とするところは戸籍上の離婚手続が除外されているだけで、実質的には両者の婚姻生活の解消を目的とするものであることは明らかである(同書一項及び三項)。そして三郎は家を出て外山福江と同棲したが、まもなく原告の許にもどつて来た。しかし、これで夫婦の間が円満になつたわけではなく、同じ家に住んでいながら実質的には別居同然の状態であつた。
その後、三郎は昭和三〇年頃から中嶋とみ子と親しくなり、昭和三一年一一月末頃、再び家を出ることになつたが、その際、原告と子供らが三郎を縛り上げるという事態まで発生した。三郎はその頃から熱海市に住んでいた右中嶋と同棲を始め、昭和三四年に三鷹市に、次いで立川市に居を移し、以来、死亡時に至るまで一〇年余にわたり右中嶋と夫婦同然の生活を営み、原告とはその間別居の状態が続いた。
ところで、三郎が原告の許を去つて中嶋と同棲するに至る直前に、原告と三郎との間に再度前記協約書の如きものが作成されたことはないが、三郎の兄の内藤信太郎や弟の鈴木豊の仲介により、前同様三郎が家を出て別居し、警察庁恩給を全て原告に与えること、末娘の美智子が一八才になるまで養育費として月額八〇〇〇円を原告に対し支給すること、ボーナス時に若干の仕送りをすること等の合意が成立した。そして、右警視庁恩給受領の承諾書(乙第五号証の二)には、終期を昭和三九年一一月三〇日と定めているが、これは、それが子供の養育費に当てるためであることを示すものであり、前記協約書第二項に相当する合意がその内容を変更して成立していること、その後における三郎の行動等からみて、今回の合意も、右協約書と同様事実上の離婚を意味するものと解せざるをえない。
以来、原告と三郎は別居し、三郎は原告主張のとおりの仕送り(別紙(一))を続け、ボーナス時には若干増額した金員を支給し、また、原告は三郎の警察恩給を原告主張のとおり代理受領していたが、右金額を合算しても、原告及び子供等四人の生活費というには極めて僅少な額にすぎなかつた。
その間、原告と三郎との関係は夫婦らしい接触は全くなく、三郎はもとより、原告自身も再び円満な夫婦生活にもどる意図があると見受けられる態度は、一切示しておらず、両者は事実上の離婚同然の状態にあつた。また、前記仕送りも、その実態は離婚した夫婦間での子供の養育費の支給であり、事実、末娘の美智子が成人して間もない昭和三九年頃には途絶えてしまつている。
以上の事実から判断すれば、原告と三郎の結婚生活は、昭和三一年一一月末以降、三郎の死に至るまで愛情関係は破綻し、戸籍上は夫婦であつても、その実体が失われ固定化していたのであつて、実質的には原告は三郎の「配偶者」といえない状態にあつた。
(三) 他方、三郎と中嶋とみ子との関係についてみると、二人は昭和三一年の暮頃から同棲を始めたのであるが、至極円満であつたばかりでなく、右中嶋は、住民票には世帯主三郎、未届の妻とみ子と登録されており、三郎の勤務先である東京都資源利用農業協同組合連合会(以下、「農協連合会」という。)に対する扶養家族の届出及び扶養手当、健康保険における被扶養者、税法上の扶養親族等の関係において、それぞれ妻として取り扱われていた。後に判決により取消、あるいは無効が確認されたものの昭和四〇年七月二〇日、三郎との婚姻届が受理され戸籍上の妻となるとともに、同月二四日、とみ子の連子二人と三郎との間に養子縁組の届出が受理された。また、三郎の葬儀、遺骨の埋葬等も中嶋が執り行つた。
以上のとおり、中嶋とみ子は三郎の親戚関係を含む社会生活の全般にわたつて三郎の妻として処遇され、かつ、行動しているのであるから、同人は共済組合法二四条にいう「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するものというべきである。
したがつて、仮に、婚姻生活の実体が失われた場合にも届出のある原告が同条項にいう「配偶者」に一応該当するとしても、遺族給付を受けるべき者は原告ではなく、実際に共同生活を営んでいた中嶋とみ子であるというべきである。
3(組合員の収入による生計の維持)
(一) 原告は遺族給付を受けるべき遺族が組合員の配偶者(法律上の妻)である場合は、共済組合法二四条に規定する組合員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していたものとの要件は不要であると主張するが、右の要件は遺族給付支給のための資格要件と解すべきであるから、原告の右主張は誤りである。
(二) 右の要件には、現実に組合員の収入が生活費の大部分を占めている場合が含まれることは当然であるが、被告はこのような場合のみが右の要件をみたすものと主張するのではない。仮に、遺族が組合員の死亡当時には組合員以外の者の収入によつて生計を維持していたとしても、組合員の収入がその家族の生計に当てられていなかつた事情が、一時的、臨時的な事由によるものであつたならば、既に述べた遺族給付制度の趣旨から見て、なお右の要件をみたすと解する余地はある。
しかしながら、主として組合員の収入によつて生計を維持されていないという状態が単なる一時的、臨時的なものではなく、それが近く解消するとは予想しえない場合においては、右の要件は充足されていないと解するのが制度の趣旨に合致する。
(三) これを本件についてみると、前述(2の(二)、(三))のとおり、三郎の死亡当時、その収入によつて生計を維持されていたのは三郎と中嶋とみ子(及びその子供)との生活であつて、原告ではなかつたことは明らかであり、かつ、この状態は一〇年余にわたつて継続していたものである。しかも、その状態が近く解消するとは到底考えられない状況にあつたから、原告は右の要件を充足していないものというべきである。
(四) なお、原告は三郎と中嶋とみ子との関係を反倫理的なものとして非難し、法の許さない重婚的内縁者である中嶋とみ子には公的給付である遺族給付を支給すべきではないと主張するが、三郎と右中嶋との関係が反倫理的なものであるかどうかは、右中嶋が受給資格を有するか否かの判断については格別、原告の受給資格の有無を左右するものではない。右中嶋に対する遺族給付の支給が適法ではないからといつて、反射的に原告の受給資格が肯定されるものではない。
したがつて、原告の右主張も失当である。
4 よつて、原告が共済組合法二四条の遺族給付を支給すべき遺族に該当しないことは明らかであるから被告がした本件却下決定には何らの違法はなく、また、原告が同法に基づく遺族給付の支給を求める申立は理由がないものというべきである。
三 被告の主張に対する原告の認否及び反論
(認否)
1 被告の主張1及び同2の(一)は争う。
2 同2の(二)の事実中、原告と三郎が戦後中国より引揚げてきたことは認めるが、引揚後の夫婦仲はいたつて悪く夫婦間にはいざこざが絶えなかつたとの点は否認する。昭和二八年七月頃、被告主張のような協約書が原告と三郎の間に作成されたことは認めるが、右協約書は荒川が作成したものであり、原告は同人から押印を求められ、四囲の状況からやむなく押印したのである。その時、原告と三郎の間には別居の話は出なかつたし、その後間もなく三郎は家にもどり、右協約書は原告に返された。三郎が昭和三一年一一月末頃、中嶋とみ子と同棲するため再び家を出たこと、及びその際、原告と息子が三郎を縛り上げたとの点は認めるが、その時の経過は次のとおりである。すなわち、三郎が女の許に行くというので母子一家をあげて三郎を止めたが、どうしても聞きいれず、暴れまわり荷物を持ち出そうとしたので、母子は家を出られては困ると考え第三者に説得してもらうべく、それまでの間、一時、三郎を縛つたことがあつたにすぎない。なお、この時荒川は全く関与していない。その後、三郎が右中嶋と同棲を始めたことは認める。三郎の兄の内藤信太郎や原告の弟の鈴木豊の仲介により原告と三郎との間に養育費の支給、恩給の受領等の話し合いが成立したことは認めるが、二人が別居することに同意した前記協約書を復活させるという話し合いはなかつたし、そもそも右協約書は昭和二八年七月作成のものであり、それから三年余を経た後になつて、同じ内容の合意が当然成立したとみる根拠はない。その後、三郎が被告主張のとおり仕送りを続けたこと、原告が警察恩給等を受領していたことは認める。三郎はもとより、原告自身も再び円満な夫婦生活にもどる意図があると見受けられる態度は、一切示していなかつたとの点は否認する。原告としては夫の女道楽は昔からのことであり、いずれ女に飽きたらもどつてくるであろうという考えを持つていたのである。もちろん離婚を承諾していたわけではなかつた。その他、原告が三郎の死亡当時、実質的にみて事実上離婚状態にあり、共済組合法二四条の「配偶者」とはいえないとの趣旨の主張は全て争う。
3 同2の(三)の事実中、三郎と中嶋とみ子の仲は円満であつたとの点は否認する。右中嶋はパチンコ遊びに熱中し、金がなくなると三郎の品物を質入れしたりしたため、三郎との間には争いが絶えず、中嶋母子で何回も三郎に対し暴力行為を行つたことがある。右中嶋が扶養家族及び健康保険において三郎の妻としての取扱いを受けるようになつたことは認める。但し、その時期は扶養家族については昭和四三年以降のことであり、健康保険については右中嶋が内藤姓に変つた昭和四〇年七月以降のことである。中嶋とその子供達について被告主張のような戸籍上の変動があつたとは認める。その余の被告の主張は全て争う。
4 同3の(一)、(二)、(四)の主張はいずれも争い、(三)の事実は全て否認する。
(反論)
1(組合員の配偶者)
(一) 「原告のような婚姻の届出がなされていても、婚姻生活の実体が失われ、その状態が固定化しているような者は配偶者とはいえず給付を受けえない」との被告の主張について次のとおり反論する。
(二) 仮に被告のように解するとすれば、組合員の意思が反道徳的、反法律的なものであつてもなお、組合員の意思に従つて受給者を決定せよということになり、例えば民法七三四条に違反するような近親婚の内縁関係があつた場合においても、組合員の意思を尊重するならこれらの不倫な内縁者が受給者となるが、このようなことは到底容認しがたい。また、夫が一方的に妻を捨て、他の女と共同生活を長期間していたというだけで妻に受給権がなくなると解すべきではない。蓋し、夫の一方的、かつ勝手な反倫理的行動によつて、妻の生活権が奪われてはならないからである。
(三) 仮に、被告主張の基準を採用したとしても、原告は依然として「配偶者」である。
すなわち、内縁者に受給権がある場合とは、例えば婚姻生活に入つたが、届出をしないうちに夫が死亡した場合とか、妻が死亡した後、夫が後妻をむかえたが婚姻届をしないうちに夫が死亡したというような場合であつて違法な重婚的内縁者にまで受給権があるとは到底いえない。したがつて、被告の主張する「届出による婚姻関係の実体が失われ固定化している」という状態は届出のある婚姻が夫婦間の明示又は黙示の合意によりその実体を失い、この事実上の離婚状態につき何らの争いも交渉もなく、他方、内縁者が夫婦と同一視できるような状態が安定し、固定的に継続している場合をいうのであつて、このような内縁者にしてはじめて受給権者とされるのである。単に、長期間共同生活を営んでいたというだけでは足りず、届出のある夫婦の間において、婚姻及び婚姻生活の実体を解消させることについての明示又は黙示の合意の存在が必須の要件である。
これを本件についてみると、原告は三郎との離婚に同意していないことは、既にその生存中の昭和四一年七月一四日、東京地方裁判所八王子支部に協議離婚無効確認等の調停申立をしていることによつて明らかである。原告としては三郎の放埓な女性関係を病的なものとして締めていたのであつて、離婚しようとの意思は持つていなかつたのである。
なお、原告と三郎の間に夫婦の性生活がなくなつたのは、原告が数度にわたり三郎から梅毒を感染させられ、昭和二六年一月発病した際、医師より「著しく悪性で今度感染させられると治療方法がないかもしれない」といわれたことによるものである。
したがつて、原告と三郎の関係を、被告主張のように婚姻生活の実体を失つた夫婦とみることはできない。
2(組合員の収入による生計の維持)
被告は「組合員の収入によつて、妻がその生計を維持されていないという状態が一時的、臨時的なものではなく、近く解消するとは予想しえない場合、妻には受給権がない」と主張するが、前述のとおり、単に不倫な共同生活が長期間存続したことを重視するべきではなく、また、「近く解消する」か否かはいわゆる男女間の今日あつて明日を知らない問題であるから、このようなあいまいな尺度で判定すべきではない。
第三証拠〈省略〉
理由
一 請求原因1及び同2の(一)、(二)の事実関係は当事者間に争いがない。
二 原告は農林漁業団体職員共済組合法(以下、「共済組合法」という。)による遺族給付の支給を求めているが、同法の遺族給付を受けるべき遺族の範囲は同法二四条に規定されており、同条は原告主張のとおり、同法が昭和三三年四月法律九九号(以下、「当初の法」という。)として公布されてから数次の改正を経ているところ、本件においては、給付事由が生じたのは組合員である三郎が死亡した昭和四三年八月四日であるから(同法四六条参照)、昭和三九年六月法律一一二号による第一次改正後のもの(以下、「第一次改正法」という。)が適用されることになる。
なお、昭和四六年五月法律八五号による本条の第二次改正(以下、「第二次改正」という。)は昭和四六年一〇月一日から施行され、右施行期日以後に給付事由が生じた給付について適用されるが、同日前に給付事由が生じた給付についてはなお従前の例によるとされている(附則一項及び五項)。
そこで、本件の争点は、原告が第一次改正法二四条一項にいう「組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、……で組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの」に該当するか否かにある。
この点につき原告は本条改正の経緯等に照らし、第一次改正法二四条一項にいう「配偶者」についても、当初の法及び第二次改正法と同様、組合員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたこと(以下、「生計維持」という。)は遺族給付の受給資格の要件ではないと主張する。
しかしながら、遺族給付の受給権者の範囲を画する右条項が、民法上相続人たりえない内縁者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)を明文で右条項にいう「配偶者」に含ませていることからも明らかなように、共済組合法による配偶者に対する遺族給付は、死亡した組合員又は組合員であつた者との間において社会通念上、夫婦としての生活共同体を現実に営み、その死亡によつて実際上、生計の資を失う者、すなわち、死亡した者への実質的な夫婦関係上の依存者の生活を保障する社会保障的性格をもつ公的給付であり、その給付要件は本来共同生活の実態に即して定められるべきであるから「生計維持」の要件を配偶者に必要と定め、かつそのように理解したからといつて、共済組合法による遺族給付制度の立法趣旨に副いこそすれ、何ら不合理な制度ないし解釈ということはできない。
もつとも、当初の法及び第二次改正後の二四条一項の規定の文言上、同条にいう「配偶者」については「生計維持」を要件とはしていないようにも読めるが、「配偶者」の場合は、他に列記されている組合員の子、父母、孫及び祖父母とは異なり、前記の意味における現実の共同生活を営むことが婚姻関係の通常の在り方であることに鑑み、組合員の収入により生計を維持していることはむしろ当然のこととされ、ことさらにこれを明記しなかつたものと解されるのであり、改正前後を通じ、その取扱いを異にしたとはいえずまた、この要件を「配偶者」に加えることによつて、前記のとおり、社会保障法としての共済組合法による遺族給付制度の立法趣旨がより生かされるものというべきであるから、前記解釈は違憲とはいえず原告の右要件を不要とする主張は採用しがたい。
なお附言するに、原告が主張の根拠とした当初の法の二五条は第一次改正で削除され、また、第二次改正法の二四条についても、昭和四八年九月法律八三号による第三次改正(本条全部改正)によつて第一次改正と同様の規定の体裁になつた(但し、同条一項一号に規定されることになつた。)。
三 そこで三郎死亡に至るまでの原告と三郎の婚姻生活及び三郎と中嶋とみ子との関係についてみるに、当事者間に争いのない事実及びいずれも原本の存在並びに成立につき当事者間に争いのない乙第一号証の六、同第三号証の六、同第四号証の一二及び二四、同第五号証の二、同第七号証、並びに証人荒川源三郎、同中嶋とみ子、同岡野百合子、同鈴木豊の各証言(但し、証人荒川、同鈴木の証言中、後記措信しない部分を除く)、原告本人尋問の結果(第一ないし第三回但し、後記措信しない部分を除く。)を総合すれば以下の事実を認めることができる。
1 原告は昭和五年九月四日、警視庁巡査の職にあつた三郎と結婚(同日婚姻届出)し、同一五年五月頃、巡査を辞した夫とともに二人の間に生まれた長女百合子、(同五年九月二五日出生)、長男隆介(同一〇年三月一二日出生)を伴つて中国に渡り、天津において二男天津男(同一六年六月二〇日出生)、三女美智子(昭和二〇年四月四日出生)をもうけた。
2 原告ら夫婦とその子供達四人は、終戦後の昭和二一年一月頃、一諸に中国から引掲げ、三郎は同二二年五月頃から東京都農業会国立支所(現在の名称、東京都資源利用農業協同組合連合会以下、「農協連合会」という。)に勤務し、家族と共に国立に居住することになつた。なお、三郎は死亡するに至るまで右農協連合会に勤務した。
3 それまでも女性関係の多かつた三郎は、昭和二七年五月頃から外山福江と親密な関係を結び、家庭を省みなくなつた結果、夫婦の仲は険悪なものとなり、原告と三郎は同二八年七月一三日に宗前清弁護士の原案になる「協約書」(乙第四号証の一二)を取りかわし、三郎は原告の許を去り外山福江と同棲するに至つた。
右協約書の内容は、まず、前文で、原告ら夫婦間において「愛情の破綻」をきたしたので以下の条件により別居生活をすることを協議決定し、これを証するために本協約書二通を作成したとして、協約事項は、
(1) 三郎は家庭を出て単独別居し、今後、双方とも相手方の生活に一切容喙しないこと。
(2) 二人の間の子供達は原告が引き取り養育するので三郎は子供達の養育料として、子供が満一八歳に達するまで月総額六〇〇〇円を毎月二一日、原告に支払う義務を負うこと。三郎の権利に属する警視庁恩給はその二分の一相当額を二期に分けて原告に分与すること。
(3) 戸籍上における地位は現在のまま持続するが両名の生活上の所持品は持分により区分すること。
(4) 原告及び三郎は本協定を履行する限り裁判を提訴しないものとする。
というにあつた。
4 その後、原告は昭和二八年九月一〇日離婚調停の申立てをしたが、同年一二月不調となつたけれども、その頃、三郎は原告の許へ帰り、再び、原告及び子供達と同居するようになり、昭和二九年八月には府中市貫井の都営住宅に家族全員で引越したが、この間も三郎と原告の間に夫婦の性関係はなく、三郎は家内では孤立し、外泊することがたびたびであつた。
5 その後、三郎は昭和三一年六月頃、当時熱海に住んでいた中嶋とみ子と知り合い、親密になつた。そして、同年一一月二一日頃、再度家を出ることを決意し、同日午前八時頃荷物を持ち出そうとしたが、その際原告には、三郎を子供達と協力して縛るなどの行動があつたため、三郎は同日夜、静岡県袋井市居住の三郎の兄の内藤信太郎に電報で来宅を求め、翌二二日頃、右信太郎は近くに住む原告の弟鈴木豊を誘つて府中市の原告方に赴き、二人が間に入つて説得を重ねたが、結局三郎の家を出る決意は固く両者は「いずれ別れよう」「そうしよう」という趣旨の応酬を重ね到底同居の見込みがなかつたので、別居の前提として、末子美智子が一八歳になるまでの原告による養育料の支給等が協議された。その後、三郎は府中の家を出て、都内文京区西片町の平野方に身を寄せた如く、同月二八日妻との性生活の長年にわたる欠如、家庭内の不和、虐待等を理由に離婚を希望する旨の「離婚に関する調停の御願い」と題する書面(乙第四号証の二四)を作成したが、その翌々日にあたる同月三〇日、自己の警察恩給を同日以降昭和三九年一一月三〇日まで原告が直接受領することを承諾する旨の承諾書(乙第五号証の二)を作成して原告に交付した。そして、その頃、子供が一八歳になるまで月額八〇〇〇円の養育費の仕送りをするほか、年二回のボーナス時には若干増額支払いをすることを約した。やがて、三郎は中嶋とみ子と同棲を始め、死亡する同四三年八月四日に至るまで右中嶋とその連れ子である信夫、香代子と共に生活し、その間、一度も原告の許に帰り宿泊することはなかつた。
6 中嶋とみ子と同棲を始めた後、三郎は原告との前記約束に基づいて、同三二年初め頃から当初は毎月八、〇〇〇円を、次男天津男が一八歳になつた後の同三四年七月からは毎月約五、〇〇〇円をそれぞれ仕送り、末娘の美智子が一八歳になつた翌年の同三九年三月二四日に至るまで別紙(一)のとおり(但し、同三四年以降の分のみ記載されている。)の仕送りを続けたほか、年二回のボーナス時にはこれを若干増額していたこと、警視庁から支給されていた恩給は同三一年一一月以降、別紙(三)の割合で原告に全額受領させていたこと、また、同四三年八月四日の三郎の死亡後は右恩給はなくなり、その約五分の三に当る額が原告に対する扶助料として現在も引き続き支給されている。
なお、原本の存在並びに成立につき当事者間に争いのない乙第四号証の二七、二八及び成立につき当事者間に争いのない乙第一〇号証の一ないし三並びに原告本人尋問の結果(第二回)によれば、原告及びその子供達(隆介、美智子)は昭和三五年八月一七日付をもつて三郎の健康保険の被扶養者及び税法上の扶養親族から削除され、代つて中嶋とみ子とその連れ子である信夫、香代子が同年一二月一四日付をもつてその対象となつていることが認められる。
7 中嶋とみ子は昭和三二年頃から三郎と熱海市で同棲生活を始め、約二年後の同三四年夏三鷹市に、次いで同三九年一一月立川市にそれぞれ移り住んだが、その間同人は三郎の原告に対する前記送金を助けるため内職、派出婦等をして共に働き、二人協力して前記送金をしていたこと、また、前記のとおり、三郎の勤務先の健康保険や税法上の扶養親族の関係ではそれぞれ妻として取り扱われていたこと、同三九年二月頃、三郎は右中嶋を静岡県袋井市の自己の郷里に伴い、実母や親戚に対し、同人を新しい妻であるとして紹介したほか、昭和四〇年七月五日三郎が原告との間に偽造の離婚届を提出した後には、とみ子及びその子らと三郎との間に婚姻並びに養子縁組の届出がなされている。また、三郎の葬式は中嶋側で行われ、遺骨も右中嶋によつて手厚く葬られた。
8 原告は昭和三一年一一月二二日頃三郎と別居して以来、子供らと生活を共にし、三郎に対し毎月の仕送りを求める等の経済的要求を行つてはいるものの、中嶋とみ子との関係を清算し、再び正常な婚姻関係に復させるべく何らの働きかけもしていないばかりか、三郎の勤務先の上司であつた荒川源三郎が同三七、八年頃原告に対し、三郎を引き取り同居して旧に復してはどうかとの助言をしたが言を左右にしてこれに応ぜず、結果的にはこれを断つており、また、原告と三郎との性関係は昭和二六年頃から全くなかつた。
以上の事実が認められ、右認定に反する証人荒川源三郎、同鈴木豊の各証言、原告本人尋問の結果は措信しがたく他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
四 ところで、第一次改正法二四条一項所定の「配偶者」の意義如何であるが、同条が遺族給付を受けるべき遺族に属する配偶者につき、「組合員又は組合員であつた者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」で「組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者」と規定してあることに徴すれば、同条が定める配偶者の概念は、必ずしも民法のそれと厳密な意味で符合するものではなく、そこには共済組合法のもつ独自の理念や目的に照らし、これにふさわしい解釈をいれるべき余地があることが窺われること、一般に共済組合は、同一の事業に従事する者の強制加入によつて設立される相互扶助団体であり、組合が給付する遺族年金は、組合員がその組合に一定額の金銭を掛金として積立てておき(このほか、国の補助金がある)、その組合員が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付される年金であつてこれにより遺族の生活の安定と福祉の向上を図り、延いては業務の能率的運営に資することを目的とする社会保障的性格をもつ公的給付であること等に照らすと、右遺族の範囲は組合員の生活の実態に即してより現実的な観点から理解すべきであつて、これに属する「配偶者」とは、組合員との関係において、相協力して社会通念上、夫婦としての共同生活を現実に営んでいたものと解するのが相当であり、戸籍上届出のある配偶者であつても、その婚姻関係(法律婚)が実体を失つて形骸化し、かつその状態が固定化して近い将来解消されるみこみのないとき、いいかえれば、事実上の離婚ともいえる状態にある場合には、もはや右遺族給付を受けるべき「配偶者」には該当しないものというべきである。
五 以上の説示認定事実に基づいて判断するに、
1 昭和二八年七月一三日、三郎と原告は前認定の協約書(乙第四号証の一二)を作成のうえ事実上別居しているが(第一回別居)、前示認定の別居に至る経緯及び右協約書の内容を全体として考察すれば、当時、両者は届出こそしないが、事実上婚姻関係を解消することを合意したうえ別居するに至つたものと認められる。もつとも、同年一二月に至つて、三郎は原告の許に戻り、両者は再び同居を始めたことにより、前示協約書に示された婚姻関係を事実上解消する旨の合意は、両者間で一応失われたものと解するのが相当であるが、右同居を始めた後も、両者の夫婦としての性関係は一切もたれていないし、三郎はしばしば外泊を重ねていたこと前認定のとおりである。そして、昭和三一年一一月二二日頃、両者は再び別居するに至つた(第二回別居)。この際は、両者の間に前示協約書の如き書面は作成されていないけれども、三郎は原告に対して、昭和三九年一一月末日まで自己の警察恩給の受領権限を認める趣旨の承諾書(乙第五号証の二)を作成したほか、子供が一八歳になるまで月額八、〇〇〇円(一人宛四、〇〇〇円)の仕送りをし、ボーナス時にはこれを若干増額する旨の合意をなしたうえ別居しているのである。以上、第二回目の別居に至るまでの経緯、別居の態様、その際の合意の内容、別居後の両者の関係等に照らせば、三郎と原告の間には、第二回目の別居のときにも、第一回別居のときとほぼ同様の合意が成立していたものと推認するのが相当である(証人荒川源三郎の証言も上記認定判断と符合する)。
2 原告は前記認定の経済的給付を受け取つてはいたが、右は、前記認定のように三郎との別居の際の合意に伴う措置であり、三郎の右原告に対する経済的給付は、夫婦としての共同生活を廃止し、別居している原告に対する慰謝料、その子供達に対する養育費等事実上の離婚給付としての性格を有していたものとみるべきであり、それも子供達が皆自活するようになつた同三九年三月頃には送金は打切られ、別居に際して三郎が原告に対してなした約束は一応果し終つたものというべきであり、その頃、三郎は中嶋とみ子を新しい妻として郷里に連れ帰り親族に紹介している。
3 原告は三郎との婚姻関係を正常なものに回復しようとする何らの働きかけもしていないばかりか、前認定のとおり、昭和三七年頃には荒川の仲介による三郎との復縁を拒絶していることが窺われ、共同生活を伴う婚姻関係を維持継続していこうとする意思が第二回別居当初からなかつたと認められる。
この点につき原告本人は、三郎のこれまでの女性関係に徴し、今回もいつか帰つてくるであろうと締めていたにすぎないと供述するが、一〇年余に亘つて別居状態を継続し、中嶋とみ子との関係を黙認した事実からすれば、右はたやすく措信しがたいものというべきである。
以上、1ないし3の点を併せ考えれば原告と三郎の婚姻関係は昭和三一年一二月以降は事実上の離婚状態にあり、三郎が死亡した昭和四三年八月四日頃にはその婚姻関係は実体が失われて形骸化し、かつその状態が固定化していたものというべきである。
したがつて、原告は共済組合法二四条一項(第一次改正法)にいう遺族給付を受けるべき「配偶者」には該当せず、また前記認定事実により、組合員である三郎の「死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた」とは認めえないものというべきであり、右判断を覆すに足りる証拠はない。
よつて、原告が右遺族給付を受けるべき「配偶者」に該当することを前提に本件却下決定の取消と、右遺族給付の全額の支給を求める原告本訴請求はいずれも理由がない。
六 以上の次第であるから、原告の遺族給付請求を排斥した本件却下決定は相当であり、これが違法であるとしてその取消と、共済組合法に基づく遺族給付の全額の支給を求める原告の本訴請求はいずれも理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 安部剛 山下薫 高橋利文)










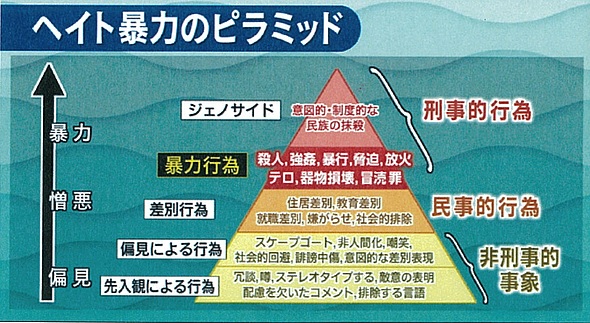

 ピンクの8番車が宿口選手
ピンクの8番車が宿口選手
 関東地区の若手選手から祝福される宿口選手。
関東地区の若手選手から祝福される宿口選手。




