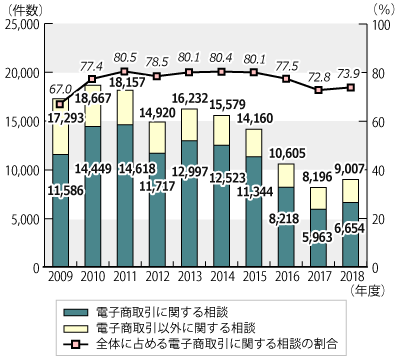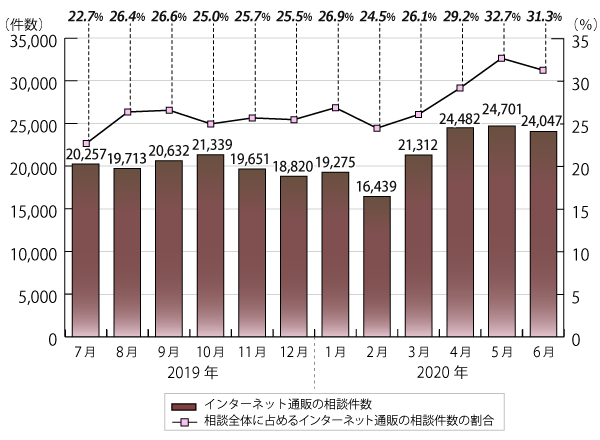9/22(火) 7:01配信
現代ビジネス
「最大5割程度の値下がりが期待できる」
先週水曜日(9月16日)に発足したばかりの菅義偉政権が、早くも目玉政策のひとつ「携帯電話料金引き下げ」の本格的なアピールに乗り出した。
「ペイペイの毒」に潰されたキャッシュレス企業…その残酷すぎる末路
総理就任2日後の18日、菅氏が官邸に武田良太総務大臣を呼び、トップダウンで値下げを急ぐよう指示したのである。
武田大臣は会談の直後に、「国民生活に直結する問題なので、できるだけ早く結論を出す」としたうえで、値下げ幅について「1割程度では改革にならない。海外では健全な競争を導入して70%下げたところもある」と語り、大幅な値下げの実現に強い決意を表明した。
そこで、筆者が取材したところ、総務省はすでにMVNO(仮想移動体通信事業者、「格安スマホ会社」のこと)を通じた大幅値下げに向けて布石を打っており、「今後3年程度の間に最大5割程度の値下がりが期待できる」と予測しているという。
だが、こうした値下げの加速を手放しで喜ぶのは難しい。というのは、過剰な値下げは、海外勢との技術革新を巡る日本の携帯大手3社の競争力を削ぎ、5Gや6Gといった次世代モバイル通信網の整備が遅れる恐れが出て来るからだ。
そうなれば、製造業やサービス業はもちろん第1次産業も含めた、すべての産業がアフター・コロナ時代の生き残りに不可欠なデジタル革命に乗り後れ、国民がその恩恵を享受できないリスクを膨らませることになりかねない。
「内外価格差」という言葉が存在することが示しているように、歴史的に見て、日本では、携帯電話に限らず、固定電話、電気・ガス、高速道路といったインフラの料金が高かったことは事実である。
筆者も、新聞記者だった1980年代から2000年代初頭にかけて、担当した金融、電気通信、放送のほか、電気・ガス、有料道路、鉄道など、日本の公共料金が押しなべて米国の2倍から8倍程度に達しているといった記事をいくつも書いた記憶がある。
「既得権打破」の思いは総務大臣時から
そうした中で、光ファイバー網を使った固定通信のブロードバンド分野で2000年代半ば頃までに、先進国で1、2位を争うほど日本の利用料金が大きく下がったのとは対照的に、携帯電話の料金引き下げは遅れてきた。このため、安倍前政権の誕生前から、総務省ではお役人主導で料金引き下げが何度も試みられてきた。
例えば、総務省が2007年6月に公表した「モバイルビジネス研究会」の報告書はそうした試みの一つだ。
この報告書には、料金引き下げの具体策として、「販売奨励金」の廃止・縮小を目指すことのほか、MVNOの参入を加速することや、携帯電話会社の乗り換えを容易にするSIMロックの解除を実現することなどが盛り込まれていた。
これは当時、携帯電話機のゼロ円販売などを可能にしていた販売奨励金の原資がユーザーの支払う通信料金だったことから、頻繁に電話機を買い換える人とそうでない人の間で不公平が生じているとのロジックによるものだ。
だが、当時は、どの施策も、携帯電話事業者だけでなく、携帯電話機を製造・販売していた家電メーカーなどの強い抵抗にあい、なかなか進展しなかった。その状況をつぶさに見ていたのが、当時、総務大臣だった菅総理だ。そうした状況に、菅氏が持論の既得権打破の思いを強めたことは想像に難くない。
携帯電話料金の引き下げは、その後も折に触れて、政治問題化した。2015年9月の経済財政諮問会議の場で、高市早苗総務大臣に携帯電話料金の引き下げを検討するよう指示したのが、安倍前総理だった。このことを記憶している読者は少なくないはずだ。
最近では、2018年8月に、官房長官だった菅総理が札幌市内の講演で、日本の携帯電話の利用料について「今よりも4割程度下げる余地がある」「競争が働いていない」などと述べた。
携帯電話料金は減少傾向だが…
Photo by GettyImages
その2ヵ月後の記者会見でも「3社でおよそ9割の寡占が続いており、競争がまったく行われていない」と繰り返し、同年11月発売の総合雑誌に「国民の財産である電波を使っているにもかかわらず、利益を得すぎている」とする論文を寄稿したこともよく報じられている。
2017年度の東京電力ホールディングスの売上高営業利益率が4.9%、同じく東京ガスが6.5%なのに対して、大手携帯電話3社の平均は20.4%で「過度な利益に走るのは不健全だ」と主張したのである。この主張は今とほぼ同じ論理である。
一方、激しい抵抗を見せた2000年代の値下げ議論の際とは違い、ここ数年の政治的な値下げ要請に対しては、携帯電話各社は相応の対応をしてきたと言って良いだろう。素知らぬ顔で無視していたわけでは決してない。
最も大きかったのは、NTTドコモが2019年6月に投入した2つの新料金プラン「ギガホ」と「ギガライト」である。これらは利用の仕方にもよるが、最大4割の値下げを実施するものだった。
ドコモはあの手この手の減収対策を打ったものの、この値下げの影響は大きく、2020年3月期の連結決算(国際会計基準)で、売上高(営業収益)が前期比4%減の4兆6512億円、営業利益が16%減の8546億円と業績が減収減益に陥った。ドコモの営業減益は5年ぶりという異変である。
こうした中で、一定の効果があったのだろう。総務省の消費支出調査を見ても、携帯電話の通信料と携帯電話機の合計金額は今年7月に1万872円と、2015年に現在の形での調査が始まって以来のピークとなった昨年5月(1万2073円)と比べて9.9%の減少を記録した。
猛烈な値下げ競争が実現したワケ
また、今年6月以降は、MVNOの安売り攻勢も目立っている。
例えば、日本通信というMVNOは7月15日から「合理的かけほプラン」をスタートした。このプランは、「もしもし」の音声通話がかけ放題のうえ、上限(容量)3ギガバイトまでのデータ通信も含めて、月額2480円(税別)という格安料金だ。
日本通信に通信回線を卸売りしているドコモで似たようなプランを契約すると、月額料金は5680円(昨年6月に値下げしたプラン)になる。つまり、日本通信はドコモの4割安どころか、半額以下だ。
そのドコモの料金は、すでに昨年6月に最大4割下がった料金体系に基づくものであり、日本通信の新料金の格安ぶりは際立っていると言っても過言ではない。
さらに、音声通話はいらない、高速データ通信も1ギガバイトまででよいという利用者には、月額480円というワンコインでお釣りが来るプランも登場した。これはインターネットイニシアティブ(IIJ)が8月から扱い始めたプランである。
この他のMVNOや、KDDI系のUQモバイル、ソフトバンクモバイル系のYモバイルといったサブブランド会社でも格安MVNOに迫るプランを提供するケースが相次いでいる。こうした格安サービスへは乗り換えが必要だが、それさえ厭わなければ消費者も相応のメリットを享受できるはずだ。
では、なぜ、この夏、MVNOやサブブランドで突然、こうした猛烈な値下げが実現したのか。そのカラクリこそ、冒頭で、筆者が「総務省の布石」と表現したものである。
実は、日本通信の新サービスは、ドコモが日本通信に卸す「もしもしの音声サービス」の接続料金について、総務大臣が6月に裁定を行い、「原価+適正利潤」で提供するよう命じたことが背景にある。従来は「小売り料金-営業経費=卸価格」だったが、この裁定を契機に、MVNOにはできなかった定額で廉価の音声サービス提供の道が開かれたのだ。
携帯大手3社に忍び寄る危機
Photo by GettyImages
さらに、総務省は、もう一つ布石を打っている。
格安スマホ会社に対するデータ通信の接続料について、今年度から「将来原価方式」という新方式に切り替えたのだ。これは、大手携帯電話会社側のコストが一定ならば、MVNOが扱う通信量が増えれば増えるほど接続料が下がる仕組みだ。
これにより、今後3年間で最大50%、つまり半分にデータ通信の接続料が下がるとの予測もある。仮に、接続料の低下分を全額サービス料金の値下げに注ぎ込むMVNOが現れれば、サービス料金が5割下がる可能性があるわけだ。
データ通信の接続料の低下が定着すれば、MVNOの泣き所だった、大容量の格安データ通信プランの登場も現実味を帯びる。2000年頃から高止まりが目立っていた携帯電話料金はようやく大きく下がる時期を迎えようとしている。
気掛かりなのは、総務省が調子づき、さらなる値下げ促進策の準備に余念がないことだ。固定ブロードバンドと携帯電話のセット販売や、スマートフォンでは実現できていないネットだけでの事業者の変更を可能にする方策などを視野に入れており、携帯電話会社の収益力を弱体化させるリスクが出ているのである。
菅総理が武田総務大臣を首相官邸に呼び、携帯電話料金の引き下げを指示したとのニュースが市場に伝わった9月18日午後、東京証券取引所では一時、NTTドコモ株がほぼ1年ぶりの安値をつけた。同様に後場、auを運営するKDDIも安値をつけ、ソフトバンクモバイルも下げた。
市場は、政府主導の携帯電話料金引き下げが携帯大手3社の経営にダメージを与えることを警戒したのである。
比べるべき相手を間違えている
筆者が特に懸念するのが、菅総理が携帯3社の売上高営業利益率を東電や東ガスと比べて「過度な利益で、不健全だ」と主張し続けていることだ。
いったい、なぜ、福島第一原発事故を起こして破綻に瀕し、国営化され、事故の後始末に喘ぐ東電と比べるのか。比べるなら、世界のデジタル革命の中で競い合う立場にある米国の携帯電話会社、中でも経営の健全な大手と比較すべきである。
ちなみに、日本勢3社はここ2、3年の値下げもあって、直近2019年度の売上高営業利益率が18.9%(3社平均)に低下、米国の2強であるAT&Tとベライゾン・コミュニケーションの19.2%(2社平均)を下回った。
それ以上にショッキングなのは、日本勢の営業利益が3社合計で2兆7900万円強と、米携帯2位のベライゾン単独の2兆9400万円弱(1ドル105円で換算)にさえ届かないことだ。
デジタル革命の世界では、携帯大手だけでなく、アプリやSNS大手のGAFAやBATと呼ばれる巨大IT企業もひしめきあい、研究開発と技術革新の競争にしのぎを削っている。
モノを言うのは豊富な資金力、つまり収益力であるにもかかわらず、日本の携帯3社は束になってかかったとしても米国2位の携帯電話会社ベライゾン1社にすら太刀打ちできないのである。
これでは、日本は、デジタル革命のインフラであるモバイル通信サービスで旧式ネットワークしか持てず、産業競争力が劣化しかねない。新総理に失礼だとお叱りを受けるかもしれないが、言うべきことは言うべきだろう。比べるべき相手を間違えている。
携帯電話事業は、国民の財産であるばかりか、希少な資源である周波数の割り当てを受けないと事業に参入できないため、他の産業に比べて参入障壁が格段に高いのが特色だ。それゆえ、政府は、常に市場の競争環境の整備を怠ってはならない。これは自明のことである。
このままでは世界から遅れをとるばかり
Photo by iStock
ただし、政府として料金の引き下げを要求する場合には、利用者だけでなく、事業者も納得させることができる、透明で、客観的な料金水準の国際比較の物差しが必要だ。
というのは、菅総理や総務省が値下げの根拠にしてきた「電気通信サービスに係る内外価格差に関する調査」については、携帯電話事業者から「実態を表していない」との批判が絶えないからである。
ちなみに、総務省の調査は、対象の通信サービスや可能な音声通話の時間、メールの本数、データ通信量などを揃えて、各国の代表的な料金を比較する「モデル調査」と呼ばれるものだ。
が、携帯各社は、実際の通信速度や繋がり易さ、地下街やビル影の周波数の不感地域の多寡、トラブルの際のカスタマーサービスの充実度などが調査対象になっておらず、信頼性のある比較といえないと不満を隠さない。
最後に思い出してほしいのは、去年から米国や韓国、中国では日本に先駆けて新世代の通信規格5Gを用いた商用サービスが本格的に始まったのに対して、日本では依然としてサービス地域が限定的で大きく遅れをとっているという現実だ。かつて世界をリードした日本の姿は、影も形もない。
こうした事態に危機感を抱いたからこそ、安倍前政権も今年度から、この次の世代の通信規格6Gの開発競争へ向けて異例の補助金付与や税制優遇を打ち出した経緯がある。
ところが、そうした現実への危機感を忘れ去り、過度な値下げ圧力を携帯電話会社に加えることは政策の方向性がちぐはぐなだけでなく、携帯電話会社とユーザーである一般産業の両方の国際競争力の回復と強化を難しくする行為だ。ひいては、利用者である我々が享受できるサービスの高度化も遅れることにもなりかねない。
町田 徹(経済ジャーナリスト)