プロジェクトの規模と工数の関係はどのような関係になると思いますか?
1機能に該当する成果物を作成するために、1人月が必要だったとします。
そうすると、10機能であれば10人月、1000機能であれば1000人月が必要となると考えがちですが、実際は異なります。
規模と生産性の関係を図で表すと、一般的に下記のような関係になります。
規模が大きくなればなるほど、生産性は低下します。
なぜならば、プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、オーバーヘッドも大きくなるからです。
ここでいっているオーバーヘッドとは、簡単にいうとコミュニケーションに必要となる工数のことです。
プロジェクトに携わっている人数が多くなればなるほど、コミュニケーションの工数は大きくなってきます。
数人で開発する場合であれば、1時間程度打ち合わせを行えば、意識合わせを行うことができるかもしれません。
しかし、これが100人規模になってくると、100人の意識合わせを行うためには、100人に対する説明を行っていく必要があります。
そのためには、100人にいっぺんに説明するためのスペースやスケジュール調整が必要になってきます。
一度に全員に対して説明することができないということであれば、数回に分けてグループ単位に説明を行うことになるかもしれません。
そうなってくると、今度はグループ間の意見の相違について事前あるいは事後に調整を行う必要が出てきます。
さらには、説明用の資料を作成したり、説明会の議事録を作成したり、事前に合意をとっておくべきステークホルダーも多くなってきますので、なかなか調整がつきません。
そうこうしているうちに、状況が変化してきて、合意をとろうとしていたこと自体が無意味になってきたりします。
このようなコミュニケーションに関する工数は、規模が大きくなればなるほど増加していくことになります。
しかし、実際にはこのようなコミュニケーションの工数を甘くみて(あるいは全く無視して)スケジュールを作成するプロジェクトは結構多いのではないでしょうか?
どのような規模のプロジェクトであろうと、ある単位の機能を開発する場合は一定の生産性が保証されるという前提で計画を立ててはいないでしょうか?
そのような計画は、計画を立案した時点で既に破綻していると言わざるを得ません。













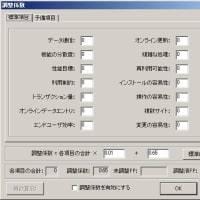

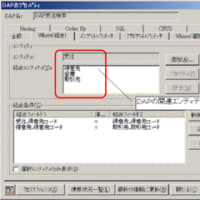


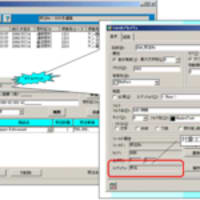
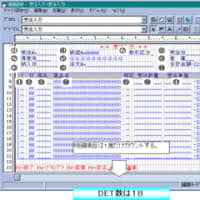







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます