はじめに-2009年度教室年報
2009年度もようやく終わりになる。一息つきたいというのが実感である。とはいえ、いろいろなことがあったこの1年を振りかえって、記録にとどめることも重要だと思われる。
2009年は、1979年の養護学校教育義務制の実施、そして、女性差別撤廃条約の採択から30周年であり、また、1989年の子どもの権利条約の採択から20周年という年であった。そんな人権法制の歴史を踏まえて、2009年を振り返ってみると、障害のある人にとっても、大学に関わる私たちにとっても重要な年となったと思われる。
戦後55年体制と経済成長、1970年代の経済危機、90年代の経済のグローバル化と政治体制の崩壊、そして新自由主義に基づく構造改革が進められてきた。「自民党をぶっ壊す」として登場した小泉構造改革路線は、様々な分野で民営化をすすめてきた。企業のリストラが進み、内部留保の蓄積の一方で非正規労働が蔓延してきた。結果として格差社会が進行した。教育・医療・福祉の分野においては矛盾が集中し、「子どもの貧困」が議論になる状況である。セーフティネットがない「滑り台社会」となり、一昨年のリーマンショックによる世界恐慌の打撃をうけ、生活困難とそのくびきから逃れられない状況となった。そんな社会の閉塞感と危機感の中で、社会的にも混迷を深めてきた。
2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙が行われ、その結果、政権の交代があった。民主党、社会民主党、国民新党の3党による連立政権の樹立が合意され、9月16日には、民主党代表の鳩山由紀夫が国会において首班指名を受け、同日、鳩山内閣が発足した。「モノから人へ」「官僚依存からの脱却」などが掲げられ、国民の一定の要求を反映した政策が示された。しかしながら、予算編成において、財政上の危機は大きく、事業仕分けなどがおこなわれて話題となった。政治上は、10月以降、新政権への期待と不安での様子見となった。
この年、大学においても重大な転換期となった。本年度は、法人化後中期計画・目標の6年間を終えることになった。10月には、学長交代となっていた。しかし、次期学長に内定していたU先生が、ご病気のため長く休まれることとなり、残念なことに6月にお亡くなりになった。U先生は、法人化前のO学長の時代に、副学長となり、法人化後のY学長の時期においても教育担当副学長として本学の発展に貢献してきた方であり、特別支援教育教室のメンバーが所属する学校教育講座の精神的大黒柱となってこられた方であった。6月には臨時の説明会が開催され、8月には学長の意向投票がなされ、8月末に新学長が選考された。8月から9月の初めに新しい学部の運営体制が確立されていくという綱渡りのような運営となった。本学の学部・大学院をめぐっては、総合教育課程を教員養成学部に統合し新たな学部組織をつくっていく学部改組の議論が継続されてきたが、新政権の教員養成6年制の提案もあり、教員養成の高度化の方向で議論が多方面で行われていることも視野に入れる必要もあった。2009年度前期以降、教室幹事のみならず、学校教育講座全体をみる立場の学校教育講座主任としても悩みはつきない状況だったことも記しておきたい。
振り返って、新年度の開始は、はじめに障害児医学のポストにN先生がご着任になり、教室としてはセンターも含めて3名の専任から4名の専任となった。また、教育実践総合センターの教育臨床部門にI先生がご着任になった。学部と大学院の指導体制の違いもあるが、引き続きお世話になっている特任のT先生も含めて教育・研究のスタートをきった。学部の学校教育教員養成課程教育発達基礎コース特別支援教育専修、そして大学院教育学研究科学校教育専攻教育臨床・特別支援教育専修、そして特別支援教育特別専攻科情緒障害・発達障害専攻での教育・研究を支えるには、十分とは言えないが、新たな先生方を迎えることができたことは非常に嬉しいことであった。
2006年度に入学した学生は、学校教育教員養成課程特別支援教育専修のはじめての卒業生となり、他方では、従来の養護学校教員免許状を取得させるカリキュラムのもとで学習をしてきた最後の学生となった。2007年度の特別支援教育の発足に合わせて設置された特別支援教育研究センターも特別経費による運営の最終年度となり、総括と新たな展開を模索する1年でもあった。本年度、学部・大学院・特別専攻科の修了・卒業となる学生・院生にいろいろな模索の中で、ともに教育・研究を一緒にやってきたことを忘れないでほしい。学部の卒業生は、学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース障害児教育履修分野で14人が卒業となり、大学院教育学研究科学校教育専攻教育臨床・特別支援教育専修(旧教育実践開発専攻教育臨床・特別支援教育専修)で7人が修了し、また、特別支援教育特別専攻科10名が修了することとなった。また、特任教員の規定の関係もあり、長くお世話になったT先生も本年度で最終となる。あらためて、深く感謝を申し上げたい。
これまでの大学でのそれぞれの学びの到達点として、卒業論文、修士論文、修了論文を作成したものの抄録を本誌は、それぞれの単位でまとめて掲載している。これまで、非常勤講師として多くの内容をお教えいただいた諸先生方、あるいは教育実習でご指導いただいた諸先生方、そして論文作成に際してご協力いただいた先生方に、この場で心からお礼を申し上げたい。
最後に、2010年に入って、新政権のもとで、障害のある人たちへの施策に対して一律に負担を強いてきた障害者自立支援法は廃止されることが明確にされた。全国の障害者自立支援法違憲訴訟の原告・弁護団は、1月7日に、基本合意書に賛同し、その足で、厚生労働省の長妻厚生労働大臣と合意をかわすことになった。国との基本合意は、「国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める」として、自立支援法の廃止を文書において確認している。新たな障がい者制度改革推進会議が発足し、障害者権利条約と障害者自立支援法訴訟での合意に基づいて、今後、障害者制度改革が審議されることとなる。障害のある人たちの権利に基づいた障害者施策となるよう、特別支援教育の改革も含めてともに点検し、検討し、議論しあっていきたい。
これまでの縁のあった先生方、学生・院生、卒業生の皆さんの健康を祈念すると共に、今後のご指導、ご鞭撻をお願いする次第である。
2009年度もようやく終わりになる。一息つきたいというのが実感である。とはいえ、いろいろなことがあったこの1年を振りかえって、記録にとどめることも重要だと思われる。
2009年は、1979年の養護学校教育義務制の実施、そして、女性差別撤廃条約の採択から30周年であり、また、1989年の子どもの権利条約の採択から20周年という年であった。そんな人権法制の歴史を踏まえて、2009年を振り返ってみると、障害のある人にとっても、大学に関わる私たちにとっても重要な年となったと思われる。
戦後55年体制と経済成長、1970年代の経済危機、90年代の経済のグローバル化と政治体制の崩壊、そして新自由主義に基づく構造改革が進められてきた。「自民党をぶっ壊す」として登場した小泉構造改革路線は、様々な分野で民営化をすすめてきた。企業のリストラが進み、内部留保の蓄積の一方で非正規労働が蔓延してきた。結果として格差社会が進行した。教育・医療・福祉の分野においては矛盾が集中し、「子どもの貧困」が議論になる状況である。セーフティネットがない「滑り台社会」となり、一昨年のリーマンショックによる世界恐慌の打撃をうけ、生活困難とそのくびきから逃れられない状況となった。そんな社会の閉塞感と危機感の中で、社会的にも混迷を深めてきた。
2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙が行われ、その結果、政権の交代があった。民主党、社会民主党、国民新党の3党による連立政権の樹立が合意され、9月16日には、民主党代表の鳩山由紀夫が国会において首班指名を受け、同日、鳩山内閣が発足した。「モノから人へ」「官僚依存からの脱却」などが掲げられ、国民の一定の要求を反映した政策が示された。しかしながら、予算編成において、財政上の危機は大きく、事業仕分けなどがおこなわれて話題となった。政治上は、10月以降、新政権への期待と不安での様子見となった。
この年、大学においても重大な転換期となった。本年度は、法人化後中期計画・目標の6年間を終えることになった。10月には、学長交代となっていた。しかし、次期学長に内定していたU先生が、ご病気のため長く休まれることとなり、残念なことに6月にお亡くなりになった。U先生は、法人化前のO学長の時代に、副学長となり、法人化後のY学長の時期においても教育担当副学長として本学の発展に貢献してきた方であり、特別支援教育教室のメンバーが所属する学校教育講座の精神的大黒柱となってこられた方であった。6月には臨時の説明会が開催され、8月には学長の意向投票がなされ、8月末に新学長が選考された。8月から9月の初めに新しい学部の運営体制が確立されていくという綱渡りのような運営となった。本学の学部・大学院をめぐっては、総合教育課程を教員養成学部に統合し新たな学部組織をつくっていく学部改組の議論が継続されてきたが、新政権の教員養成6年制の提案もあり、教員養成の高度化の方向で議論が多方面で行われていることも視野に入れる必要もあった。2009年度前期以降、教室幹事のみならず、学校教育講座全体をみる立場の学校教育講座主任としても悩みはつきない状況だったことも記しておきたい。
振り返って、新年度の開始は、はじめに障害児医学のポストにN先生がご着任になり、教室としてはセンターも含めて3名の専任から4名の専任となった。また、教育実践総合センターの教育臨床部門にI先生がご着任になった。学部と大学院の指導体制の違いもあるが、引き続きお世話になっている特任のT先生も含めて教育・研究のスタートをきった。学部の学校教育教員養成課程教育発達基礎コース特別支援教育専修、そして大学院教育学研究科学校教育専攻教育臨床・特別支援教育専修、そして特別支援教育特別専攻科情緒障害・発達障害専攻での教育・研究を支えるには、十分とは言えないが、新たな先生方を迎えることができたことは非常に嬉しいことであった。
2006年度に入学した学生は、学校教育教員養成課程特別支援教育専修のはじめての卒業生となり、他方では、従来の養護学校教員免許状を取得させるカリキュラムのもとで学習をしてきた最後の学生となった。2007年度の特別支援教育の発足に合わせて設置された特別支援教育研究センターも特別経費による運営の最終年度となり、総括と新たな展開を模索する1年でもあった。本年度、学部・大学院・特別専攻科の修了・卒業となる学生・院生にいろいろな模索の中で、ともに教育・研究を一緒にやってきたことを忘れないでほしい。学部の卒業生は、学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース障害児教育履修分野で14人が卒業となり、大学院教育学研究科学校教育専攻教育臨床・特別支援教育専修(旧教育実践開発専攻教育臨床・特別支援教育専修)で7人が修了し、また、特別支援教育特別専攻科10名が修了することとなった。また、特任教員の規定の関係もあり、長くお世話になったT先生も本年度で最終となる。あらためて、深く感謝を申し上げたい。
これまでの大学でのそれぞれの学びの到達点として、卒業論文、修士論文、修了論文を作成したものの抄録を本誌は、それぞれの単位でまとめて掲載している。これまで、非常勤講師として多くの内容をお教えいただいた諸先生方、あるいは教育実習でご指導いただいた諸先生方、そして論文作成に際してご協力いただいた先生方に、この場で心からお礼を申し上げたい。
最後に、2010年に入って、新政権のもとで、障害のある人たちへの施策に対して一律に負担を強いてきた障害者自立支援法は廃止されることが明確にされた。全国の障害者自立支援法違憲訴訟の原告・弁護団は、1月7日に、基本合意書に賛同し、その足で、厚生労働省の長妻厚生労働大臣と合意をかわすことになった。国との基本合意は、「国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める」として、自立支援法の廃止を文書において確認している。新たな障がい者制度改革推進会議が発足し、障害者権利条約と障害者自立支援法訴訟での合意に基づいて、今後、障害者制度改革が審議されることとなる。障害のある人たちの権利に基づいた障害者施策となるよう、特別支援教育の改革も含めてともに点検し、検討し、議論しあっていきたい。
これまでの縁のあった先生方、学生・院生、卒業生の皆さんの健康を祈念すると共に、今後のご指導、ご鞭撻をお願いする次第である。












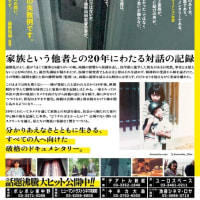




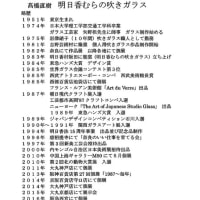

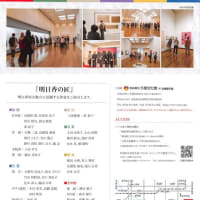
科学では反証可能性。繰り返し証明することができる可能性。これが成り立たなければ理論は成り立たない。
然しだ。何を繰り返すのか。この絶対条件を得て(=知り), 更に絶対条件を再び揃えなければならない。にも拘わらず, 以前と同じ視点を持ち得ないのに反証などできない。故に理論は単純で一番難しい処で破綻する。
究極を斥ける絶対的でないものは理論ではない。但し, 一般的には絶対的でなくとも類似事的な繰り返し, 即ち法則性【習慣性】が観測者の要求を満たす精度であれば, それは理論だ。
問題は法則性の善悪【法則が私の要求を繰り返し満たしうるか】を超えて, 其処に名誉や力【人に頼りにされる, より多くの要求を確実に満たしうる高精度な法則が欲しい】・征服感や優越感という, 更なる良し悪しがあるからこそ科学者は努力を惜しまない。これが真理の探究に置き換わる。
だから科学者は俗ではないのかと言えば, 私は俗だと思う。真理の探究なんて名目上の理由だ。
何故か?
客観的な真理が反証する度に脅かされてはいけないし, 結局そこを無視するのは自分だからである。客観的真理が無いことを知るならば, 純粋なる真理の探究という名目は選択から除外され, 何故に真理の探究を行うのかという理由にはならない。裏を返せば, 何故に主観的な真理を探究するのか。ということだ。
物語りなのだ。科学も巧くできた寓話【ぐうわ】だ。
これを拒絶する手段は科学者には与えない。問い掛けるだけでたやすく崩壊する。
意味は無意味に含まれ, 無意味は意味を含む。
我思う故に我在り。
『俺の質問に答えろ。お前は何のために学ぶ。純粋なる真理を得るためか。それとも生きるためか…』